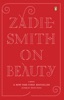- Amazon.co.jp ・本 (389ページ)
- / ISBN・EAN: 9784105900243
作品紹介・あらすじ
アーチーのジョーンズ家とサマードのイクバル家。妻子にはなにかと不評の二人である。そこへ、リベラルを気取るチャルフェン一家が登場し、二組の家族をさらなる混乱に陥れる。折りしもロンドン北西部では、あらゆる急進主義がはびこっていた。過激なイスラム原理主義者、熱烈なエホバの証人、闘う動物愛護主義者、危ない遺伝子工学者…一筋縄ではいかない面々が繰り広げる世紀末の狂想曲。多文化社会の困難と希望を恐るべき力技で描きだす、超絶ノンストップ・ノヴェル。ウィットブレッド賞処女長篇賞、ガーディアン新人賞、英国図書賞新人賞、コモンウェルス作家賞最優秀新人賞受賞。
感想・レビュー・書評
-
楽しいロンドン移民ホームドラマ。実際はそんなに単純なものじゃないけれど、入り口として、こんな風に楽しい雰囲気に仕上げてあるのかな、という印象。登場人物みんなキャラは立っているけれど、与えられた設定をこなしているだけのようで。みんなあまりに逡巡しないから、物足りなかった。
チャルフェン一家と成長したマジドの苛立たしさの描写、イライラするけど邪悪ではないさじ加減はとても良いと思った。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
行動力のある移民たちが社会では異端扱いになって行きがちなのは何故?
分断を排除し、寛容の社会になって行くための説得や強制を減らしていくには「不寛容」が主軸になって行く。そのためのキーワードは「なんとなく」。。。
下巻は皆がバラバラでパワーを枯渇、そして次に見えてきた世界は~そんな世界だった。
逡巡の塊り、煮え切らないアーチ―が消えてしまったような影の薄さ・・でも終わってみれば一番ノーマルだったかも。
クララが義母の宗教に反発してがちゃがちゃになる姿
サマードと若い嫁の絶えないけんかの明け暮れ・・
美男子の双子マジドとミラド・・一方はバングラデシュの正統を求めさせたのに逆に英国正当になってしまうのは笑える
そしてミラド・・パンク・ピッピ―?!英国の若者の点景のような自由溢れる若者に。
皆がアドバルーンの様に空に広がって行き、最後の光明を幽かには感じたが。 -
図書館で。
本屋で文庫版を見かけたものの、初めて読む作家さんだし…と図書館で借りてみました。正直ちょっと読み終えるのがしんどかったので、図書館で借りてヨカッタ。
登場人物がとにかく多い。そして彼らの背景というか、色々なゴタゴタが付随してきてその描写が長い長い。それが人生よ、と言われればそうなんだろうけど、大したこともない人間が大したこともしてないエピソードがてんこ盛りでナンダカナ、となるというか。ま、そりゃぁ物語の主人公のような人生送っている人の方が少ないでしょうけれども。
そして二人の主人公男性の言動が一々カンに触る。まぁ70年代80年代のオッサンなんかそうでしょうよ、とも思うけれども愛すべき存在とは到底思えないし。個人的にはもっとクララが主人公的立場になるかと思ったら、違ってましたね。どちらかというとパキスタン一家の方が色々とすったもんだあって、でもその行動と思考回路のほぼすべてに共感出来ないというある意味面白い作品だったかな、とは思いますが。
後は海外ならではの文化というか、通りを一本隔てただけで区画が変わり、金持ちエリアと貧乏人エリアに隔てられているとか、学校での微妙な人間関係とかが日本人の自分にはわかりにくいというのはあるかも。彼らが感じている疎外感とか、生まれた国に属さない不安定さとかはわからないんだろうなぁと思いました。
登場人物の感情に寄り添わずに、一歩引いた視点から書いている感じなので何とか読み終えました。でもこういう系の作品だったら、私は「オスカー・ワオの短く凄まじい人生」の方が好きだなぁ。
アルシ的に言えば「面白かったかも。でも面白くなかったかもね。」という感じでしょうか。 -
2001-07-00
-
この移民した側も受け入れ側ものアイデンティティ崩壊の後がトランプ大統領、BREXITなのかなと思う。あまりに盛りだくさんで最後まで読めるか不安になったが人物像が頭に描けるので最後まで楽しめた。
-
「おれたちの子供はおれたちの行動から生まれる。おれたちの偶然が子供の運命になるんだ(十八字分傍点)。そうさ、行動はあとに残る。つまりは、ここだってときに何をするかだよ。最後のときに。壁が崩れ落ち、空が暗くなり、大地が鳴動するときに。そういうときの行動がおれたちの人間性を明らかにするんだ。そしてそれは、おまえに視線を注ぐのがアッラーだろうがキリストだろうがブッダだろうが、あるいは誰の視線も注がれていなかろうが、関係ないんだ。寒い日には自分が吐いた息が見える。暑い日には見えない。でもどちらの場合も息はしてるんだ(七字分傍点)」
ベンガル人のサマード・ミアーには学歴があったが、従軍中の事故で右手が不自由なため、やむなく従兄弟の店でウェイターをしている。サマードは、敬虔なムスリムとして生きたいと思いながらも飲酒や手淫、浮気といった罪から逃れられない。アーチーはイギリス風朝食と日曜大工を愛する白人。優柔不断で、何かを決める時にはコイン投げに頼る。イタリア人の前妻に逃げられ、自殺を試み失敗した後、コミューンで出会ったジャマイカ出身の美しい黒人娘クララと再婚した。第二次世界大戦の終末を遠い異国で共に迎えた二人は、女房そっちのけで、始終オコンネルズというアラブ人が経営するカフェで顔を突き合わす毎日。
いろいろな国からやってきた移民が集まるロンドンの一地区で暮らす二組の家族に、もう一組ドイツ・ポーランド系のリベラルなチャルフェン一家がからんで起きる家庭騒動を、コミカルななかにも辛口の諷刺を利かせた、とびっきり愉快な英国流風俗小説である。移民にはそれぞれ異なるアイデンティティがある。宗教がちがえば、夫婦関係のあり方や子育ての仕方も異なる。そこから生じる実に様々な齟齬が、ほとんどマンガチックと思えるほど戯画化され、極端から極端に走る子どもたちの行動が、英国だけにとどまらない、信仰と科学、イデオロギーの衝突といった諸々の現代的な問題を引き起こす。
ジャマイカ系のクララは「エホバの証人」の熱心な信者である母を嫌い、ヒッピー仲間のコミューンに逃げ込んでいてアーチーと出会った。母は、今でもランベス自治区でクララのかつてのボーイフレンドであったライアン・トップスと布教活動を共にしている。そのライアンの計算によれば、世界の終りは一九九二年十二月三十一日に訪れる。二人はクララの娘アイリーにそのことを警告する電話を何度もかけてよこす。
サマードの双子の息子、マジドとミラトは二人とも類い稀な美貌の持ち主だ。ただ、それ以外は正反対。成績良好でイギリス人たらんとする学者肌のマジドに比べ、弟のミラトはマフィア映画にかぶれ、デニーロやパチーノの真似をし、ギャング仲間を引き連れて歩く不良少年だが、やたらと女性にもてる。ファミリーという集団に固執するミラトはイスラム系の過激な集団KEVINと行動を共にするようになる。同じ頃、チャルフェン家の当主マーカスの秘蔵っ子となったマジドは大晦日に行なわれる科学イヴェントに向けて準備を進めていた。
遺伝子工学で癌細胞を移植したマウスの公開実験を目的とするイヴェントは、神の意志に背く行為として反対を唱えるエホバの証人やKEVINの他に、動物愛護を唱える団体FATEからも攻撃されていた。そこには運動を主催する女性に魅かれて仲間になったマーカスの息子ジョシュアもいた。こうして、三家族の子どもたちがそれぞれの立場から、マーカスとマジドのイヴェント阻止に向けて一気に行動を起こす。
自分たちの主義主張が正しいと信じて行動に飛び込んでゆくのは、若者の特権のようなものだが、自分たち以外の人間の思想や信仰、慣習を認めない不寛容さは、多様性を認めない窮屈な世界を現出してしまう。大人になれば、その性急さも理解でき、一歩離れた位置から見直すこともできる。一概に愚かしさを責めるのではなく、カリカチュアライズすることで、相対視させるのが、ゼイディー・スミスの真骨頂だ。
笑われているのは若者だけに限らない。カルト的な宗教者やタコツボ的な視野でしか周りが見えない科学者、せっかくイギリスでの生活を選びながら生国の縛りから抜け出せずにいるサマードのような移民たちも同じだ。それらをいかにも滑稽に描いてみせるが、上から目線で見るような意地の悪いものではない。自身英国とジャマイカ生まれの父母を持つスミスの視線には心ならずも移民となった世代に寄せる愛情がこめられている。
自在に回想を挿入し、時代や空間を自由に行き来するスミスだが、収拾がつかないほどこんがらがっていた多くのエピソードが次第に一点に集まってきて大団円を迎える展開は、しっかりしたプロットあってのことである。多少あざとくも見える結末のつけ方も、巧妙に張りめぐらせた伏線のせいもあって、不自然さを感じさせない。これが大学在学中の作品だというからその才能の豊かさには驚くよりほかはない。なにより、アーチーやサマードをはじめとする中年男性のセックスその他のどうしようもない生態が、あからさまにされているところに驚きもし、感心させられる。うら若い女性作家の筆になるとは到底思えない。こうした才能が歳を重ねたらどんな作品を書くのだろう、と末恐ろしくも楽しみなことである。(上巻も含む) -
イギリスのドタバタって、アメリカのドタバタよりもえげつない気がします。
とにかく極端から極端へ、振れ幅がハンパない。
君たちには中庸という言葉がないのか!と言いたくなります。
しかし、中心人物の一人であるアーチーが、中庸の人でした。
下巻になって影が薄かったから、忘れてました。
唯一の、純粋なイギリス人で、とことん何かを決定することのできない男、アーチー。
最初の結婚に失敗し、自殺を図って失敗し、なりゆきで(?)かなり年下のジャマイカ系イギリス人クララと再婚。一人娘アイリーを得る。
大学を出ているというのに、仕事はチラシを折りたたむこと。
そこには何の判断もいらないから。
アーチーの親友が、先の戦争で同じ部隊にいたインド系イギリス人サマード。
学があり、野心があり、仕切りたがりのサマードは、戦争で片手が不自由になったために英雄になることができなかったことが無念でたまらない。
いとこが経営するレストランで給仕として働いているものの、世の中に不満だらけ。
自分の娘のように若いアルサナは、黙って夫に従うようなタイプではなかったために、夫婦の間にケンカが絶えない。
サマードの双子の息子マジドとミラト。
サマードは何とか息子二人を敬虔なムスリムとして育てたかった。
とりあえず長男を故郷のバングラディシュに送り出したのだが、戻ってきたマジドはイギリス人よりもイギリス人的な、論理を最大の武器にする上っ面だけの紳士だった。
手元で育てたミラトは、そんな親や兄弟に反発するように自堕落な生活を送り、気がつけばがちがちのイスラム原理主義者たちと行動を共にするようになる。(しかし映画やロック、酒やマリファナなどの西洋の悪癖を捨てきれないことは内緒だ)
アーチーの義理の母ホーテンスは、熱烈なエホバの証人の信者である。
今の生活に、考えない様にしているが数々ある不満はさておき、最後の審判の日、神に許される人の中に入るように、神が望むことはすべてやる。
神に許されることが、ホーテンスの生きた証になるはずなのだ。
娘クララにも布教活動をさせていたのだが、クララは思う。
救われる人が少なすぎる。もし自分が神に許され楽園に行けたとしても、自分の足元に数え切れないほどの救われなかった人たちの屍があるとするのなら、それは本当に楽園と言えるのだろうか。
宗教から離れるために、家から出るために、結婚するクララ。
とにかくとにかく極端な人たちばかりが出てくる小説。
人物紹介が物語になっているような気までしてくる。
これ以外にもまだ極端な人たちがたくさん出てきて、それぞれに交錯して、最終的に一堂に会するシーンが圧巻。
どうなるんだろう、どこに着地するんだろう。
これは移民の物語なんです。
常にここは自分の場所ではないと思いながら生きていく。自分の居場所探しに人生を費やす人たちの。
そして、子ども世代のアイリー、マジド、ミラトたちは、イギリスで生まれ育っているのにイギリス人ではない自分をもてあまし、家族に反発する。
みんなバラバラ。
みんな、自分のことばかり。
移民は新しい血を運んでくるはずなのに、社会の端っこに追いやられているのはなぜ?
極端なことをしないと認めてもらえないのはなぜ?
最後の最後に、この物語の主人公がくっきりと立ち現れる。
みんながおんなじになるのでも、みんながバラバラになるのでもない。
みんながなんとなく仲良く一緒に暮らせないかな?
この「なんとなく」がいいと思うのね。
先日読んだ伊坂幸太郎の「死神の浮力」を思い出す。
寛容は自分を守るために、不寛容に対して不寛容になるべきなのか。
「寛容」にとっての武器は、「説得」と「自己反省」しかない。ただ「寛容」によって、「不寛容」は少しずつ弱っていく。「不寛容」が滅亡することはなくとも、力が弱くなるはずなのだ
排他的な不寛容の世界から、なんとなく寛容な世界へ。
21世紀がそんな世界になれるよう、祈る気持ちで本を閉じる。 -
すごいわー。けっこう時間をかけて読んだのだけれど、ものすごいエネルギーを消費した。リアル大河小説。 人種も生い立ちも宗教も考え方もてんでばらばらな二人の男が、それぞれ思い通りにならない家族を作り、相いれない知人と交わり、見も知らぬ祖先に思いを馳せる。時間も場所も視点もいったりきたりしながら、この狭い架空の家族の歴史に深く深くおりていく。冴えない彼らの人生の何と混沌にみちていることか。 よくわからない他人とともに生きる、このわけのわからない人生に乾杯!誰が何と言おうと乾杯!!
-
この先私が生きている時代の地球上のドラマを先取りされた気分だが、日本だったらもっとウエットかもしれない。移動することって本当不思議でおかしくて悲しみも喜びも、しかし、人間は弱くもあるが強くもある。思い出しレビューだからちょっと抽象的過ぎるか。
著者プロフィール
ゼイディー・スミスの作品










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :