- Amazon.co.jp ・本 (446ページ)
- / ISBN・EAN: 9784124034202
感想・レビュー・書評
-
詳細をみるコメント0件をすべて表示
-
4位
十七世紀までは、イスラーム世界は決してヨーロッパに劣ってはいなかった。オスマン・トルコ帝国は世界史上屈指の大帝国であり、首都のイスタンブールは壮大な宇宙論をそなえた国際都市だった。
それなのに、なぜイスラームはヨーロッパに後れをとってしまったのか。山内昌之は丁寧にイスラーム衰退の歴史をたどってゆく。
十八世紀から凋落が始まり、十九世紀になると完全に「支配する側」から「支配される側」に回った。『地中海』のブローデルはそれを「生きた人間たちのあの煉獄、われわれが遠慮から第三世界と呼んでいるなか」に入っていったと書いている。
オスマン・トルコ帝国は広大な領土を有していたが、特にエジプトは重要な州だった(その支配者ムハンマド・アリーとフランスのナポレオン、そしてイギリスのウェリントンは同じ1769年生れ、という偶然が面白い)。1798年にナポレオンが征服するまでのエジプトでは、異民族のマムルークが圧制を布いていた。フランス皇帝は彼らを斥けたが、同じように略奪をはたらき、不信の徒としてエジプトの民に嫌われた。
当時、地元の歴史家ファパルディーは、今年で一番大事なのはナポレオンのエジプト遠征ではなく、そのせいでメッカへの巡礼船がとだえたことだと評した。なぜか? 巡礼という制度は、世界中のムスリムの同胞精神を作り上げる。それが下火になるなら、イスラーム圏は危殆に瀕するのだ、という。実際、その危惧は当った。イスラーム国際システムというものが、機能しなくなっていったのである。
西欧資本主義の市場経済がイスラームを襲う。白人は、我々はおくれた植民地を保護し、教化する責務があると考えるようになる。自由主義者トクヴィルも、一面では露骨な植民地主義者だった。こうした偏見を初めて正そうとしたヨーロッパ人は二十世紀のトインビーである、と著者は言う。
イスラーム側も手をこまねいていたわけではない。西欧の文物を取り入れ、組織を近代的に改革し、なんとか対抗しようと努力してきた。
それがうまくいかなかった理由は主に四つある。
一つ目は、イギリスとフランスとロシアと、多方面で外交をしなければならなかったこと。ひとつ防いだと思っても、また違うところから攻めてくる。特にイギリスの外交上手は背筋が凍るほどで、着実にトルコを骨抜きにしていった。
二つ目は、上層部が腐敗していたこと。賄賂は茶飯事で、ノーブレス・オブリージェの思想などはまずなかった。有能な大人物がでてきてもすぐに失脚させてしまう。
三つ目は、トルコとエジプトが対立してしまったこと。あくまでもオスマン・トルコ帝国の属州だったエジプトは、独立を目指した。トルコのマフムト2世とエジプトのムハンマド・アリーは共に名君だったのに牽制しあい、それを複雑な外交に利用される。
四つ目は、イスラーム内部からも改革運動が巻き起こったこと。中世までの帝国という制度は時代遅れになりつつあり、もし植民地主義がなかったら百年か二百年かけて、ゆっくり改革が行われたかもしれない。しかし列強の侵略と時期が重なってしまったため(というより、外からの刺激を受けて加速したため)、オスマン・トルコ帝国はなかなかヨーロッパに反撃ができない。
イスラームはますます泥沼にはまってゆく。トルコでは一度立憲政治が行われるが、皇帝の専横によってつぶされる。エジプトには高潔の士ウラービー・パシャが現れるが、島流しにあう。侵略と腐敗は止らない。
決定的にまずかったのは、欧化のために、やすやすと外国に借金をしたことである。自国の経済体制が整う前に列強の資本がイスラームをしぼりとり、財政は破綻してしまう。このあたりは、読んでいてもう胸が痛くなってくる。
イランの場合も、外交、腐敗、借金などは似たような道をたどった。興味深いのはタバコ・ボイコット運動である。十九世紀のイランではフランス系の企業が煙草利権を独占しており、それに反発した商人たちが民衆を取り入れて大規模なボイコット運動を展開した。これは1905年以降の立憲革命、そして1979年以降のホメイニー革命の先取りだった。
シルクロード、カザンやカフカースのイスラーム教徒にとっては、敵はヨーロッパよりもロシアだった。ロシアは数百年に渡って侵略を重ね、改宗をせまったが、ムスリムはそれを頑としてこばんだ。この構図は、ソ連崩壊後のチェチェン紛争にもあてはまる。
そんな中、東洋の小国日本がロシアを破った日露戦争は、イスラーム諸国に衝撃と感動をもたらした。黄人も、白人に勝てる! これがはげみとなり、イラン立憲革命や青年トルコ党の改革運動は躍進した。
しかし日本はこれ以後ヨーロッパの侵略主義を範とするようになる。青年トルコ党は志だけは高いけれど行動が場当り的でものを考えず、まるで五・一五事件の青年将校たちのようだ、という著者の指摘は両者の蹉跌を暗示させる。
著者プロフィール
山内昌之の作品







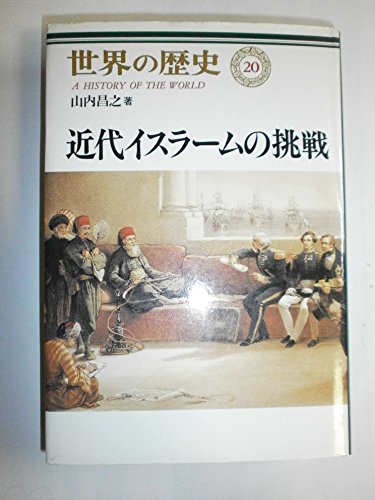


 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 






















