- Amazon.co.jp ・本 (421ページ)
- / ISBN・EAN: 9784061591059
作品紹介・あらすじ
1930年代の世界恐慌下、大量失業を救うために低金利政策と積極的な公共投資を主張して、伝統的理論を一新したケインズ。その経済思想と彼の代表的学説『雇用・利用および貨幣の一般理論』の骨格を、豊富な図表を用いて平易に説き、ケインズ経済学の真髄を論究。欧米など先進各国の経済運営に画期的変革をもたらし、いま再び世界的な長期不況の下で注目される大経済学者の理論と影響力を描く力作。
感想・レビュー・書評
-
ケインズの経済や思考法が分かりやすく書いてあって、読みやすかった。
ケインズの良いところは、大掛かりな哲学や経済思想を構築したりするんじゃなくて、その時々の経済に対する適切な処方箋を書いて、状況に合わなくなれば、すぐにそれを捨て去って、また新しい対策を練っていくという、現実主義なところ。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
ケインズは一般理論を書くにあたって見たものは1920年代のイギリスに過ぎなかった。イギリスを頂点をする経済体制は崩れていくにも拘らず、イギリスは三つの階級に分かれていたとみていた。すなわちロンドンシティに集まり海外投資を行う「投資家階級」、企業・工場を運営する「企業家階級」、そして「労働者階級」である。19世紀ならば植民地への投資(例えば鉄道)は、イギリスの需要となったが、当時はもはや海外投資=アメリカへの需要となり、イギリスの需要とはならず、ポンド安を生み輸入品の高騰が企業家・労働者階級への負担となる。第一次世界大戦以後では国内の資金を海外に流出させることなく、国内産業への投資がなされるならば対外競争力が生まれるというのがケインズの時論であった。
新古典派経済学は縦軸に価格、横軸に需要量・供給量を取り、財市場・労働市場・金融市場の三つの市場を基にパイの最適配分を分析するのであって大きさを分析するのではない。これはリカード体系を代表とし、セー法則を暗黙の間に組み込んだ理論であった。しかし、ケインズは古典派理論を間違ったものとしては考えず、現実と大きく異なった特殊な状況下におかれたときに成立する理論としてとらえた。
新古典派経済学では均衡点付近においては新興産業・衰退産業の下で解雇・新規雇用が生まれる。それは経済においては至って普通であり、これらを”摩擦的失業”と呼び、ケインズはこれ自体を問題視しなかった。なぜならすぐに雇用されると考えたからである。
自発的失業はより高い賃金を求めて発生する失業である。自然に存在する失業率を越えてくると労働市場に圧力が生じ、それが社会問題となる。これをケインズは中止したのである。これに対してケインズは職業紹介所など充実、労働環境の充実、賃金財産業における労働の物的限界生産力の向上(物理的生産力が向上すれば賃金財が安くなり、実質賃金が低下することで労働市場がシフトし、雇用が増す。ただし、社会全体ではなく部分的にという意味である)を挙げた。
ケインズが問題視したのは摩擦的失業でも自発的失業でもない、”非自発的失業”である。古典派では大量失業の原因を労働者が高すぎる賃金にあり、これを引き下げることによって雇用問題は解決できると求めたが、大量失業者があふれている状況下にあって労働者が求めるのは”実質賃金”ではなく”貨幣賃金”であると見たのである。なるほど、我々は物価の変動を加味して賃金を考えない。あくまでも表面上の賃金を見ていることからもそのように言えるであろう。また古典派経済学では物価水準も労働者が決められるようになるが、現実では労働者が決められるのは貨幣賃金だけであり、物価水準は労使関係の範囲外であると説いたのである。新古典派理論では労働市場を二つの曲線で雇用量・実質賃金を決定しようとしているが、実質賃金は前述の通り労使間で決められる問題ではなく、物価水準と貨幣賃金が決まらなければならないのである。
古典派経済学ではMV=PTというフィッシャー方程式をとる。PT(物価水準と取引量)財の取引総額と支払われた貨幣の額は等しく、同じ貨幣が何度も回転するからMV(貨幣量と流通速度)と等しくなる、という貨幣数量説をとっていたのである。ここから物価水準P=(V/T)Mで示されるが、これは貨幣数量に依存するものであるということになる。つまり貨幣においては限界効用逓減の法則は当てはまらないことを前提としているのである。
貨幣賃金の切り下げは物価水準に影響を与えないという新古典派体系に対して、ケインズは完全雇用の場合にのみ適用されると主張した。
古典派がセー法則を採用した理由は、貨幣を「交換の仲立ち」「価格を測る尺度」においてのみ成立するのであり、これこそまさにMV=PTのフィッシャーの貨幣数量説となる。しかし、貨幣が富としての貯蔵手段をもった瞬間にセー法則は否定されるのである。
ケインズは国際貿易が存在せず、政府の活動もない単純なモデルを想定する。縦軸に消費C、横軸に所得Yをとり、所得が全て消費されたとすると45°線となる。しかし、実際は所得が増加しても消費に全て回されるわけではない。この時において、貯蓄Sが現れる。一方縦軸の下に雇用量Nをとる。所得が増えるにつれて貯蓄が生まれるのは経験的に実証されているため、実際は45°よりも緩やかになる。ここからなぜ失業が存在するかを明らかにする。それは社会全体の生産水準が低すぎるためであり、不完全雇用が発生するのは45°よりも緩やかな総需要曲線の位置が低いためである。
前述の通り、ケインズは国際貿易を無視し、政府の役割が存在しないシンプルな経済をモデルとした。Aを社会全体の販売総額とすると、企業が別の企業から財A1を購入した時、消費はA-A1である。次にケインズは資本価値について、企業家が生産した場合、期末に保持している資本価値をGと表現し、生産をせずに最良な状態で保持していた場合G'とする。この時、最良な状態に保持するためにはメンテナンスなどの費用B'を投入しなければならない。この二つの異なる期末の資本価値をU=(G'-B')-(G-A)を以てU=Aの使用費用(user cost)と定義する。
ここで投資Iは期末の資本価値-期首の資本価値である。これは設備投資であり、在庫投資でもある。原材料の場合もある。減価償却は定率法・定額法で操作できるが、粗投資は操作できない。ここから粗投資I=期末資本価値G-期首資本価値G0+減耗分Vとしたのである。
以上によってケインズは所得・投資・消費を定義するのである。ここから所得Y=消費C+貯蓄Sとなり、投資と貯蓄は等しいという命題が出てくる。こうしてケインズは利子率とは無関係に投資、貯蓄が等しくなることを論証したのである。
ケインズは所得と消費の関係において生産をするしないに関わらず発生する減価償却を含む所得概念を採用する。だが、所得のうち、消費するという問題には減価償却を除かなければならない。ケインズは限界所得の増加の中で、消費に回る部分を限界消費性向としてとらえる。そして利子率が上昇した場合は貯蓄が増えると考えるため、現在の消費を抑制し、将来の消費の増加を表す。
そして国が成熟してゆけば貯蓄性向が高まる傾向にあり、それを補うのに十分な投資水準がなければ所得、つまり生産水準は維持できない。しかし、豊かな国には十分な資本設備がある以上、毎年毎年投資需要があるとは限らない。それこそ、豊かな社会において大量失業者が存在する問題であるとケインズは考えたのである。
新古典派が労働市場において完全雇用になるかどうかが財市場を決定すると考えたのに対して、ケインズは財市場の均衡こそ労働市場を従属させると考えたのである。
雇用量を増やすには投資の水準を引き上げることが必要であり、社会全体の有効需要曲線を上にシフトさせる必要がある。現在の経済学のテキストブックでは限界消費性向をαとすると、投資の増加=(1/1-α)倍の所得増につながるとしている。例えば限界消費性向が90%の時、100億円の投資があれば1000億円の所得増加をもたらすことになる。しかし、不況下においては100億円の投資をしても企業は在庫の圧縮から図るであろう。ダムで100億円の投資が行われても在庫の圧縮がある限り生産活動は行われないし、在庫の圧縮は投資の減少である。さらに仮に50億円が所得の増加として生まれたとしても消費財の購入などに充てられるとするとさらにマイナス要因になる。新古典派経済学では在庫減少分だけ生産がおこなわれるという前提があるが、常にそうであるとは限らない。ケインズは社会全体として投資の合計と貯蓄の合計は等しく、投資と所得の増加の間にこそ乗数が関係があるとしたのである。サムエルソンなどのアメリカケインジアンの誤った理解が日本にも取り入れられていることに注意しなければならない。
日本のような経済的に豊かで資源や資本設備が十分に余っているとするならば、投資水準を引き上げることでいくらかの所得を増やすことが出来る。所得の増加こそ雇用量の増大につながるのである。
投資を決定づけるものは基本的に古典派経済学を踏襲している。すなわち企業家は資本の限界効率を見て「新たに設備投資をした方が得か」「既存設備の稼働率を上げたほうが得か」である。ケインズが見た世界は投資をする人間が「資本家」であり、現在のような企業家ではない。資本と経営が分離してくると資本家=株主は株の買換えを自由にできる。ある事件が発生した時に大衆はどのように判断するのかを考え、「予想利潤率が上昇すると考えれば株価を引き上げに入るであろう」と指摘したのである。それはあたかも美人投票の原理である。この砂上の楼閣のような不安定要素に対して、ケインズは合理的な予想をする政府が介入せざるを得ないのではないかとしたのである。
投資を決定させる極大利潤は資本の限界効率=利子率となるところまでである。この理論に従うならば利子率の低下は投資を呼び込むこととなる。しかし、利子率の低下以上に砂上の楼閣のような不確実性によって投資が妨げられるならば、民間ではなく政府投資が有効と考えたのである。
ではケインズが指摘している利子率であるが、新古典派経済学では利子率は消費を抑制する我慢によって発生すると考える。しかし、ケインズは「タンス預金に利子はつかない」と指摘し、利子は債権債務関係にあると求めたのである。新古典派経済学は貸付資金需給説を説き、利子率は所得に関係すると考えたが、ケインズは債券に着目し、流動性選好説を唱えた。金利が下がれば債券価格は上昇し、利回りは低下する。逆も然りである。ケインズは新古典派のように一人の人間の合理性ではなく、あくまでも多様な価値観があることで市場が存在すると考えたのである。ブル・ベアの均衡するところに市場利子率が決定され、株価利回りも決定されるというのがケインズの利子決定理論である。そしてイギリスでは富裕層が遺産相続で富を蓄えていたという現実があったのである。こうしてケインズは新古典派の自由放任による投資・貯蓄・利子率決定理論を否定し、人為的に利子率に介入することで投資量を増やし、完全雇用を維持させる正当性であった。ただし、これは国際貿易を考えない閉鎖体系を前提としていることも忘れてはならない。
繰り返そう、ケインズは金本位制の下で発行に限度がある貨幣制度において非自発的失業が生じているならば、管理通貨制度を導入し、貨幣を潤沢に供給し、利子率を低下させる。つまり政府の公開市場操作を行うことで設備投資を刺激するか、政府が国債を発行し公共投資による有効需要増加を狙ったのである。後に発生するであろうインフレーションに対しても知性によってコントロールしようと考えたのである。
本書によるとケインズは、平和にとって好ましい経済制度は各国が国内において産出高の水準を引き上げ、雇用を改善することが可能であることを示した としている。そして国際的に自国の経済問題を自国で解決できることを理論的に示したのである。そのことが行われるならば国際的紛争は取り除かれると説いたのである。ケインズは第一次世界大戦のような事態が起きるのかを考えた。もし古典派経済学のように自由放任主義を採用し、金本位制度を継続するならば、一国の不況に対処する道は輸出量の増大と輸入量の制限に他ならない。これによって海外から金を流入させることで貨幣量を増やし、金利を引き下げることが出来るし、民間投資を刺激することが期待できるのである。しかし、一国の貿易黒字は他国の貿易赤字であり、利子率の騰貴を起こし逆に有効需要の減少を招く。海外市場による国内し経済の繁栄は近隣窮乏化政策であると説いたのである。これこそケインズ一般理論の政策的帰結である。
古典派の所得と利子率の絶対不可侵を打ち破り、ビルトインスタビライザーと呼ばれる政策を提示したことにケインズの経済観念の意義があるだろう。これは経済学の立場を越えて検討されなければならない点である。 -
¥105
伊東光晴の作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。







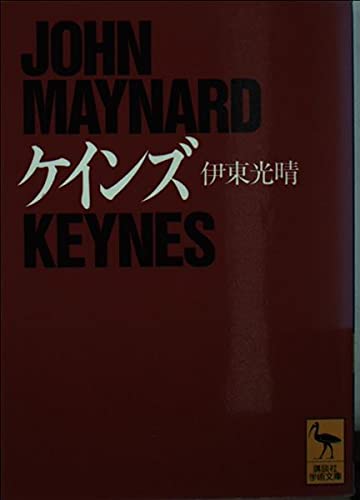



 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 



















![みすず 2018年 02 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41sGlH7ySeL._SL160_.jpg)






























