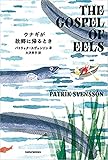- Amazon.co.jp ・本 (272ページ)
- / ISBN・EAN: 9784105072414
作品紹介・あらすじ
ウナギの旅は、人生の旅だ。34カ国で翻訳の世界的ベストセラー。アリストテレスの時代から人々を魅了してきたウナギの生態。彼らはどこから来てどこへ行くのか。今なお謎に包まれたウナギの一生を解き明かしつつ、謎に挑んだ科学者、ウナギと生きる漁師、幼き日の著者と父とのウナギ釣りの思い出を縦横に語り、我々に「生きることの意味」を問いかける。圧倒的な評価を得たスウェーデンの傑作。
感想・レビュー・書評
-
ヒトがこの世に現れたときよりもさらに昔から、つつましく生を繰り返してきたウナギ。故郷に帰る、という本能は、誰に教えられたものでもないけれど、それはウナギの遺伝子に脈々と受け継がれていて、彼らはそれを知らずに生きている。
故郷に帰る、という行動について、サケと比較して論じているが、進行方向は海→河→海であり、これはサケと真逆。しかも、時間の概念がまた違いすぎるくらいに違う。
ヒトと他の生物とでは何が大きく違うか、というと、私はコミュニケーション手段(会話・書物)だと考えていた。
でもわからなくなってきた。
書物や会話により効率よく、深く他人に伝えることができるのがヒトである。
優れていると思っていた。
もちろん、これはヒトの驕りである。言語や文字によらない伝達手段(たとえば、樹木にも伝達手段・ネットワーク(「樹木たちの知らぜらる生活」参照)、これはヒトのコミュニケーションを超えるものかもしれない)が存在する。
ウナギは、親から「河に行って、そこで暮らせ」、とか「最後にサルガッソーに戻ってこい」、とか教わるわけではない。そこが驚きである。教わらない、ということは、自分がこの先どうなるかを(基本的には、一寸先もまったく)知らない、ということだ。明日のことも、ニュースも何も知らない中で決断する。
本能と遺伝子、それに我々の知らないところのコミュニケーション手段により、あるとき(それは数十年後だったりする=これがサケと違うところ)思い立って、サルガッソー海域に行こうと思い立つ(どうして?)。
それはきっと突然なのだろう。それからは、なんと食べないで泳ぎ続ける。
生きる目的は何だろう。食べることでも、娯楽でも、なんでもない。泳いだ先に何があるのか知らない。行くことだけを目的に9000キロ?も泳ぎ続ける。
そして、そこに到着したとき、終わりを迎える。
ウナギは永遠ともいえる、100年前後を孤独の中で生きる。
そんな中で、一人でサルガッソーに行こうとおもうだろうか? 今の安住の地を捨てて? コミュニケーション手段を持っているのだろうか、とおもったのはそこである。
そして、彼らば突然サルガッソーに終結する。
そこに仲間がいる。
私たちの知らない、ウナギネットワークがあるとしか思えない。樹木ネットワークのように。
何千万年も河とサルガッソーを行き来してきたウナギ。
そんな彼らの住処を、たかだか200年くらいで破壊し、絶滅に追いやろうとしているヒトはなんだろう。
ヒトなんて、ちっぽけな存在かもしれない。
長い時間をゆったりと自然に任せて生きている彼ら。
美しいとおもった。
ただただ、邪魔しないであげたい。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
ウナギを巡って、アリストテレスもフロイトも頭を悩ませた。謎を追いかけたいあらゆる地球上の知識人を翻弄し続けてきた、魚なのか何なのか分からないこの生物にこだわる一冊。
北欧のジャーナリストが世に問うたこの本は、基本的には「環境問題」を考えさせる本であり、もはやその手の話題の多さに閉口させられる現代人の我々だが、がっつりこの世の悪業を糾弾するタイプの本ではなく、ほどよく文学的あいまいさが同居しており、読ませる。
ウナギがヌルヌルと人間たちを翻弄する姿も相まって、むしろおかしみとともに最終ページを閉じることになる。 -
スェーデンのジャーナリストが鰻の生態についてをまとめた作品。農場で育った主人公の父親との鰻にまつわる思い出と鰻に関するレポートが交互に出てくる構成。一見して鱗もなく魚か動物かもわからない、そして生殖器官も分からない鰻について、今分かっているとされていることがどのような経緯を辿って判明したのか、ということが一方のストーリーでもう一方では肉体労働者である父親との鰻に纏わる思い出が語られている。鰻が好物で煮たり焼いたりして食べていた父親と異なり作者自身は食物としてそんなに好んで無さそうなところも面白い。最もそのまんまぶつ切りにしてフライパンで焼いたりするだけの調理法で全く美味そうに思えないのだが…。それにしても鰻のことを知ろうとしてきた人類の、というか西欧の人々の歴史は興味深い。今でこそヨーロッパやアメリカの鰻はサルガッソー海付近で産まれ、親の育った川を遡って暮らし、また産卵のために海に帰っていく、ということがわかっているものの生殖自体どのように成されているかは今以て分からず、産卵後の成体もいまだ発見されていないのだという。アリストテレスは泥から忽然と誕生すると説き、長らくそれが定説だったらしい。第一次大戦を挟んでなぜか鰻の産卵場所を突き止めようという情熱に駆られたデンマーク人が、大手ビール会社の娘壻という財力もあって20年に渡り大西洋で鰻の稚魚を採り続け最小のものが採れたところがサルガッソー海近辺、ということなのだという。ニホンウナギはマリアナ海溝近辺で産まれる、ということだけは同様にわかっているが同じく細かな生態はわかっていない。そもそ産卵のシーンも誰も見たことがないというまだまだ謎の生き物。ここに書かれている西欧の食べ方を見るといかにも不味そうで脂分目当ての労働者の食べものというのが一般的な評価らしい。それ故にたぶんそこまで危惧していないのでは、という気がした。個人的には絶滅危惧種なのでいっときは食べないようにしようと思ったのだけど食べなくなる→無関心→絶滅のほうがシナリオとしてはあり得る気がしたので食べることにしたが本作読んで方針転換は間違っていないと思った。高くて手が出ないけども(笑)
-
●うなぎは50年くらい生きる。
●繁殖思い立ったら体が変化する。生殖器官が発達し、ヒレが長くなる。消化活動が停止し、胃袋が消滅する。これから先は必要なエネルギーは全て体に蓄えられた脂肪に頼ることになる。
●フロイトはうなぎの解剖を熱心に行ったが、どこにも雄が存在しない。
●デンマークの海洋生物学者ピーターセンは、黄うなぎが銀うなぎに変態することを見つけた。
● 1932年の秋、大学院で海洋生物学の研究を始めたばかりのレイチェル・カーソンは、研究室の角の大きな水槽でうなぎを飼育していた。うなぎが塩分濃度の変化にどう反応するか調べたいと考えていた。
●サルガッソー海に向かおうとしているうなぎの調査。最も若いものは8歳、最年長は57歳。相対年代が同じにもかかわらず、最年長のうなぎは7倍の年月を生きていた。
●追跡調査の結果。渡り鳥飛行機の旅とは違ううなぎの旅。すべてのヨーロッパうなぎは、中間地点であるアドレス諸島周辺のどこかで集合し、そこから先は、より密集した隊列を組んでさらに西へと向かいサルガッソー海を目指す。
●北海道大学が人工的な孵化に成功して生まれた柳の波野ようなレプトセファルス幼生たちは、何も食べず餓死する。
30年後ようやく18日生きながらえさせることに成功。 -
ウナギの生態についてのサイエンス本かと思いきや、文学作品のような語り口で生と死について問いを投げかけられた。しかしウナギが食べたい。
-
久々に面白くてためになる、サイエンスノンフィクション系の本に出会えて感謝しています。まさに帯にあるように「アリストテレスの時代から、不思議な生態で人々を魅了してきたウナギ。彼らはどこから来てどこへ行くのか?今なお謎に包まれたウナギの一生は、我々に『生きることの意味』を問いかける。」です。レイチェル・カーソンの著作に関する話が良かったです。
-
土用の丑の日に思い出し、てわけでもないが、文庫が出たので積んでた単行本を慌てて読む。
読んでると鰻を食べたくなる。
馴染み深い魚なのに、その正体は謎に充ちみちている。
そもそも魚なのか?彼らはどこから来てどこへ行くのか?
ウナギの辿る道のりは、私たちの起源や、宇宙の謎を探る冒険に似ている。
アリストテレス、ジークムント・フロイト、レイチェル・カーソン。みんな魅了された。
作者の人生、父との想い出、父のルーツ。それらがウナギ研究の歴史と交互に描かれる。
極上のサイエンス・エッセイ、いやこれは歴とした文学であろう。 -
なにかの書評でみて気になっていた本。
ウナギという生物の魅力、人間からみたウナギという生物に関する眼差しを感じた一冊。




 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :