- Amazon.co.jp ・本 (384ページ)
- / ISBN・EAN: 9784152100160
作品紹介・あらすじ
出自に関係なく、人は自らの努力と才能で成功できる――能力主義(メリトクラシー)の夢は残酷な自己責任論と表裏一体であり、「勝者」と「敗者」の間に未曾有の分断をもたらしている。この難題に解決策はあるのか? ハーバード大の超人気教授の新たなる主著
感想・レビュー・書評
-
「自己責任」という言葉が嫌いだ。
自らの恵まれた境遇に無自覚な人がその言葉を使うときは特に。
実力も運のうち。タイトルからして我が意を得たりの本書。
行き過ぎたメリトクラシー(功績主義、能力主義)の罪を説く。
頑張っているのは認めるけど、もっと謙虚にね。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
【感想】
トランプ当選後、彼を支持していた白人労働者にキャスターがインタビューを行っていた。
テレビカメラを前に興奮気味に話す彼に投げかけられた、「何故トランプに投票したのか?」という質問への答えが、私の中で強く印象に残っている。
「トランプだけが、俺たちの話を聞いてくれる」
その言葉は、分断の原因をこの上なく端的に説明してくれていた。
現代社会の根幹を成す学歴主義――勉強さえしっかりすれば誰でも成功できるという信仰――が、実のところ富める者をさらに裕福にしているだけだということは、今や広く知られる事実である。
しかし、かといって全ての大学入試をくじ引きで行うわけにもいかない。万人が平等の所得を得られるよう、ランダムに職業を割り当てるわけにもいかない。
民主主義社会においては一定の能力主義と格差はつきものなのだ。
では、能力主義のどこが不公平なのだろうか。
それは、能力主義によって格差が生まれることではなく、能力主義世界にいるにもかかわらず、階層間を上がるための努力を重ねても状況が好転しないことにあるのだ。そして、成功者たちが「努力」という曖昧な概念を紋切型に当てはめて、「努力をしたけれども這い上がれなかったのは、努力の量が足りていないからだ」と、各人の事情も知らずに切り捨てることにあるのだ。
努力という言葉は、確かに甘い響きを持っている。
しかし、よく考えてみれば、努力とはなんとも抽象的で胡散臭い概念ではないだろうか?
「才能」と「努力」というのは、本来であれば複雑に絡み合っており、簡単に切り離せるものではない。優秀な成績を収めた者にとっては、どちらが優位に働いたかというのは分からないままだ。
ただし、「敗者が負けた原因」を論じる際には容易に分離できる。「お前が失敗したのは努力が足りなかったからだ」と、簡単に切って捨てることが可能になるのだ。
とすると、「才能」と「努力」をめぐる議論が紛糾し、能力主義を擁護するのに役に立ちそうにない理由というのは、強者側がこの言葉を、自分に都合のよい文脈で恣意的に使っている点にあるのではないだろうか。言いかえれば、自説を補強するためだけに言葉を悪用しておきながら、敗者側の言い分を聞きもせず上から抑えつけていることにあるのではないだろうか。
歴史を紐解くと、こうした「都合のよい言葉」の数々が、労働者に不信感を与え続けてきた。
グローバリゼーションでは、労働環境の複雑化に伴って果たすべきだった「国内労働者の権利保護」を政府が放棄し、「より能力の高い働き手になろう」という言葉で、ツケを労働者側に押し付けていることをごまかしていた。
また、リーマンショックで銀行に救済措置を行ったときの「規模が大きすぎて潰せない。公的資金を注入せざるを得ない」という言い訳は、それほどまでに脆弱化したシステムにメスを入れずに放置してしまった政府の責任を、債務者のリテラシー不足とすり替えてしまった。
結局のところ、エリート層と政府は、労働者の話など聞かず、自分に都合のいい文脈で言葉をすり替え続けていたのだ。
こうした積み重ねが労働者の怒りを買い、トランプを勝利に導いた。
彼らにとって「話を聞いてくれる人」は、今までどこにも存在しなかったのだ。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【本書の概要】
能力主義的な信念は、連帯をほとんど不可能なプロジェクトにしてしまう。われわれはどれほど頑張ったにしても、自分だけの力で身を立て、生きているのではないこと、才能を認めてくれる社会に生まれたのは幸運のおかげで、自分の手柄ではないことを認めなくてはならない。
消費者的共通善ではなく市民的共通善が、機会の平等ではなく条件の平等が必要だ。
サンデルの主張は次のとおり:大学入試については、社会階層別アファーマティブ・アクションと適格者のくじ引きによる合否決定を行う。また、名門大学における道徳・市民教育を拡大する。労働や福祉については、賃金補助と消費・富・金融取引への課税を行う。
これを通じて、社会的に評価される仕事の能力を身に着けて発揮し、広く行き渡った学びの文化を共有し、仲間の市民と公共の問題について熟議する社会のあり方を目指す。
【本書のまとめ】
1 能力への入札
勝者は自らの才能と努力によって成功を勝ち取ったと信じたがる。裏を返せば、失敗すれば、その責めを負うのは自分だけなのだと信じ込んでしまっている。
この考えが市民感情を蝕んでいる。自分のことは自分で作り上げるという考えが強くなるほど、感謝の気持ちや謙虚さを身につけるのはますます難しくなるからだ。
2 勝者と敗者
労働者階級と中流階級の多くの有権者がエリートに感じている怒りを駆り立ててきたものはなんだろうか。それは不平等自体よりも、その裏にひそむものであった。
不平等の拡大を受け、主流派の政党と政治家は、労働者の再教育や人種・ジェンダーの壁を取り除くことで対処してきた。これは「機会のレトリック」であり、そのレトリックを支える考えは、「機会を与えさえすればみな努力する」「やればできる」というものだった。
そのレトリックはもはや破綻している。現代の経済においては、生まれによる格差が機会の平等を凌駕している。貧しい親のもとに生まれた人は大人になっても貧しいままなのだ。
そしてなにより、例え完全な能力主義が実現したとしても、正義にかなう社会となるかどうかは疑わしい。自分の才能のおかげで成功を収める人々は、同じように努力していながら、市場がたまたま高く評価してくれる才能に恵まれていない人々よりも、多くの報酬を受けるに値するのだろうか?
能力主義的なおごりは、勝者の次のような傾向を反映している。すなわち、彼らは自らの成功の空気を深く吸い込みすぎ、成功へと至る途中で助けとなってくれた幸運を忘れてしまうのだ。
同時に、能力主義は敗者に屈辱を与える。能力主義社会の中で低い地位にあることは、100%自己責任として勝者から見下されることになる。
トランプを代表するナショナリズム政治に勝利をもたらしたのは、この屈辱が復讐心に転化して人々を動かしたからなのだ。
3 「能力の道徳」の歴史
かつてのカルヴァンやピューリタンにとって、神の目から見れば誰もが同じように卑しい存在であった。誰もが報いを受けるに値しないのだから、救済は神の恩寵にすがるしかなかった。
しかし、リベラル化した神学者が自らを救う人間の能力を強調し始めると、成功は個人の能力と摂理による予定の収斂を意味するようになった。信仰が経済的不平等を宗教的に承認する手段となったのだ。
「繁栄の福音」という言葉がある。「神は信仰に対して富と健康をもって報いる」とする考えのことだ。
この言葉は裏を返せば、世に起こるあらゆることは、われわれの生き方への報酬あるいは罰である――われわれの偉大さは善良さに由来し、今苦しんでいるものはそうしなかった罰が下っている――という考え方なのだ。
4 出世のレトリック
能力主義の専制を打破するということは、能力を考慮せずに仕事や社会的役割を分配すべきだという意味ではない。そうではなく、成功についてわれわれが抱く概念を再考し、頂点にいる者は自力でそこに登りつめたのだとするうぬぼれに疑問を呈しなければならないのだ。
能力主義にとって成功は美徳だ。われわれは自分の運命に責任があり、わたし自身の価値は自力で手に入れたものに値しているという考えが強まっている。頂点を占める人々も底辺に甘んじる人々も、自分のいるべき場所に立っているという風潮がある。
加えて、機会に対する不公平な障壁を取り除きさえすれば、誰もが才能と努力の度合いによって自分の居るべき場所に到達するはずだという考えも一般的になっている。同様の理論は「能力」の観点のみならず「責任」の観点にも適用されている。
これが出世のレトリックであり、オバマまでの米国大統領が揃って口にした概念である。
しかし、能力主義エリートは次の点に気づかなかった。それは、底辺から浮かび上がれなかったり、沈まないようもがいている人々にとって、出世のレトリックは将来を約束するどころか自分たちをあざ笑うものだったという事実だ。
能力の専制の土台には一連の態度と環境があり、それらが一つにまとまって、能力主義を有害なものにしてしまった。次の3つが具体的な害だ。
①自己責任論が人々の連帯を蝕んだ。
②大学の学位の過度な尊重が学歴偏重の偏見を生み出し、大学に行かなかった人々を貶めた。
③社会的・政治的問題を最もうまく解決するのが、高度な教育を受けた価値中立的な専門家だと主張することが、民主主義を腐敗させた。
多くのアメリカ人は、賢明に努力する人々が出世できる「アメリカン・ドリーム」を信じている。しかし、今日の世界では、アメリカ本国にそのチャンスは少なく、北欧諸国や中国のほうが、経済的流動性(階層移動の確率)が高く、アメリカン・ドリームを体現できる環境にある。
5 学歴偏重主義
学歴が武器となる現象は、能力や功績がいかにして一種の専制となりうるかを示すものだ。
この数十年のあいだに、リベラルで進歩的な政治によってなされた基本的主張は、グローバル経済が、まるで人間の力の及ばない事実であるかのように、どういうわけかわれわれにのしかかり、頑として動こうとしないというのだ。政治の中心問題は、そうした事態をいかにして変革するかではなく、いかにしてそれに適応するかであり、低所得労働者の保護ではなく安楽死であったのだ。
状況を変えるための具体的な方法として提案されたのは、彼らもまた「グローバル経済の中で競争し、勝利を収める」ことができるようにすることだった。
高等教育の間口を広げようとしたのである。
しかしそれは、グローバル経済の中で過酷な状況に出くわしてしまう責任は、大学の学位を持っていない人「自身」にあると暗黙のうちに認めている。
現代の容赦ない学歴偏重主義は、労働者階級の有権者をポピュリストや国家主義者の政党へと走らせ、大学の学位を持つ者と持たない者の分断を深めることとなった。
しかし、学歴偏重主義のなにがいけないのだろうか?高い教育を受けた者に政府を運営させることは、彼らが健全な判断力と労働者の暮らしへの共感的な理解を身に着けている限り、一般的には望ましいと言える。ただ、歴史が示すところによれば、一流の学歴と、実践知や共通善を見極める能力のあいだには、ほとんど関係がない。
それどころか、欧米においては、低学歴の人々も高学歴のエリートたちも、「低学歴者」に――違う人種の人間や性的マイノリティよりも強く――否定的態度を示すことが分かっている。いい点を取る能力と、政治的判断能力や道徳的人格の高さは関係ないのだ。
6 成功の倫理学
実際問題、完全な能力主義社会が実現し、すべての子供に平等な機会が与えられたとき、正義に叶う社会が成立するのか?
それはいささか疑わしい。まず、能力主義の理想にとって重要なのは流動性であり、平等ではない。格差は問題ではなく、自身の努力や堕落によって階層間の移動が容易に起こり得ることを望んでいるのだ。
ハイエクは「功績」と「価値」を明確に区別している。ある人が優れた仕事をしたからといって、その人の価値自体が高いわけではない。たまたま社会が評価してくれる才能を持っていることは、自分の手柄ではなく、道徳的には偶然のことであり、運の問題なのだ。
ロールズは、「格差原理」によって、才能ある者にはその才能を育て発揮するよう促すとともに、そうした才能によって市場で獲得される報酬はコミュニティ全体と分け合うべきだと主張している。
両者はともに、経済的報酬は人々が値するものを反映すべきだという考え方を拒絶している。
「懸命に働き、ルールを守って行動する人々は、その才能が許す限り出世できなければならない」。能力主義エリートはこのスローガンを唱えることにすっかりなれてしまったので、そのスローガンがグローバリゼーションについていけなかった人々への侮辱を内包していることに気づかなかったのだ。
7 高等教育がいかにして選別装置と化したか
コナントは、高等教育の機会の平等化に力を入れていた。しかし、将来の市民全員を政治的民主社会の一員として教育することが大切だと考えてはいたが、公立学校のそうした市民的目的は二の次で、重視したのは地頭のいい学生へ奨学金を貸し付けるという「選抜制度」だった。彼が求めていたのは平等の解消ではなく、ヒエラルキーの位置を流動的に変えられるシステムだった。
彼の理念は、大学を支払い能力による入学から能力にもとづいた入学に変えるというものであり、実際、大学教育は彼の理念どおりに方針転換した。しかし、100%彼が期待したような展開にはならなかった。
①SATの得点は富に比例している。
②能力主義が不平等を固定化している。
③能力主義時代の高等教育は社会的流動性を生まず、特権階級の親が子に与える優位性を強化している。
しかし、勝者が生き残るトーナメント制の高等教育のどこが好ましくないのだろうか?
その理由は2つある。第1に、不平等を拡大したことだ。第2に、勝者に大きな犠牲を強いることだ。
名門大学のキャンパスには裕福な家庭の子女が圧倒的に多いことを考えれば、勝敗はあらかじめ決まっているようなものだ。ところが、熾烈な受験競争の中にいると、合格は個人の努力と学力の成果だとしか考えられない。こうした見方が、「成功は自らの努力の賜物であり、自力で勝ち取ったものである」という信念を芽生えさせる。
こうした大学受験への(たいていは大学入学後も続く)選別と競争の消耗戦のサイクルが、学生にかつてないほどの精神的苦痛を与えている。彼らは「ひそかに蔓延する完璧主義という病」を患っているのだ。
現在の大学入試制度に対するサンデルの意見は主に次の通りだ。
・貧困家庭へのアファーマティブ・アクションを実施する
・標準テストの受験を必須としない
・SATへの依存を減らすとともに、レガシー出願者、スポーツ選手、寄付者の子どもなどの優遇をやめる。
・ある程度適格な受験生の中からくじ引きで入学者を決める(能力を資格の一基準として扱うだけで、最大化すべき理想とは捉えない)。
8 労働を承認する
能力主義の時代は、働く人々を陰険なかたちで傷つけてきた。労働の尊厳を蝕んできたのだ。だからこそ、グローバリゼーションがもたらす不平等が多くの怒りと反感を生んだのだ。
繁栄する人々がいる一方で、グローバリゼーションから取り残された人々は悪戦苦闘しただけでなく、自らの労働がもはや社会的評価の源ではないとも感じてきた。社会の目に、そしておそらく自身の目にも、彼らの労働は共通善への価値ある貢献のようには映らなくなった。
経済的懸念は、自分の懐にあるお金だけに関わるわけではない。経済に果たす役割が社会の中の自分の地位にどう影響するかにも関わる。言い換えれば、経済においてわれわれが演じる最も重要な役割は、消費者ではなく生産者としての役割なのだ。
労働の尊厳について議論することが必要だ。共通善への真に価値ある貢献とは何か、市場の裁定のどこが的はずれなのかについて、慎重かつ民主的な考察を促す方法を論じ、規定することが求められている。
また、税負担を労働から、消費と資産と金融取引に移すことも必要だ。
そして、機会の平等を、広い意味での「条件の平等」に変えていくことも大切である。社会的に評価される仕事の能力を身に着けて、発揮し、広く行き渡った学びの文化を共有し、仲間の市民と公共の問題について熟議することによって、万人がまともで尊厳ある暮らしができるようにしていくことが求められている。 -
サンデル先生の講義シリーズが好きで、今回は著作に手を出したのだけど、例を変えながら同じ所にぐるぐる戻ってきているみたいに思えて、読み進めていくのに時間がかかった……。
能力主義(功績主義)つまり「努力と才能で、人は誰でも成功できる」という激励の言葉に、違和感を感じるだろうか。
偏差値的に高い学校を目指して努力を重ね、ゆくゆくは有名な企業に入り、高額なお給料を貰うというストーリーは、ある意味平凡なものだ。
けれど、努力を重ねる以前に、生まれている前提条件、生育環境で既に差はついている。
誰もが努力をすれば成功するのではなく、成功する可能性自体、生まれた時に決まっていると言えるのかもしれない。
そんな前提を無視して、地位と名誉を得た人は、その能力を「正しい」ものであるかのように評価されている。果たして、そうなのだろうか。
職業の価値や給料の多寡、そして自身の能力は、ある意味、単なる偶然から成り立っている。
そして、自身が進んできた道は、自身の功績によるものだ、とだけ思うのではなく、偶然が作用した結果だと思うことで視界は広がる。
富める者がますます富み、貧しい者は「自身の能力」を呪うしかない社会を覆すには。
サンデル先生の共通善の在り方は面白い、しかし、私たちはそこに戻っていけるのだろうか。
巻末の本田由紀先生の解説も、非常に面白い。
「日本は「メリット(功績)の専制」というよりも、「能力の専制」と言える状況にある。些末な違いと考える読者もいるかもしれない。しかし、人びとに内在する「能力」という幻想•仮構に支配されている点で、日本の問題のほうがより根深いと筆者は考えている」 -
-
 【本棚を探索】第21回『実力主義も運のうち 能力主義は正義か?』マイケル・サンデル著/濱口 桂一郎|書評|労働新聞社
【本棚を探索】第21回『実力主義も運のうち 能力主義は正義か?』マイケル・サンデル著/濱口 桂一郎|書評|労働新聞社
https://www...【本棚を探索】第21回『実力主義も運のうち 能力主義は正義か?』マイケル・サンデル著/濱口 桂一郎|書評|労働新聞社
https://www.rodo.co.jp/column/131006/2022/06/09
-
-
【はじめに】
『これからの「正義」の話をしよう』が十年ほど前にベストセラーになったハーバードで政治学の教鞭を取るサンデル教授が、グローバル資本主義の「能力主義」が生む弊害について論じた本。2016年のトランプ大統領の誕生やブレグジットの成立の社会的背景をこれまでとは違う視点で指摘しており、『これからの「正義」の話をしよう』や『ハーバード白熱教室』ほどではないが、日本でもそれなりに売れてベストセラーとなっている。
その内容には反対や留保を付けたがる意見も多いと思われるが、少なくとも謙虚に耳を傾けるべきものが多い。
原題は、”The Tyranny of the Meritcracy”だが、『実力も運のうち』という邦題は出色の出来だと思う。「運も実力のうち」という日本語にうまく掛けた上、本の内容・主張を端的に表現しているし、キャッチ―でもある。副題として添えられた『能力主義は正義か?』も原題の意図を汲んで、著者の主張を明確に伝えるという役割も果たしていてよいと思う。これだけ成功していると思える邦題訳も珍しいかと。
以下、少し長くなってしまったが、ざっと見ていきたい。
【概要】
■ ドナルド・トランプの勝利
トランプが2016年の大統領選を事前の想定を覆して制したとき、さらにはそれ以前にトランプが人気を集めて共和党の予備選を勝ち上がったときから、その理由を多くの人、トランプを支持した人も含めて、おそらくは理解していなかった。少なくとも自分は理解できていなかったその理由を本書は明確に示している。それについて、自分を含む多くの人びとは単に気づこうとしていなかったのかもしれないし、何かがそれを気づくことを妨げていたのかもしれない。
その理由とは巷間そう思われている経済的な不平等や貧困ではなかった。本書によれば、少なくともそれだけではないし、それが主な理由ではないという。彼らの不満の主な理由は、不平等であるがゆえに彼らがエリート層や民主党政治家に見下されていると感じたからだという。そこにあるべき「労働の尊厳」が奪われたことによる怒りがその源であった。そう指摘されると、おそらくはそうだったのだろうと納得がいった。
考えてみれば、不平等の拡大を正当化するためにしきりに持ち出された「トリクルダウン」も随分と見下した考え方である。誰もおこぼれに預かりたいわけではないし、少なくともおこぼれで生かされているなどと他人から思われたくないのは当然だろう。
この話を読んでいたとき、少しほろ苦さとともに思い起こした動画がある。当時、さすがオバマは違うといたく感心した動画だ。
”Slow Jam the News with President Obama”
https://www.youtube.com/watch?v=ziwYbVx_-qg
その年の秋に大統領選挙を控えた2016年6月、トランプの勢いがいよいよ無視できなくなっていた中で現職大統領であるオバマが有名なトークショーに登場し、定番コーナー”Slow Jam the News”で、二期に渡って務めた大統領としての成果をバンドの音に乗せて歌い上げている。このとき、オバマも数か月後にヒラリーがトランプに負けるなどとは思っていなかっただろう。気候変動対策、オバマケア、同性婚、キューバ、イラン核合意、TPPなど ―― いずれも歌の中でその名前を挙げることで笑いが起きたトランプによって後にズタボロにされた政策が並ぶ。トランプ支持者は、それがオバマ政権が推し進めた政策だからというだけではないだろうが、喝采を送ってトランプを称えた(ように思われた)。
今見返すと、この動画には民主党やエリート層が持っていた驕りの態度というものが詰まっている。オバマはたくさんの仕事を作ってきた、と胸を張り、”He put us back to ... work, work, work, work, work♪”と歌う。しかし、トランプを支持していた人びとが求めていたのは単なる仕事ではなく棄損されてきた「労働の尊厳」だったことをわかっていなかった。民主党に必要なことは、Netflixのドラマをもじって”Orange Is NOT the New Black”などとオバマがうまいことを言うことではなかった(オレンジはトランプのイメージカラー)。オバマやヒラリーなど民主党員や支持者の態度は既存の支持者をさらに惹きつけることはしたが、彼らに反する人びとからはさらなる反発を招くだけだった。そのアピールは結局は投票行動を変えることなく、その分断をますます深くするだけだった。彼らは、与えた成果を誇るのではなく、謙虚になって感謝を口にするべきだったのに。そして、そのことを誰もわかっていなかったのが大きな問題だったのだ。そういったことが本書では事例を挙げて繰り返し説明される。その原因が原書のタイトルにもなっている「能力主義の専制」であることが説明される。
■ 能力主義の専制 (The Tyranny of the Meritocracy)
主流の政党や政治家を含めて、いわゆる成功を勝ち得た人びとは、自分たちの側にはいない人びとの不満が何であるかに気が付かなかった。経済的不平等があることは認めつつ、それを克服するための機会はこのアメリカでは誰しもに平等に開かれており、その気があれば誰でも同じ立場になることができるのですよ、と言うことでよしとしていた。その能力主義のテーゼである出世と責任のレトリックは、能力主義社会における成功者が必然的に持つことになる観点とマッチし、成功に手が届いていない人に対してではなく、自らに対して非常に心地よい言葉であったために、そのことに疑問を差し挟むことができなかったのだと次のように指摘する。
「「懸命に働き、ルールを守って行動する人びとは、その才能が許すかぎり出世できなければならない」。能力主義エリートはこのスローガンを唱えることにすっかり慣れてしまったので、それが人を鼓舞する力を失いつつあることに気づかなかった。グローバリゼーションの恩恵を分かち合えない人びとの怒りの高まりにも鈍感で、不満の空気を見逃してしまった。ポピュリストによる反発は彼らを驚かせた。能力主義エリートは、自らが提唱する能力主義社会に内在する侮辱に気がつかなかったのだ」
それが、トランプが選挙を制することを許した理由だった。なぜなら、成功者はあまりにもそれが自分にとって当たり前であるがゆえに違う考え方があるということに気が付かなかったからだ、という指摘だ。さらに踏み込んで言えば、それに気付きたくなかったのだ。
「不平等な社会で頂点に立つ人びとは、自分の成功は道徳的に正当なものだと思い込みたがる。能力主義の社会において、これは次のことを意味する。つまり、勝者は自らの才能と努力によって成功を勝ち取ったと信じなければならないということだ」
成功者は能力社会の正当性を心から信じるあまり、反対側から見ると自分たちの主張がどのように見えるのかを考える想像力が欠けていた。想像することの必要性を感じることができず、想像するという発想すら妨げられていたのだ。サンデルの次の指摘はおそらく正しいと思う。自分は納得した。
「底辺から浮かび上がれなかったり、沈まないようもがいている人びとにとって、出世のレトリックは将来を約束するどころか自分たちをあざ笑うものだったのだ。トランプに一票を投じた人たちには、ヒラリー・クリントンの能力主義の呪文がそんなふうに聞こえたのかもしれない。彼らにとって、出世のレトリックは激励というより侮辱だった」
この行き過ぎた能力主義の弊害の指摘がこの本の主題である。サンデルは、この「能力主義(Meritocracy)」という言葉を初めて使ったともいわれているマイケル・ヤングが能力社会をディストピアとして描いた1958年の先見性のある風刺小説「The Rise Of The Meritocracy」の紹介や、マックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で指摘した神の恩寵の変質、ハイエクとロールズという対極的な主張を持つ思想家の能力主義に対する意外な共通性の分析、などを通して能力主義の課題をしつこくあぶり出していく。
■ 大学受験競争の過熱と「くじ引き」の意義
そのような能力社会において、教育の重要性を強調することは、能力主義の正当性を支える上での肝になっている。貧困家庭の学費無償化や奨学金の強化は、経済的な理由で大学進学をあきらめるようなことがないようにという正しそうに見える理由から、機会の平等性を担保することで逆に成功者自らの現在の状況を平等な競争と努力の結果であると正当化することに貢献している。
実態としては、裕福な家庭の子息は受験競争において大いに優位に立っている。この本によると、アイビーリーグの学生の2/3あまりが所得規模で上位20%の家庭の出身であり、プリンストン大学とイェール大学にいたっては、国全体の上位1%出身の学生の方が、下位60%出身の学生よりも多い状況であるという。つまり、個々人の努力以前にどういう家庭に生まれたかということが、上位校に行くことができるかどうかを大きく左右しているのだ。しかしながら、成功者はその「幸運」を簡単に忘れてしまう。
貧困家庭から出てイェール大学を卒業して成功をつかんだ『ヒルビリー・エレジー』の著者とその物語は、貧困と尊厳の喪失に喘ぐ人びとの希望などではなく、言い訳を封じてしまう忌むべき存在であるのかもしれない。
個人的には、アメリカの受験戦争がいまや日本よりも激しくなっているということに驚いた。「いまや学歴授与機能が肥大化し、教育機能を圧倒しているのだ。選別と競争が、教育と学習を押しのけてしまっている」とのサンデルの指摘は、過去の日本と同じだ(今はずいぶんとマシになっているように感じるが)。昔は、日本の大学は入るのは難しく出るのは易しいので、大学がレジャーランドになるとして批判され、一方でアメリカの大学は入るのは易しいが、出るのは難しいので皆必死で勉強すると持ち上げられていたのだが。韓国や中国でも受験競争は熾烈を極めるとも聞くが、よい大学が出世のための切符だといったん認識されると、その社会や文化の違いに関わらず同じ状況に収斂するものなのかもしれない。大学の学位、特に上位校のそれは、規律に従って受験を通りぬけることができる能力を有している「シグナル」として機能しており、採用する企業側がその人の能力を評価する手軽で効率的な指標のひとつとなっているのだ。長らく維持されていた大企業での終身雇用の神話が崩れて、東大や京大に行っても成功するとは限らないよ、という必ずしも妥当かどうかはわからない認識が広まりつつある日本は逆に受験競争の熾烈さは緩和されているのかもしれない。
本書は、アメリカで起きた大規模で組織的な大学入試の不正問題から始められている。その事件が能力主義がいかに社会に根深く浸み込んでいるかを示しているからである。サンデルはあるべき大学教育と過熱する受験競争について詳しく持論述べるのだが、それは彼が教育を能力主義へ対抗する際に、アプローチすべき重要な標的のひとつであると認識しているからだろう。
サンデルは大学入試について次のことを提案する。
1. SATへの依存を減らす
2. レガシー出願者、スポーツ選手、寄付者の子どもなどの優遇をやめる
3. 一定の基準を満たした層でのくじ引きの採用
なるほど、1.や2.は、SATが共通試験に当たるとすれば、東京大学が堅持していた入学試験方針ではある(どうやら2016年から推薦入試を始めたらしいが)。ただ、よい問題が多いとの評価もある二次試験一発勝負は能力主義と成功者の驕りをさらに高めるようにも思うが。サンデルは、よほど2.の弊害が大きいと感じているのだろう。
3.のくじ引きの採用については、おそらく実際に行おうとすると能力主義や平等の観点から大きな反発が想定される。しかし、自分としてはサンデルの意見におそらく賛成である。また、もう少し踏み込んで考えると、能力主義による選抜は大学入試以外の様々な場面で行われているのであるから、受験以外の場面でも採用されてもよい制度ではないかとも思う。例えば、裁判員が抽選で選ばれるのであるから、議員の選出の過程の一部に抽選を取り入れてもよかろう。議員の多様性の確保にもそれは貢献するだろうし、民主主義的概念を絶対的価値と信ずるなら、それにも適うだろう。
くじ引きという仕組みを取り入れることに違和感と嫌悪感を覚えるとすると、それはもしかしたら能力主義の専制の罠にはまっている証拠なのかもしれない。もし、能力主義が必然的に次のような弊害を生み(そうであるように思われる)、また同時に社会から取り除くことが不可能であるのであれば、その課題を解消するためのくじ引きという「仕組み」の導入はもっと真剣に検討されてもよいように思われる。そこには新たな道徳の起源となるものがあるようにも思われるのである。
「頂点に登り詰める人の場合、不安をかき立て、疲れ切ってしまうほどの完璧主義に導き、脆い自己評価を能力主義的なおごりによってどうにかごまかすよう仕向ける。置き去りにされた人には、自信を失わせ、屈辱さえ感じさせるほどの敗北感を植えつける。
これら二つの専制には、共通の道徳的起源がある ―― われわれは自分の運命に個人として全責任を負うという普遍の能力主義的信念だ」
くじ引きは自分の運命は自分の責任だという信念を壊してくれるだろう。そして、日本ではすでに国立小学校の受験においてくじ引きが制度として採用されていることと(目的は若干違っているが、一部の効果は同じものがあると思われる)、柄谷光人という人がNAMという団体で代表者をくじ引きで決定するという試みを行っていたことをサンデルさんには伝えたい。
■ 共通善 (Common Good)について
本書で、”Common Good”を「共通善」という聞き慣れない言葉に訳しているが、「公益」とした方が分かりやすいのではないだろうか。「共通善」とすることで、何らかのこれまでにはない新しい概念であるかのように誤解させ、理解を妨げてしまったのではないか。サンデルはここでそれほど難しいことを言っているわけでも新しいことを言っているわけでもないように思われる。「公益」というより一般的であろう訳語を当てていれば、もっと最後の提言や理念を語ったパートが理解されやすくなったのではないか。
一方、インターネット上のブリタニカ国際大百科辞典で試しに「共通善」を引いてみると、次のように説明されている。
「共同体の成員によって達成すべく合意された普遍的価値ないしは集合的目標をさすが,しばしば支配の正統性の根拠とされる政治思想史上の概念である。中世キリスト教世界では,カトリック信仰の確立とキリスト教的諸価値に基づく社会の安寧が共通善とみなされ,それに合致するかどうかの解釈権は教会のものであった。近代になると,中世的世界観の解体と自由な個人の出現によって,共通善の解釈に新たな問題が生じる。すなわち,それが政治社会全体の利益なのか社会の成員一人一人の利益の総体なのかという議論である。それは,同意を正統性や政治的服従の根拠とする解釈から共通善をへだてる議論でもある。ルソーによる一般意志と全体意志の区別は有名であるが,それはカントや功利主義者の議論を経て,今日においても政治哲学上の大きな論点である」
これを読むと単に「公益」と訳すのもサンデルが伝えようとする大きな何かを落としてしまうような気がする。訳者も悩んだ点だったのだと理解した上で最後の章は読み進めるべきなのだろう。
「だが、共通善に到達する唯一の手段が、われわれの政治共同体にふさわしい目的と目標をめぐる仲間の市民との熟議だとすれば、民主主義は共同生活の性格と無縁であるはずがない。完璧な平等が必要というわけではない。それでも、多様な職業や地位の市民が共通の空間や公共の場で出会うことは必要だ。なぜなら、それが互いについて折り合いをつけ、差異を受容することを学ぶ方法だからだ。また、共通善を尊重することを知る方法でもある」
上記の指摘を読むと、大学受験の仕組みへの提言とされたくじ引きの多様な社会システムへの導入が、何だか「共通善」の実現の鍵になりうるのではないかとも思える。何となれば、サンデルが主張する「共通善」実現への必要条件とすら思えてくる。神の恩寵がかつていた場所に、代わりにくじ引きの恩寵がその場所を見つけるのである。それは極論なのであろうか。
本書は、次のような成功者への呼びかけで終わっている。
「いったいなぜ、成功者が社会の恵まれないメンバーに負うものがあるというのだろうか?その問いに答えるためには、われわれはどれほど頑張ったにしても、自分だけの力で身を立て、生きているのではないこと、才能を認めてくれる社会に生まれたのは幸運のおかげで、自分の手柄ではないことを認めなくてはならない。自分の運命が偶然の産物であることを身にしみて感じれば、ある種の謙虚さが生まれ、こんなふうに思うのではないだろうか。「神の恩寵か、出自の偶然か、運命の神秘がなかったら、私もああなっていた」。そのような謙虚さが、われわれを分断する冷酷な成功の倫理から引き返すきっかけとなる。能力の専制を超えて、怨嗟の少ない、より寛容な公共生活へ向かわせてくれるのだ」
【所感】
すでに言いたいことはここまでに書いてしまっているような気がする。
この本の受け止め方は、読む側が分断線のどちら側にいると考えているのかで大きく違ってくるだろう。サンデル自身は、この本のメッセージを分断線よりも上にいるエリート層に向けて発している。何しろ自身がハーバード大学の教授であり、いつも授業で話しかけているのはエリート層にいるであろうハーバード大学の学生なのだ。このことは、報道ステーションが行ったサンデルへのインタビューの中で明確にコメントしている。
https://www.youtube.com/watch?v=N-HrFRnATTE
(17:55 「そうですね 私のメッセージは 主にエリートや政治家に向けられたものです」 マイケル・サンデル)
ただ、どちらの立場にいようともサンデルがここで指摘する内容は現在のグローバル資本主義社会において非常に重要な指摘だということは言えると思う。
「能力主義の倫理は、勝者のあいだにはおごりを、敗者のあいだには屈辱と怒りを生み出す」ということが必然であるならば、何らかの対応が必要な時期に来ていると思われる。そして、サンデルのその指摘をまず第一に受け止めるべきであるのは、成功を味わっている層なのだ。大学受験競争過熱への対策として提案されたくじ引きの受験に限定しない社会システムへの何らかの導入は試みられてよいのではと思った。それには、本書で論じられた内容や倫理的感覚が広く受け入れらることが必要ではあると思うが。
同じような主張を繰り返す、というサンデルさんのいつもの癖が出ていて長くなってしまうというところはあるが(大事なことなので繰り返し言ってます、ということなのだろう)、多くの気づきを得られた本であった。
-----
『ヒルビリー・エレジー』(J.D.ヴァンス)のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4334039790
『これからの「正義」の話をしよう――いまを生き延びるための哲学』(マイケル・サンデル)のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4152091312
『完全な人間を目指さなくてもよい理由-遺伝子操作とエンハンスメントの倫理-』
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4779504767
『それをお金で買いますか――市場主義の限界』
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/415209284X -
「努力する人は、成功を勝ち取る権利がある。」
これは正しい。がしかし、同じような努力をしても、失敗する人が一定数いるのは何故だろう。それは、成功には、運が絡んでいるからであり、努力に加えて、たまたま運がよかったから成功したというのが事実であり、「絶え間ない努力の末、手に入れた栄光」というものは、実は、脚色された物語なのかもしれない。
「多様性」という言葉のもとに、さまざまな差別を撤廃する動きが生まれた。身分の差別、人種差別、性差別など、「違い」をなくそう、よいものとして捉えようという社会の動きは、より活発になってきているように思える。
しかしながら、それは逆に「失敗の責任は個人に帰結する」という事実が待ち受けている。
例えば、貴族社会の時代では、「生まれ」が強く影響しており、貧しい暮らしをしなければならないのは、自分の身分が低いから、であった。
では、一見さまざまなチャンスに恵まれた現代において、努力したにもかかわらず、自分の思い通りにいかないのは、一体何が原因なのだろうか。
ここに、能力主義の闇の部分があるのだ。
自分が「できないこと」は、自分が「努力してこなかったから」だ、と。
能力主義のメリットは、努力すれば、成功する見込みがあると考えられることだ。
努力次第で、人生は欲しいままにできるという希望は、自分の前にある大きな壁に立ち向かうための、充分な理由になる。
しかし、その壁を越えられなかったとき、能力主義は、あなたに対して牙をむく。「越えられなかったのは、あなたの責任だ。」
自分の人生を振り返ると、思い当たるところは多くあり、「運が悪かったから」と片付けるのは、一種の「逃げ」のようにすら思えてしまう。
この本では、能力主義がどうしてこれほど根強く社会に残っているのか、能力主義は正義か、それとも悪か。ではどうすればよいのかについて、書かれてはいるが、以前の本と同様に、答えは明確には書かれていない。
サンデル教授の本を読むと、なんとなく自分の今のレベルが推し測れるので、定期的に読むようにしている。
再び読み終えたとき、もしかしたら、違った感想を持っているかもしれない。現時点では、ただ、咀嚼するばかりで、追いつくのに必死な一冊であった。 -
やればできるは魔の言葉
やればできるは魔法の合言葉ではなかった?「頑張れば報われる、大切なのは機会の平等」という通説を鋭く指摘し覆す。
※なお私は「やればできる」という言葉自体は好きであり、この言葉を励みに生きている。一方で、この言葉を裏の意味「できないやつ(成功してしない、貧困層)はやってない(努力不足、自己責任)」に捉え、安易に片付けるのは危険という意味で『やればできるは魔の言葉』と表現した。
■概要
能力主義、功績主義の欺瞞を社会、政治、宗教、哲学とあらゆる観点で指摘する。
特に学歴という選別装置が機能不全になっている、過剰な選抜体制になっていることを指摘。
それにより高等教育を受けられない、大卒でない労働者(工場労働者や小売店員ら低賃金の人々)の尊厳が奪われている。しかも彼らは身分制でなく、能力主義によってその職にあるのだから、彼ら自身の選択、原因という屈辱を押し付けてしまっている。世界がますます分断に向かうか、人類が驕りと屈辱ではなく尊厳を回復できるか。まずは能力主義の問題という現状に目を向けることを本書では訴えている。
・アメリカドリームはない
格差が固定されているのは、富の再分配や機会の平等が不十分なだけでなく、機会の平等そのものという考えそのものに欠陥がある。
機械の平等に見えるものも、①実は運によるものが大きいこと、②ニセ実力主義≒身分制の延長(親のコネや寄付)によるゲタ、③アファーマティブアクションなど時代の調整によるものが影響している
・壮大な人生観、社会学、哲学書
本書は心理学にとどまらず、ギリシア哲学、プロテスタントと資本主義(ウェーバー)、大学の歴史、そして近年の2016ポピュリズム政治「トランプ政権誕生&ブレグジット」をふまえて能力主義を捉えている。まさに能力主義(功績主義)により屈辱を浴び、尊厳を奪われた人たちの反乱が2016年の帰結だと。民主党、特にオバマやヒラリークリントンが唱える「機会の平等」に問題があったからこそ、能力主義から漏れた人たちがトランプを支持した。
また一見正義に見える能力主義が形成された歴史が分かる。カトリック=貴族制、身分制、ひいては免罪符による腐敗であり、ネガティブなイメージがあった。一方でプロテスタント=勤勉、平等、自由と発展というイメージだったが、そのProtestantism(それ自体は崇高でも)が資本主義の歪み、行き過ぎた能力主義の源流である。
(参考)
ふろむだ『人生は運よりも勘違いさせる力〜』と少し重なる。こちらは超簡易版で、これはこれでおすすめ。ハロー効果による錯覚資産をどう活かしていけるかを考えられ、まずは心理学の一分野というミクロかつ具体から帰納的に理解するのもあり
■所感
・改めて人生は運
これまで人生は運であり、その運をいかに最大化するか、確率を少しでも高めるかが本人の努力という認識だったが、それも驕りであるのかもしれない。人事を尽くして天命を待つ、の人事を尽くせるのも運なのだと
・『共通善への貢献』に共感した
貧困は貧困で問題だが、やはり共感善に貢献する機会、貢献していることを実家できないことが課題。貧困はUBIや所得調整で解決できるが、共通善への貢献を感じられるようにするには所得調整は必要条件であり、他の要素も必要だと感じた。
具体的な解がある訳ではないが、贈与と感謝だとか文化的な喜びがヒントになるような気がする。そのためにも、自分は何者であり何のために生きるのか、を考えさせる教育(本書内の学歴獲得のための高等教育とは異なる)をあらゆる人々に提供することは大切ではないか?
・難しく読むのに苦労
このような英語の論説は翻訳が難しく、訳の分からない日本語になりがち。その一方で本書の日本語自体は悪くないものの、いかんせん元の英文が抽象概念を説く内容なので、日本語に訳すと難解な文章になりがち。英語力ある人なら原文で読んだ方が理解できるかも -
もしいま、何かしらの社会的な地位や栄誉を得ているとしたら、少なくとも貧困ではないとしたら、それは何故だろうか。
成功者の多くは、それを自分の手柄であり、自らの努力や才能のおかげだと考えるという。しかし、はたしてその考えは正しいのだろうか。サンデルは読者に問いかける。単に恵まれた家庭に育ったからではないのか。親や友人、周りの者が惜しみない愛情を与えてくれたからではないのか。あなたが才能と呼ぶものも、たまたま今の社会でマッチしただけではないのか。それは幸運に過ぎないのではないか。
才能があり努力さえすれば、出世できる。あなたはそれに値する。政治家は口を揃えてバラ色の能力主義を語る。大学に進学し教育を受けるべきだ。高等教育こそが社会的地位向上への近道だ。こうして学歴偏重社会が到来する。「出自は関係ありません。懸命に努力すれば報われるのです!」
しかし、それはグローバル化の流れにのれていない者、学歴のない者を不当に貶め、自信を失わせることとなった。実際のところ、学歴が平等の象徴とはほど遠いことをサンデルは膨大な事例を挙げて解説していく。名門大学のほとんどの生徒が富裕層に属し、身分は流動化どころか固定化していた。富める者はより富を増やし、格差は桁違いになった。アメリカンドリームは、文字通りのドリームとなってしまった。アメリカの大学のレガシー制度とは少し違うが、日本でも有名大学に通う生徒の家庭は富裕層が多いことはよく指摘される。この問題に対して、自身も教育者であるサンデルはなかなかエキセントリックな解決策を提示している。
本書は、能力主義の是非について、承認、評価、功績、幸運、尊厳等、さまざまなキーワードで解説している。お馴染みの説得力ある語り口は健在である。自然と自分で考えるように仕向けられるていることに気がつく。英語力があれば、サンデル先生の講義も受けてみたいなぁ。 -
タイトルからもう秀逸。学べる環境の豊かさは普通のことではない。自分の子供達もそうやって得た報酬や地位は共通益のために使いたいと思える人になって欲しい。子供達が、1人も取りこぼれず満足に食べ、望む教育が受けれる社会を作ること以外に国家は何をすべきことがあるのだろうと心から思う。
-
『私の受け取っている報酬は、私の頑張りに対する正当なもの。功績、能力に値するものである。』
一見頷いてしまいそうなテーゼに疑問を投げかける。
マイケル・サンデルの新作は、能力主義が包括してしまった格差社会の正当化と、無能力者を生み出す課題。根深い倫理の問題を掘り起こします。
国家という枠で話されるスケールとは少しずれますが、この本は働く私にとって身近な緊急課題でもあります。
人事改革。会社は定期的に人をどのように評価するか決めます。この本を読み、私が所属する職場が、いかに能力主義に拘泥しているかが理解できました。
私は大学出身です。学士号をもっている。そして、評価基準を決める側の人間もほとんどが大学出身者です。
ですが、会社にはそうではない社員が多数います。比率は三分の一でしょうか。作中でこの比率で語られた事例があり、話を急に振られた気分になりました。
昇格のルールが厳格に定められるにつれ、既に会社内で権限を持つ者は優遇される。一方、現場で仕事に貢献しつつも、学歴や資格、ノウハウを証明できない社員はキャリアパスが狭まっていく。
極めつけは、その狭き門はあくまで『個人の責任に基づく成長』でクリアすべき。と喧伝します。会社はチャンスを与えた。いつでも昇格していいよ、と自由な社風を謳うわけです。
この本を読む前から、その自己責任理論に辟易していましたが、読了後考えが改まりました。
辟易する、どころではない。
私の部下を、後輩から自信をくじかせ、無能力者にする仕組みだということです。
そして今職場では、尊厳を傷つけられた社員の離職が後を断ちません。
本から学んだことは次の通りです。
給与の多少、権限の問題ではない。
我々が反省すべきは尊厳を大事にすること。共同体意識を株価やその場の利益に目を眩ませて、陳腐化させないこと。
そして、何より謙虚さを持つこと。
働く実務者を守る、新たな武器を得た気分です。
政治哲学の本。そうカテゴライズするには、その課題は深刻で、あなたの身の回りで、見聞きしたことですぐ実感できる内容ばかりです。
能力評価、学歴社会に疑問をもっているかたは特にオススメです。
著者プロフィール
マイケル・サンデルの作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。







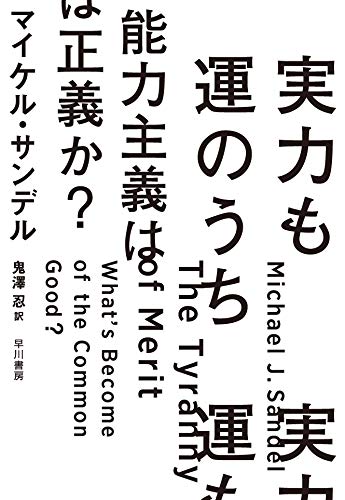



 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 


















































