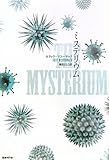- Amazon.co.jp ・本 (284ページ)
- / ISBN・EAN: 9784560081518
作品紹介・あらすじ
上空から見下ろす作者"土星"の存在に気づき、自由意志を求めて立ち上がった登場人物たち。ページの上で繰り広げられる奇想天外な「対土星戦争」の行方は?メキシコ出身の鬼才による鮮烈な処女小説。
感想・レビュー・書評
-
妻に見捨てられた男は新しい職と生活を求め、
小学生の娘を連れてカリフォルニアへ。
カーネーションを収穫する仕事に就き、
地元の荒くれ――と呼ぶには随分おとなしい、
若者のグループとも親しくなったが、
常に何ものかに監視されている気がして落ち着かない。
ある日「敵」の存在に気づいた彼は、
娘や若い仲間たちと共に戦闘を開始した。
敵の名は「土星」……。
という、荒唐無稽な「戦争」と「紙製人間」を巡る奇譚
――かと思いきや、
実は登場人物 vs 作者という一層珍妙な物語だった……
……のだけれども。
期待値が高過ぎたかなぁ。
途中まではドキドキしながら読めて、とても楽しかったが、
お父っつぁんの「敵」の正体が判明して以降、しょんぼり。
女にフラれ続けてクサクサした男の八つ当たりみたいで(笑)。
創作者が神の視座を有するのは当然だし、
それ自体をテーマに長編を物する試みも面白いとは思うが、
一編の小説として深みは感じられなかった。
多分、肝心な「土星」こと「創造主サル」の人物造形が
好みではなかったせいで、白けてしまったのだろう。
時間を置いて読み返したら印象が変わるのかな……。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
失尿症のため妻に去られたフェデルコ・デ・ラ・フェは、自分を高みから覗き込む土星の存在に気がつき、仲間を集め土星に対して戦いを挑む。
土星の名前はサルバドール・プラセンシア。失恋を小説にぶつけていた。彼の小説には紙でできた女、メキシコ人という設定の往年のハリウッド女優リタ・ヘイワース、白痴にして全能の赤ちゃんノストラダムス、実は聖人のプロレスラータイガーマスク、教会の使いとその狭間と生きる製薬師などが交差する。
フェデルコ・デ・ラ・フェたちの攻撃で、土星は失墜し余白に追いやられそうになる。しかし全ての惑星で一番残酷で強大で哀しみに満ちた土星が力を失うことはない。
人間の日常や哀しみを抱えて物語は収束する。
===
作品としては粗い部分も多いのですが、作家として、事実を変えられないなら世界を作ってしまえ!という感じの小説です。
幾多の登場人物の言動と、それを覗き見する土星の姿を表現するために、ページは自由な段組、図形が使われています。
紙でできた女性というのがでてくるのですが、愛し合う男たちは紙で傷をつくり、筆跡を残しても剥がされ、男から男へ渡る女の象徴として面白い描き方だなと思いました。 -
『でも、それは紙の上でのことだった。そして、この物語から学んだことがあるとすれば、それは紙には用心せよということだったーー紙の脆い作りと鋭い端に用心すること、ただし、もっぱらその上に書かれていることに気をつけること』-『ラルフ・ランディン&エリサ・ランディン』
紙の上に並べられた文字に、何かがある訳ではない。血が通った人がいる訳でも、風が吹く訳でも、雨が降るわけでもない。けれど、本を読む者は文字を追い掛けながら「その世界」に入ってゆく。そしてあたかもそこで本物の人に出会い、風を身に受け、雨に濡れるような感覚に囚われる。そこで展開する物語を生き生きとしたものとして捉えてしまう。不思議だ。
余りにその世界に接近して臨場感を持って物語を眺めていると、激しく心を揺さぶられ時に涙したりすることもある。しかし読者には一つの安全地帯が与えられてもいる。それは全てを見渡す場所。作者によって築かれた砦と言ってもよい場所で、一般的には堅牢強固であって、如何に物語の登場人物に読者が揺さぶられても、身が切られるようなことはない。それどころかその砦は透明な造りで登場人物の目には触れることもない。開いている頁を閉じれば直ちにその世界からは切り離される。そしてまた誰にも見咎められることの無い場所へこっそりと戻ることも出来る。
ところがこの「紙の民」ではその安全装置の存在が激しく揺さぶられる。何とも居心地の悪い状態を読者に強要する。それどころか一種の罪悪感のようなものさえ湧いてくる。
似たような作りの本はこれまでにも読んだことがある。例えばガルヴィーノの「冬の夜ひとりの旅人が」、あるいはエンデの「果てしない物語」。また、装丁としての類似ではダニエレブスキーの「紙葉の家」も挙げられるかもしれない。しかし、ここまで作者(=読者)と登場人物の対立が激しく交わされる本は読んだことがない。一人一人の登場人物、作者、作者を取り巻く環境などが入り乱れ、否応なくそこに普段は意識していない軸が存在していることを思い知らされる。引いては本を読むということはどういう行為なのかを、そこに隠された原罪のようなものがあることを、どうしても考えてしまう。
所詮、紙の上に書かれたことを再構築する自分がいて、その再構築により初めて本の世界は具現化する。であればこそ、本を読むことは自分の知らない自分に出会うことに近い行為だと常々思ってはいるのだけれども、ことこの本に関する限り自分に出会う感覚はほとんどない。その紙の上の世界の意味付けは書く側に一方的に委ねられている。かと言って踊らされているという感覚があるわけでもない。文字の配置によって巧みに登場人物が同時並行的に存在していることを意識させ、読む者と読まれる者との戦いを、煽る。不思議な味わいである。いやいや、味わいなどという穏やかな言葉を使うことは許されていないだろう。うっかりしていると、読んでいる内に読む者は読まれる者(=作者)に切りつけられて、深い傷さえ負ってしまいかねない。文字通りの意味でも、比喩としても。 -
出版当時にマークしていたところ、いつの間にやら本屋さんの店先から消え、今年の白水社100周年記念の復刊本となったのを知って手に取った。でも、わずか4年で「復刊」カテゴリに入るんだな、海外文学って。
内容がどうというより、ブックデザインによる第一印象が非常にいい。グレイがかかった水色に銀色の装画、帯の趣向がとてもクリーンで上品なうえに凝っているのが素敵。
この凝りようは物語自体にも現れていて、通常の段組と変則の段組が入り乱れたレイアウトで、夫婦、親子、恋人、戦闘員の話が進むが、決して読みにくいわけではなく(順に追っていけば普通に話はつながる)ので、視覚的にも非常に楽しい。ストーリーはあるといえばある、ないといえばないように感じるが、ざっくり言えば、円城塔のスタイルを持ったガルシア=マルケス『百年の孤独』だと思う。まあ、訳者あとがきによれば、プラセンシアは3年間この作品を読みつづけたというから、影響を強く受けているのは当然だと思うけれど、ラテンアメリカ系の作家にはやっぱり彼抜きでは語れない面も強く感じる。それに、「報われない戦いを、いるのかいないのかわからない敵に挑む」という点には、セルバンテス『ドン・キホーテ』からの流れを感じる。
「敵は土星!」というキーワードからはなんだかもっと殺伐としたむちゃくちゃな話かと思ったら、設定の投げっぱなしやぶった切りはあるものの、実はそれほどでもなくて(これは私の読書経験の問題で、こういう作品を初めて読んだかたには十分衝撃的だと思う)、面白悲しくきれいにまとまった感じはある。タイトルとタイトルロールは勢いで創作したのかなあと思うくらい扱いが雑なのがご愛敬かと。あと、枝葉の話になるが、佐山聡がフィーチャーされてる場面があるのが、往年の格闘技ファンの琴線に触れてしまい、非常に印象に残りました。初代タイガーマスク、そこまでやらんでも。 -
なんの情報も持たず読み始めて20~30ページも読んだころ、作者を確認。ガルシア=マルケスじゃないよね?
作者はメキシコの人で、三年間にわたって『百年の孤独』を読みふけったのだそうだ。
なるほど。
紙でできた人間。
人と同じように行動するが、水に濡れれば柔かくぼろぼろになり、インクは溶けて滲み、端はひとの体を傷つける。
妻に逃げられた男はある日、自分の生活や思考が何者かに上からのぞかれていることに気づく。
のぞかれ監視されているだけではなく、運命まで握られていることに反発した男は、上空にある存在、「土星」に戦いを挑む。
登場人物の多くが「痛み」や「悲しみ」を抱え、それに耽溺している。
ライム。火傷。蜜蜂。
決して自分を幸せにしないものにすがり、それを断ち切ることができない。
執着し、捉われることによって身動きができない、諦念。
ああ、何をどのように書いてもそれは本質ではない。
本を読むということは作品世界を傍観者のように眺めるだけではなく、自分自身を作品の中に晒し、己の「痛み」や「悲しみ」そして「執着」に己が傷つけられることもある。
紙の民は読者の私を包み込みあまやかになぐさめてくれることもあるが、鋭く見えない傷をつけることもある。
アメリカ国内で書かれた作品なのに、ねっとりと濃密な空気感が中南米を思わせる。
時間も空間もシャッフルされた中で、キリスト教やタイガーマスクことサヤマサトルまでも同じ重さで物語に関わり、同化していく。
“悲しみに続編は存在しないのである。” -
奇妙な本だ。連想するのは・・・作家が愛読しているというマルケス、それはある。南米マジックリアリズム系統。ヴォネガット・・・うん、オフビート感。ボリス・ヴィアンのシュールレアリスティックかつメルヘンな幻想の世界。レイアウトやイラス使いで、本を読むということ自体で遊ぶ感覚がフォアの「ものあり」。作家も役者も若い。現代的な感覚を感じる。
まずプロローグの超短編の密度の高さと完成度、面白さに度肝を抜かれ、読み進めることになる。正直言って荒唐無稽系はきらいではないがやや苦手なので、途中中だるみもして辛くはあった。内容を説明することは不可能だ。土星=作者(サルバドール)との戦争、紙でできた人間が水で溶ける、リタ・ヘイワースはレタスを投げつけられ、障害児ならぬベビー・ノストラダモスが予言し・・・奇想天外。
とはいえ根底にあるのは失恋の悲しみというシンプルな物語だ。作家の想いによって複雑で構築されたプラモデルのような繊細さと親密さを感じる。
とにかく非常にユニークで才能あふれる現代の作家。 -
奇妙奇天烈摩訶不思議出前迅速落書無用!
でもホンワカパッパはしない。
『百年の孤独』を読み、マジックリアリズムが解った気がしている方にオススメ。ガルシア・マルケスは全然正当派だったんだなーとしみじみ思いました。
電子書籍が普及している今こそ、こちらの紙媒体の【遊び】を手にとって、ページをめくり、目で愉しんでいただきたいです。
星の評価なんて私なぞに出来るもんか!です。訳わかんねーもんw
二次元時代の現代アートですね。 -
最初は奇想かと思ったが、幻想とラテンアメリカの現実とが一体となって描かれるので、ガルシア・マルケスに連なるマジックリアリズム小説だった。主人公の少女以外の登場人物はすべて心か肉体に痛みを持っている。この「痛み」が幻想とリアルをがっちりとつなぎ、奇想の出発点になっている気がした。で、痛み要素が苦手なので途中でリタイヤ。決して詰まらないわけではなかったし、いつかまた手に取るかも。個人的には幻想が現実を軽くしてくれるものが好み。土星から逃れるため機械亀の甲羅に逃げ込むのはちょっと面白かった。
-
ふだん誰もがなんとなく感じているであろう、誰かに動かされているんじゃないか、山の向こうにふと巨人が見えるんじゃないか、ここは箱庭に過ぎないんじゃないのか、という感覚を、内から、そしてさらには外から描く長編。
とにかく出来事ひとつひとつが面白く、またそこに込められた感情はリリカルで、読んでよかった。
悲しみの商品化、要約というテロリズム。
おしっこや包皮やクンニリングスなど妙にシモの話が多いこと、そして火傷であれライムであれ蜂の毒であれ、依存する性向が多いことも、なぜだかしっくりくる。
NTRの男たち。
その代表になってしまう土星の混迷が始まってから乗りに乗る。
本の見開きというしかけの中で遊びまくる作者のおちゃめにもにんまりしてしまう。
本当に読んでよかった。
藤井光の作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。











 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :