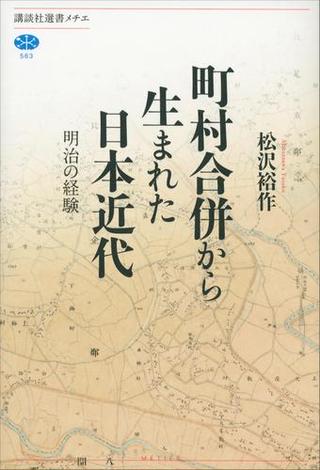重野安繹と久米邦武: 「正史」を夢みた歴史家 (日本史リブレット人 82)
- 山川出版社 (2012年3月1日発売)
 本棚登録 : 32人
本棚登録 : 32人
 感想 : 2件
感想 : 2件
- Amazon.co.jp ・本 (85ページ)
- / ISBN・EAN: 9784634548824
作品紹介・あらすじ
歴史研究は社会にとってどのような意味をもつのか。重野安繹と久米邦武は、日本の近代歴史学の草創期を担った歴史家である。しかし、彼らが歴史家となった経緯は、後の時代の歴史学者とはまったく異なっている。そして彼らに求められたのは、明治政府の官吏として、国家の「正史」を執筆することであった。彼らの栄光と挫折の軌跡を追うことは、社会にとっての歴史研究の意味という問いを改めて考えることでもある。
感想・レビュー・書評
-
日本の東大系官学アカデミズムの歴史家の元祖ともいえる、重野安繹と久米邦武についての簡潔な伝記。久米邦武の「神道は祭天の古俗」論文(1891年発表)が筆禍事件と化したことによる東大からの追放について知りたくて読んだが、むしろ、著者が論じる重野安繹の歴史意識に対する論評の方が興味深かった。
“ これまで、太政官から内閣へと、政府の直轄事業であった修史事業が大学に移管されたのは、帝国大学に日本の歴史を研究する学科としての国史科を設立する計画と関連していた。大学における日本史教育のために、修史部局が蓄積してきた史料とメンバーを、帝国大学に移して活用することがその目的だったのである。
一八八八年十一月、重野安繹は帝国大学臨時編年史編纂係の臨時編年史編纂委員長となり、これにさきだち久米邦武は星野恒とともに臨時編年史編纂委員に任ぜられた。そして、この三人は帝国大学文科大学教授を兼任し、「大日本(←47頁48頁→)編年史」編纂のかたわら、一八八九年(明治二十二)年に設置された帝国大学文科大学国史科で教育にもあたることになったのである。同年には、文科大学史学科のドイツ人お雇い教師であったルートヴィヒ=リースの提唱で、日本初の歴史学の学会である史学会が設立され、重野はその会長に就任した。”(本書47-48頁より引用)
興味深いのは、歴史学におけるお雇い外国人がドイツ人のルートヴィヒ=リースであったのにもかかわらず、これに先立って漢学の紀伝体や記事本末体や編年体に代わる近代歴史学の方法での歴史叙述の際に参考にされたのはドイツのランケ主義ではなく、イギリスとフランスの方法であり、ハンガリー人ゼルフィーが明治政府の要請に応じて英語でギリシャやローマ以来のヨーロッパ史学史を書いた『歴史の科学』(1879年)だったという(本書48-50頁)。
上述の引用部からも明らかなように、重野安繹と久米邦武は明治国家から西洋近代歴史学の方法によって日本史を叙述するための最初の専門家に任ぜられた、東大系官学アカデミズムの先駆者であった。特に重野は「抹殺博士」の異名を取ったように、近代歴史学の事実考証から『太平記』や日蓮の伝記に見られる史実であることが確認できない巷説を抹殺したことにより民間や他の歴史家からの反発を買ったが、とりわけ興味深いのは川田剛との論争であった。概略を示すと、川田は史実であることが実証できない水準の頼山陽の『日本外史』もその歴史像によって幕末の志士の精神を鼓舞したので、それを考えるとどこまで実証主義にこだわる必要がるのかというものであり、重野はそれに対して実証主義の重要性を論じることしかできなかったということであった(本書54-55頁)。
“ ここで問われているのは、一次史料を用いて正確な歴史を書くことの社会的有用性の問題である。川田は不正確な物語でも、国家に対する道徳的規範を提供しうるのであれば、あえて正確さをめざす目的はどこにあるのか、と言外に問うている。それに対する重野の反論は、単に事実解明の重要性を説くにとどまっている。(←55頁56頁→)
重野は、前にふれた「大日本史を論じ歴史の体裁に及ぶ」のなかで、歴史と道徳の関係を、「実に拠り直書すれば、人をして鑑戒せしめ、自然に名教を維持する」、つまり、事実をそのまま書けば、自然と善悪を知る材料になる、と述べている。重野は歴史研究を道徳的先入観から切り離せ、とは主張しながらも、歴史研究が道徳的善悪を知るという目的から切り離せる、とは主張しないのである。
実は、こうした表現は『大日本史』にもみられるし、さらにさかのぼれば朱子学の祖朱熹も同様のことをいっている。江戸時代の儒学者にはありふれた表現だった。むしろ重野による「抹殺」の進行によって、そうした考え方に矛盾があるという新しい問題に気がついたのは川田のほうだったのだ。事実でなくても道徳を知る材料になるものはいくらでもあるではないか、むしろ事実のほうが道徳の材料としては不適切なのではないか、という批判に重野は有効な解答を返すことができないのである。”(本書55-56頁より引用)
重野と久米の歴史学の道徳性についての判断(それは社会的有用性についての判断でもある)には微妙な差があったが(久米の意見については本書60-61頁を参照)、二人とも近代歴史学の実証主義的な考証による事実の発掘・確定を『太平記』のような物語よりも優位に置く志向においては共通していた。そして、正にこの点が問題になったのが、冒頭で触れた久米邦武の「神道は祭天の古俗」論文事件だったのである。1891年に発表したこの論文が神道家の敵愾心を招いたことにより、久米は1892年3月30日に帝国大学を辞職することになったのだが、問題は久米の「神道は宗教ではない」(「祭天の古俗」)という主張が、皇室に対する不敬とみなされて国体論に触れ(本書70頁)、国家の依拠する「道徳」への攻撃とみなされたが故に、近代歴史学が沈黙と撤回を余儀なくされたことにあった。事実を事実として(少なくとも近代歴史学の史料批判の方法論に沿って行われた歴史家の目から見た事実として)書くだけでは、国家権力(天皇制)に正統性を神話的な歴史解釈(国体論)の前に対抗できないということが、史学会の設立から五年も立たないうちに明らかになってしまったのである。
久米邦武の失脚以後の官学アカデミズムは三上参次、黒板勝美、辻善之助らは、久米の轍を踏まないように余暇であっても「世上の物議」を醸すような論説の発表は控えるようにと厳命され、社会に対して何かを訴えることは厳重に自粛することが示し合わされた(75-76頁)。恐らく東大系のアカデミズムが京大系に比べて見るべきものを輩出していないのも、「神道は祭天の古俗」論文事件の余波なのだろうと本書を読んで感じた次第である。
さて、私自身は本書で提示された、歴史学の社会的有用性に関する、事実の実証性と物語性のどちらを重視すべきかのついての論争について、今も明確な意見を持っていない。物語として示され、久米を失脚に追い込んだ水戸学的な皇国史観には断乎反対だが、しかし、そのような歴史の見方が人々をして政治的な行動に動かす力は、川田と同様に無視してはならないと思う。あえて言うならば、重野や久米と同じく、事実を実証することをまず重視しなければならないと考えているが、やはり考証された事実を一つの線で纏めて提示する物語的な歴史観が必要ということになろうか。事実無根なオカルトやフィクションやフェイクニュースを実証主義的な事実に代わるものとして、歴史学が提示する訳にはいかないが、その提示の方法に当たっては、何らかの価値基準に基づく物語の一部としなければ、道徳な価値も得られないのではないかということになる。最後にこの点について、著者の見解を引用することで本稿を終えることにする。
“ 重野や久米たちは、歴史家として教育を受け、歴史学を志し、歴史家になったわけではない。彼らにとって、本来、歴史の研究は、一官吏としての「業務」だったといってよい。彼らにとって「史学」がそれ以上の意味をもったのは、その業務の遂行を通じて、その意味を発見していったからである。
そして、彼らにとって歴史学が「業務」であったことは、彼らに歴史学の社会的有用性を説明する責任を負わせることになった。重野は、事実を明らかにすることは道徳的秩序を「おのずから」明らかにすることだ、としてこれに答え、一方、久米は近代社会を生き抜くために必要な、社会の複雑さの認識の手段として歴史を知ることの必要性を説いた。今日、二人の講演記録や論説を読む者は、「史学」という新しい知を手にした知識人たちの、ある種の明るさを感じるだろう。彼らは楽天的であった。
しかし、こうした歴史学の有用性の説明は、同時代の社会において必ずしも受け入れられなかった。重野は、事実がフィクションに対して道徳的優位性をもつことの論証に成功しなかったし、久米もまた、かれの近代社会像を他者と共(←83頁84頁→)有することはできなかった。
重野や久米の次世代にあたる官学アカデミズム史家たちは、こうした社会的有用性の問いを、大学という「学問の独立」の場を確保することで、さしあたり封印した。それでも、問いは何度でも亡霊のようによみがえる。一九一一(明治四十四)年、教科書記述を発端として発生した南北朝正閏問題においては、官学アカデミズムも無傷ではいられなかった。十五年戦争期の皇国史観はいうにおよばない。戦後、官学アカデミズムを批判し、よりよき未来をつくるという目標によって社会的有用性を前面に押し出したマルクス主義歴史学も、その依拠した未来像が説得力を失うことによって危機に直面する。
歴史認識が、それを主張する人の立場や歴史的条件に左右されることが指摘されるようになって久しい。しかし、今なお、政治的に対立する人びとが、おたがいの「歴史認識」を問題にするとき、争点となるのはしばしば「史実」そのものである。多くの「歴史認識論争」においては、史実を明らかにすれば、自分の道徳的優位は「おのずから」明らかになることが信じられている。これこそ、かつて重野と川田剛のあいだで争われた論点にほかならない。”(本書83-84頁より引用)詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
二人の人物について分かりやすく簡潔にまとめられた評伝。白眉は終わりのほうの重野や久米が雑誌で論争してる部分で、とうじ歴史学が社会的にどのように有用かのべているところ。重野の、事実をありのまま語ることで道徳的になるという一見よくわからない理屈個人的には嫌いじゃない。久米のほうは複雑であることを教えるといういまにも通じそうなことをいうが、論争的な性分からか大学にのこれなかった。彼らのこの活動が、ある意味反省されて大人しい官学アカデミズムに繋がるという指摘もなるほどと思った。
著者プロフィール
松沢裕作の作品