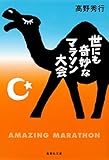- Amazon.co.jp ・本 (340ページ)
- / ISBN・EAN: 9784797674149
作品紹介・あらすじ
語学は魔法の剣!
学んだ言語は25以上!の辺境ノンフィクション作家による、超ド級・語学青春記。
自身の「言語体験」に基づき、「言語」を深く楽しく考察。自動翻訳時代の語学の意味を問う。
さらにネイティヴに習う、テキストを自作するなどユニークな学習法も披露。語学上達のためのヒントが満載。
そしてコンゴの怪獣やアマゾンの幻覚剤探し、アヘン栽培体験などの仰天エピソードにおける語学についても語られる。『幻獣ムベンベを追え』から『アヘン王国潜入記』まで、高野作品の舞台裏も次々と登場。
インドで身ぐるみはがされたせいで、英語が上達、暗黒舞踏家のフランス人女性に生きたフランス語を学び、コンゴでリンガラ語を話してウケまくる。
コンゴでの「語学ビッグバン」体験により、語学の面白さに目覚め、以後、現地を訪れる際に必ずその言語を学ぶ言語オタクと化した著者。
辺境の言語で辞書もテキストもない場合は、ネイティヴを探して学び、文法の法則は自分で見つける。
現地で適当に振り回すと、開かずの扉が開くこともある語学は「魔法の剣」だという著者。地域や人々を深く知る上で、語学がいかに有効な手段であるかも綴られる。
著者自作の地図や図版を多数掲載。各国、民族の言語観や、言語同士の相関をわかりやすく解説。知的好奇心が満たされるとともに、破天荒で自由な著者の青春記を堪能できる一冊。
言語愛あふれるエピローグも感動的。
【目次より抜粋】
第一章 語学ビッグバン前夜(インド篇)
・奈落の底で語学の真実に開眼
第二章 怪獣体験と語学ビッグバン(アフリカ篇)
・ゴジラ襲来
・民族語の世界とムベンベの正体
第三章 ロマンス諸語との闘い(ヨーロッパ・南米篇)
・イタリア語との初対決デスマッチ
・スペイン語は"平安京言語“
・魔術的リアリズムの旅
第四章 ゴールデン・トライアングルの多言語世界(東南アジア篇)
・みんなが満足! マンガ学習法
・麻薬王のアジトでシャン語に出会う
第五章 世界で最も不思議な「国」の言語(中国・ワ州篇)
・言葉のノリと中国語の衝撃
・「こんにちは」も「ありがとう」もない世界
高野秀行(たかのひでゆき)
ノンフィクション作家。1966年、東京都生まれ。
ポリシーは「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」。
『ワセダ三畳青春記』(集英社文庫)で酒飲み書店員大賞を、『謎の独立国家ソマリランド』(集英社文庫)で講談社ノンフィクション賞等を受賞。著書に『幻のアフリカ納豆を追え!』(新潮社)など多数。歴史家・清水克行との共著に『世界の辺境とハードボイルド室町時代』(集英社文庫)などがある。
感想・レビュー・書評
-
この人の著書を読むたびに(といっても最近ご無沙汰…)、短期間でどうやって現地語を習得したのか気になっていた。著書の数から見ても、結構な数の国に渡航されているはずだし、実際「学んだ言語は25以上!」と知り合いの言語オタクが飛びつきそうな売り文句が掲げられている。
しかし学ばれた言語の数こそ多いが、途中から「別にエキスパートにならなくたっていい」と言われている気がした。我々日本人は目標値を高く設定しがちで、自身もそのせいで何度も高山病にかかった。本書のタイトルはまるで山の中腹に設置された立て札とも言えよう。(著者の場合、具体的な目標がなくなると途端に継続へのモチベーションが下がってしまうみたい…)
第一章 語学ビッグバン前夜(インド篇)
今までの著書では語られなかった、彼の貴重な(?)青年期の出来事を垣間見られる!笑
これまた著書ではお馴染みの(?)早大探検部にも当初は馴染めておらず、単独行動から全てが始まったと言うのがいかにも彼らしい笑
第二章 怪獣探検と語学ビッグバン(アフリカ篇)
怪獣とはコンゴに伝わる幻獣ムベンベとのこと。
幻獣を糸口に公用語の仏語やリンガラ語へと「探索」を進めていく著者。途中陥った「アイデンティティ・クライシス」(自身の無力さ・存在意義のなさに絶望する現象)が、のちの著者のスタンス(「誰もやらないことをする」)を生み出したような気がしてならない。
第三章 ロマンス諸語との闘い(ヨーロッパ・南米篇)
初心者レベルにも拘らず、バイトの一環でちょっとした翻訳業もされていたとはこれも初耳!ついでに未邦訳のコンゴ文学を卒論のテーマにされていたことも。一度は彼の翻訳で刊行されていたのに現在絶版なのが残念でならない…
第四章 ゴールデン・トライアングルの多言語世界(東南アジア篇)
かつてタイ・ラオス・ミャンマーの三国国境に広がっていた麻薬地帯のことらしい。
幻獣の次はアヘン栽培…突拍子もないところが著者の魅力なんだけどね。本章の魅力はというと、タイの日本語学校でのびのびと教員生活を送った刹那、麻薬王のアジトでビルマ語を習うところかな。
第五章 世界で最も不思議な「国」の言語(中国・ワ州篇)
大連に住む中国語の先生とのエピソードが心温まる。先生の、日本語への”飢え”にも近い学習意欲はこちらも良い刺激になった。
一方ワ州とは、ミャンマー国内のエリア。ここで著者は念願のアヘン栽培に潜入。想像以上に牧歌的で度肝を抜かれること必至。
彼なりのためになる言葉も要所要所で散りばめられており、それらをメモしていく。
著者は言語をconquer(制覇する)ではなくdiscover(知り合う)したいだけだった。一つ極め切ってから次に行かずとも、一つ学べば一つ忘れ更に一つ学んでいくやり方でもいい。
「一億光年かかろうとも、絶えず天上を見上げている方が夢があるじゃん!」と言われている気がした。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
【感想】
AI翻訳が進化した現代において、「語学学習」はコスパが悪いのか?
確かに、システマティックな学習法によって身に着ける「ビジネス英語」は、いずれ機械に取って代わられてしまうかもしれない。しかし、現地の文化と生活を学び、異国民と親睦を深める「草の根の学習法」は、きっとこれからも残り続けるし、むしろ、言葉を学ぶ意義は次第にそちら側に収束していく。そう感じさせる要素が、本書には散りばめられていた。
本書の著者である高野秀行さんは、『謎の独立国家ソマリランド』や『アヘン王国潜入記』など、数々の辺境地をテーマにエッセイを書いてきたノンフィクション作家だ。本作では冒険の際に修得した「語学」をテーマにしているのだが、学術書というほど形式ばってはいない。今までの破天荒な辺境紀行の合間に語学のノウハウを詰めたような構成であり、各地の民族や文化を楽しみながら学べるエッセイとなっている。
高野さんは25以上の言語を学んだというが、彼は決して「語学の天才」ではなかった。むしろ勉強は嫌いなほうであり、目標がなくなると、とたんにモチベーションがゼロになり、学んだ言語を忘れてしまうという。
そんな高野さんが語る上達のコツは、「それをやらないと目的が達せられない」状況に身を置き、体当たりで学ぶことである。
具体的には、実際に現地を訪れ、住民に「〇〇ってなんて言うの?」と聞き、それをノートに取る。辞書があれば辞書を引きながら、動詞の活用変化、時制といった大まかな要素を体系化してみる。もし辞書が作られないほどのマイナー言語であれば、原住民の発音を細かく書き記し、自作のテキストを作ってみる。そうしたインプットの後は、とりあえず片言で何か喋ってみて、反応をもらう。
こうした現地調達型の修得方法は、現地民からおおいに喜ばれるという。特に話者一万人程度の超マイナー言語であれば、外国人が話すというのは考えられないから、一気に親近感を持たれる。そうして相手を「こちらのファン」にさせてしまえば、あとは向こうからネイティブが寄って来て、どんどん言葉が身についていく。このテクニックにより、筆者は麻薬王の自宅にまでお呼ばれして言語を学んでいたという。まさに行動力が成し得る学習方法だ。
高野さんいわく、「外国旅行で何か語学を上達させたいと思ったら、決して自分より(少しでも)できる人と一緒に行ってはいけない」。旅行中は現地の人とのやりとりをその人に頼ってしまい、通訳として使ってしまうからだ。また、筆者は徹底的に「使う表現から覚える(目的に特化した学習をする)」ことと、「現地で学んで現地で使うサイクル」の重要性を強調している。これは、面倒くさがりの筆者自身が「楽しみながら勉強すると楽に上達する」と実感していたからだろう。特に興味もなく外国語を聞くのと、何か目的があって主体的に現地の人と話すのでは、上達の幅が違う。好きなものこそ上手なれとはよく言うが、語学学習においてそれは絶対的ということだ。
日本語は、世界最大のマイナー言語である。インド・ヨーロッパ語族と違い、日本語族のメンバーは日本語しかいない。英語を話す人間にはフランス語やドイツ語といった「仲間」がいる。コンゴの奥地に住むボミタバ族の人たちは一見、秘境の民に思えるが、実は周囲を親戚言語で囲まれており、アフリカ大陸の半分が親戚である。一方で、日本語はユーラシアの極東の小さな列島にしか存在しない。
そう考えれば、筆者が様々な「辺境言語」を学んだといっても、日本語のほうがよっぽど辺境言語なのだ。そんな仲間外れな言語圏に住む私たちだからこそ、言葉が通じることを喜ばしく思える。異郷の地でコミュニケーションが取れる喜びをかみしめることができる。高野さんのような志を持っていれば、語学が苦手と言われている日本人にも希望が見える。
「文化的に成熟した辺境民族」である日本人にこそ読んで欲しい一冊。文句なしにオススメだ。
――――――――――――――――――――――
【まとめ】
0 まえがき
通常、語学というのは入門から始まり、初級・中級・上級と何年もかけて少しずつ階段を上がっていくものと思われているが、筆者は決してそのような手順を踏まない。一つの言語を何年も勉強したこと自体がほとんどない。学習期間は長くてもせいぜい実質1年、短いときは2,3週間、平均すれば数カ月といったところだろうか。現地で出会った言語を即興で習いながら旅をすることもある。
いつの間にか、筆者にとって語学(言語)は「探検の道具」であると同時に「探検の対象」にもなっていた。
1 異国での会話は助け合い
外国語でのコミュニケーションは協働作業である。自分一人で会話するということはない。必ず相手がおり、その相手はたいていの場合、コミュニケーションを成立させるためにこちらに協力してくれる。助けないと会話が成立せず相手も困るのである。下手な車を避けないと他の車が困るように。
筆者はインド旅行の途中で有り金とパスポートを全部スられて一文無しになった。そこで、経緯を全て現地の警察に説明した。この緊急事態が「何としてでも話さなければならない」という状況を作り、英語が磨かれた。
2 語学ビッグバン
コンゴで幻獣ムベンベの調査を予定していた筆者。色々あってリンガラ語の習得に追われるのだが、リンガラ語には文字がない。おまけに話者もほとんどいない。日本に住んでいるザイール人のウィリーに協力を頼み、彼の言葉をローマ字で書き表して習得していった。
1987年、ムベンベ探索の偵察という目的ではじめてアフリカに降り立つ。
コンゴではフランス語とリンガラ語を両方話していたのだが、リンガラ語を喋ると現地民に大ウケだった。外国人はみなフランス語でコミュニケーションをとり、誰もリンガラ語を学んだりしないのだ。特に西洋人はアフリカ人と同じレベルに身を置くことを嫌う。だからコンゴの人たちの頭の中には「外国人は決してリンガラ語を喋らない」という常識ができている。それを変な東洋人の若者が打破するから驚かれ、喜ばれたのだ。
筆者でも地元の言語を習って片言を喋るくらいはできる。そしてそれがめっぽうウケる。筆者は旅先のローカル言語を話す醍醐味に完全に目覚めてしまった。
コミュニケーションをとるための言語と仲良くなるための言語。外国へ行って現地の人と交わるとき、この二種類の言語が使えれば最強なのだ。いわば「語学の二刀流」、これを使いこなす快感を知ってしまった。筆者にとって「語学ビッグバン」である。
言語には「うまく話せる人の方が優位に立てる」という理不尽な法則がある。筆者はこれを「言語内序列」と呼ぶ。フランス人はもちろんのこと、アメリカ人や日本人がコンゴに来て、フランス語を話しているかぎりはいい。彼ら(私たち)はもともと政治経済文化的に「優位」に立っているし、コンゴの人たちにとってもフランス語は第二言語であり、それほど自信をもっているわけではない。でも、リンガラ語とくれば話は別だ。コンゴの人にとっては母語同然の言語だから絶対の自信をもっている。かたや外国人は頑張って話しても子供レベルの会話しかできない。すると、言語内序列の法則により、人間関係までもが「大人と子供」になってしまうのだ。
日本に暮らして英語の話せる西洋人や一部のアフリカ人、アジア人が日本語をあえて習おうとしない理由の一つはそこにあると思っている。
3 スペイン語は快適な言語
言語というものは時間が経つうちに、「その方が言いやすい」とか「他の単語と区別するため」とか、あるいはただ単純な言い間違いや、その他はっきりしない歴史的な事情から変化していく。非母語の学習者にとって、このような微妙な変化は「あまりに複雑」で「難しい」ように思える。
スペイン語は、世界中で長い間使われてきたにもかかわらず、話者の便宜を図った微調整もほとんどないし、発音と文字のズレも小さい。世界中で話されているのに方言差も少ない。母音はa・i・u・e・oの五つだが、日本語の母音に近い「ア・イ・ウ・エ・オ」であり、他の読み方はない。男性名詞と女性名詞もはっきりしている。驚くほどに規則的なのだ。
特筆すべきは、スペイン語話者の間では「言語内序列」がないことだ。コロンビアでも、本場スペインでも、「スペイン語が話せるんだね!」と驚いたり喜んだりせず、かといって会話がスムーズに進まなくても見下した態度を取らない。英語ネイティヴは相手が英語を話して喜ぶことはないが、理解しないときには苛つく人が多い。英語は世界普遍の言語だと思っているからだ。フランス語ネイティヴはフランス語に強い誇りをもっていて、外国人がフランス語を話すこと(話せないこと)に多少なりとも喜んだり苛ついたりする。日本語を含む非メジャー言語は、相手が話せると喜び、子どものように扱う。唯一の例外がこのスペイン語なのだ。
コンゴで多言語が渦巻く環境に興奮し、「現地語を話してウケる喜び」を知った筆者だったが、コロンビアでは「現地語を話してスベらない安心感」に浸った。覚束ないスペイン語を話しても、明らかに外国人とわかっても、彼らはまるで同じ国の人間のように接してくれた。
4 独立言語の勉強方法
次に学んだのはタイ語だった。このタイ語が、他の言葉と比べても圧倒的に難しかったと筆者は言う。
言語は、学習するうえで大きく4つの要素に分けられる。①文法、②発音、③語彙、④文字である。
このうち①文法は、進化系統の結果である語族やそのサブグループである語派に大きく左右される。語族や語派が同じであれば文法も似通っている。フランス語とスペイン語、あるいはリンガラ語とボミタバ語とスワヒリ語などがその例だ。
②発音は語族・語派という系統だけでなく、地域にも左右される。異なる言語系統でも、近い場所にある言語は互いに影響し合い、発音が似てくることがある。例えば、後にわかったことだが、タイ語とビルマ語と中国語はいずれも系統が大きく異なるのに、みな声調があり、有気音・無気音の区別があるなど、発音に共通性が高い。
③語彙はとても面白い。語族や語派が同じなら「おじさん」とか「頭」とか「食べる」といった基礎的な単語は似通っているケースが多いが、「政府」「学校」「状況」「世界」といった抽象的、科学的な単語は言語系統にあまり関係がない。これらはむしろ「その地域が歴史的にどの文明圏に影響を受けてきたか」による。例えば、日本語と中は全く別の言語統語族だが、文明用語の半分以上を共有している。
最後の④文字は言語系統にいちばん関係が薄く、文明圏による影響がひじょうに強い。これも「漢字」を考えればすぐ納得がいくはずだ。世界の主な文明圏には、「ヨーロッパ文明圏」「中華文明圏」「アラビア(イスラム)文明圏」「インド文明圏」「ペルシア文明圏」などがある。
タイは日本と同様に植民地にされた経験がない国であり、日本語以上にヨーロッパからの借用語が少ない。また、文字はアルファベットではなくタイ文字であり、1から覚えなければならない。
タイでの勉強方法は、語学学校でのマンツーマン・レッスンだった。月謝を払ってプロの語学学校教師にマンツーマン授業を受けるもので、相当にしっかりしている。しかし、逆に言えばあまりに公式すぎるきらいがあり、くだけた日常会話は学べなかった。
くだけた表現を学ぶには、翻訳された漫画がうってつけだった。1990年代の前半、タイでは日本のマンガが異常なほど人気であり、あちこちに貸本屋があった。これは最高の口語表現テキストであり、筆者が現地の学生に日本語を教える際にも重宝した。
その後筆者は、日本語観光ガイドの講座で知り合った人物を介して「麻薬王クンサー」の軍隊とコネを作る。そして麻薬王のアジトでビルマ語を教えてもらうことになる。
ビルマ語は他の言語との相関性が全くわからなかった。まず確認したのは、主語の人称(私・あなた・彼/彼女など)によって動詞が変化するかどうかだった。
ビルマ語を教えてくれた人に訊くと、「ご飯」は「タミン」だという。それから人称代名詞については、「私」は「ジャノー(男性の場合)/ジャマ(女性の場合)」、「あなた」は「ケミャー」、「彼/彼女」は「ドゥー」…と教えてくれる。それらをふまえ、「ご飯を食べる」という例文を作ってもらう。
私はご飯を食べる ジャノー・タミン・サー・デー
あなたはご飯を食べる ケミャー・タミン・サー・デー
彼/彼女はご飯を食べる ドゥー・タミン・サー・デー
私たちはご飯を食べる ジャノロー・タミン・サー・デー
以上のように並べると、ビルマ語の動詞は、主語の人称によって変化しないことがわかる。これを時制にも適用し、動詞が変化するか調べたり、助詞や声調の種類について探っていったりした。
このように常に「暫定的に法則を見つけ、新しいことがわかれば、随時その法則に変更を加える」というのが、筆者が独力で編み出した調査法だ。とはいっても、フィールド言語学の世界ではごく初歩的な手法であると思う。
5 中国で学んだ「言語のノリ」
さまざまな言語を学んでいくと、どの言語にもその言語特有のノリとか癖とか何らかの傾向などがあることがわかる。それが語学で決定的に重要だということに気づかざるをえない。
言語のノリには文法やことばの使い方のほか、発音、口調、話すときの態度、会話の進め方などが含まれると思う。
例えば、タイ語は口を大きく開けて発音することがまず大事だ。それから音程は常に高め。タイ語ネイティブの会話は鳥のさえずりに聞こえる。そして話し方は、ひたすら柔らかく優しい。タイ人はマッチョを嫌い、上品な立ち振る舞いを好むから、女性はもちろん、男性もなよなよっとしている。だから繊細なガラス細工を扱うかのように優しく喋ると、タイ語っぽくなる。
ビルマ語の音程は全体的にもっと低く、もっと舌を口の中にべた〜っとつける感じで発声する。さらに、喋るときはタイ人より堂々とした態度をとり、相手の目をしっかり見ながら、でも明るく優しく喋るとちょうどいい。
日本語の発音は口の先の方で行う。唇は最小限しか動かさない。「口を開けずにぼそぼそ喋る」のは日本語全体に当てはまる。外国人(日本語が母語でない人)が日本語を発音すると、口調がはっきりしすぎていて違和感を覚えるのはそのせいだ。声の音量は小さめで、「じゃ、そんな感じで……」とか「よくわからなくて……」など、センテンスを最後まで言い切らないことが多いから、ますますもやもやした印象を外国人に与える。
筆者が中国で出会った莫先生も、まさにこの「ノリ」を体得した人物だった。無愛想で剛直な先生が、日本語を喋るときだけ体を小さくし、部下が上司にへりくだるような口調になる。声を細め、口先で軽くぼそぼそと喋る。筆者は彼から生きた中国語を学んでいった。
中国語は日本語と同様に漢字を使っているため学びやすいし、文法も難しくない。厄介なのは発音だ。発音を覚えるため、日本語と中国語の音の対応を片っ端から調べ、一覧にしていった。
中国人の世界観は今でも「中華思想」なのだろうと当時よく思った。中華とは国家ではなく、文化圏である。中国の文化やシステムを受け入れると、その土地は中華世界に入り、人も中国人となる。中華グローバリズムと言っていい。そして中華思想の中核をなすのが中国語なのではないかと思う。要は中国語を話し、中国式に振る舞えば、どの民族だろうがあまり関係ないのだ。筆者にしても、中国語を話して中国のご飯を普通に食べているかぎり、「中国の日本族」みたいな扱いになっていた。
6 語学学習という「魔法の剣」
筆者の行った言語学習のスタイルをまとめると、次のとおりだ。
・誰でもいいからネイティブに習う
・使う表現から覚える(目的に特化した学習)
・実際に現地で使ってウケる
・目的を果たすと、学習を終え、速やかに忘れる
筆者は20代のころ、この方法で世界各地の言語を習得し、旅をしていた。
では、機械翻訳・通訳が進化した現代において、果たして語学をやる意味はあるのか?
「やはり、語学の必要性が完全になくなることはないのではないか」。筆者はそう答える。言語には「情報を伝えるための言語」と「親しくなるための言語」の二つがある。ITでまかなえるのはもっぱら「情報を伝えるための言語」なのである。いっぽう、「親しくなるための言語」はそもそも情報伝達には必要のないものなのだ。フランス語で話して通じるなら、リンガラ語を使う必要はないはずだ。でも、リンガラ語で話すと「共感」が得られる。仲良くなれる。そういう語学は、なくならないはずだ。
翻訳や通訳は、ガラス越しでの会話みたいなものだ。興味を抱いた他人と、ガラス越しではなくじかに触れたいと思うことは、人間の本能に根ざしているのかもしれない。互いの心臓の鼓動を聞くような語学は生き続けると確信している。
従来、学校教育で行われているのはエンジニアリング的語学教育である。基礎から始まり、初級、中級、上級とシステマティックに進み、最終的には完成に至るとされる。あたかも超高層ビルや大阪城を建設するような壮大な語学なので、完成までに相当な時間と労力がかかる。
かたや筆者の語学(ブリコラージュ的学習法)は、辺境の民の仮小屋みたいなものだ。そのときの役に立てばよく、明日はもう使わないかもしれないし、一週間後には朽ち果てているかもしれない。そういう語学があってもいいのではないか。
あるいは、ブリコラージュとエンジニアリングを組み合わせることも、ときには有効なのではないか。ブリコラージュは身の回りにあるもののいいとこどりだから、伝統的な語学と部分的に組み合わさること自体が、広い意味でのブリコラージュとも言える。その人の目的、学習期間、年齢によって、臨機応変に変えられる。ブリコラージュは、時代の変化にも強い学習法なのではないか。 -
「語学(言語)の何がいったいそんなに魅力的なのか。語学が少しでもできるとどんなことがわかるのか。言語を短期間で覚えるにはどのような方法が有効なのか」。好奇心の赴くまま世界の辺境の地を探索し続ける著者が、19歳から29歳までの約10年間、必要に迫られて様々な言語を実践学習した、その悪戦苦闘の語学学習遍歴を綴った書。若かりし頃の悩める著者の青春放蕩記でもある。
著者にとって「言語はあくまで道具」。なので語学学習は、現地に滞在し、人々とコミュニケーションを図り、親密な関係を築き、その風土や文化を感じ取るために必要最低限のもので十分。言語を極めることに執着しないし、目的を達したら次の探検へと興味が移っていき、せっかく身につけた言語もあっさりと手放して(忘れて)いくのだという(「地道に物事に取り組むことができない」「興味が湧かないことは苦痛でしかな」いのが著者の性分だから仕方ないのかもしれないが、勿体ないなあ)。
また、文字や文法さえ体系的に整理されていない辺境の地の言語と接する中で、「いつの間にか、私にとって語学(言語)は「探検の道具」であると同時に「探検の対象」にもなっていた」という。
そして様々な言語を学ぶうちにたどり着い境地「どの言語でも原理的に言い表せない事柄はない。どの言語も似たような性質を共有している。そしてどの言語も美しい」。この言葉には、著者のマイナーな人々への強い愛情が込められている。
著者によれば、「言語には「情報を伝える言語」と「親しくなるための言語」の二つがある」。機械翻訳が進んでも、後者の言語を身につける意義はなくならないんだな(そうだといいな)。
中国大連の鉄道学院前で鉄道部若手と撮った写真が掲載されてた(P260)。鉄道部若手は昭和の日本人と見分けがつかないが、著者はどう見ても日本人に見えなかった(笑)。 -
著者が自分とあまりにかけ離れすぎていて、未知なる世界を開拓した気分になりました。笑
世界ウルルン滞在記(もう終わってしまった?)を素でいく人なんですね。
体験談が腹を抱えて笑えるレベルですので、語学に興味のない方でも充分楽しめると思います。
実はこの本を手に取ったのには理由があります。
過去、仕事で英語(メールのやり取りのみ)を使っていたので、英会話に通っていました。
「これを機に英語を勉強して英語が話せるようになろう。転職の時に有利になるだろうから」とかそんな理由で。
ところが、英語学習を始めて数年後、英語を全く使わない部署に異動に。
目的を失い、英語はフェードアウトしていきました。
(日ごろ使わない語学のために、時間とお金はつぎ込めません)
自分の中では英語は終わったものになっていたのですが、転職したら再び英語がカムバックしてきました。
(今回もテキストのみのやり取り。メールに加えてチャットがついてきました)
もはや英語からは逃れられないのか。。。
「(英語)どうするかな~」
英語を勉強を再開しようか決めかねていた時に発見したのがこちらの書籍。
(タイミングが良かった!)
(英語を)やるにしても前回の敗因は何だったのか?
そして、前回の二の舞になるのだけは避けたい。
(7年間も通っていたので、かなりの金額を英会話につぎ込んでいた)
敗因を分析したうえで英語と向き合おうと思い、読んでみました。
うん。読むだけの価値はありました。
私が英語を喋れない理由がよーーーくわかった。
理由は主にこちらになります。
”話したいことがあれば、英語は話せるのだ。”(抜粋)
”言語はあくまで道具。それが私のスタンスなのである。何か大きな目的のために学ぶのだ。”(抜粋)
私、英語ネイティブに何が何でも死に物狂いで伝えたい事がない。。。(文章ではあるが、話す必要性はない)
それに英語を学んだ先に何がしたいのか、目的がなかった。英語を学ぶことが目的化していた。
そりゃ、喋れるようにならないわけだよ。
(そもそも英語って必要なの?な感じが)
この本を読んだら、英語に対して完全に吹っ切れる事ができました。
私には著者のような言語で伝えたい情熱は持っていません。なので、著者のような語学勉強をやる気力も持ち合わせておりません。
現時点では英語は「情報を伝える言語(テキストOnly)」として使いこなせればよい。先方の要望を読み取り、失礼のない言い回しでそれに回答する。反対も然り。私が今困っているのはこれなのです。
であれば、今の私に必要なのは、英会話に再び通って英語が話せるようになることではなく、洋画を字幕で観れるようになることでもないのです。
最も必要なテクニックは、Google翻訳を上手く使いこなせるようになることなのではないか……。(身も蓋もない解決策な気も)
まずは目先のお困り事を解決することに集中しようと思った次第です。(選択と集中)
※ちなみにGoogle翻訳を使うにしても、ある程度英語の知識はあった方がいいかもですね。単語を微調整しながら使ってます。7年間の英語学習は全く無駄ではなかったようです。 -
初読みのライターさん。
「スペイン語話者」と「フランス語話者・英語話者」(いずれもネイティブの場合)の対比は興味深く読んだ。
麻薬地帯潜入以降は飛ばし読み。 -
語学の解説と著者が実践してきた習得法、その習得とは切り離せない青春記。
高野さんの本は、私にとって馴染みのない難しい話も面白く読めちゃうところが魅力だ。
私は言語学について「語族って何?」の素人なので、生物学のような分類があるということにまず驚いた。単語が似ているなあと思うことはあったけれど、地理的に近いからかなぐらいにしか思っていなかった。
しかしそんな単純なことではないようで、全然関係なさそうなイメージの言語も同じ語族だったりして、興味深い。
出てくる言語の中で、これから学ぶならスペイン語がいいな。スペイン語を話す人のスペイン語に対するフラットな感じに、意欲をそそられる。
そして言語の習得と同時進行する辺境での体験がやっぱり面白い。
ワ州生活を綴った「アヘン王国潜入記」を早く読まなくては。 -
楽しい本!
外国語だけでなく、未知の世界への危険で誘惑に満ちた探検が追体験できて面白い!
外国語は英語だけではないこと、外国語を学ぶ方法は教科書通りでなくてもよいこと、外国語には独特のノリがあること、自動翻訳が台頭してきているが、現地の人の懐に飛び込むには一言二言の言葉がテキメンということがよくわかった。
今の会社に中国人が何人かいる。
入社当時、まだ若くて可愛く?、外国語への憧れがあった私は中国人のおじさんたちに沢山教わった。
今ではほとんどが頭から抜けてしまったけど、汚い言葉や下ネタだけはしっかり残っていて、新しく入ってくる中国人に披露しては「女の子はそんなこと言っちゃダメヨ!でももっと言ったらダメナ言葉はね...」なんて笑ってもらい、距離を縮める助けになっている。
外国語はツールなので、目的に応じて覚えたり忘れたり、教科書通りじゃなくても伝わればよいと思う。
日本の英語教育は、穴埋め問題や、決まった答えでないと×だったりして、カタい。
言いたいことの表現方法はたくさんあるのだから、もっと柔軟であれば楽しく学べるのにな。 -
ノンフィクション作家である著者の、おおよそ20代を通しての一風変わった海外経験を素材として、「語学」という側面からスポットを当てて捉えなおしたユーモラスな体験記兼、ソフトな語学(言語)論となっている。時代としては1980年代中頃から1990年代中頃までの約10年間。全五章で、舞台となる国々は主にアジア、南米、アフリカの約8ヵ国にわたり、これに拠点である日本での語学習得や就業体験なども加わる。本書で習得の対象として登場する言語は12にのぼり、各章の表紙でどの言語が扱われているかが掲示される。約320ページ。活字以外に、随所で当時の写真も掲載されている。
現在もノンフィクション作家として活躍する著者のポリシーは「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」。このポリシーの原型は早くから心に秘められていたようで、外国語の習得は当時から著者の求める活動を実現するための重要なツールとして意識されていた。そんな著者だからこそ、UMA探索や覚せい剤栽培といった一般人であれば経験することのない数多くの奇妙な海外体験とともに、それに相応しい独特の言語学習方法が編み出されていった。本書はそのような著者の特性を活かした、「海外体験記」と「語学」のハイブリッドをコンセプトとしたノンフィクション作品になっている。
序文で断られている通り、本書内で扱われるエピソードには著者の過去作で紹介された体験記が数多く含まれる。そんななかでも本書は著者の海外体験の嚆矢となるインドでの英語にまつわる顛末に始まり、多感な二十代の約十年間の様々なエピソードを時系列に沿うかたちでたどりつつ、言語・語学の観点からの考察や分析などを織り交ぜていく流れとなっている。約四年前に出版された『辺境メシ』が著者の経験から「食」の要素を抽出するコンセプトだったとすれば、今回は「語学版」にあたるといえるだろう。
体験記としては、あらかじめ既出の著作と重複していることを意識して、各エピソードが過去のどの著作で登場したかが都度紹介されるため、各部の詳細に興味をもった読者が(再読も含めて)該当の作品に当たりやすいよう配慮されている。著者の体験記としてはダイジェスト版、すでに馴染みのある読者にとっては再放送的な側面は強いのだが、だいたいの著者作品に一度は目を通している私も楽しめて特に不満はなかった。この理由としては、本書が著者の20代全般を対象とした「青春記」も兼ね備えた体験記として他の著書との差別化がなされ、ひとつのストーリーとしての一貫性が保たれていることにもあるように思える。
本書随一の特色は何より、著者独自の海外体験を言語・語学の観点から捉えなおして、言語にまつわる情報や知見が紹介されるとともに、さまざまな考察がなされる点にあるだろう。
まずひとつは語学学習の側面について、25を超えるという多数の語学を学習した経験から、著者が有用と感じた学習法・コツが随所で具体的に紹介される。著者の言語との向き合い方をエピローグの言葉からふたつを挙げるとすれば、「ブリコラージュ的」で「親しくなるための言語」ということになる。つまり、手法としてはあり合わせの手作業・即時的で、コミュニケーションを潤滑にするという目的を重視する。これに対置されるのが、「エンジニアリング的」で「情報を伝えるための言語」であって、学校や資格習得で一般的な勉強法はまさにこちらに当たるだろう。最低限の座学はこなしながらも、ネイティヴとのコミュニケーションから生きた言語を貪欲に学び、その言語を操る人々とシンクロしようというのが著者の指向ということになりそうだ。なかでも、「言語特有のノリ」に合わせなければ、その言語を円滑に使うことはできないという視点は新鮮で、納得させられた。
語学だけでなく言語という観点でも、多数の言語への知識から言語同士を比較して俯瞰的に見渡す視点から導き出される数々の考察も興味深い。第三章で紹介される比較言語学と進化論の類比をベースとした捉え方は本書全体を貫き、各言語の類似や差異をイメージさせてくれる。個別の地域や言語としては、コンゴにおける言語の階層性や、南米のマジックリアリズム的現実を可能にした「平安京言語」としてのスペイン(ポルトガル)語の性質、定型の挨拶語や儀礼語が欠けている社会の特徴、などといった興味深い指摘が多く見られ、この点も本書を支える魅力のひとつとなっている。
ユーモラスな語り口で自虐も多分に交えつつ自身のユニークな体験を面白おかしく語るという著者特有の楽しさは相変わらずだった。同時に、随所で文化人類学・社会学的な視点から提起される鋭い観察眼が、語学・言語という新たな分野でも発揮されたのが本書だろう。ソフトでフレンドリーなスタンスを基本としながらも、社会や人間を見渡すときにみせる鋭さによって適度に起伏があり、一冊の読み物として飽きることなく読み通せる。個人的には言語という切り口への興味も手伝って、著者の新作を堪能できた。終章にあたる第五章のラストでは、かつて『アヘン王国潜入記』を読み終えたときの感動が鮮やかに蘇った。 -
語学の学習スタイル
・ネイティブに習う
・使う表現から覚える
・現地で使ってウケる
の3つは、まさにそうだと思う。
加えて、ITの普及した現代では語学は、単に情報を伝えるためのものではなくて、気持ちを通じ合わせるためのものだというのも共感した。
すっかり忘れてしまった語学の勉強をまたやりたくなった。 -
およそ一年前に読了した本だが、今年のうちに感想を書いてしまおう!ということで思い出しながら感想。
私を高野秀行氏にハマらせ、そして長らく離れていた読書の世界に舞い戻らせてくれた記念すべき一冊。私がチャンネル登録しているYouTube「丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニー」で、丸山氏と対談していたのを観て著者のことを初めて知った。丸山氏が尊敬してやまない作家とのことで、興味を持ち本書を手に取った。
いやー、面白い。面白すぎる!
学生時代、ミステリばかり読書していた私。ミステリには“冒険小説”というジャンルがあるが、高野氏のノンフィクションは、「事実は小説より奇なり」を地で行く破天荒さで、愉快痛快極まりない。幻の怪獣を探しにコンゴに行ったり、東南アジアの麻薬密造地帯に潜入して“ワ語”なる超マイナー言語を習得したり、とにかくそのバイタリティに感心する。文章もユーモアに溢れ、思わず声を出して笑ってしまうエピソードもそこかしこに散りばめられている。
本書を読んだのを機に、著者の作品は全部読もう!と心に誓った。長らく遠ざかっていた読書習慣が復活し、ブクログを始めるキッカケにもなった、私にとって記念すべき作品。
著者プロフィール
高野秀行の作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :