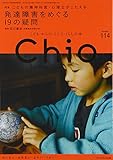- Amazon.co.jp ・本 (198ページ)
- / ISBN・EAN: 9784880491752
作品紹介・あらすじ
親子を楽しむ精神医学入門
こどもやその心についての知識は、ずいぶん豊かになりました。脳や心に関する研究は飛躍的に発展し、気軽に相談できる専門家や相談機関も増えています。ところが、「こどもの心が見えない」「今の子は、どう対応していいのかわからない」といった声は、かえって大きくなっています。
情報の洪水の中で、専門的な知識の正しさや価値を見分けるには、どうすればよいか。この本で、私が精神科医としておこなってきた解決方法について、書いてみました。情報の判断や選択は、もし科学的に追究しようとすれば、正直いって専門家でもお手上げです。しかし、忘れてならないのは「人間が生物であり、同時に生活者である」という事実です。
童心に返る。気持ちを汲む。これらができない大人はいません。ただ、これらを「できない」とか「してはいけない」と自己に暗示をかけている人が、少なくありません。ほんの少しゆとりと勇気と忍耐を取り戻して、こどもに寄り添ってみてください。すべては、ふしぎなほど簡単に見えてきます。暗示をとくために、本書が役立つよう、祈ります。
(「はじめに」より一部抜粋)
感想・レビュー・書評
-
詳細をみるコメント0件をすべて表示
-
『治療という幻想―障害の医療からみえること』に続いて読む。
本文挿画は山口ヒロミさんだった。
「バブル後の不況は、こどもをとりかこむ環境やこどもの心に対する見解を激変させ」、「悪質なこども観が、良質なものを学校や社会から駆逐している」との思いで、石川さんはこの本にまとめられた文章を書いたのだという。
おとなになるにつれて、こども時代とはちがった空間感覚、時間感覚をもつようになる。「こどもが待てなくなる未来には、けっこう楽しいことがたくさんあった」(p.15)のに、「待つ楽しさより、待ち時間の無駄のほうが気になるのがおとな」(pp.15-16)なのだ。
▼同じ一分が、時計を使うおとなにはほんの一分となり、こどもには永遠の待ち遠しさとなる。
…空間の認識。時間の認識。人間の基本的な感覚でさえ、おとなとこどもではまったくすれちがっている。(pp.16-17)
その「すれちがい」を中心に、児童精神医学のさまざまな問題を考えたのがこの本。
正常と異常、普通か普通でないか、それはあいまいなものなのに、こんなにも「フツー」へのこだわりが強い時代。
▼今日、幼児虐待の診断基準を、統一しようとする動きがあります。しかし、本当に求められているのは、正しい診断ではなく、殺さないし虐待しないで一緒に生きあおうとするおとな社会の新しい姿勢のように思えるのです。(p.30)
1994年の夏にこう書いた石川さんは、秋に続けてこう書いている。
人が人を殴っている。その表面的にあらわれた力関係に気をとられて、私たちは殴る側を抑えようとしがちだ。「暴力はいけない、相手は無抵抗なんだ、口でいえ」と。それは正論ではあるけれど、ゆとりのある人にとってのみの正論でもある。
殴っている人を見たら、まず「よほどの攻撃を受けて、自分を保つことすら困難な危うい立場に立たされている」と理解する必要があるのだが、そうわかっていてもなお、私たちは正論を口にし、殴っている側を抑えるのだと。
▼しかし、攻撃されて危うい立場に立たされている人に「攻撃をやめろ」というのは、「何をされてもあきらめろ」としか聞こえません。私たちは、どこかで堅苦しく固定化した理想像を愛情に求めて、息苦しい対応をしてしまうのです。(p.34)
だからこそ、とりあえずの解決、応急の処置は「力関係の変更」、つまり「弱者が、本当の味方を得ることで、自分のほうが強者になったと実感できること」だと石川さんは続ける。殴っている当人の味方になれるか?殴っている当人の気持ちを冷静に理解する必要があると、石川さんはその理解の程度を推量するア、イ、ウの基準をあげる。(これは、おそらく『援助者援助論』にもつうじる。)
こどもと親の関係、育児環境といったことについて書かれているいろいろにも、はっとする。
「親の影響が大きい」ことと、「だから親にはできることがある」ということは、簡単につながるものではない、むしろまったくつながらないと考えたほうがいいくらいだと石川さんは書く。
▼…自分のことであれ他人のことであれ、おとなであれ赤ちゃんであれ、精神については「わかった気になって納得する」以外に、理解したり、共有したりする術がないのです。はっきりしないところをとりあえず「わかった気になって」説明しようとするとき、いちばん有効なのは、たとえ話です。ただし、たとえ話がうまく伝わるには、たとえを共有する環境と、たとえが伝わる独自の雰囲気づくりが必要になります。
この環境や、雰囲気を、こどもに用意するのは親です。その意味で、親の影響は多大です。しかし、この環境や雰囲気は…努力によって「できる」ものではありません。(p.67)
「嘘つきはおとなの始まり」というII章では、学者の研究といわれるものが「科学的な見せかけの裏で予断による偏見を強めていく」ことに、石川さんはずいぶん怒っている。とりわけ"遺伝か環境か"の図式によって問題を腑分けしようとする態度に怒っている。それは、治療者にとって魅惑的な区分であるだけだと。
個人を遺伝によって差別する傾向が生まれ、それで切り捨てられるいのちの一方で、生きる権利を与えられた個人にはものすごい自助努力が求められる。この"遺伝か環境か"は、不登校にも応用されて、"脳の損傷か、親の育て方か"という問題にされ、脳が病気ならクスリ、悪い親なら良い親に変わらなければならない、という話になっていく。ここでも、求められるのは、当人の別枠処遇か、親の自助努力。
▼治療者は、区分が大好きです。近代の黎明期「敵か味方か」という区分で、バイキン撲滅に成功したためでしょうか。「自己と非自己」「脳死と心臓死」など、区分して治すのが西洋医学。精神医学もその影響を受け、不登校をはじめ多様で多面的な人間の行為を、単純に二分します。(p.83)
精神医療が、一大産業として次々と新しい病名をつくりだし(この本の104ページに羅列されている略語─MBD、MBD、LD、EC、AC、AT、ADHD、HHS、PSNS、SDD、SLD、ASD、HC、CD、CD、DBD…これらはすべて学習障害と診断されるこどもに与えられる呼び名のほんの一部だという)、消費者ニーズをあおって市場を開発している。
石川さんは、おとなが、おとなにとって耳触りのよい学習障害というレッテルをつくりだして、「結局こどもを保護される対象に追いこんでいく」(p.116)、そのような関係の差別にこだわって、しつこく書いていく。
▼差別は、「障害」があるから起こるのではありません。分けるから起こるのです。(p.118)
そして、こども時代の「ちがったまま、みんなと一緒にいたい」願望と、おとなになってからの「人並みでありたい」欲望とは、まったくちがうものだという。学校で勉強がわからないのは時につらい、しんどい。でも、「特別扱いさえしなければ、こどもは、わからないならわからないなりに、みんなと一緒にいる位置づけを、自分で見出して」いくものなのだと、その位置づけがみつかるまでの苦しみは大変でも、ぶつかって乗り越えるしかないと。
学習障害とレッテルを貼って、親やおとながそのこどもを特別扱いすることよりも、おとながやらなあかんのは「こどもの苦しみに寄り添いながら、特別扱いする障害者差別の圧力と戦うことだけ」(p.121)。
そんな石川さんも、身内である自分の母の希死願望の口癖には、むなしくなり、怒ってしまう。「自分でやる」ことで人生を支えてきた母が、される立場になっていくことにがまんならず、死にたいという。障害者とのつきあいがなかったら、自分も、母の尊厳死を願ったことだろう、と書いている。
▼「できなくなったら終わり」「人のお世話になりたくない」。この潔癖すぎる個人主義は、人間と人間の本来の関係を否定します。できないままの自分を素直に生き、おたがいに迷惑をかけあうところから、初めて本当の人間関係が始まる。障害者の主張を、そんなふうに聞けるようになり、すべてを一人で背負いこむ自己完結型の自立を幻想であると理解できるまでには、ずいぶん時間がかかりました。(p.137)
III章「素直にだまされること」では、大自然の偉大な摂理には素直にだまされることが肝心だと書いてある。
▼だまされるためには、わかろうとしすぎないことです。実際、親が知らなければうまくいくことがほとんど。虐待も、わかろうとしすぎたり、知ろうとしすぎたりするところから生まれることが少なくありません。(p.169)
どこか知りたがりの私は、こう読んで、ドキーっとする。でも、「わからへんことは、わからへんままでもっていよう」という気持ちもずーっとあって、それを忘れんとこうと思う。
(7/15了)
著者プロフィール
石川憲彦の作品











 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 














![こどもと出会い別れるまで―希望の家族学 [2冊セット]](https://m.media-amazon.com/images/I/31vnLgIR4xL._SL160_.jpg)