- Amazon.co.jp ・本
感想・レビュー・書評
-
人は遊戯なしにはあり得ない。「あそび」こそが人間の最も根源的な欲求の一つである。同時に、精神の最も高貴な機能でもある。
「あそび」の精神を欠いた文化は文化に非ず。「あそび」を失った文化は廃退の危機に立つ。急激な近代化のせいで「あそび」の土壌が突き崩されるに至るまで、われわれの伝統的文化は、この精神のたぐいまれな諸形式を生んだ。祭祀しかり、ダンスしかり、詩歌しかり、音楽しかり、闘技しかり、戦争しかり、法律しかり、学問しかり、政治しかり。
だが、現代は「あそび」を失ってしまった。「あそび」のみが機縁となる創造性を回復するには、人間性の根源に立ち返るほかない。
遊戯の定義として、ホイジンガは次のように示している。
「遊戯とは、①あるはっきり定められた時間・空間の範囲内で行われる②自発的な行為、もしくは活動である。それは自発的に受け入れた③規則に従っている。その規則はいったん受け入れられた以上は④絶対的拘束力を持っている。遊戯の⑤目的は行為そのものの中にある。それは、⑥緊張と歓びの感情を伴い、またこれは⑦日常とは別物だという意識に裏付けられている。」
また別のところで、
自らの意思で受け入れたその規則(ルール)は、物質的有用性、あるいは必要性の領域の外で働く
ということも重要な指摘となる。
ポイントは以下の7点。
①独自の時空間で完全遮断された別宇宙の開闢
②自発性
③独自ルール
④ルールの絶対的拘束力
⑤目的は行為そのもの(よって、物質的有用性・必要性の埒外、その対極にある)
⑥緊張と歓び
⑦非日常性
加えて、⑥の点に伴って次の要素も重要だ。
その不確定性ゆえの緊張から、競争意識、闘争本能が生まれる。競技、賭け事等はいずれも遊戯をその本質的特性とするものである。そして勝利したときの歓び、自らがその道の第一人者であることを誇示できた歓び、平たく言えば相手にマウント取ったときの歓び、これこそが人を遊戯に駆り立ててやまない根源的な欲求となるのである。
②自発性及び⑤行為性に関連して興味深い記述がある。古くギリシャの伝統から引き継いだ傾向として、中世ヨーロッパでは、芸術といえば音楽や詩歌、合唱、ダンスに限る、というのがあった。ミューズの恩恵を受けてしかるべき高尚な営みとは、それら現に今演じられている「行為」に限る。それに対し、彫刻や建築、絵画などは二流のお飾りに過ぎず、芸術などではない。それらは工作物に過ぎず、卑しい職人技なのだという。
もっとも、音楽やダンス、歌謡などに従事する芸人にしてもまた卑しい者と蔑まれてきた経緯があるので、一概に職人よりも社会的地位が高かったわけではない。ただ、芸術の評価として、静止物=彫刻や絵画、建築物、道路や橋などの公共施設等々はその範疇になかったというだけのことである。
それはともあれ、不確実でたえず動きのあるもの、現に今演じられているもの、それが「遊戯」の特性の一つである。それは同時にまた人間存在にとってもなくてはならない要素の一つといえる。なぜなら、「遊戯」の特質たる不確実性、絶えず動いていること、それは「生」そのものといえるが、人が人として生きていくのには、その「生」の本質に触れざるを得ない、絶えずそこに立ち戻ざるを得ないからである。
要は、人はその本性として「あそび」を求めてやまない存在である。すなわち、「ホモ・ルーデンス、遊び人」こそが人を人足らしめているものであることを端的に言い表しているといえよう。
そして、人の創造性は、それら「あそび」の時空間から発出されるのである。人が人であり続けるためには、創造性に支えられなければならない。創造性の源泉は「あそび」にのみ求められる。人が、食物、水を求めるのと同様に「あそび」を求めてやまないのは、この人を人たら占める源泉がそこに隠されているからである。「あそび」を喪失した人はもはや「人」たるを辞めざるを得ない。滅びの道に必然的に突き進んでいくであろう。
以前、糸井重里のコピー「くう・ねる・あそぶ」がお茶の間のCMに登場して話題をさらったが、あれなどもまさしく人間の本質を突いているからこそヒットしたのだといえる。
「遊戯」の対立概念として提示されているのが「真面目」である。これは、日常生活上のあらゆる領域に当てはまるものといっていい。要は「リアル」な現実世界のことである。「現実」なので因果律に支配され、目的が設定される。何か有益なことに従事していなければならない。逆に言えば、無益無用、役立たずは嫌われ、排除される。それが「真面目」世界の掟である。
近代合理化の流れは、この「真面目」世界一辺倒が目指されてきた。必然的に非生産的とされた一群の人々、障碍者等々が「役立たず」のレッテルを張られ、ゲットー送りとなった。まさにナチスが台頭し幅を利かせていた1930年代の時代空気がそれだった。その空気をまざまざと受け、時代に対して真っ向から警鐘を鳴らす意味で執筆されたのが本書である。
詩こそが遊びを最も本質的に捉えている。詩の形式は常に遊戯形式であると、ホイジンガは述べている。
「言葉の外的な形式の中だけに、詩と遊戯の関連があるのではない。それは、イメージを形づくるときとか、さまざまのモチーフに性格を与えて表現するやり方の中にも本質的な意味で現れる。神話的イメージの場合であろうと、抒情詩、叙事詩、戯曲であろうと、遠い過去の口碑であろうと、現代小説であろうと、そこには意識するとしないとにかかわらず、いつでも聞き手や読者を捉え、呪縛する緊張感を、言語によって創ろうという目標がある。常にある効果を達成しようとする問題がる。そして常にその土台は、緊張を人々に伝えるのに適したある種の人間生活の状況であり、人間感情のケースである。だが、そういう状況、場合は決して多くはない。非常に広い意味にとるなら、その大部分は闘争、あるいは恋愛の状況、もしくはその二つの複合したものである。(p230)」
「…すべて、何かを語るということは、イメージ、形象(ビジュアル)の中で表現をするということである。客観的に存在しているものと、人間がそれを理解するということの間に落ち込んでいる深淵は、ただ存在しているものを形象に変える働きが放つ一閃の火花によって、橋をかけ渡すことができるだけなのだ。
ただ、言葉に縛りつけられている概念というものは、動いている生の流れに対しては、どうしてもうまく適合できないのはやむを得ない。イメージを創る形象の言葉が事物を表現の中でくるみ、それに概念の光を当てるのである。イメージの中で、観念と物が統一されるのだ。日常生活の言葉は実際的な、慣用的な道具だから、全ての言語から形象性という性格を削り落としてしまい、一見したところ厳しく論理的な自立性を帯びているように見える。これに対して詩は、言語の象徴的、形象的な性格をことさら意図しながら培養し続けるのだ。
詩的言語が形象を用いてすること、それは遊戯である。それはさまざまの形象を様式的に整った形に系列づけて秩序を与え、そこにある秘義を含蓄させる。このようにして、どんな形象、イメージも、遊戯しつつある謎に対する答えを示すものとなる。(p232)」
長々と引用したが、この二か所からは特に強いインパクトを受けた。改めて、自分が詩人であることを、詩人となりたいことを強く自覚させられた箇所だからである。
以前は、散文と違って詩文を好ましく思っていなかった。今でもそうである。短い形式ばった詩文は、とっつきにくく、自分には決して好ましいものになりえない。
が、「詩人」とは、そうした形式ばった短文をものする人に限定されるのではない、と上記の引用文は強く示唆してくれている。現代小説という形式もまさにそれ、言葉をもって読者を捉えて離さぬ緊張感、独自の世界を目前に開こうとするわけだから、ファンタジー小説という形式をもって自分の世界観を構築し、表現を与えたいと切望するのも、やはり、「詩人」の在り方なのだ。
ヘルマン・ヘッセは幼少期より「言葉の魔法使いになりたい」と切望していたそうだ。かつて学生時代にヘッセに相当入れ込んでいた自分を振り返り、改めて思う。このヘッセのように、私も、「詩人」すなわち「言葉の魔法使い」になりたい、そうありたい、と魂の底から願うものである、と。詳細をみるコメント0件をすべて表示
著者プロフィール
ヨハン・ホイジンガの作品







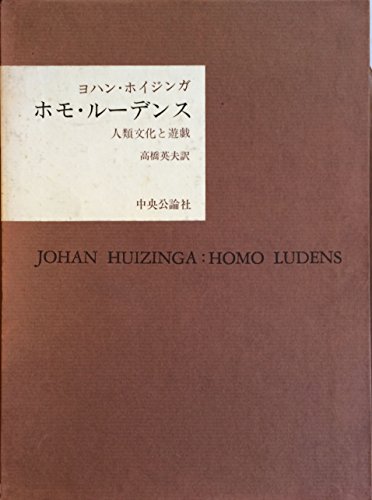


 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 



















