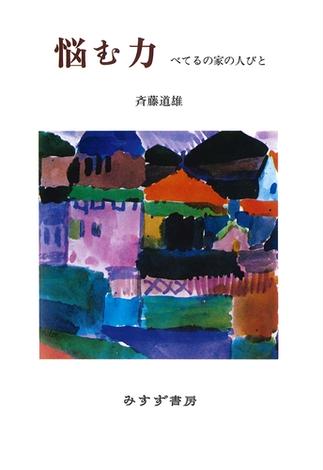- Amazon.co.jp ・本 (256ページ)
- / ISBN・EAN: 9784622089001
作品紹介・あらすじ
障害をもつ人びとを、精神科病棟のベッドから、医師や看護師のコントロール下から地域の中に戻すこと。グループホームで生活することで自分たちの苦労を取り戻し、そのことが、町も、健常者の側も、そして精神科医療そのものも変えてゆくこと……「治したくない」医師と「治りませんように」と願う当事者たちが織りなす浦河の四季。べてるの家の、さらにその先へ歩き出す。最新ルポルタージュ。
感想・レビュー・書評
-
『「先生、なんかやんないの?」診療が一息ついたところで、“師長さん”が先生に横目で語りかける。「あたし手伝うからさ、やんなさいよ」』―『あたしがなるから』
あたしが患者になってあげるから、新しい診療所を開きなさいよ、という看護師の言葉に背中を押されて本書が取り上げる「浦河ひがし町診療所」の精神科医は決心したという。もちろん、その言葉を字義通りに真に受けている訳ではないけれど、その言葉の真意を真に受けての決断だ。本書には、そんな表面上の理屈では片付けきれない、その裏にある根本的なもの(あるいはそれを本質的なものと言い換えても良いけれど、それが何かを鮮明にする訳でもない。あるいは、動物的な本能によるもの、と言い換えても良いような気もするけれど、それはただ単に、自然の摂理、と複雑なものも雑にまとめたくらいの意味しか持ち得ないだろう)との乖離が其処彼処に登場する。
そもそもの始まりも、言ってみれば矛盾に満ちた話なのである。長期入院の精神科の患者を退院させた(言ってみれば治療の成果が出た)結果、病院の経営が悪化し精神科病棟を閉鎖(新たな入院患者や外来患者の受け入れを放棄)せざるを得なくなる。そこで、吹っ切れて、新しい診療所を作(ってやりたいことをやりたいようにや)る、という流れなのだ。そして、この川村医師の患者への対応方針を端的に言い表した言葉が「治したくない」なのである。
本書で描かれている主に統合失調症の患者さんたちは、もちろん病に苦しんでいるし、社会的に不都合な状態に陥ることも多い。それでも、鎮静作用のある薬で「大人しく」させておくことが治療の究極の目標だと川村医師は考えない。地域で生活出来るのなら、病という名の性格と上手く付き合えるのなら、それで良いじゃないか、という。もちろん支援は必要であるし、その支援も時として壮絶なものになることもある。しかし、むしろ患者に人間とは何かを教えられる経験を積み重ねて、浦河ひがし町診療所メソッドは進化してゆく。その過程を放送局に所属していた元記者が丹念に追いかけまとめたものがこの本だ。
とはいえ、本書は決して「どう対応すれば良いか」を示したものではない。飽くまで「どうしてそれが起きたか」を読み取る本。そのための丹念なルポルタージュ、あるいはディテール(詳細)。そこから読み取れるものを端的に言うならば、多様性、ということになる。一人ひとり、その時々で事情やそれに対する反応は異なっているという「当たり前」を再認識する。
本書に登場する人々に限らず、人の悩みの大半は対人関係にあるとも言われる。つまり、単純に言えば「他人がいればイライラする」ということ。けれど他人が全く居なければ、意識は自分の中だけでぐるぐるとフィードバックを繰り返し、ハウリングのようにどこまでも増幅してしまう。結局、人はどうしたって人「間」であるということ、人「類」ではなくて(剥製にでもなれば人類だろうけど)。「類」というように複雑なものの共通項を抽出し、分類して一般化しようとすれば「個」は消失せざるを得なくなる。だから目の前の患者さんを個性のある人として見なくなる。何だか養老先生がいつも言っていることと同じような話(偏差値とか喫煙や高血圧の話とか、高いから良いとか異常だとかいう話じゃない、人によるだろ、という話)だけれど、そんなことを再認識するようなエピソードがこれでもかと記されている。そして、他人との関係を川村医師が一番に考えていること(干渉し過ぎないこと)こそが、まさに患者をして人として復権させ、社会適応出来る状態にすることを可能にした理由なのだと解る。とはいえ、川村医師も他人が解るとは言わない。むしろ分からない、積極的な意味で判ろう(それは対人関係をともすると主従関係に近い状態に押し込もうとする行為)としない。ああ、まるでレヴィナスの言う「他者」だなあ、と思っていたら、こんな文章に行き当たる。
『まるで鏡のように、精神障害は私たちのありようを反映するのである。そして精神障害への向きあい方は、私たちの社会のありようを反映する。(中略)それは何なのか。そこで診療所の人びとはいったい何をしているのだろう。なぜそんなことをしつづけていられるのだろう。そのようなとき、私の頭のなかではいつも「他者」ということばが浮かんでくる。それは二〇世紀フランスの哲学者、レヴィナスのいう意味での他者だ。「世界の組織のなかでは〈他者〉はほとんど無にひとしい。それでも〈他者〉が私に闘いをいどむことができる。言い換えるなら〈他者〉を打つ力に対抗することが可能であるのは、抵抗の力によってではない。対抗が可能であるのは、〈他者〉の反応が予見不可能であるからにほかならない」』―『無力、微力』
御意、という他ない。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
北海道の浦河でひがし町診療所を運営する川村敏明先生が、精神科の患者にどのように対応しているかを克明に記述した本だが、出てくるエピソードが全てユニークで非常に考えさせられた.所謂、統合失調症の患者が入院しないで普通の生活を営めるように支援することを実践しているのだが、医者とスタッフの連携が素晴らしく、余裕を持って対応して環境を維持しているのが特筆ものだ.様々な症状が出る患者を薬で抑えるのではなく、人間として対応することで自尊心を復活させるものだと理解した.大変なことだが、それを続けていることは敬服に値すると思う.
-
「くらしと教育をつなぐ We」2022年12・1月号の「日々、手話、楽し。」という明晴学園の事務職員で手話通訳者で学園の写真を撮っている清水愛さんのインタビューを読んだ→この学園の校長だった斉藤道雄さんというジャーナリストを知った→著作を読みたいなと思った
北海道の浦河というところで、日赤病院の精神科医だった川村敏明先生が開いた小さな診療所の記録。 -
何が普通で 何がそうでないのか
何が健常で 何がそうでないのか
斉藤道雄さんの本を読むたびに
深く考えさせられる
「べてるの家」に関する著作の時にも
たっぷり考えさせてもらいましたが、
今回は そのより発展した形での
「今」ということで
より思考をほぐしてもらえた気がします
「治したくない」
よくも 名付けたり
見事な 書名ですね -
2階書架 : WM075/SAI : https://opac.lib.kagawa-u.ac.jp/opac/search?barcode=3410168791
-
みすず書房
斉藤道雄 「治したくない」
総合失調症患者を 薬やベットから解放し、医療から生活ケアに 治療の重点を置いた「ひがし町診療所」のドキュメンタリー
「診療所の日々のありようは〜答えはない けれど 意味はある」という言葉から、治らない病気に向き合う無力感、そんな中で自分が何を求められているのか問い続ける探究心が 伝わってくる
当事者研究(患者が自分の病気を見直そうとする試み)としての様々なミーティングは 、解決を求めるのでなく、語る場を設け、たっぷりムダな話をしながら、まわり道と脱線を重ねて、少しずつ改善していく様子が読みとれる
-
読む前の書名からのイメージ。治ったら診療所を出ていくからそうしたくない。
読んだら違った。
治すことを目標にしなくなった、と書いたら誤解だろうか。
先生やスタッフの方の具体的な対応も学べるが、方向性や心の持ちようが印象に残った。 -
摂南大学図書館OPACへ⇒
https://opac2.lib.setsunan.ac.jp/webopac/BB50202195
精神科疾患を有する方が地域で生活するための支援やあり方について参考になります。 -
おもに医療やコミュニティのお話なのだけど、哲学や芸術のこととしても読むことができる。「社会/個人」などといった二項対立の間にある「/」についてもっと考えていこうぜっていう提言。とても良い本。
ただ、これはこれとして非常に存在意義のある本なのだけれど、ひがし町診療所の取り組みをもう少し簡便に伝えるような本もあればなおよいかと。 -
「べてるの家」について書いてきた著者であるが、これまでは当事者と彼らを支える向谷地さんの話が主であった。今回は、浦河日赤精神科がなくなり、「ひがし町診療所」が立ち上がり、そこでの経緯ややり取りを通じて、川村医師の人となりを伝え、精神障害者が地域でいかに生きているかを述べられた本である。今回は川村医師と彼を取り巻く当事者とスタッフのやり取りが中心であるが、当事者と援助者だけでの関係ではなく、ヒトとヒトがいかに関わっていくかを考えていくのにたくさんのヒントが詰まった本である。そのヒントの文として、「『しっかりしてない』たくさんの人たちがかかわるという援助のあり方は、じつは地域を作る上での核となる考え方ではないだろうか」「考えながら問題を引き受け、その時々に右往左往しつつさらに考え悩むとき、私達は自分自身の苦労を担い、自分自身の生き方を取り戻すことになるからだ」「なぜ失敗し、なぜ自分にはできないのかと悩みなげくとき、そしてまたその悩みを仲間とともに語るとき、そこには再生の契機がある」など。最後の章は、「出会い」。オープンダイアログ(OD)との共通性も感じるし、現在、当事者研究はODとも共同している。
著者プロフィール
斉藤道雄の作品










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :