- Amazon.co.jp ・本 (162ページ)
感想・レビュー・書評
-
天性の詩人という印象。都市における徘徊者。画家で言えば長谷川利行を彷彿とさせる。言葉の鋭利。感覚の鋭敏。
一見、堅いようだけれど、高村高太郎みたいなごわごわ積み上げていく建築性みたいなものは感じない。流麗さや、温情のやうなものを残しつつ、それを言葉の的確性・鋭利で練り上げて結晶化していく感じ。
日本の正統派の詩人の持つ調べや流れを引き受けつつ、その土台の上に、論理や鋭利な言葉が配置されていると言い換えても好い。なので、全体としては非常に柔らかな印象を受けるし、やはり日本人にしか書けないものを書いたという印象を受ける。
◎
琺瑯の野外の空に 明けの鳥一つ
アルカリ性水溶液にて この身を洗へ
蜻蛉は眼光らせ 露しげき叢を出づ
わが手は 緑玉製ISISの御膝の上に
◎
あけぼの未だ来ず
静かにして平らかなる野よ
風は死人の髪の如く
枯枝のほとりに震ふ
刈られざる雑草の上に、
目のごとく露は結びそめ
その上に暗き空かかりて
星はかすかに青みを帯びて動く
彼方に地平あり、
黒き断頭壺は、されど地に隠れず。
夜は濃くその上にあつまりたれど、
音もなし、底知れぬ海のごとくに
◎
ただひとり黎明の森を行く
風は 心虚しく 幹のあはひを翔り、
木々はみな、 その白き葉裏を反す
木の間がくれに 足速に
白き馬を牽きゆくは誰ぞ。
道の邊の群れをののけり。
かかるとき、湿りたる岩根を踏めば
ああわが出生の記憶蘇る
◎
雪解けの午後は淋し
砂利を噛む荷車の
轍の音遠くきこえ
疲れ心地にふくみたる
パイプの煙をののく
室ぬちは冬の日うすれ
描きさしのセント・セバスチャンは
低くためいきす。
電灯のとぼるを待ちつ
われは今わが心の洞を眺む
◎
★
ありがたい静かな夕べ
何とて我がこころは波うつ
いざ今宵一夜は
われととり出でた
この心の臓を
窓ぎはの白き皿にのせ
心静かに眺めあかさう
月も間もなく出るだらう
◎★
病みさらぼへたこの肉身を
湿りたるわくら葉に横たへよう
わがまはりにはすくすくと
節の間長き竹が生え
冬の夜の黒い速い風ゆえに
茎は憂々の音を立てる
節の間長き竹の茎は
我が頭上に黒々と天蓋を捧げ
網目なすそのひと葉ひと葉は
夜半の白い露を帯び
いとも鋭い葉先をさし述べ
わが力ない心臓の方をゆびさす
◎
古池の上に
ぬつと突き出たマドロスパイプ
下ではあめんぼが
番つたまますつと走る
しやがんだ散策者の
吐き出す煙が
池の中で夕焼雲に追ひすがる
◎
五月のほのかな葉桜の下を
遠き自動車は走り去る
わが欲情を吸収する
堀ばたの赤き光塔よ
埃立つ道に沿ひて
兵営の白き塀は曲りゆくなり。
◎
坂を上り詰めてみたら
盆のやうな月と並んで
黒い松の木の影一本
私は、子供らが手をつないで歌ふ
『籠の鳥』の歌を歌はうと思った。
が、忘れていたので、
煙草の煙を月の面に吐きかけた。
煙草は私の歌だ
◎
陽の眼を知らぬ原始林の
幾日幾夜の旅の間
わたくし 熟練な未知の探検者は
ただふかふかと頭上に生ひ伏した枯葉の
思いつめた吐息を聴いたのみだ
ただ脚裏に踏む湿潤な苔類の
ひたむきな情感を感じたのみだ詳細をみるコメント0件をすべて表示
富永太郎の作品







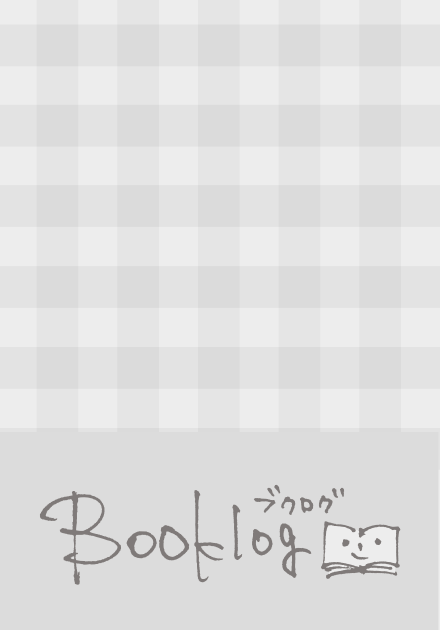

 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 























