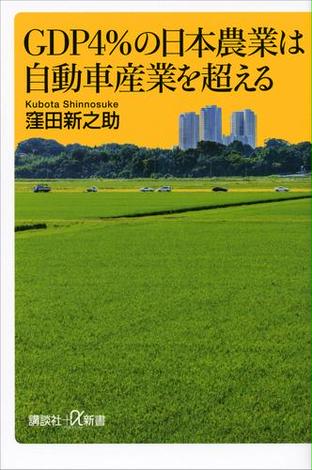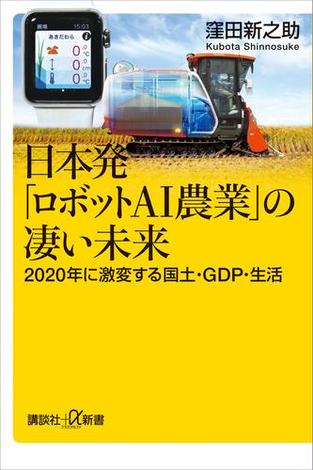- Amazon.co.jp ・電子書籍 (221ページ)
感想・レビュー・書評
-
日本が一生懸命に育てて、改良した新品種を無断で隣国で栽培される。農業新規従事者に多額の補助金を配って支援したものの、数年後には農業とは別の雇用に従事される。国内でまかなえない米の供給を輸出ではなく、減反で解決しようとする。
本書で並べられる日本の農政には未来を感じられない。
タイトルの「誰が農業を殺すのか」の答えは無責任でヤル気がなく、予算さえ確保すればいいという「これぞお役所」的な日本農政になるのだろう。が、こんなお役所に誰がしたと考えると、それは日本の農家に行き着く。
親から引き継いだ農地があるから、補助金がもらえるから、食費の足しになるから、といった理由で農業で稼ぐことを目指さず、なんとなく存在している農家が日本には多すぎる。収支を考えない農家は無償で退場してもらい、農業をビジネスとして本気で経営する農家が出しゃばってくれるくらいが、この閉じた農業界にはちょうどいいはずだ。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
かなりセンセーショナルな題名である。農業は殺されていると言う判断とその犯人は誰なのか?ということだ。農業を殺している犯人は、農水省とJAである。なぜ?その根拠は?をるると語る。
農家が減少している。2020年農家数は107万人。5年間で30万人減少している。平均年齢67.8歳。65歳以上が69.6%。さらに5年経てば、さらに10年経てば、農家が集団離農する時代がやってきている。
1つ目に、農水省の保護政策が農業を殺している。農家のためではなく、農水省と農協のための保護政策である。減少している農家は、儲からない農家、高齢のために離農する農家、後継者のいない農家。農水省はそういう農家を保護してきたから生き残っているだけで、本来ならば、もっと早く離農していたはずだ。保護政策をしてきた農水省が、殺してきた根拠にあげる。
2つ目に、日本で育種されている植物は、民間においてはF1種子の技術で野菜などは知財で守られている。しかし、農研機構や県で育種された品種は、いつの間にか中国や韓国で作られていて、知財保護に対して、国や県が保護することをしてこなかった。これは、明らかに怠慢である。
愛媛38号というみかんが「果凍橙」という名前になって、中国の12000ヘクタールの15%で作られている。それも、試験品種で日本では普及していない。「愛媛生まれ、四川で興る」。一般的なカンキツよりも高品質で、高単価となっているという。著者はそのことを愛媛県の担当者に問い合わせたら、そのことさえも知らなかった。まぁ。県の育種って、その程度の認識しかないのだ。農研機構の育種したシャインマスカットにしても、中国で53000ヘクタール、韓国で1800ヘクタール、そして日本では1840ヘクタール栽培しているという。まったく、アホですね。静岡県育種のイチゴの紅ほっぺも、中国で44000ヘクタール、日本のイチゴ栽培の総面積の8倍近い面積で作られている。知財軽視は、農水省が犯人だ。そこに大きな利益損失がある。著者は、知財こそ日本農業の利益を上げていくものだとしている。
3つ目に、コメにおいて奨励品種という品種の縛りがあり、それが大きな問題となる。さらに、お米の先物取引を進めようとしてが、コメ族の議員と全農の横槍で中止された。先物取引きは、コメの価格を明確化し、安定した取引が可能となる。日本は200年以上のコメの先物取引の歴史があり、戦争中に取りやめになった。それ以降コメの先物取引がされていない。中国の大連では、先物取引きが同じ時期に始められて、大きくコメの取引が変化している。コメの価格のブラックボックスは時代にそぐわない。いずれ、コメの価格は中国が決めることになるかもしれない。
4つ目に、農水省は海外市場展開でといい、2020年の輸出1兆円達成が、農水産物の比率は少ない。金額ベースで加工食品の輸出が40%占めている。穀類等で、コメが59億円なのに、穀類などで560億円としている。小麦粉や麺類なども含まれてる。それはアベノミクスの方策の一つである「農業、農村の所得倍増計画」2013年がある。まったく、実現されなかった。農業生産額を当時の9兆円から12兆円に回復させる。そのために海外市場がターゲットになったのだが、やはり国のやることはお粗末というしかない。
5つ目に、みどりの食糧システム戦略に、「2050年までに化学農薬の使用量50%減、化学肥料の使用量30%減、有機農業の面積を農地全体の25%とする」。その時の有機農業の栽培面積は06%だった。ふーむ。有機農法は、収量を上げることができない、手間もかかる、湿潤な気候で病害虫が出やすい中で、出口戦略がなく、単価もあまり高くない。
慣行農業で儲からないのに、有機農業で儲けるとは至難の業だ。問題は、有機農業をやる有機資材が限られていて、高いのだ。結局は、日本において狭い栽培面積で農業をすること自体が非効率だ。
スリランカの例が象徴している。2021年政府は、国内全土を有機農業を100%にすると宣言して、化学肥料、農薬などの輸入禁止をした。コメや紅茶の生産量と品質が落ちるという指摘があったが、大統領は無視した。結果2022年7月にそれが間違いだったと撤回、大統領は辞任せざるを得なかった。
農業は、思想や理念で成立するものではない。
まぁ。こうやって殺されてきた農業を、どう蘇生できるか?ピンチであれば、チャンスだという単純な話ではない。スマート農業で、ドローン、AIを駆使すれば、農業がイノベーションできるかといえば、無理がある。人口減少による市場の縮小、資材、肥料、アブラの高騰、輸送費の高騰、気候の温暖化による線状降水帯の被害、など農業をめぐる環境はますます厳しい。
意欲のある農業経営者の努力と育成だけで、解決はしない。こうやって、農業を殺した犯人を見つけて、解決した訳ではない。なぜなら、犯人はそのまま逮捕もされていない。読んでいて、痛快だった。ただ農業は、殺され続ける現実から、抜け出す方策を見出すしかない。 -
まとも過ぎて、特に突っ込むことは無いですね。
鈴木某、山田某、堤某など農業・食に関するデマ本は破り捨てこの本を読みましょう。
https://seisenudoku.seesaa.net/article/497651920.html
著者プロフィール
窪田新之助の作品










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :