- Amazon.co.jp ・本 (276ページ)
- / ISBN・EAN: 9784121025944
作品紹介・あらすじ
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』『仕事としての政治』などで知られるマックス・ウェーバー(一八六四~一九二〇)。資本主義の発展や近代社会の特質を研究し、政治・経済はじめ、幅広い学問領域で活躍した。本書は、彼の生きた時代と生涯をたどりつつ、思想のエッセンスを解説する。彼の「近代」への思索は今、何を問いかけるのか。没後一〇〇年という節目に、巨人の遺産に向き合う。
感想・レビュー・書評
-
少々だらだらと長い備忘録のようになって申し訳ない。ウェーバーに興味を持つ人なら、いろいろとメモを取りたくなる本である。
著者はウェーバーの『仕事としての政治』『仕事としての学問』を翻訳し直した野口雅弘さんである。冒頭、「本書では、ドイツの法学者・経済学者・社会学者のマックス・ウェーバーの「哲学的・政治学的プロフィール」を描く」と書く。特に、代表作である『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』や、宗教政治学の探求、その日本での受容についての解説が詳しい。また、学問上の業績だけではなく、ウェーバーが父と大喧嘩をした後、家を出た父が旅先で和解の機会なく亡くなったこと、その後精神病を患って一度研究の場から身を引いたこと、など彼のパーソナルヒストリーも程よい長さで説明されている。妻のマリアンネがウェーバーの死後、彼の名声や業績を維持するために果たした役割などまで言及されている。新書フォーマットで、著者は入門書としているが、十分に厚い内容をもった本になっている。
マックス・ウェーバーが亡くなったのは今からちょうど100年前の1920年6月14日。当時流行していたスペイン風邪(インフルエンザ)によって亡くなったと言われているが、100年後の世界が新型コロナの世界的流行に襲われているのは奇遇でもある。没後100年、あらためてその業績と現代における意味を問い直すのによい機会であるとも言える。
【プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神】
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、ウェーバーの主著であり、「今日、マックス・ウェーバーがマックス・ウェーバーとして世界的に名声を享受しているとすれば、その多くの部分は、彼が病み上がりの時期に、この作品を書いたからといっても過言ではない」と世間的にも高く評価されている。難解とされる同書であるが、合間に挟まれた詳細な注解を飛ばして読むのであれば、ウェーバーの主張するところは非常に明解である。本書ではこの主著の概略とその読まれ方、宗教社会学への発展について分かりやすく解説されている。
同書は、「近代の大商工企業における資本所有や経営、それから高級労働にかかわりをもつプロテスタントの数が相対的にきわめて大きい」という事実がいかにして説明可能であるかを検証するものである。欲望を肯定し、その欲望にドライブされた自由な競争によって発展するというのが資本主義の一般的な直観であるとすれば、非常に禁欲的なプロテスタント社会においてこそ発展したことはその直観に反することである。しかし、まさにそこには「選択的親和性」があったがゆえにそのエートスが資本主義の爆発的な発展を生むこととなったとするのがウェーバーの慧眼である。ここで「選択的親和性」とは、「一見、まったく関係のない両者が相互に科学反応を起こす、というイメージの言葉である」と解説される。完全に論理的な因果関係でもなく、必要十分な条件でもないが、プロテスタンティズムの倫理が資本主義の発展を準備したとは言えるのではないか、というのが「選択的親和性」がここで示す意味である。その論理は次のように要約できるだろう。
「正当な利潤をBeruf〔仕事〕として組織的かつ合理的に追求するという心情〔信条〕を、われわれがここで暫定的に「(近代)資本主義の精神」と名づけるのは、近代資本主義的企業がこの心情〔信条〕のもっとも適合的な形態として現れ、また逆にこの心情〔信条〕が資本主義的企業のもっとも適合的な精神的推進力となったという歴史的理由による」
そして、天職(Beruf)の理念と誠実に仕事を打ち込むことこそが自らが救われていることの確信を得ることにつながるという思考こそが、資本主義の資本家と労働者ともに親和性をもたらしたというのである。『プロ倫』のなかでも次のようにプロテスタンティズムの宗教的倫理による人材形成の重要性が説かれている。
「決定的な転換を生み出したのは、通常〔…〕厚顔な投機屋や冒険者たち、あるいは端的に「大富豪」などではなくて、むしろ厳格な生活のしつけのもとで成長し、厳密に市民的な物の見方と「原則」を身につけて熟慮と断行を兼ねそなえ、とりわけ醒めた目でまたたゆみなく綿密に、また徹底的に物事に打ちこんでいくような人々だったのだ」
また、著者は次のように語る。
「こうして、プロテスタンティズムの倫理から「意図せざる結果」として近代資本主義が生み出されていく。ウェーバーは次のように述べている。「近代資本主義の精神の、いやそれのみでなく、近代文化の本質的構成要素の一つというべき、ベルーフ理念を土台とした合理的生活態度は〔…〕キリスト教的禁欲の精神から生まれ出た」
ここでの「ベルーフ理念」はウェーバーの理論にとって非常に重要な理念である。聖書にはそういった含意がなかったがドイツ語への翻訳にあたってベルーフ(Beruf)という訳語を採用したことにより世俗の仕事が神から与えられた天命という意味を含むこととなり、それがゆえに世俗の仕事に一層勤しむことが宗教的に正しいこととされたというのである。そのベルーフ理念は現代的な課題とも言えるのである。
「今日、「働き方」がますます難しくなっているなかで、ベルーフの訳語の再検討はウェーバー研究だけの問題ではない。彼にとってこの言葉は、ワーカホリックなまでに、「仕事」に痙攣的にしがみついていた、ついこの前までの自分を読み解く鍵でもあった」
この辺りが、当時からも続く『プロ倫』の今日的意義でもある。なぜなら、宗教心がなくなってからも、資本主義の精神はわれわれを縛り続けるからである。
「宗教的な動機によって世俗の労働に勤しんでいた人たちから宗教心が抜ければ、勤勉で、合理的な営利活動と、それを善とする経済倫理が残る」
これをウェーバーの言葉で言うと次の有名なフレーズにつながる。
「ピューリタンは仕事人間たろうとした。私たちは仕事人間にならざるをえない」
いわゆる「鉄の檻」に閉じ込められるという話である。
「内面ではなく、外枠が自己展開するなかで、内面はむしろ外面によって閉じ込められ、それどころか無用なものにされていく。今日の資本主義的な営利活動は、あたかも「スポーツのような」性格を帯びてきている、とウェーバーはいう。〔…〕内面があって外的な仕事がなされるのではなく、外的な仕事の要請に合わせて内面的なモチベーションがでっちあげられる。こうした状況では、もはや「天職人」であることはできない」
なお、「鉄の檻」については、アメリカで同書が翻訳された際に、翻訳者であり社会学者のタルコット・パーソンズがあえてそのように訳したのだが、動物園の猛獣の檻のようなイメージを持ってしまうのは間違いである。著者も次のように補足する。
「パーソンズはこの英訳のなかで、「鋼鉄のように硬い殻」というフレーズを「鉄の檻」(iron cage)と翻訳した。この語は、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の末尾に出てくる。資本主義のシステムが自己展開していくなかで、このシステムの外枠に人間が組み込まれ、閉じ込められていく、というイメージが語られる部分である」
これに続きまた有名な個所であるが、ウェーバーも『プロ倫』を締めるにあたり、ニーチェの末人を引いて次のように語るのである。
「こうした文化発展の最後に現れる「末人たち」にとっては、次の言葉が真理になるのではなかろうか。「精神のない専門人、心情のない享楽人、この無のもの(ニヒツ)は、人間性のかつて達したことのない段階まですでに登りつめた、と自惚れるだろう」と」
著者は、こういった思考の裏にはウェーバーの出自にも関係があるのではとも示唆するが、興味深い議論である。
「最も信仰心に篤く、それゆえ拝金主義を嫌悪している禁欲的プロテスタンティズムの信者が最も熱心にビジネスに勤しみ、そして成功しているのはなぜなのか。社会科学の方法論の水準でこの論証が成功しているのかどうかについてはいろいろな議論がありうる。ただ、ウェーバーの生涯をたどる本書の視点からして興味深いのは、プロテスタント的な信仰から金儲けをひどく憎みながら、実際は事業で思考したモデルが、まさにウェーバーの家系だった点である」
また、宗教改革にその起源を求めるという思考が、西洋社会で生まれた人権思想がフランス革命や啓蒙主義から来ているのではなく、宗教改革にその源流を求めることができるとしたイェリネクの論理思考にもある種の相同性を持っているとの指摘も非常に興味深い。
「「個人の、譲渡できない、生得的で、神聖な諸権利を法的に確定しようとする理念は、政治的ではなく、宗教的な起源をもつ。これまで革命の産物であると思われていたものは、実は宗教改革およびその闘争の果実なのである」(イェリネク『人権宣言論争』)。ウェーバーは、人権宣言の宗教的な期限というイェリネクのテーゼを、経済と宗教の関係に転用した」
そういう観点では「規律化をはじめ、ある意味ではとても近いことを問題にしながら、ミシェル・フーコーがウェーバーに言及することはほとんどなかった」という著者の指摘について、自分もその違和感に同意するものであり、それはフランスでのウェーバーの受容がある意味不十分であることを示しているのではと思うところである。また同時にフーコーがウェーバーを論じるとすれば、どのようなものとなったであろうかと少し残念にも思うのである。
なお、ここで注意しなくてはならないことは、『プロ倫』で論じられたことが「理念型」であることである。それを見失うと、あらぬ批判や疑問を持つことになる。
「理念型はひとびとがそれに準拠して行為する規範ではなく、あくまで理論的な構成である。ウェーバーは禁欲的プロテスタンティズムの理念型を描こうと試みているが、こうして提示された理念型に準拠して、人びとがプロテスタント的に生きなければならない、というわけではないし、それを求めているわけでもない」
また、『プロ倫』で論じたことによってすべての説明がつくものではないというのも繰り返し述べているのも、ウェーバーの学問への誠実さの現れなのである。
いずれにせよ本書の解説は非常に的を射たものであり、理解を助けるものであった。また同書が資本主義の力学や働き方について非常に深い洞察を与えてくれる本であることは間違いなく、その名声に恥じぬ著作であるという認識を新たにするものであった。
【比較宗教学プロジェクト】
『プロ倫』でプロテスタントと西洋社会の関係を論じたウェーバーは、宗教と社会の関係を世界的視座に捉えた比較宗教学のプロジェクトを推進する。
「このプロジェクトでウェーバーは、「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を起点に据えながら、その枠組みを発展させて「世界宗教の経済倫理」を比較し、「ヨーロッパ近代」の固有性を明らかにしようとする」のである。
何より、宗教に頼ることができない初めての時代を生きた政治哲学者の一人として、ウェーバーはそのことに非常に意識的であったとする。何より「自分の時代を「魔法が解ける」という表現で特徴づけたのは、ほかでもないウェーバーだった」のである。
ウェーバーは次のように語る。
「人間の行為を直接に支配するものは、(物質的ならびに観念的な)利害関心であって、理念ではない。しかし、「理念」によってつくりだされた「世界像」は、きわめてしばしば転轍機として軌道を決定し、そしてその軌道の上を利害のダイナミズムが人間の行為を推し進めてきたのである。つまり、「どこから」、そして「どこへ」「救われる」ことを欲し、また――これを忘れてはならないが――「救われる」ことができるのか、その基準となるものこそが世界像だったのである」(マックス・ウェーバー『宗教社会学論選』)
宗教が世界像を含んでいる限り、その魔術への信仰が失われたとしても、その宗教がどのような理念を持っていたのかは重要である。それは『プロ倫』において論じられたように、プロテスタンティズムが資本主義の世界像に影響を持っていたのと同じである。
「ウェーバーは人を動かし、社会を変革していく力として、理念や「世界観」に注目する。世界の見方、人間の理解の仕方、生きる意味などについての思想や情報がプールされているのは、宗教的な観念世界である、と彼は考えた」
「魔法が解ければ解けるほど、人は生きる「意味」を切実に求める。魔術が解けて、再魔術化が呼びこまれる」と言うのは、まったく正しい認識である。
ウェーバーは彼の問題意識を次のように表現する。
「近代ヨーロッパの文化世界に生を享けた者が普遍史的な諸問題を取扱おうとする場合、この人は必然的に、そしてそれは当をえたことでもあるが、次のような問題の立て方をするであろう。すなわち、いったい、どのような諸事情の連鎖が存在したために、他ならぬ西洋という地盤において、またそこにおいてのみ、普遍的な意義と妥当性をもつような発展的傾向をとる文化的諸現象――少なくともわれわれはそう考えたいのだが――が姿を現すことになったのか、と」(マックス・ウェーバー『宗教社会学』)
「たんなる営利活動ではなく、近代的な資本主義は、プロテスタンティズムによって特徴づけられたある特有の文化的な背景のもとで成立したのではないか、という『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』での問題関心を、ここでは「西洋」の地盤で成立した「普遍的な意義と妥当性を持つような発展傾向をとる文化的諸現象」へと一般化している」と著者が説くように、そのスコープはより一般化されたが、西洋中心主義の思考はより先鋭化されることになっている。現在で同じ分野の研究をしようとすれば、もう少しナイーブなアプローチが必要となろうが、この時代のウェーバーにとっては、いかにして西洋がそのときにあったようにならしめたのかを宗教から論じるのは強い内在的な必然性とある種の確信をもっていたものと思われるのである。しかし、少なくとも現代においても宗教の問題は総体的に見れば「脱魔術化」された状態とはほど遠く、いまだ世界が分断される理由にもなっている。ウェーバーが確立しようとした宗教社会学は。現代でも形を変えた有用性を持っていると言えるのではないかと思うのである。
【戦争と政治とナチズム】
ウェーバーが生きた時代は、第一次世界大戦を経て、欧州が政治的混乱に陥っていた時代でもあった。晩年、ウェーバーも政治に深くかかわることとなった。『仕事としての政治』は、政治に関する深い分析であるとともに、ある種のコミットを進めると宣言する類のものであったのではなかったか。本書は、ウェーバーの政治、特に戦争や正義に関わる議論やコミットメントに対して、主に後の思想家・政治家によってどのように扱われたかが解説されている。
この時代において、武力行使と国家の問題は、非常にアクチュアルな問題であったが、それに対してウェーバーはある意味でとても明確である。ウェーバーは国家とは、「ある一定の領域〔…〕のなかで、レジティマシーを有する物理的な暴力行使の独占を要求する(そして、それを実行する)人間の共同体である」と定義している。
著者はウェーバーの正義に対する態度をロールズと比較して次のように評価する。
「ウェーバーは基本的に「正義とはなにか」を主題化して問おうとはしない。正義について論じても、彼が関心を寄せるのは、正義をめぐるコンフリクトに対してである。形式合理性と実質合理性の対立は論じるが、それに対する一義的な解答を出すことはない。これに対してロールズの著作では、権力(power)が主題化されることはない。たしかに『政治的リベラリズム』でロールズは、さまざまな価値が理に適う仕方で対立することを確認する。しかしそうした認識から権力と権力行使をめぐる理論を展開するわけではない」
また、第二次世界大戦の悲劇を通して文明や啓蒙の野蛮さを論じた『否定弁証法』のホルクハイマーとアドルノが、いかにウェーバーの議論を継承しているのかについて解説している。
「ホルクハイマーとアドルノは、「合理化の過程が新たな野蛮を生む」という。ここにはウェーバーの議論の一つの暗い側面が、彼ら独自の仕方で、より先鋭的に表現されている」
逆にアーレントがウェーバーに対して否定的であったのは、家長父主義的な部分や、それとつながる西洋至上主義的な部分があるからだと理解できる。
ウェーバー自身は、ナチズムの台頭を見ることなく亡くなったわけだが、当時の哲学者・政治学者にとって、ナチズムとの関係は一種の踏み絵でもあった。すでにその場にはいなかったウェーバーもあるときにはその意図とは離れて政治的に引用されることもあった。特にドイツにおいては、ナチスの理論的支柱にもなった「カール・シュミットがマックス・ウェーバーの正統的な弟子であったという事実を蔑ろにはできない」という側面もある。また、カリスマを待望するかのような論述をしたことや、大統領制を希求したことも、それがまだ姿を見ぬヒトラーを受け入れる素地になったのではないかという指摘も受ける。自分も、ウェーバーが西洋の優位性を隠すことがないことから、優生主義との親和性もあったのかもしれない。
しかしながら、どのように考えてみても、仮にウェーバーがその時代まで生きていたとして、安易にナチスのサポートをしたとは思えない。次の有名な言葉は、どちら側の人間であっても手に取ることができる便利な言葉ではあるが、それでもナチズムの思想には向かない言葉であると思う。
「政治というのは、硬い板に力強く、ゆっくりと穴をあけてゆく作業です。情熱と目測能力とを同時にもちながら掘るのです。この世界で何度でも不可能なことに手を伸ばさなかったとしたら、人は可能なことすらも成し遂げることはなかった」(マックス・ウェーバー『仕事としての政治』)
著者もまた次のように語るとき、政治家と政治学者が守るべき誠実さについて語っているのではないかと思う。
「この意味で、真理は政治の敵である。複数の意見の可能性があるところでのみ、政治的な議論は成り立つ。全員の賛同を得ることが期待できないが、「私はこう思う」と一人称で語る余地を確保できない政治理論は非政治的である。カッコの付かない客観性を我がものとして、その他の意見を排除することを目指す理論的な営みは、政治学の名のもとで、政治を否定しかねない」
『プロ倫』でもそうであったが、ウェーバーの政治論については、それが「理念型」について論じているのかどうかを気に掛けることであろう。著者の次の記述がその理解には役に立つのである。
「理念型の善し悪しを評価する基準は、現実との摩擦のなさではない。あまりに違和感なく受け入れられる理論は、それがある角度からの「切り取り」であることを忘れさせる。理念型の特徴となる機能は、なんとなく生きていると気づかないことに気づかせることである」
【日本でのウェーバーの受容】
著者は「日本では、世界的にも例外的なまでに、ウェーバーの著作が熱心に読まれてきた」と書くが、日本おけるウェーバーの受容の分析が本書のひとつの特色であるとも言える。著者も「ウェーバ没後100年にウェーバーについて書くということは、彼の著作が彼の死後どのように多様に読まれてきたのかについて考察するという作業を抜きにしては不可能である」と意気込む。
日本で特異的に受容された理由として著者は、日本が「ヨーロッパ近代」を学ぶ必要性があり、ウェーバーの問題意識と合致するものであったからである。よって、「ヨーロッパ近代」を素描した人という側面に注目して、ウェーバーの哲学的・政治的プロフィールを描く、というのが本書の基本コンセプトにもなっているのである。
一方、パーソンズの弟子筋にも当たるN.ベラーが『徳川時代の宗教』という著作を書いているが、その中で日本の古来の思想の中にプロテスタンティズムの代替物があることが論じられている。それが、日本が近代化に成功した要因であるかもしれないし(わかりやすい図式だが)、また日本でウェーバーが広く受容される素地を作ったのかもしれない。
「ベラーは、近代日本の経済発展の成功を説明するために、ウェーバーの「プロテスタンティズム・資本主義テーゼ」に注目した。そしてパーソンズの図式から、日本の思想伝統に禁欲的プロテスタンティズムの「機能的代替物」を探し、江戸中期の思想家の石田梅岩(1685~1744)が開いた石門心学を発見した。たしかに心学では正直、倹約、勤勉が重視された。そして心学に共鳴した近江商人は、日本の初期近代の資本主義に多大な影響を及ぼした」
このテーゼは、明治日本の近代化だけでなく、また第二次世界大戦の敗戦後の復興にも当てはまることなのかもしれず、ビジネス論としても深堀りすべきテーマであるように思う。
日本で、大塚久雄や丸山眞男といったサポーターを得て、これだけしつこく読み継がれる一方で、当のウェーバーは日本に関してはあまり多くを触れていない。「宗教社会学」のコンセプトに日本がしっくりとはまらないとウェーバーが判断したことも原因かもしれない。著者によると宗教社会学の一連の研究の中でも次のように触れられているのみだということである。
「日本人の生活態度の精神が持つ、我々の関連にとって重要な特性は、宗教的要因以外のまったく別の事情、つまり政治的社会的構造の封建的な性格によって作られている」(『ヒンドゥー教と仏教』)
近代ヨーロッパの特異性を論じたウェーバーにとって、西洋以外で近代化を果たした日本はより強い興味を引いてもおかしくはなかっただろうにとも思うのである。スペイン風邪に倒れることがなかったら、以降台頭し世界史の舞台に躍り出ることになる日本についてもより深い分析がされたのではないかと残念である。
いずれにせよ、日本では著者がロスト・イン・トランスレーションというように、翻訳や文化的背景の違いのもと正当ではないであろうものも含めて多くの解釈がなされて受容されてきた。それは、日本にとってやはり近代ヨーロッパとは何かということが何よりも重要だという問題意識があり、西洋において自明であったものが、必ずしも自明でない中でそれを読むことによって豊饒さが生まれたのではないかと思うのである。
「日本でウェーバーを読むという作業の連続には、こうした広い意味での「開国」の経験が伴っていた。開国の必要がウェーバーのテクストを読むことを促し、ウェーバーのテクストを読むことで日本を反省的に捉えかえす試みがなされてきた。「普遍的なもの」がなにかをめぐっては論争があるとしても、「普遍的なもの」を追求する未完の試みがそこにはあった」
「あるテクストが時代を超えて読まれるということは、別の地域や時代の文脈でそのテクストが新しい意味合いを獲得するからである。古典と呼ばれる本は、その時代のコンテクストが失われてすら、読み継がれる「余地」があるから古典になる」
素晴らしい「古典」へのよき水先案内として必要十分な本だと思う。
----
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(マックス・ウェーバー)のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4003420934
『仕事としての学問 仕事としての政治』(マックス・ウェーバー)のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4065122198 -
ウェーバーは「問題の人」だった、ということを論じた本である。
■
【父的か、母的か、という問題】
ウェーバーには父と母の影が常に付きまとっていたのかもしれない。
ひとつは母が抱いていたようなもの。それは、職業軍人を人殺しと同列に置くような平和主義だ。軍人に軽蔑の烙印を押した場合、戦争は人道的にならず、正義のなくなった集団に堕ちてしまうのではないかとウェーバーは思う。
同時にウェーバーは、父の家父長的振る舞いにも嫌悪を抱いていた。家族に優しい父によるパターナルな支配が、「家族のため」という外見に反してしばしば、自分にだけ都合がよいようなダブルスタンダードや恣意性を含んでいる、という点に、ウェーバーは敏感である。
父のことを誰よりも尊敬していたが。父でもなく、母でもなく、かつ、父でもあり母でもあろうとしたウェーバーの姿が本著では書かれている。
法学を学び、政治家になった父と信仰心に篤いユグノーの末裔の母の間の緊張関係は、後年のウェーバーの基本的な考えを深く規定した。父と母の物語を同時に引き継いでいくことで、彼の仕事は形成されていくのだった。
■
【母的な愛か、父的な祖国か、結局多神なのか問題】
ウェーバーにとっての最大級のテーマは、「キリスト教の律法」と「祖国に対する義務」の二つである。最終的にウェーバーは、いくら事実やエビデンスを積み重ねても、価値をめぐる対立には決着がつかず、人は「多神論」に行きつかざるをえないと論じた。この多神論とは、複数の神が争い合う事態を指す。
■
【正義と第三者の問題。なんでもかんでも公開すると、当事者が暴走し、敗れた当事者を糾弾させることになるのではないか問題】
彼がのちに書くことになる時事的・政治的な文章には「騎士道的礼節」という表現が出てくる。戦争で負けた側が道義的にも悪かったとする。「勝てば官軍」のような論理を、ウェーバーは礼節に反するとして斥けた。
これを踏まえて、公文書と情報公開のポリティクスが興味深い。
クルト・アイスナーはカント主義者だった。アイスナーは前政権の秘密外交を公開性の原則にのせた。
ウェーバーはその公文書の公開にきわめて否定的だった。
「戦争は、その終結とともに、少なくとも道徳の上では埋葬されければ、何十年後かに公文書が明るみに出るたびに、品位のない金切り声、憎悪、そして怒りが息を吹き返すことになります。」とウェーバーは言う。
自国にとって不利な公文書を、敗戦などによって一方的に公開されることは、結果として、真実は明らかにされない。むしろ、情念が濫用され、確実に真実が曇らされる。成果が出せるのは、第三者によるあらゆる角度からの計画的な確認作業によってのみだ。
ある断片的な文書が出てくることによって、なんらかの結論がでるということはありえない。「事実をして語らしめる」という姿勢を、ウェーバーは執拗に批判した。文書でも、映像でも、ボイスレコーダーでも、文脈から切り離された「エビデンス」が必要以上に大きなセンセーションを巻き起こしてしまうことがある。ウェーバーが投げかけた公文書の公開をめぐるポリティクスという問題は今日、ますます重要になっている。
ウェーバーはアイスナーのような政治家を信条倫理という概念で説明し、そうした政治家の問題を明らかにしようとしていた。いくら正しい信条をもち、それに基づいてブレずに行為する政治家が「英雄」的であったとしても、結果として事態をさらに悪くしてしまうことがある。これが、ウェーバーの突きつけた問題であった。
もし日本が中国やどこかの国と戦争に負けたら、おそらく情報公開として、いかに日本が悪かったか、真相はこうであるとして、公文書が広められるはずである。これは「騎士道的礼節」に反する事態を引き起こすのではないのだろうか、ということだ。
■
【日本はまだ近代化されていない問題】
日本の社会科学者は、近代官僚制のモデルを尺度にしながら、家産官僚制における温情的で、かつ恣意的な権力の運用を問題にし、その克服を課題とし続けてきた。
日本でウェーバーを読んできた読者は、近代ヨーロッパにはあるが、アジアには「欠如」している、という図式をしばしば強化してきた。
外国にくらべて、日本に民主主義はない。もしくは近代化されていない、という議論のもとがウェーバーにあるという。しかもこの現象は日本独自であるという。
■
【プロ倫の誕生についての問題】
「プロ倫」についてだが、拝金主義を嫌悪し、信仰心に篤い禁欲的プロテスタンティズムが、最も熱心にビジネスに勤しみ、そして成功するのはなぜだろうか。本書においては、「プロテスタント的な信仰から金儲けをひどく憎みながら、実際は事業で成功したモデルが、まさにウェーバーの家系だった点である」と述べる。ウェーバーの仕事は、自分がいまの自分になったことをめぐる系譜学的な研究になっているという。
■
【体験至上主義が、全体・排外主義をもたらす問題】
体験をした人が「個性をもった人」とみなされる。したがってセンセーショナルな体験をすればするほど、その人は「ホンモノ」として評価される。<自分はすごい体験をした。修羅場をくぐってきた。だから自分にはわかる。そしてお前にはわからない>。こうした論理はまったく論証になっていないが、常識が崩壊し、みなが確信をもてずにいるときには、「体験」を根拠にした断定調の語りはそのぶん説得力をもってくる。基準がこうした意味での「体験」になれば、体験は人種主義的排外主義にも、急進的なコミュニズムにも結びつきうるし、実際結びつくことになる。
■
【相対主義がいきつく果てについての問題】
「われわれはたいていの場合、見てから定義しないで、定義してから見る」(リップマン)とウェーバーの意見は似ており、すべての価値から解放された客観性はありえない、というのが、ウェーバーの「価値自由」論の基本である。
その「価値」をもった人間はどう生きていけばいいのか。ウェーバーによれば、人間は合理的になればなるほど、かつては偏在した非合理はカリスマの決断という一点に煮詰められていくという。
そしてこの合理化についてだが、合理化と一口に言っても、あらゆる文化圏にわたって、生の領域がさまざまに異なるに応じてきわめて多種多様の合理化が存在する。絶対的な価値はなく、合理化のやり方も人それぞれである。きわめて相対主義的な分析のなか、人はカリスマにひかれてしまう。ヒトラーの出現を預言するかのようだ。
「体系」に還元不可能な多様性や葛藤を指差しし続けることで、品位を保とうとするようなタイプの思想家がウェーバーだったと、著者は言う。
■
【宗教の分類の問題】
宗教を分類する二つの基準は、現世肯定か現世否定である。この世界での快楽を肯定し、「ご利益」を追求することと矛盾しない宗教(儒教など)なのか、あるいはそうした世俗の論理の生きにくさからの「救済」を求める宗教なのか。もう一つが「禁欲」(目的達成のための意識的かつ積極的な断念と、生活の規律化)と「瞑想」(神ないし調和的秩序との感情的な「合一」に意味を求める)だ。
■
【公務員と政治家の関係の問題】
ウェーバーの述べる「ゲホイゼ」の機能について、コストと人員を削られ、過酷な条件で働くことを強いられている公務員には、見識のない政治家から身を守る「外衣」が必要ではないか。「鉄の檻」という訳語を見直すべきだという議論も面白かった。 -
マックス・ウェーバーを扱った本。
ウェーバーは日本で社会学を学ぶ上で避けて通れない人。私は大学は社会学部だったが、中退したのでウェーバーの本をちゃんと読んでない。有名な「プロ倫」も。なので、入門書としてこの本を手に取った。
この本ではウェーバーの生まれや育ちから入っているが、私にはそれが理解しやすかった。いきなり理論から入るより、どんな人物がその理論を唱えているか?の方に私は興味があるので。
なるほど、「ヨーロッパ近代の特殊性」をプロテスタンティズムに求め、神が死んだ(魔術が解けた)後でも、その行為態度(エートス)が資本主義を発展させた、ってことか。明治以降に近代化を余儀なくされた日本で、ヨーロッパ近代を理解する上でウェーバーが読まれたのも納得。「三方よし」の近江商人との親和性も面白い。石門心学の「正直、倹約、勤勉」はたしかに宗教性を感じるし、現代の日本社会にまだ多少なりとも残っている価値観(倫理観)という気はする。
日本の社会学者はあまりにヨーロッパを理想化するよな、と感じてはいたが、その源流が大塚久雄にあった、という話も興味深かった。ウェーバーが西洋の独自性を論じたのは彼が西洋人だからで、他の地域を知る機会がなかっただけだろう。別に西洋が東洋より優位、ということもでないし、逆でもない。今の民主主義・資本主義は西洋発なので西洋社会の人の方が親和性が高いのは事実だが。
しかし、音楽社会学が面白いな。こんな学問分野があるんだ。「情念」を扱う際にたしかに音楽は避けられないもんね。
まだ表面的にしか理解できてないから、何度か読み返してみよう。その上で、いつか「プロ倫」や別のウェーバーの著者にも挑戦してみたい。 -
本ノ猪2023122twより
-
『プロ倫』の助走として久々に読んだ
現実主義に対する熱の入り方
女性問題的なところを切り上げるところで詳しく扱わないって念押しするの好き
結局バランス感覚みたいなところあるな言うのは簡単だけど
「価値自由」というキーワードがあるからウェーバーの受容のされ方っていうトピックが面白い
「普遍的なもの」に疑問を持ちながら「普遍的なもの」を追求するエートス?
すみませんもっと勉強します
西洋の合理主義から普遍性を読み取るという問題関心
叔父さんを想定している
カルヴァン派の新教徒ユグノー母方
多神論 神々の闘争 決着がつかない
母反カルヴィニズム 神の単一性 人間の自由
ウェーバーはチャニングに懐疑的
二つの律法 宗教と愛国
理解社会学 主観的な意味と社会的な結果
レジティマシー 伝統、カリスマ、合法性
近代と格闘したという側面から読もうとする日本独自の需要なされ方
移民排斥
近代法の形式合理性と個別の実質合理性
究極的な実体との対立
観点や党派性を前提としている?自覚して価値自由
ニュートラルに見える指標の危険性
カルヴィニズム、予定説、人格の内面化 孤独
エートスは気風
選択的親和性 関係のない両者の相互反応
理念型 理想理論
脱魔術化 知りたいと思えば確かめられること
儒教と封建制の適応力
呪術から帰結する伝統の不可侵性
公文書の公開は第三者による確認作業が必要 キャンセルカルチャー
責任倫理 信条倫理
ロトクラシー
最晩年のピアニッシモに至るまで
相互の倫理的責任という思想
アンチノミー
価値多元論
鉄の檻 システムに組み込まれる 護られるという原語のニュアンス
受容のされ方を語る -
社会学者とも政治学者ともいえるマックス・ウェーバーの思想とその受容の変遷を論じた本。政治学の官僚制論のところで名前を聞いて、彼の評伝を読んでみたいと思ったので手に取った。
彼の思想は政治学的というよりは政治哲学的であり、抽象的な事項が多く、評者からすれば非常に難解だった。彼の理論を理解するためにはおそらくさらに古典的な思想を知っておくべきだろう。
ただ、筆者がいうように、ウェーバーの著作が今でも世界で読み継がれているのはそれなりの理由があるのはたしかなようだ。
-
頻繁に目にする名前ではあるけれど、何をした人なのか、いつの時代の人なのか、わかりませんでした。この本では、彼の多分野にわたる活動がまとめてあり、人物像を掴むにはよいと思います。
-
マックス・ウェーバーの人生と思想を概観するのにとても役に立った。
本書の特徴のひとつは、ウェーバーの生い立ち、特に彼が学問的な成果を上げる以前の青年期、修学期についても、ページを多く割いていることである。それによって、比較的多面的な印象の彼の思想が、若い時期の経験や家族や友人との人間関係に影響を受けて形成されてきたということがよく分かった。
もちろん、全てをそのような個人的な要因に帰することはできないが、社会思想というものが現実の社会に着地していなければ意味をなさない以上、ある程度その思想家自身の人生と関わりを持つことは当然であるし、むしろそうあることで思索により深みが増すこともあるであろう。
もう一つ印象的だったのが、同時代や、彼の人生の前後の時代を生きた多くの人の著作が、ウェーバーの思想を読み解き、その意味するところを照らし出すために紹介されているという点である。
カフカやフィッツジェラルドといった作家の作品が描き出す世界とウェーバーの近代官僚制や職業的価値観の関係性は非常に興味深かった。また、ハンナ・アーレントのように、ウェーバーに対して批判的と思われる思想家の著作を取り上げることで、ウェーバーの思想の射程距離とその外側にあるものがより認識しやすくなっていると思う。
これらの幅の広い記述があることで、ウェーバーの思想の世界をより興味深く読むことができた。
ウェーバーは、本書の副題にもあるとおり、ヨーロッパ近代の理解とその行く末を考えることに奮闘した思想家であったのだと思う。そして、そのテーマとして主に取り組んだのが、本書でもメインで取り上げられている「資本主義」、「暴力装置としての国家と官僚制」、そして「宗教社会学」だった。
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で彼が描き出そうとしたのは、禁欲的なプロテスタンティズムと利己主義的とも思える資本主義の間にある、親和性である。
一見、正反対にも見えるこの2つの姿勢をつなぐのが、「仕事(Beruf)」である。仕事は、プロテスタンティズムの禁欲的な価値観を日常生活の営みにつなぎ、西洋においてたゆみなく徹底的に物事に打ち込んでいくという形での資本主義を定着させた。
この変化はさらに進み、やがて宗教的な価値観が徐々に脱色され、勤勉、合理性といった要素だけが残っていく。プロテスタンティズムの「倫理」から資本主義の「精神」への変容をウェーバーは指摘している。その行き着く先は「精神のない専門人、心情のない享楽人」という人間性であるとウェーバーは論じている。
続いての章で紹介される国家や官僚制に関するウェーバーの理論は、彼が第一次世界大戦やロシア革命といった世界の大きな動きを見つめる中で構築された。この出来事からウェーバーが帰結したのは、物理的な暴力行使の権限を独占する国家という存在と、その機構を動かす原理としての官僚制の進展であった。
国家は暴力行使を独占することを要望するがゆえに、その存在にはレジティマシー(正統性/正当性)が求められるとウェーバーは考えている。一方で、その国家を駆動するのは、粛々と業務を遂行する官僚制であり、レジティマシーの源泉となる民主主義や政治的な言論空間については、ウェーバーのこの理論からは導き出されない。
資本主義に関する議論も、国家や官僚制に対する議論も、近代の持つ合理性が行き着く先を冷静に見つめて描写した議論であるが、いずれも倫理や正統性といった「価値」の側面は徐々に脱色されていく姿として描かれている。
このことが、ウェーバーが近代合理主義者であるとか、暴力装置としての国家の存在を無批判に受け入れているといった理解に、時に繋がってしまった要因ではないかと思う。
一方で、本書がもう一つのテーマとして取り上げている「宗教社会学」の議論は、それらの議論のなかで失われていた価値や理念の役割を考え直そうという取り組みだったようである。
ウェーバーの理論が脱価値、脱宗教といった印象を与えがちであるものの、本来ウェーバーにとって宗教や理念とは、社会を変革していく力の源泉になるものであった。
宗教自体は近代において徐々に変容し、呪術や共同体の束縛によって個人の理性や自由を閉じ込めるような性格が失われていく。しかし、そのような束縛から自由になった人間にも、生きる意味を考え、社会の進む方向性に影響を与える役割があるというのが、ウェーバーの理解であったと思う。
社会の変遷は必然的な因果関係で規定されているのではなく、人間が持っている理念や価値に対する意識が社会を変えていく仕組みを解明しようというのが、宗教社会学の研究であった。
残念ながらこの研究は未完に終わってしまったが、ウェーバーがヨーロッパの近代を考える上で、決して機械的な社会の変化を論じるだけにとどまっているのではなく、人間の存在やその人間が考える価値にも目を拡げて理論を構築しようとしていたということは、大切な点であると感じた。
ウェーバーの社会理論は全体としては複数の視点に立脚しており、どれか一つの著作だけを読んでその体系が理解できるようなものではないということを、本書で知ることができた。
彼が主に描き出そうとしたのは「ヨーロッパ近代」であったが、彼がとった複数の視点からアプローチするという方法論は、その他の対象を考える時にも有益なものであろう。ウェーバーの思想を知るというだけでなく、社会科学の方法論としてのウェーバーの取り組みを知るという点でも、興味深い本であった。 -
ウェーバーの思想と生涯を、主に宗教社会学と政治理論に重点を置いて紹介している本です。
ウェーバーの宗教に対する態度や、彼の政治的心情の根幹に存在していたナショナリズム、官僚制とカリスマにまつわる問題の指摘など、ウェーバーの思想のなかから重要な論点をとりだしてわかりやすく解説しながら、それらの論点が現代の議論のなかでどのように受け継がれているのか、あるいは批判されているのかということにも触れられています。さらに終章では、大塚久雄による近代主義的な立場からのウェーバー受容と、山之内靖に代表されるニーチェ的な反近代主義的解釈など、日本のウェーバー研究の経緯が簡潔にたどられており、現代においてウェーバーを読むことが、われわれにとってどのような意味をもっているのかという問題への目配りがなされています。
著者は「はじめに」で、「かなり前に彼の本を読んだことはあるが、長らく忘れていたという人や、最近どこかで彼の名前をはじめて耳にして、少し気になっているという人が、本書が主として想定する読者である」と述べられています。わたくし自身は前者に近い読者の一人でしたが、ウェーバーについて学ぼうとしたものの彼の多岐にわたる思索の焦点がどこにあるのかわかりにくいという思いをいだいていたので、本書によって一つの参照軸を教えられたように感じています。また後者の読者にとっても、ウェーバーの現代的意義と問題性に手厚い解説がなされている本書は有益なのではないかと思います。 -
本書は、ドイツの法学者・経済学者・社会学者のマックス・ウェーバーの「哲学的・政治的プロフィール」を描くことを意図しており、マックス・ウェーバーの生きた時代、重要著作、基礎概念などに言及しつつ、基本的に年代順にウェーバーの生涯を解説している。日本におけるウェーバー受容についても触れている。
本書は、マックス・ウェーバーの生涯がどのようなものであったのか、また、主要著作やウェーバーの思想のエッセンスがよくまとまっており、ウェーバーについて理解するための入門書として優れていると感じた。また、今、ここの自分たちの社会を理解するためにも違う時代、場所の社会との比較が重要であるということや、その上でウェーバーが描こうとした「ヨーロッパ近代」は比較のための参照軸として今でも有効でありうるということなどを感じ、現代の日本社会を考える上での示唆も得ることができた。
著者プロフィール
野口雅弘の作品











 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 
















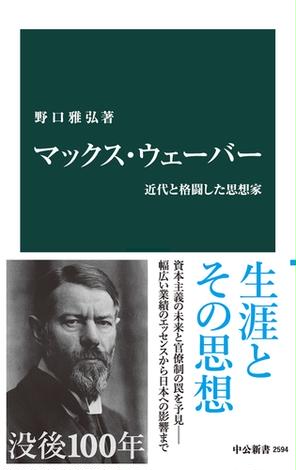



いつも楽しみに拝見しております。
「職業としての学問」はかつて非常に感銘を受けた本です。
ところが...
いつも楽しみに拝見しております。
「職業としての学問」はかつて非常に感銘を受けた本です。
ところが上手くまとまらず、今もデスクの上に常置してつれづれに開く一冊と化しています。
こうしてレビューを読んで、ああこのようにまとめれば良かったのかと、非常に納得がいく思いです。
これで再読するチャンスを得ることが出来ました。ありがとうございます!
野口さんの講談社文庫の『学問』の新訳は読みやすいと思いました。この本もとてもよくまとめられた本でした。
...
野口さんの講談社文庫の『学問』の新訳は読みやすいと思いました。この本もとてもよくまとめられた本でした。
ウェーバーは、『プロ倫』の手際が鮮やかで好きになりましたが、現代においてもそこで扱われた課題と分析はまだ有効だと思っています。