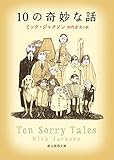- Amazon.co.jp ・本 (264ページ)
- / ISBN・EAN: 9784309208381
感想・レビュー・書評
-
ある国で突然人が死ななくなった。死なないといっても、いわゆる「不老不死」ではなく単なる「不死」である。瀕死の病人は瀕死状態のまま命を長らえている。もってあと数日と見られていた皇太后も現状維持のままだ。
いったんは喜びにつつまれた国はすぐに混乱に陥る。「死」を扱う葬儀屋や墓守は政府に陳情し、病院は患者で満杯状態、政府は膨らむ社会保障費に頭を抱える。この辺りは超高齢化社会に入っている日本の現状を見ているようでもあり、読んでいてもやもやした不安を覚える。
死を迎えることのできる隣国へと病人を出国させる国民が続出し、それに目を付けたマフィアは国境越ビジネスを展開する。また、ここが日本にはない面白いところだと思ったのが、カトリック教会の対応だ。彼らは「死」の不在を認めようとしない。なぜなら死がなければ復活もあり得ず、復活がなければ祈る必要もなく、したがって教会が存在する意味がなくなるのだ。
突然の「死」の不在は、これまた突然終わりを告げ、今度はさらなる混乱が人々を襲う。
死に翻弄される人々は一見滑稽だが、もしも自分が同じ立場だったら、と思うと、笑うに笑えない。
こんな混乱状況を果たしてどう収束させていくのか、と心配になってくる後半、物語は突然人間の死を司る「死(モルト)」の視点で語られ始める。
この「死(モルト)」パートについて、正直私は違和感を否めないのだが、遅咲きだった著者のジョゼ・サラマーゴが本書を執筆したのは83歳の時。死(モルト)に「舌を突きだ」すことで、身近に意識していた死を振り払い、まだまだ書き続けたい、という彼の願いが込められていたのかもしれない。
また、意外だったのは死(モルト)の性別が女性として描かれていることだ。権威を持つ者は大概男性として描かれることが多いので、自分の中では勝手に男性をイメージしていた。
本書は改行、句点がほとんどなく、会話も「 」でくくられない独特の文体で書かれており、慣れないととても読みにくい。ただ、慣れてくると、物語の中の出来事を双眼鏡で覗いているような不思議な感覚になる。
読むのに体力がいる作家なので手に取るのは少々勇気がいるが、コロナ下で有名になった『白い闇』を手始めに、もう少しこの作家の本を読んでみたい。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
もしだれも人が死ななかったら?
不死を求める物語は多々あるが、この物語は実際に人が死ななくなる、そのような状況になったとある国の、そのような「もし」を元に描かれた、ジョゼ・サラマーゴ節の効いた寓話的な物語である。
前半と後半では描写される対象が異なり、二部作のような展開となっている。
簡単にまとめると、前半では人間に、後半では死(モルト)に焦点を当てた話が展開されている。
その巧みな構成が、また物語に味を与えこちらを引きこませる。
前半の人間の話はともかく、後半の死に焦点を当てた物語ってどういうこと?と疑問や興味を持った方はぜひ読んでみてください。
さて、以下あらすじと感想を書きますが、ネタバレやだ!って方は本書を読んだ後にでも見てください。
前半では、とある国で大晦日を境に急に人が死ななくなったことに気がついた人々の様々を描いている。
最初のうちは人が死ななくなったことに歓喜の意を記して家に国旗を掲げることが流行るなどしたが、次第に「人が死なない」ということの事態の深刻さが浮き彫りになっていく。
怪我や病気、老いは止まることなく、ただただ人が死なない。葬儀会社は仕事がなくなることに、介護施設や病院は増えゆく利用者・患者に阿鼻叫喚を呈し、介護問題は家庭で解決してもらおうなどの動きも出てくる。この辺りは(葬儀会社以外)現在日本社会の更に問題が大きくなったような感じで、とても他人事とは思えないような気持ちで読んだ。
そして死を望む老いた父に、とある家族がくだした決断と行動により、また新たな手強い問題が嵐のように巻き起こり、さらに二転三転…。
生き死にに対する…いや人間に対する、だろうか、人間の業と、まるで理想的のように語られる不死を多くの人が余儀なく得てしまったら…といった仮定を詳細に綴られぶつけられることで、死そのものについて、死が在ることについて、改めて考えさせられた。
後半では擬人化された死(モルト)に焦点を当てて描かれている。
人間に死を与える権限を与えられているモルトは、私は失敗をしない。死は絶対なのだから。と気位が高く傲慢に描かれている。モルトは慈悲として、人が死ぬ一週間前に、紫の封筒の手紙を送り、直面する死の瞬間までに成したいことをしなさいと人間に促していた。
しかしモルトは、ある日送ったはずの封筒が、人間が逃げられないはずの死が、舞い戻ってくることにかなり取り乱した。
この私が仕事をし損ねるなど。
そして、その死の封筒から逃れた人間について調べると、その人間はチェロ奏者の男であり、本来四十九歳で死ぬ運命のはずだった。だがその男はすでに五十歳になってしまっている。
自分の仕事を全うするために男の家に向かい、男と、また彼と共に住む犬の生活の様子を見ながらモルトは、とうとう大胆な行動に出る…。
前半の、「人が死なない国」で生きることを余儀なくされた人々の混乱ぶりや起きた出来事を、皮肉めきながらも寓話として面白く描いているところも面白いのだが、私は後半のモルトの物語の方にググッと引き込まれた。
死を彼女、女性として描いているのも面白いし(私は神話に詳しくないのだが本書を読んでいると神話や聖書を元にしているように読めた)、この死、モルトは、あくまで人間の死にしか干渉できず、その他の動物などの命には関わらない。
人間から恐れられるモルトだが、人間の数は所詮七十億ほど。もっと多く存在する他の命の死の裁量に権限を与えられた他の死神たちと比べて、モルトは死神としては最下層の部類に入るという話が、とても印象に残った。
改めて、まるで地球を牛耳っているかのような人間は、本当にちっぽけな存在なのだと、モルトは傲慢だと描かれていたが、つい地球において最上位の存在かのように思っている人間こそが傲慢なのではないかと、再認識させられた。
そして後半の最後の一文に心を動かされた。痺れた。
死を擬人化したからこその結末だ。
天才的な終わり方だと思う。
訳者あとがきも面白い。
本書についての詳しい解説はもちろん、なぜサラマーゴがこの物語を描くに至ったか、彼の人生と死生観、そして描いてきたサラマーゴの作品紹介を短い尺に詰め込んでいて、とてもサラマーゴ愛に溢れたあとがきだ。 -
面白すぎる!!
サラマーゴ、晩年の死についてのユーモアといらだちに満ちた物語
そうか〜、そうきたか〜でラストの一文を読み終えた
皆川博子「天涯図書館」で紹介されてたのも頷ける
「白の闇」「象の旅」はニガテで面白いとも思わなかったが
これは素晴らしい
だれも死なない高齢化社会の問題が
ユーモアといらだちの一部
【死】を司る彼女のロマンスのような
二部
無神論者のサラマーゴが老齢に達しての叫びを聞く、共感しかない
-
誰にでも訪れる、それなのに未知の世界、死。三回位読み返して、後から後から色んな思いが湧いてくる、そんな内容だった。ざっくりあらすじ。突然人が死ななくなる。しかし誰一人喜んでいない。むしろ暗黒絶望の雰囲気。死神のうっかりミスですぐに改善(また死に始める)。「今までいきなり予告なしに命を奪ってすまなかった」そして一週間の猶予を与えられるようになる。「この上なく最悪だ」これこそが地獄みたいな書かれ方。
だからさ、人間なんてのは絶対に満足しない生き物なんだよ。わざわざ不幸を見つけて探して、日々感謝して生きるとか無理な生き物なんだよ。 -
もし誰も死ななくなったらどうなるのかという前半。
急にまた死ぬようになり、“死”が姿を現す後半。
前半と後半の毛色の違いになぜこんな話になったのかすごく気になる。 -
あとがきにもあるが、独特すぎる文体で読むのに
難儀した。
人が死なない国で起こる弊害が、正に日本がたどり着く未来なのか(極端だけど)と想像して、頭が重くなった
擬人化された死(モルト)が辿るラスト…
最終頁で、思わず「えーー…」と声出してしまった。そうかー。
著者プロフィール
ジョゼ・サラマーゴの作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :