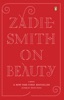- Amazon.co.jp ・本 (520ページ)
- / ISBN・EAN: 9784309206912
感想・レビュー・書評
-
2段組500ページの大作なうえ、まとまって読む時間がとれず、えらい時間かかった。が、すごく面白かった!
物語の中で季節が何度か巡るように、人間関係の温度もまたゆるやかな上昇と下降を繰り返す。読み終わってあらすじを振り返ると、こんなにページ数必要だったか?と思わないでもなかったが、この量があって初めてあのぬくもりと冷ややかさの機微が生まれるのだろうし、それを体験できなければこんなに登場人物たちを愛せなかっただろう。今、彼らを本物の友人のように懐かしく思い返せるのは、良い小説だったことの何よりの証左だと思う。
登場人物の多くが黒人で、なかでも主要なベルシー家のこどもたちは混血だったので、頭の中で多少描き分ける必要があった(自分は文章を割とはっきり映像化しないと読み進められないタチなので)。序盤の段階で何人か混血の俳優とかを画像検索しながらイメージを固めていったり。キキ・ベルシーに関してはもう最初からはっきりとオクタヴィア・スペンサーがキャスティングされてたけど。
モンティ・キップスの「アファーマティブ・アクションに対して反対の立場をとる黒人」という人物像も、自分にとっては想像しづらいものだったが、その主張は普段意識しないものだっただけに、なかなか興味深かった。この小説を読まなければ理解することもなかったであろうトピックのひとつ。
理屈っぽくて若干論破厨なハワードだが、ちょっとしたことで涙したりその場にいられないくらい笑いが止まらなくなったりするような、意外な繊細さも持ち合わせている。キキもそんな感性の持ち主だ。思えば、ベルシー家の人々は必ず物語のどこかで芸術や出来事に触れ涙している。子どもたちは二人の親からそういう柔らかさ傷つきやすさを受け継いだのかもしれない。美に触れたとき、彼らはしばしば論理やしがらみを脱ぎ捨ててしまう。雄弁な登場人物たちの沈黙が、何にも増して美の本質を語っているように感じられた。ラストシーンは特にうっとりするような美しい時間が流れている。
詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
階級や家風のちがう二つの家が結婚問題をきっかけとして交際が始まることによって起こる騒動の顛末を描く、E・M・フォースター作『ハワーズ・エンド』を下敷きに、現代アメリカを舞台に描いた喜劇風味の風俗小説である。フォースターの代表作をいじるなど、なかなかの度胸だが、名作『ハワーズ・エンド』のパロディーを意識したものではない。むしろ大好きな作品にオマージュを捧げている、という感じだろうか。ただ、よくも悪しくも階級社会が当然視されている英国とは異なり、多くの人種や文化がフラットに混在するアメリカという国を舞台にすることで、階級差のずれから生まれる微妙なヒューモアは薄まり、それに代わって人種問題、貧富の差、大学内でのセックスを含めた交遊の実態が暴露されるなど、シニカルな諷刺劇風のニュアンスが加わった。
『ハワーズ・エンド』におけるアッパー・ミドルの知識人階級と富裕ではあるが無教養な商人階層という二つの家を隔てる階層差の壁に対し、作者が持ち込んだのは、二つの家を代表する男たちを宿敵同士とする工夫である。二人はレンブラントを専門とする教授で、英国生まれの白人ハワードは無宗教で個人を尊重するリベラル。レンブラントを巨匠と仰ぎ見る世評を徹底的に批判する論文は書きかけで放置されている。それに対し、カリブ系黒人のモンティ・キップスはキリスト教を奉じ、家族を重視する保守派である。レンブラントに関する論文はハードカバーで刊行され、よく読まれている。
事の起こりは、ハワードの長男ジェロームが、インターンをしているキップス家の娘ヴィクトリアに結婚を断られたことで、もともと犬猿の仲だった両家の間がいっそう気まずくなったうえに、何の因果かロンドンの大学に勤めていたキップスが、ハワードのいるアメリカの大学に転職し、近所に住むことになる。不倶戴天の二人はアファーマティブ・アクションをはじめ、弱者を優遇する措置に対し、ことごとく対立する。その上、ハワードの娘ゾラが不倫相手のクレアの講座を受講したり、奔放な美女のヴィクトリアがハワードに接近したり、と人間関係が複雑な様相を呈し始める。
『ハワーズ・エンド』の枠組みを踏まえているところは多々ある。弱い立場の人々を放っておけない性格の持ち主は『ハワーズ・エンド』では妹のヘレンの役だったが、本作ではジェロームの弟リーヴァイが担当する。才能はあるが恵まれない環境にいる若者レナード役は、コンサート会場で傘ならぬディスクマンを取り違えられたカールとなり、この世に埋もれた詩人をめぐって、ゾラがヴィクトリアとぶつかってしまう。ややこしい対立関係にある両家の中で、ハワードの妻キキとキップス夫人は心を通わせあう関係となり、遺言で遺贈された物が恥知らずにもキップスに握りつぶされてしまうところまで『ハワーズ・エンド』に倣っている。
英国風俗小説の骨格を譲り受けながら、中身は現代アメリカの中流家庭が抱く問題、それは中年男の浮気による家庭内別居だったり、親子の意思疎通の難しさだったり、子どもの恋愛問題だったり、といろいろだが、まあ、どこにでもある問題が二つの家族とその周りにいるボストン郊外の大学町に住む人々や、よりましな暮らしを求めてアメリカに移住してきた中南米諸国の移民からなる人々を巻き込んで、あれやこれやの騒動を捲き起こす、てんやわんやを描いたものと一口で言えばそうなる。
すでに『ハワーズ・エンド』を読んでいれば、ああ、なるほど、とにんまりすることは多々あるだろうけれど、別に読んでいなくとも充分面白く読める小説である。ラップやヒップホップという音楽、それに美術、詩、そして小説、といった作者の関心を集めた諸々が惜しげもなく配され、なかには、敬愛するナボコフの『ロリータ』の一場面を思わせる中年男と美少女の危うい場面まで登場する。これまでの自分を作ってきた因子をすべて突っ込んだのではないか、と思わせるフル装備である。
普通だったら主人公の位置を占めるだろうハワードという人物が、教授としての腕はともかく、家庭の父親として、あるいは年老いた父親を独り異国に住まわせる息子として、そして愛する妻の夫として、あまりにも好い加減で、まあ、たしかにこういう人物の方が、リアルなんだろうけれど、身もふたもない、その生き方に口あんぐりとなってしまったのだが、それでいてどこか憎めない。独りよがりの思い込みで、とんでもない行動に走ってしまうリーヴァイも、頭が良く、議論に強く、粘り強いネゴシエイターであり、父のよき理解者であるゾラも、家庭内のよき調停役であるジェロームもみんないい子であるのは、昔はすごい美女だったが、太ってからは大女と化したキキあってのことだ。このキキの人物像は魅力的で、キップス夫人が家族よりもキキを心のよすがとしたのは、とてもよくわかる。人物がよく描けている小説はおもしろい。そういう意味でも、この小説はとてもおもしろい小説であるといえる。 -
思索
-
自分は田舎にいる時から黒人文化に憧れてきた。そしていくつものフィルターにかかった何かに都合のいい情報を得、1人納得し、彼らに近付いた気になり自己満足に浸っていた。彼らとは黒い肌を持つ人々であり、1人1人バックグラウンドは違う。同じ肌を持つ人間でも立場生き方は違い、民族越えて共通するものである。
初めて現代を生きる黒人の生の呼吸の存在に触れた気がする。
アメリカに住むアフリカンとハイチに住む彼らは全然違う。
フージーズという音楽グループはハイチ出身のワイクリフジョンとアメリカで生まれ育った二人のチームで、出身については気まずくやり過ごすインタビューが印象に残る。彼本人から話すのは構わないが、私達からは何も言えない、そうでしょ?
この作品は家族5人のそれぞれの生き方をあぶり出すような作品で、大学が建ち並ぶ街で過ごすインテリ有色人種。末っ子のリーヴァイは緩い志のブラダーに見切りを付け、ハイチ出身の出稼ぎグループの生活向上のために奮闘している。しかし当事者にとっては生温くうっとおしく、利用できる部分は利用するが、同士になんか絶対なれないという意志がある。子供だからそれに気付かない。
知ることは出来ても決して彼等には近付けないんだ。彼等の魂には。 -
面白かった!!
人生の残酷さと滑稽さが切実に、でもまったく重くなくユーモラスに描かれていて、ゼイディー・スミス、すごくうまい作家だと思った。
海外ドラマを楽しみに待つように、毎日少しずつ読むつもりだったけど、気付けば最後は一気読み。ああ、でも、この世界にもっと浸っていたかった…(現実の世界同様、たいして素晴らしい世界ではないのだけれど)。
登場人物それぞれに異なるポイントで共感できるのも、海外ドラマっぽい気がする。みんな、ちょっとずつ知ってる誰かに似ていて、ちょっとずつ自分に似ている、みたいな。
あと、いま日本でも流行してる(のよね?)ラップ界隈が描かれるのも面白かった。いろいろ詰め込んでいるのに、どの要素も無駄なく無理なく描かれていて、何度も言うけど、うまいわ…。
お父さんであるハワード(大学教授、家族の中で唯一の白人)は情けない、それどころか最低の部類の男なんだけども、どうにも憎めない。そして、三人の子どもたちも(たぶん妻のキキも)あきれながらもハワードを憎むことはできないんだよね。そのあたりの描写がすごくよかった。私ももうちょっとお父さんと長い時間を過ごしたかったなあ、となんだか寂しいような気持ちになったり。
ちなみに、私はネタ元(?)であるフォースターの『ハワーズエンド』は読んでいないけれど、十分楽しめた。でも、せっかくだから、この機会に読んでみようかなと思っている。 -
登場人物が黒人であることを意識させられる小説は久しぶりかも。アカデミー賞が”白い”と話題になっているが日本で翻訳されている英語文学も同様か。トニ・モリソンよりはぐっと軽やかに現代的だが、黒人妻と白人夫を中心に据えた本書の重要なテーマとなっている。先日見た映画「ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります」で老夫婦が「私達が結婚した時は黒人と白人の結婚が違法な州があった」といっていたが、ごく最近まで当たり前のことではなかったわけだ。
読みどころはそこだけではない。中産階級の知的な家族だが、俗物な父親たちはアカデミズムの厭らしさや下半身のだらしなさを晒し、若い世代は若さの勢いで宗教やブラックへの憧れや恋に走り、母親たちは頑張る。ダメ夫・父のハワードを含めてさえ嫌な人は誰もいない、作家の視点は、皆弱く傷つきやすい、理解し合うのがますます難しくなっている、”わたしたち”だ、と語りかける。
分厚いボリュームにふさわしくみっちりと書き込まれており面白かったが、風呂敷を広げすぎて500ページでも語り尽くせなかったと言わんばかりに、終盤は慌ただしい店じまいモードに入るが…本書がハワーズ・エンドのオマージュだそうだが、後書きにあるように、ハワード終わったな、の「Howard’s End」な結末。 -
夫婦。家族。人生観。不倫。仕事。
価値観が根底から違う2つの家族の人間関係。父親同士の仕事での対立。母親同士のぎこちなくも温かな交流。子ども達同士の恋愛や不和など。
イギリスでの宗教観や社会的背景や人種問題などが無知なためか、心情の機微が不明瞭で読みながら退屈した。
長編だけど、実際以上に長い実感。そもそもホームドラマ的なものが好きではないので読むのがしんどかった。
著者プロフィール
ゼイディー・スミスの作品










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :