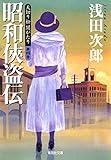- Amazon.co.jp ・本 (256ページ)
- / ISBN・EAN: 9784101019253
作品紹介・あらすじ
勢州桑名藩の岩井五郎治は、新政府の命で、旧藩士の整理という辛い役目についていた。だが、それも廃藩置県によって御役御免。すでに戊辰の戦で倅を亡くしている老武士は、家財を売り払い、幼い孫を連れて桑名を離れたが…「五郎治殿御始末」。江戸から明治へ、侍たちは如何にして己の始末をつけ、時代の垣根を乗り越えたか。激動の世を生きる、名も無き武士の姿を描く珠玉の全6編。
感想・レビュー・書評
-
久しぶりの浅田次郎作品でした。
江戸から明治への一新の中で、自身の身の振り方を模索する武士の姿が6つの短編で描かれている。
明治維新は侍の視点で見ればリストラと再就職活動の戦いと言えるのだろう。
武士としての矜持を否定されて、新時代への恭順を強いられる辛さは如何程のものであっただろう。
「遠い砲音」では日本が新時代に向け進み始め西洋化していく時、今までの日本を支えてきたゆったりとした文化が消えてゆく寂しさはさもあらんと感じた。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
明治維新により居場所を失った武士たちの悲哀と、生き様を描いた短編集です。登場人物の描かれ方はただただ美しく、もはやファンタジーです。日本史が少しでもわかるなら、絶対に共感できるだろうと、浅田節全開な書きっぷりです。
特筆すべきは、文字の配置ではないかと思います。難しい単語も所々にあるのですが、文章は決して読みにくいわけではないのです。おそらく仮名と漢字のバランスが絶妙で、読者に極力負担を与えないように配慮されているのかと思われます。文庫を見開きでみても、学術書のように漢字が多すぎて、黒くみえるわけでもなく、むしろ美しいとさえ感じてしまいます。まさしく日本語を堪能できる一冊かと思います。 -
「柘榴坂の仇討」が映画化されてたので読んでみた作品
幕末に命懸けで戦った人にスポットが当たりがちだが
明治維新が終わってからも人々の生活は続くわけで
180度世界が変わってしまった人々の話が短編でまとめられています
私は最初全然面白いと思いませんでした
でも全部読むと何とか前に進もうと頑張る姿にじんわり来ました
激動の時代で無くても例えば環境が変わった時に
どうやって乗り切るのか
参考になると言うか共感出来ると思います
「五郎次殿御始末」が一番好きです -
映画「柘榴坂の仇討ち」の原作を読むために購入しました。(映画まだ観ていませんが…)幕末から明治にかけての武士達の悲哀を描いた短編集六編です。桜田門外の変で井伊大老を討たれた時、護衛をしていた彦根藩士の物語「柘榴坂の仇討ち」より、本の表題作である戊辰戦争から西南戦争に関わる桑名藩士の物語「五朗治殿御始末」の方が断然に面白いです!ところで、
映画のキャッチコピー「浅田文学の最高峰 待望の映画化」は陳腐だし作者に失礼だと思いますが… -
六つの短編とも維新後の武士がどのように考え生きたかが中心の小説。そんな時代は知らないのに何故か懐かしい感覚を覚える。
椿寺まで
勝沼の戦で敗れた小兵衛が商人となり、戦で救い大きくなった新太を母親に見せに行く。日本橋から八王子までの甲州街道沿いの宿場町の様子は読んで想像するのが楽しかった。小兵衛は最後まで武士の心を持った商人だと思う。
函館証文
維新後、金壱千両で命を助けてあげた者に金を受け取りに行くが自分も他の戦で同額で命を助けて貰った証文が出て来てしまう。函館戦争の一つ、二股口の戦い、白河城の戦い、鳥羽伏見の戦いでの出来事で四人の武士が登場する悲しくも楽しい内容。最後は清々しい。
美しかった当時の楓の御門を見てみたいとも思った。
西を向く侍
幕府天文方の勘十郎は、政府が莫大な支出を押える為に無茶な改暦を行おうとしてる事に気付くがどうにもならない。
西向く侍、二、四、六、九、武士の士の字は十と一、混乱から皆を救える覚え方を瞬間に考えつく。この覚え方、子供の頃、教わった記憶が…
遠い砲音
西洋定時に感覚を合せる為に苦労している元武士。懐中時計を見ながら本丸で十二時に空砲を撃つが本丸と向島では二十秒伝わるのが遅れる事に気付くところが気が利いている。なんとも正直で遅刻ばかりする主人公を心配して読んでるうちに引き込まれてしまった。
柘榴坂の仇討
桜田門外の変の後、十三年もお籠回り近習役は仇討をしたく探し回る。俥引きとなっていた仇との話しは激変後の武士の悲哀を深く感じ何とも言えない余韻が残った。
五郎治殿後始末
五郎治は、息子は死に嫁は去り、藩内での役柄上、同輩達から嫌われた。桑名武士として
御一新後、西郷征伐で最後を遂げる。一人で育てた孫との関わりや会話は胸が詰まるが、全ての始末を自分でつけようとする意識の強さに武士の凄さを感じた。
六編とも面白い。 -
4.6
-
江戸から明治へと時代が変わった・・・と教科書ではさらっと読んできたけど、武士という地位がなくなった人たちは、どのように生きてきたのだろう。
武士としての矜持を持ち続けるのより、今日のご飯って思うのは、あの時代を生きてないお気楽な女だから言えることかな。
とても考えさせられたし、おもしろい作品でした。 -
「浅田次郎」の短篇時代小説集『五郎治殿御始末』を読みました。
『終わらざる夏』、『残侠―天切り松 闇がたり〈第2巻〉』、『王妃の館』、『一路』、『憑神』に続き、「浅田次郎」作品です。
-----story-------------
江戸から明治へ――侍たちは、如何にして己の始末をつけ大リストラ時代を生きのびたか?
涙さそわれる名も無き武士たちの六つの物語。
勢州桑名藩の「岩井五郎治」は、新政府の命で、旧藩士の整理という辛い役目についていた。
だが、それも廃藩置県によって御役御免。
すでに戊辰の戦で倅を亡くしている老武士は、家財を売り払い、幼い孫を連れて桑名を離れたが……『五郎治殿御始末』。
江戸から明治へ、侍たちは如何にして己の始末をつけ、時代の垣根を乗り越えたか。
激動の世を生きる、名も無き武士の姿を描く珠玉の全6編。
-----------------------
幕末維新の激動期… 江戸から明治に代わる御一新後の西欧化への大きな流れにより、千年続いた武士の時代の幕を引いた、、、
明治維新という時代の垣根を乗り越えようとしたもなき侍の生きざまを描いた短篇集… 『柘榴坂の仇討』は、2014年(平成26年)に「中井貴一」主演で映画化されていますね。
■椿寺まで
■箱館証文
■西を向く侍
■遠い砲音
■柘榴坂の仇討
■五郎治殿御始末
■解説 山本博文
『椿寺まで』は、上野での彰義隊の戦いで自ら重症を負いながらも生きのびて、武家を廃して八王子産の反物と横浜の羅紗地を扱う日本橋西河岸町の商人となった「江戸屋小兵衛」が、丁稚で十歳の「新太」を伴い甲州道中を西に向かい、日野の先の高幡にある通称椿寺まで出かけていく物語、、、
「江戸屋小兵衛」は、甲州勝沼で薩長軍と戦って討たれた友人の息子「新太」を丁稚として引き取り、手代として可愛がっていた… 道中に出遭った浪人者の追いはぎを返り討ちにしたり、一緒に入った風呂で背中に残る刀傷を見たことで、「新太」は「江戸屋小兵衛」がただの商人ではなく、他人に言えない過去を背負っていることを知る。
そして、椿寺に待っていた人物は… 寺を去るときに、足下に落ちていた大輪の椿の花をそっと懐に入れるシーンが印象的な作品でした。
『箱館証文』は、官員ながら新しい時代に馴染めない感覚を持ちながらも明治政府の役人(工部少輔)として働いていた「大河内厚」のところへ、ある日、警視局の警部「渡辺一郎」が、突然、訪ねてくるという物語、、、
「渡辺一郎」は、御一新後に改名しており、元々は「中野伝兵衛」という名前で、かつて箱舘の戦いの折、徳島藩士であった「大河内厚」は敵方であった「中野伝兵衛」と遭遇して、争い、負けて咽元に脇差しを当てられた時、「中野伝兵衛」から「そこもとの命、千両で売らぬか」と言われて、命の代金としての千両を支払う証文を書いていた… 「中野伝兵衛」は、その千両の掛け取りにやってきたというのである。
「大河内厚」は、文武を学んだ師であり、剣術の道場を営む「山野方斎」へ相談したところ、「山野方斎」は「中野伝兵衛」から千両を支払ってもらう証文を持っており、この証文を使って万事解決しようとするが、次に「中野伝兵衛」は「山野方斎」から千両を支払ってもらう証文を持っている「小池与右衛門」という人物を連れてくる、、、
証文がいろんな人物方向へと繋がっていき… という展開、さて、三通の証文と四人の男たちの運命は。
『西を向く侍』は、有能で暦の専門家として幕府の天文方に出役していた「成瀬勘十郎」を主人公に、新たに新政府が導入を決めた西洋暦(グレゴリオ暦)に戸惑う人々を描いた物語、、、
明治6年から旧暦(太陰太陽暦)を改め、西洋暦(グレゴリオ暦)を導入することが決まり、そのため明治5年は12月2日が大晦日になるというお達しがあり、下町は大混乱… 「成瀬勘十郎」は太陽暦の拙速な導入に反対するため文部省に出向くが。
西洋暦(グレゴリオ暦)の二月、四月、六月、九月、十一月(士)が小の月であることを覚えるために「西向く侍」という言葉を考え、その言葉の中に西方から来て天下をわがものとした薩長への恨みを忘れないという思いを込めたオチが印象的でした。
『遠い砲音』は、御一新後、一日の時間の数え方までがすっかり変わったことにより人々の暮らし方が変わってしまうことを描いた物語、、、
旧長門清浦藩士で新政府の近衛砲兵隊の将校として出仕している「土江彦蔵」は、新たに導入された西洋定時法の感覚をなかなか体得できずに、遅刻ばかりしていた… 以前はだいたい二時間おきに刻まれるおおよその時刻で暮らしていたが、時間単位、分単位で行動が決められることになり、なかなか頭と身体が付いていかなかった。
そして、そのことが原因となり、「土江彦蔵」は、歩兵と砲兵の合同調練において、見方の歩兵の目の前に砲弾を撃ち込むという失敗を犯してしまい、正午に旧本丸天守内から時間を報せるための空砲を撃つ近衛砲兵第一大隊に任じられる… 東の空が白む明け六つに一日が始まり、暮れ六つの鐘とともに一日が終わり、夏の一日は長く、冬の一日は短いという自然に近い時間の感覚を、ちょっとうらやましく感じました。
『柘榴坂の仇討』は、桜田門外の変の際、大老「井伊直弼」の御駕籠回り近習をしていながら、下手人「佐橋十兵衛」を追い駆けて行列を離れてしまい、主君を守れなかった侍「志村金吾」の後日談を描いた物語、、、
心形刀流伊庭道場の目録を授けられた「志村金吾」は、剣の遣い手として、彦根藩主「井伊直弼」の御駕籠回り近習役を務め、将来を嘱望されていた… 水戸尊攘浪士たちの襲撃を受け、「志村金吾」は脇差で押し寄せる刺客たちと斬り結んでいたが、騒擾の中で「「井伊掃部頭直弼」、討ち取ったり」の声を聞いたとき、戦意を喪失し、魂は天を飛んでいってしまった。
桜田門外の変から13年… 主君「井伊直弼」を守ることができなかった「志村金吾」は、明治維新を経た後も、ひたすら仇を探し続けてきた、、、
ついに見つけた刺客の生き残りは、「直吉」と名を変え、俥引きに身をやつしていた… 明治6年2月7日、仇討禁止令が布告されたその日、雪の降り積もる高輪の柘榴坂で、二人の男の運命が交錯する――。
仇討という自分の気持ちの整理のために妻や、色々なものを犠牲にした「志村金吾」が選んだ道は… 柘榴坂で、刃を交えることはありませんでしたが、これにより、彼の心は解放されたんでしょうね、、、
武士としての美学、男として生きるための美学を感じさせる作品でした… 映画も観てみたいな。
『五郎治殿御始末』は、明治元年に生まれた曾祖父「半之助」の思い出を孫が聞き取るという物語、、、
曾祖父の祖父に当たる「岩井五郎治」は、桑名藩士で、息子を越後での薩長との戦いで失いながらも桑名に残り、事後処理の勤めを果たしていた… 旧藩士の整理で、整理される者たちからは「長州の狗」と軽蔑され、恨まれながらその役を果たしていた。
付け髷をつけて見栄えはしないが、温厚で利発な人でもあった… そして、役を退き、政府から与えられる金子も辞退し、家財の一切を売り払い、その金を菩提寺に寄進し、寄る辺ない旧藩士に分け、使用人が生活できるように渡して、同居していた語り手である孫を尾張の母親の実家に帰すように取りはからうのである、、、
そののち「岩井五郎治」は、藩の始末をし、家の始末をし、そして、ついに自分の始末も果たした… この作品も『柘榴坂の仇討』と通じる、武士としての美学、男として生きるための美学を感じさせる作品でしたね。
御一新の後、時代は江戸から明治へ… 価値観が大きく変わる中、時代の変遷に翻弄される侍たちの悲哀、、、
明治維新により大きく運命を狂わされた武士の生き様が描かれていましたね… 教科書では教わることのない、明治維新の裏側を知ることができた貴重な一冊でした。 -
江戸時代と明治の狭間に生きた武士たちの物語。暦や時間、建造物や慣行、あらゆるものがパラダイムシフトする中、各々が抱えた個別具体の葛藤が上手く描かれていました。
著者プロフィール
浅田次郎の作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。











 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :