- Amazon.co.jp ・本 (503ページ)
- / ISBN・EAN: 9784103111085
作品紹介・あらすじ
奈良盆地の小さな村"小森"。そこに住む人々は、いわれのない差別の壁に囲まれ、貧しさに苦しみながらもなお愛を失わず、明るく真摯に生きていた。日露戦争で父を失った誠太郎と孝二の幼い兄弟は、母と祖母の温かい手に守られて、素直に、感受性豊かに成長する。しかし、小学校に通いはじめる頃、彼らは、自分たちを包む、暗い不安な環境に気づきはじめる。級友たちの針のような侮蔑の言葉、そして、無言の圧迫…。それは、生涯にわたる闘いの幕開けだった-。"部落"の歴史にメスを入れ、人間の尊さを謳いあげる不朽の名作。
感想・レビュー・書評
-
"水平社"結成から今年で100年。
100年たっても無くならない差別。
1992年発行の古い本だが、読み始めるとすぐ物語に引き込まれた。
時代は明治後期。
大和盆地の被差別部落(小森村)で、祖母ぬいと母ふでの愛情につつまれて育つ誠太郎と孝二。
小学校に上がると"エッタ"と蔑まれる日々が待っていた・・
子供らから、教師からも露骨な差別を受けて傷つく二人。
「エッタと呼ばれた!つらい」
しかし、ぬいとふでには決してこのことを話さない二人が、いじらしくも切なくなる。
読み進めていくと、自然の美しさや生きる為に働く人々の力強さ、当時の年中行事が生活にかかせないものだったことに気づかされる。
今の時期だと田植えもすっかり終わって、7/2から七夕の7/7までは"半夏生"
この5日間はお休みするそうだ。
''鎌納め"のおはぎは美味しそうで食べてみたいと思った。
農に携わった著者の細やかな筆致が、物語に彩りを添えていて、豊かな気持ちにさせられた。
穢多(えた)に生まれたものの宿命なのだから!
小森はそれでもまだましや。
人から差別されることに悩み苦しみながらも、それに堪えることが生きる道のように黙って働き続ける。
「なぜ?」の問いが膨れあがるその先には・・第二部も是非読みたい。
-
1908年(明治41年)、奈良県の被差別部落を舞台に描かれた物語です。
職場の人に勧められて図書館で探してみたらびっくり、1部でもわりと分厚いですが、7部まであるんですね。
ただ、すごく読みやすいので厚さは全く気になりません。重いくらいで。
物語の時代は、既に身分解放令が発令された後にも関わらずエタを穢れとして遠ざけたがり、交わりたがらない人々の姿が描かれていました。
日本史で穢多・非人について習った時は、なんでえぐい政策だと思ったのを覚えています。穢多と規定された人以外にとっては、常に自分より下の存在がいて、辛くてもあいつらよりはマシだ、と思えて、穢れ仕事もすべて押し付けられる。そんな都合のいい存在ですが、血まで穢れていると言われ、親子代々受け継がれる穢多と呼ばれた人にとってはたまったもんじゃないですよね。
大体、生まれた時から自由が制限され一方的に差別をされる存在なんて、絶対に間違っていますよね。
物語ではエタ村の少年の目を通して「どうしてこんな謂れ無き扱いをされなければいけないのか」という憤りと哀しみがあり、人間が平等に生きることについて考えさせられます。
人が誰かを迫害するとき、遠ざけようとするとき、その根底には誤った知識がある気がしています。ネットがこれだけ普及して私たちが容易にいろんな情報を手に入れられるようになった今でもなお、正しい知識を適切に手に入れて知るということは難しい。
でも、だからこそ伝えたい真実、正しい知識のある人はそれを世に広める責務があるのかもしれないですね。この本の存在は、日本人にとって宝のようなものだと思います。
それから、こんなにも自分の力ではどうしようもない辛くしんどい状況の中生き抜いてきた人たちの哲学や処世術にも目がいきます。辛いことがあったとき、親や家族に心配はかけたくない、というのはいつの時代も共通の認識なのですね。
辛さを乗り越えるには、分かち合ってくれる仲間の存在が本当に大きいことが本書から見て取れます。
日本人として自分の祖先が歩んできた道を知ることも大切ですね。自分からは手に取らなかったであろう、読めてよかった1冊でした。 -
「路地を旅する」「路地の子」からの被差別部落のことを知りたかったので読んでみたけど。長いわっ!人の人生を小説にしょうと思ったら、これぐらいかかるんやろけど、長いわ!で、読むのは断念。
-
三葛館一般 913.6||SU||1
部落差別の歴史と共に、部落に暮らす一家族の兄弟の成長を描いている本書。
部落差別という重いテーマを扱っていますが、差別と闘いながら成長していく兄弟のたくましさや家族愛が綴られていて、感動をおぼえたり心和みながら読み進みます。
また、本書を一読すると、人がつくるルールや定着した概念の恐ろしさを実感し、それらにとらわれることなく、自分自身の感じたことや考えを大事にして、後悔しないよう生きていくことの大切さを痛感します。
全部で第7部まである大作ですが、長いお休みの間などに本書にチャレンジして、部落差別について一度考えてみませんか。
(かき)
和医大図書館ではココ → http://opac.wakayama-med.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=32966
住井すゑの作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 


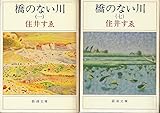

































私は遠藤周作が好きで、一昨年、念願かなって長崎を訪問する機会を得ました。そして初めて、あの『沈黙』の時代から、切支丹を信仰する集落の人たちと、被差別の集落の人たちとの対立を知りました。(結局、対立を煽って利用したのは権力の側なのですが……)。
人間の歴史は、互いに差別し合う歴史なのでしょうか。悲しい流れです。
私はまだ、島崎藤村の『破戒』を読んでいません。近いうちに手に取ろうというきっかけを得ました。ありがとうございます。
「橋のない川」の映画を初めて観たのは子供の頃だったでしょうか? 昨年、水平社のことを取...
「橋のない川」の映画を初めて観たのは子供の頃だったでしょうか? 昨年、水平社のことを取り上げていた新聞記事を読み、記憶の中の映像がまたよみがえってきました。
今も差別で苦しむ方がいらっしゃることを知るといたたまれない思いがします。
『沈黙』『破戒』はどちらも高校生の時に読みましたが、今読むとどうでしょう? まずは「橋のない川」第三部を手に取り、孝二のその後の物語を辿ってみたいと思います。有難うございました。