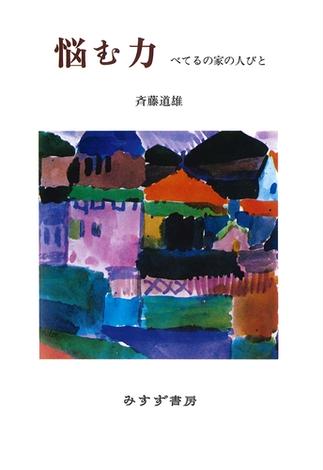- Amazon.co.jp ・本 (248ページ)
- / ISBN・EAN: 9784622039716
作品紹介・あらすじ
北海道、浦河-襟裳岬に近い海辺の町に共同住居「べてるの家」がある。病気や生きづらさを抱え呻吟の日々を送っていた人びとがここで出会い、集いはじめて二十年余り。メンバーはみずから会社をつくって、日高昆布の加工販売をはじめとする多彩でユニークな活動を展開している。そのモットーは「安心してさぼれる」会社だ。べてるのいのちは話し合いである。ぶつかりあい、みんなで悩み、苦労を重ねながら「ことば」を取りもどした人びとは、「そのままでいい」という彼らのメッセージを届けに、きょうも町へ出かけている。そんなべてるの力にふれるとき、人は自分自身への問いかけに揺さぶられ、やがて深く納得するのである。それぞれの人生を生きていくための、回復のキーワード。
感想・レビュー・書評
-
北海道の「ベてるの家」に通い続けた、ジャーナリスト斎藤道雄さんの記録です。
作家のいしいしんじさんがツイッター上で紹介されていて読みました。読みながら、いろいろなことを考えました。「悩む力」とは統合失調症を生きている人についてのことばなのか、医者やソーシャルワーカーとして彼らと出会っている人についてのことばなのか、ジャーナリストとして、その場にいる人についてなのか、あるいは、この書物を読んでいる読者である「ぼく」についてなのか。
最終的に、「ぼく」の問題として、「悩む力」という言葉について考えることになりましたが、そんな本に出合うのは久しぶりのことでした。
いしいしんじさん、ありがとうございました。
ブログにも感想書きました。覗いてみてください。
https://plaza.rakuten.co.jp/simakumakun/diary/202107240000/詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
精神疾患を持つ人々が共同で暮らす北海道の「べてるの家」のルポ。精神病に馴染みのない人が読んでも感じる事、教えられる事が沢山ある。社会からこぼれ落ちた(排除されてしまった)人々が寄せ集まり、自分を語り、周りとつながりながらその人の人生を生きている姿は、私たちが普通だと思っている人生よりも、どれだけ人間らしく豊かな生き様だろう。病気を抱えて苦労して生きている人は絶対大変だしかわいそう、守られるべき、と思う自分の感覚自体が、その人たちを生きにくくし、排除している社会の一部であることを分かった時、愕然とした。
-
みすず書房 斉藤道雄 「悩む力」 べてるの家 の人びと
総合失調症患者の共同生活の場であり、仕事の場でもある「べてるの家」の活動記録。病気を折り込みながら 自立的な生活と仕事の日々を送っている
病気を折り込んだ自立支援の例
*不平等の貫徹〜できる人が仕事をし、できない人は仕事をしない
*三度の飯よりミーティング〜議論をしつくすことを目的とする
*自由と安心感が商売につながる〜病気が出れば サボってもいい
この本には書いてないが、治すことができない精神医療の限界と ここまで 寛容的にはなれない一般企業の障害者雇用の難しさを感じた
著者のメッセージ
*病気に悩み、苦しみながら、病気とともに生きることに 生の豊かさがある
*人はパンのために生きているのでなく、人間同士のつながりのために生きている
VEフランクル「人生の意味を考えてはいけない〜この人生から自分は何を問われているかを考えなければならない」
-
「偏見差別大歓迎集会一決して糾弾致しません」という言葉を初めて聞いたときにびっくりした。これはセクシャルマイノリティ当事者の自分が幼い頃から持っていた気持ちと同じものだった。
“自分自身と和解することのできた人のみが、人とも 和解できる”181p -
絶望を掘り当てた感慨。
人生から何を問われているのか。 -
読書会の課題本になったので読みました。
思ったより、読み進むのに時間がかかった。 -
【繋がる】
人はなんのために生きるのか?
人間の繋がりのために生きている。
病気を抱えている時は
みんなと一緒にいること
みんなの中に入って、自分のことを話すこと。
精神障がいを抱えている人達の生き方に学ぶことで、誰もが幸せに生きられるだろう。 -
# 悩む力
この本の中に私は自分を発見し、生き生きとした人間の生を感じました。こんなに幸せなことはなかなかないと思う。この本は、分裂病患者が共同生活を営む「べてるの家」を取材したドキュメンタリーである。
記録に、印象に残った言葉たちを記しておこうと思う。
・(べてるでのSST社会技能訓練について記した項で。)
「じつにかんたんな会話のようであっても、メンバーの一人ひとりはSSTに集まることによってひとつのことを確認しているかのように思える。私たちはつながっていたいと。(中略)こうしたひとつひとつのことが、彼らをつなぎとめ、人間の輪の中に引き戻し、ひいては人間関係を取り戻すことに繋がっている。」
自分が休職していた頃のことを考えると、社会から断絶された孤高の存在であったと思う。少し元気になってくるとそのことに気づき、虚しくなった。いま自分が会社で働き、社会の一員として認められているという自覚が、今のしあわせな自分を作り出しているのだと、つくづく思う。そういう意味では、私も「つなぎとめられている」ことによって今の自分を保っているのだろう。
・向谷地さんの言葉
「私たちは、生活を便利にしたり豊かにしたり、自分にないものを身につけたりいろいろな努力をしているが、そういうこととは無関係に、生きることに悩みあえぐという力が与えられている。そういうことを忘れている。(中略)実は人間は、どんな境遇に生まれようとどんなに恵まれていようと、ちゃんと悩む力をもっている。」
そうか、精神病患者は悩み上手なんだな。
・分裂病患者 長友ゆみさん
「ほんとうにこわくなるというより、こわくなりそうになる、その前兆におびえてしまう。自分がどうなるかわからない、あるいは何をするかわからなくなりそうな、そのこわさ。 『いつも自分のことばかり考えてるから。そこが病気なんです。自分と付き合うのに苦労するから。もっと自信持てればいいんだろうけど。』」
前兆に怯えるということ。それはまさに今、私が経験していることです。
・ミシェル・フーコー『狂気の歴史』
精神病をつくりだしている澄みきった世界では、もはや現代人は狂人と交流してはいけない。すなわち、一方には理性の人が存在し、狂気に向かって医師を派遣し、病気という抽象的な普遍性をとおしてしか関係性をみとめない。他方には狂気の人が存在し、やはり同じく抽象的な理性、つまり秩序・身体的で精神的な拘束・集団による無名の圧力・順応性の要求たる理性を介してしか理性の人と交流をもたない。両者のあいだには共通な言語は存在しない、むしろもはや存在しないのである。
・べてるの良いところは、病気をあけっぴろげに笑ったり、平気で不謹慎な言葉でもって迎合しているところだと思う。例えば、分裂病真っ只中の人に向かって「落ちるとこまで落ちな。見ててあげるから。ばいばーいって。ワハハ」また、ある人は、自分のことを「おれ、アッパラパーだからさ」という。病気に真に向き合っているのだと思う。そこには、誰も病気を隠す人はいないし、なかったことのようにして生きる人はいない。そこが、わたしが今生きる社会とは大きく異なるところだと思う。 -
後輩から勧められて読んだ一冊。べてるの家の名前は知っていたが、「どうせキリスト教だろ?」との先入観があった。斉藤道雄はガラスのように透明な文体で微妙な揺れや綾(あや)を丹念に綴る。本書で第24回講談社ノンフィクション賞を受賞した。
http://sessendo.blogspot.jp/2016/09/blog-post_3.html -
結局、飾って装っても、そこで一瞬はしのげても、違和感しか生まれない。そればらば最初から裸で、自分を相手に預けるようにいたい。わたしというのは、自分の中にはいなくて、「あいだ」にあると思う。
●以下引用
もし管理上の規則があったら、すべてが「規則にこう書いてあるから」と片づけてしまい、ひといひとりの自由闊達な意見や発想が埋もれていくような気がしたのでした
自由闊達な意見や発想をもち、問題があればそれを「ぶつかりあいと出会い」によって解決していく。
問題をどうすればなくせるかとか、あるいは防ぐことができるかとは考えない。問題がおきるのは当然で、それがおきたときにひといひとりがどう対処するか
苦労を語れば語る程、だんだんとまわりとの関係が回復してきた
自分を語ること、自分の思いを人に伝えること、そんな簡単なことが早坂さんにはできなかった。そもそも語るべきことがなんなのかを知らなかったし、人に話しかけ自分を聞いてもらうという経験をもたなかった
乱暴な口をきいた。なんとかして彼の気持ちを開きたいと思ったからだろう
早坂さんは、「まわりとの関係が回復してきた」なかではじめて自分自身を取り戻せるようになった
★「これしなさい」とか命令口調でいわれたら、苦手な方だからな。人付き合いの苦手な方だ。だけどだんだんと人とつきあうようになったの、うまくな。それはなぜかというと、自分とつきあうのが上手になったんだ。
仕事を終えて共同住居に帰り、そこにいたものがなにくれとなくことばをかわす。
神を求め、道を求めるというよりは、礼拝の後のお茶とわずかなお菓子を求めてやってくる人々。そのひとときだけでもみんなといっしょにいたいと思ってやってくる。
なによりもまず目の前の弱きものたちに目を注ぎ、ともに悩み、迷い、苦労しながらそこにたたずんでいた
そうした人びととのかかわり方を見てきたとき、べてるの家には、あるいはべてるの家がそこからはじまった人間のかかわりのなかには、はじめから変わることなくひとつの視点が貫かれていたように思える。
既成の概念によらず、形式にたよらず、世間体にこだわることなく、そこにいる人間そのものを見ようとする視点
薬を飲むか飲まないか、どこまでがんばるか、それはすべて本人が決め、選びとることなのだ。
怒られてもせかされても、いや、怒られれば怒られるほど早坂さんの作業は進まなかった。進まないどころか、無理をすると「ひっくり返って」しまう。
早坂さんはそこで自分の弱さを非難されるのではなく、その弱さによって「三人分の仕事を生み出した」
人が見ているイメージは、じつは「自分がつけたイメージ」でしかない
★なぜ精神障害者だけが社会復帰なんだろうか…障害者はほんとうにそんなことのために生まれてきたんだろうかと。あるいは私たちの役目も、ただ障害者の障害性にだけ目を向けて、それがいい悪いというような次元のことをやっていくということがわれわれの役目なんだろうかと。
精神障害者問題の最大の不幸は、精神障害者に限り社会は彼らを社会の一員として受け入れ、その苦しさと声を聞くことを拒んできたことにあります。
★多くの人が一生をこの病気とともに過ごさなければならないのだとすれば、病気を治せ、健常者になれといわれつづけることは、すなわちその人が一生「いまのあなたであってはいけない」といわれつづけることになる。
★強固な連帯に支えられた場でも、明晰な理念に支えられた場でもなかった。規則や取り決めや上下関係によって固定されたわざとらしい場でもなかった。ただ弱いものが弱さをきずなとして結びついた場だったのである。
働けないものは寝ていてもいいという、そんな不平等なシステムを一般社会は許容しない
彼はいまこそ救いが必要なんだ、応援が必要なんだという声に意見がまとまる
★「医療」や「福祉」や「行政」の枠のなかにいるかぎり、彼らはいつも病人、すなわち治すべき人びとであり、障害者、すなわち社会復帰しなければならない未完の存在だった。
病気があっても、いや病気であるがゆえに、彼らはあるがままの自分をそのままに生きている。そう生きなければならない。飾り、気取り、自分を作ろうとすれば、どこかで破綻してしまう人びとなのだ。それはまるであらゆる飾りを取り除いた後にあらわれる、原初の人間の姿のようにもみえる。
★そのような彼らといるうちに、訪問者はそこにあぶりだされてくるのがけっして精神障害者の真実の姿なのではなく、彼らの前にいる自分自身なのだということに気づくのである。飾らず、作らず、そのままで生きているべてるの人びとの前にいるとき、仮面をかぶり、体面をとりつくろうことに懸命で、いつもまわりの評価を気にして奮闘し、気が休まることのない「こっけい」な自分というものが見えてくる
★彼らの話に耳を傾けるほどに、自らのなかにしだいに湧き上がる違和感、内なる声の問いかけを抑えることができない。目の前にいる人々の、こころ病むはずの彼らのなかにある底しれぬ安心感にたいして、自分自身がかかえこんでいるのはなんとちっぽけな不安の均衡だろうか。そのちがいはいったいなんなのだろうかと。そのように考え出す、その瞬間。訪問者はそこで鏡に映し出されたように、自分自身の姿と人生を見てしまう。自分は病気の人に会いに来たのではなかったか、だのに病者はいったいだれなのか。
★しばらくするとべてるの家は、私にとってある意味で「当惑の場所」となってしまいました。私自身がまさに病気になってしまったのです。……私は自分が考えているよりも、随分と器用に人生を送り始めていたことを知らされました。そしてべてるとは、私たちいわゆる健常者が一方的に何かをしてあげる場所ではなく、自分自身をもう一度見つめ直す場でもあることを知ったのです。
当事者であれ、訪問者であれ、人はそこで自らが病人であることを悟る。その病気とは、精神医学によって分類される病気ではない。それよりももっとずっと深く広い意味で、人間がかかえている苦悩やひずみ、不十分さ、あるいはそうしたことを回避したときにあらわれる病理をさしている。
★私は、彼らによって自分の力の無さ、未熟さ、貧しさを知らされました。…べてるに行くと私自身、安心して弱く、ありのままであることが許されているような落ち着きに満たされることがあります。そして、弱いままで生き合える信頼なくして、人間は共に生きることはできないことを教えられるのです
そこに書かれているのは、「底の底から光を見出し、魂の安らぎを得ている」人々の姿にほかならなかった。そのようなべてるの家と出会うことによって、人は「真の自己を回復する」ことができるだろう。
「心休まるっていうと変なんですけども、自分が素直になっていく」
★私もむかしは自分をいじめていた。(それが)楽な気持ちになりたかったら(自分を)“ほめること”だとわかった。いつも、私なんてどうして生まれてきたんだろう、生まれtこなきゃよかったって思ってた。真ん中にすわったことがなく、いつも端っこのほうにすわっていた。端っこ端っこばかりにいた。でもいまはちがう。いまは、私はやっぱりいてもよかったんだと思えるようになった
★「誰かに、何かにすがっていかなければならない人」がいくら集まっても、無力でばらばらな人間集団しかできないと他人は思うだろう。べてるの家がそうなってもおかしくはなかった。けれど弱さをきずなにした人びとがその弱さをさらけ出し、おたがいにその弱さを認め合って暮らしはじめたとき、そこには「底の底から光を見出し、魂のやすらぎを得る」人々の力、その人びとが集まることによって生まれる場の力が培われていた。
★私は……強くなければいけない、人に認められなければいけない、企業を成長させなければいけないと、日々緊張して生きてきました。
★それはべてるというものに触発されて、その人が賢明にかかえてきたものがどこかでどっと崩れてしまう、そのときに起こることなのだろう。あるいはひたすら信じつづけてきたものが呪縛となり、もろくひび割れ落ちてしまう覚醒のときに。
★分裂病になることが「なにかの終わり」ではなく、「そこからなにか新しくはじまること」としてイメージできる
★幸せっていうのはなんだろうということを聞いたことがあります。幸せは『いまうれしい』『いま楽しい』ことだそうです。
もしかしたらふつうの会社には勤められないけれど、それよりはるかに幸せなんだという人もいてもいいんじゃないか
★いっしょにやろうと。お互いに学び合おうと。教育しあおうと。僕は、むかしよりは思いやりも少ないし、優しさもなくなった医者になりました。障害者がこの世で幸せをつかむためにはですね、とくに私の思いやりや善意だけではなんともならない、むだなことはしなくなったということです。むしろそんなところに(患者を)囲い込んで、せまっくるしいところに追いつめていくというような、そしてそんなことをしてしまう自分も(また)追いつめられていくというような、そしてそんなことをしてしまう自分も(また)追いつめられていくということから卒業したいなというのが、最近私たちがいちばんこころがけてやっていることです。
そうやって『話せない』ことをいえて、すごいなあと思いました
いろんな地域の人たちに、しかられたりとか、出て行けといわれたりとか、そういうことにもちゃんと直面してきた。苦労にじつに直面してきました。それが元気の秘訣
★いちばん不幸なのはやっぱり直面させられなかったということなんですね。ケアされて保護されて守られて、多くの人たちが代理になってですね、代わりになって『この人はストレス与えたら発病する人です、病気になる人です』と守られている。そのおかげで“ともに暮らす”っていうことの厳しい現実に直面することから遠ざけられてきた
★そういう面では、べてるの人たちはそういう“守る乏しさ”から逆に“地域のなかに入っていく”(そこでさまざまな問題に)自分たちが直面してきたたくましさっていうのがあるんですね
問題に出会い、悩みもがく。そういうところにどうやってみんなで答えを見出すか、掘り出すかというところにもしかしたら人間が生きているということの本質があるのではないか
もうひとりの自分とのケンカ。もうひとりの、自分が描いている理想像の自分と、ほんとうの自分が格闘して、自分とつきあうのに疲れたり、楽しくなたり、泣きたくなったり。
彼女の病気が「自分とうまくつきあえない」ことからはじまったとするなら、それは結局のところ自分とつきあえるようになることしかなく、自分自身と和解することでしか解決の道がない。みんなのなかにいて、人とのつながりのなかで人間関係を回復することが必要だった。それができたとき、はじめて自分との関係も作り直すことができた
だめな自分を受け入れるきっかけとなったのは、なんといっても「人と話すこと」だったように思います。
自分を守るために、人との関わりを絶とうと必死になって引きこもっていた。けれど人と関わるという、まったく逆の方法から回復の道は開かれた。
著者プロフィール
斉藤道雄の作品










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :