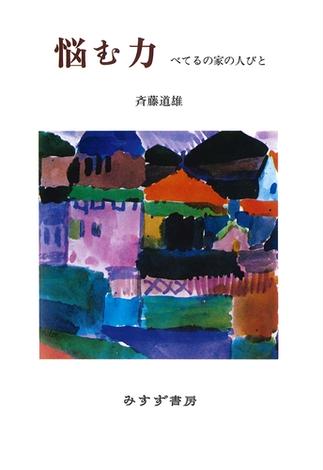- Amazon.co.jp ・本 (272ページ)
- / ISBN・EAN: 9784622079743
作品紹介・あらすじ
聞こえないこと、それは「欠陥」として意識しつづけ、絶え間ない努力によって乗り越えなければならない障害ではない。 日本のろう者・ろう児の母語、日本手話で授業を行い、手話と日本語のバイリンガル/バイカルチュラルろう教育を実践する日本初にして唯一の学校、明晴学園から見えてくる ○ ろう教育の歴史 ○手話という言語が乗り越えてきた、また今も向き合っている困難 ○ 言語学からみる手話 ○ 補聴器、人工内耳など最新の動向……ろう者・ろう児、その親、教育者、日本手話の話者・通訳者(ろう者・聴者いずれもがいる)、手話言語学の研究者といった多方面の人びとへのインタビュー、欧米の動きや事例、研究成果、国内外の文献、そして、何よりも明晴学園で「手話を生きる」子どもたちのことばをとおして、過去から未来へ、現在進行形で変わりつつある手話の世界を描く。
感想・レビュー・書評
-
知った気でいたことが何段階にも知らなかったことで上書きされていく。圧倒的多数による無意識の思い込みや一方的な対策など。効率重視や知ろうする努力を怠ることの危うさを強く感じる。
詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
卒論で使わせていただきました。
手話とは何か。歴史から現代の教育においての実態まで読みやすく分かりやすい。 -
4章と5章は他の手話関係の本ではあまり見ない内容もあって、個人的にとても楽しかった。
とても良い本なので、何かしらの形で手話に触れてる触れてない関係なくたくさんの人に読んでほしいです。 -
ろう児のための学校、明青学園の設立にかかわった作者の目からみたろう者のための手話教育についての話。
日本においてはつい最近までろう学校で手話を教えることは禁止されていた。ろう者は聴者の唇の動きを追って話を読み取り、口話と呼ばれる方法で声を出し話すことで、つまり「日本語」でコミュニケーションを取るように指導されて来た。これは世の中の大多数、すなわち聴者と交わることを最優先にしているためで、手話を知ると、口話を身につける妨げになるという理由で禁じられてきたのだ。
こういう考え方は日本に限らず世界各国でもあったようで、手話というものが決してろう者の教育の主流ではなかったということにまず驚く。
一方で日本における「手話」にも大きく二種類ある。一つは日本語を話しながら日本語の単語に対応する手話を当て振りするかのように語る「日本語対応手話」。一般に紹介されることが多いのはこの日本語対応手話だそうだ。
もう一つは「日本手話」と呼ばれるもので、これはろう者の社会において昔から使用されていた手話。日本手話がろう者における自然な言語だとすれば、日本語対応手話はこの日本手話を切り出して、日本語に当てた人工的な手話と言える。
ただ単語を当てるように使う日本語対応手話は表現力が弱い。考えてみればわかるように、仮に英語を話す人に対して日本語に英語の単語をあてて喋ったとしよう、これはまさに片言英語の最たるものになる。そこでは各単語の意味は伝わったとしても、話の内容全体が正しく伝わっているかどうかは定かではない。
そう考えるとろう者の世界で自然と使われてきた日本手話のほうがいいと考えるはずだが、これもまた身振り手振りが聴者にはちょっと変に見えるという理由で、つまりスマートではないという理由で教育の場では避けられてきたのだそうだ。
それはある意味、手話というものに対する聴者の偏見、そしてろう者という「少数者」が聴者という「大多数」に合わせるべきだという暗黙の前提で社会が動いてきたという時代性がそうさせたと言えるだろう。
作者の関わる「明晴学園」では「日本手話」を第一言語として、ろう者の教育者がろう者の生徒に手話を教えるということを実践する日本最初のろう学校として活動している。
TV番組等でも時々手話通訳がつくが、手話というものを見る目を変えてくれる本だった。 -
なぜ「手話で生きる」ではなく「手話を生きる」なのか、読んで納得。手話は日本語の補助ツールではない。むしろ、ろうの人にとっては第1言語であり、日本語は第2言語。まずそれを理解しないと何も始まらない。人工内耳を拒んでまでろうでいたいという気持ちには複雑な思いがする一方で、人間としての尊厳をベースに考えれば当たり前のことかもしれない。
-
本書によって日本語対応手話と日本手話は異なるものであることを知り、ろう者にとって手話がいかに必要不可欠なコミュニケーションツールであるかを認識する。健聴者が見過ごしてしまいがちな「言語」としての手話とろう者教育の現状を綴った良書。
-
各地で自治体主催の手話教室が開かれ、多くの手話サークルが活動する中で、日本手話に対する理解はまだまだ途上にあるということに驚きました。ほんの十年前の2006年に、元聾学校校長という方が「日本語体系の習得は手話では難しい」と新聞に寄稿していたこととか(p73)。また、ろうあ連盟が「手話を『日本手話』と『日本語対応手話』に二分」する」として日本手話でろう教育を行うことに否定的である(あった?)こととか。なるほど、「日本聴力障害新聞」はろうあ連盟の機関紙なのだから、連盟の意見が反映されて当然ですよね。つい、「新聞」だから、ある程度は両論併記されていると期待してしまいがちですが。
「手話サークルのほとんどがろう者の手話ではなく日本語対応手話を教えている」というのは、実際のところどうなんでしょうか? うちのサークルではとにかく「ろう者の手話を見る」こと、そして「その地域での表現」や「年代による表現の違い」、「その人の癖」を覚えること、とよく言われますが。この辺りは、今度サークルの先輩方に聞いてみようと思います。
<気になった誤植>
P76 L12 できないこととが → できないことが
p219 後ろからL3 これを英語でを読むことを → これを英語で読むことを
あと、p215-216の「ニワトリと卵の議論」について。「手話という言語の社会的な認知が進まないのは、手話話者が少ないからだ、いや、手話話者が少ないから社会的認知が進まないのだ」は、「ニワトリと卵」なら後半が「社会的認知が進まないから手話話者が増えないのだ」となるのでは? 次の例の「手話をきちんと使える先生がいないから、手話の教育が進まないのだ、そうではなく、手話の教育が進まないから、結局手話をきちんと使える先生が育たないのだ」は、ちゃんとひっくり返っているので。うーん、何度も読みなおしているうちにわからなくなってきました。 -
衝撃的な本である。日本のこれまでのろう教育では、口話と言って、聴者(健聴者)のように声を出し話せることを目標とした。相手のことばは読唇術で読み取るのである。そして、手話は程度の低いものとしてむしろ禁止されていたのだという。しかし、口話で成功する者は一部であったし、そもそも本人には聞こえない。相手が変わってもなかなか通じない。(習いたてのときの中国語みたいだ)それはいわば聴者に近づくことだった。しかし、斉藤さんによれば、本来の日本手話というものは、自然言語の一種であり、文字を覚えるより前に修得できるもので、口話の修得のために手話を禁じてきたことこそ、ろう者の知的発達を遅らせる原因であったという。しかし、この主張はむしろろう者の人たちの強い抵抗にあった。本書でも、斉藤さんのいう日本手話の特徴の一端が紹介されているが、それはどうも日本語の文法とは違ったもののようで、発想も日本語の察しの文化を受けたものではない。むしろ、欧米的だ。ぼくには手話が自然言語の一種ということがまだよくわからないが、現実にそれで教育され、育っていっている子どもたちがいるのである。ろう者たちはこの手話を学んだあと、日本語の習得を目指すことになる。つまり、日本語とのバイリンガル教育である。このあたり、もうすこし説明が欲しい。ともかく、かれらは日本手話の普及の運動の中で、2008年に手話でろう者を教える学校-明晴学園をつくりあげたのである。(斉藤道雄さんは聴者で、ジャーナリスト、テレビのディレクター。2008年から5年間明晴学園の校長をしている。)
-
最終章。ジャーナリストが書くとこうなる。独特だね。けど、感心する。
著者プロフィール
斉藤道雄の作品










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :