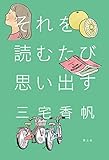- Amazon.co.jp ・本 (288ページ)
- / ISBN・EAN: 9784087213126
感想・レビュー・書評
-
2024年を迎えてから読書の冊数がガクンと落ちた。厳密に言えば、読んではいるけれども最後まで読みきれない。これまでは隙間時間が10分でもあれば本を開いていたのに、今では片道1時間以上かける通勤電車の中でさえ本を読む気になれない。読まなきゃ読まなきゃと思ううちに、月日は流れ、葉桜が目立つ時期になってしまった。
時間はある。また、読みたい気持ちもある。ただ、読むためのエンジンが駆動しない。現に本を開き読み始めさえすれば、次が気になり読み進めてしまう。だが本を開く行為そのものが億劫で、読み始めるのに膨大な労力を要する。
これはいったい何なのか──
さて、縁は異なもの味なものとは言い得て妙で、本との出会いは不思議なものだ。面白い本を求めているときに限ってめぼしい本が見つからない。逆にふらっと立ち寄ったときに「これは…!」という本に出会ったりする。
本書はまさにその一冊だ。
前置きはこのくらいにして、なぜ私は本を読むことができなくなったのか。分析するに、
1) 時間がない
2) 仕事による疲労
の二つの要因に分けられると考えた。しかし考えても考えても、①読書する時間はあるし、②疲労困憊するほど働いているわけでもない。
では、なぜ本が読めないのか。これにはさまざまなアプローチがあると思うが、本書は歴史的な文脈からこの問題を徐々に紐解き最終的には社会的な側面からアプローチを試みている。その過程が正しいのかは別として、非常に興味深い手法であり一読に値する価値がある。
私たちが読書をする目的を考えてみよう。勉強するため、情報収集、仕事へ役立てるため、単純に趣味として、などなど高邁なものから凡俗なものまで多岐にわたる。それぞれにそれぞれの良さがあり、どれが良いと区別できるものではない。しかし、どのような意識を持って読書するかによって読書の「仕方」が変化するのは事実だ。そして、現代の社会人が読書できなくなったポイントはここにある。
大衆による読書という知的慣習は日本開国に遡る。欧米諸国に追いつき追い越せを果たすために、明治政府は国民へ教育の重要性を説き読書を推奨した。だから昔も読書をする習慣は存在していた。当時の日本国民は資本主義が流入し長時間労働が蔓延する中で本を読んでいたのだ。そしてこの慣習は今もなお続いている。
要するに現代の読書は何かしらの答えを探すための読書であるのだ。出版業界の業績は下がりつつあるが、その中でも「自己啓発系」のジャンルは堅調である。それは自己啓発本が何らかの答えをくれるからだ。
その根底には「コスパ」「タイパ」の考え方が潜んでいる。無駄なく効率よく情報を集めたい、答えを知りたい。そんな下心が見え隠れしている。つまり私たちは無駄が嫌いなのだ。
本書では、小説などの本から得られる芋蔓式の知識をノイズありの知識と定義付けし、反対に、読み手が知りたい情報そのものをノイズのない知識と位置づけをしている。読者は、前者を不要なものと捉え、後者に至上の価値をおく。
しかし、そんな偶発的な知識を切り捨てて良いものだろうか。そうして得た知識が役に立つものであれ役に立たないものであれ、恩恵を与えてくれるのは確かだろうし、そうした厚みが精神的な余裕へとつながる。これを俗に「教養」と言う。
そう、私たちは「教養」が大事なものであるとは頭で理解しつつも、そんなものに労力を費やしている余裕はない。答えは今すぐに知りたいし、教養を培ったところで何の役にも立たない(可能性の方が高い)。
だから私たちは気軽に情報の手に入るSNSにのめり込むのだし、直接的な解が導出されない文学作品を読む気力が起きない。実用的な情報を絶えず求めるウォーキングデッドさながらだ。
しかし、私はこれを書いていて思うのである。即物的な情報は結局はすぐに廃れる。新聞と同じだ。新聞はありとあらゆる情報が記載されているが、一年と経てばただの紙屑でしかない。激動の荒波に耐えうる本質的な知識は長い時間をかけて収集し、知識と知識を掛け合わせて自らが見つけ出していくしかない。つまりそれは「知恵」だ。
皆さんも胸に手を当てて考えてみてほしい。ついこの間仕入れた実用知を現実世界へ上手く使うことができただろうか。おそらく多くの人が失敗に終わったことと思う。
なぜなら、状況に応じて実用知を使い分けていないからだ。のべつまくなしに「チシキ〜」「チシキ〜」とさまよい求めてみても、そっくりそのまま適用できるわけではない。情報や知識は状況に応じて「加工」する必要があるのだ。
にもかかわらず私たちは実用知を「加工」せずそのまま使おうとする。だがその試みは得てして失敗に終わりがちだ。だから私たちは次から次へと情報を求め続ける知的ゾンビへと化してしまう。
言うなれば知識は食材だ。新鮮なうちに適切な調理をすれば美味しい料理になる。しかし、腐った食材を調理しても美味しいものはできない。また、いかに新鮮でも調理法を謝れば美味しくはならない。
一方で、知恵つまり料理の技術があればどうか。食材が新鮮であればなおのこと、たとえ多少劣ったものであったとしても調理法ではいくらでもよくなる可能性がある。
要するに知恵とは既存の知識に付加価値をつける技法なのだ。
知恵の前段階には「教養」が存在し、教養の前には「ノイズありの知識」が存在する。そして、ノイズありの知識の前には「ノイズなしの知識」が横たわる。私たちはこの「ノイズなしの知識」を仕入れて満足している。本当に重要なのはその先の先だというのに。
これまで私が切り捨てたモノの中にどれだけ高価ものが眠っていたことか。それを思うと、本の隅から隅まで暗記するほど読みたくなる。
まあそれこそ本当に読む気が失せるんだろうけれど。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
-
 新書の棚に来てほしいー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』刊行によせて|三宅香帆(2024年4月18日)
新書の棚に来てほしいー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』刊行によせて|三宅香帆(2024年4月18日)
https://note.co...新書の棚に来てほしいー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』刊行によせて|三宅香帆(2024年4月18日)
https://note.com/nyake/n/n9dc3974ac1152024/04/19
-
-
読書や働き方、時代性等の様々な参考文献を引用し、時代によってなぜ本が売れたのか、当時の本の立ち位置は何かを論じ、現代における『なぜ仕事と読書は両立していないのか』が書かれている。
現代の読書はノイズだ。
今も昔も真剣に精一杯仕事をしているのは同じでも、なぜ現代では本が読めないのか。
自分は本を読むことを第一にしているからそこまで心配はしていないし、人によって本の代わりに娯楽として、または趣味として大切にしているものがあれば、それで良いのではないかとも思う。本は大切だけれども、本が全てではないし、本を読んでいれば偉いわけでもない。本書の主題とは異なるが、読み終わって感じたことは、時代に翻弄されずに自分の大切に気付けることが重要だということだ。 -
感想
時間はないし集中力は続かない。まずは隙間時間を見つける。そこから逆算して読める量を決定する。必要な本の大事な部分だけ。効率的に。 -
自分も一度本を読めなくなったことがあった。ただし、それは仕事を始めたからではなく、メンタルの不調から来るものだった。あのときはいろいろなものを受け入れるのが難しくなっていて本屋に入ると涙を流していた。筆者の言うノイズの考え方に納得がいった。安直に他の娯楽が充実しているから、などではなく、これまでの日本での読書の考え方の変遷を辿っていって今はこうという構成でとても勉強になった。
昨年は資格の勉強などであまり読書をできなかったが、今年はそれも落ち着いて月平均20冊以上読んでいる。仕事にも慣れてきて、終わったらへとへと状態から抜け出せたのが一因かなと思う。また、寝る前の一時間は電子機器から目を離すことを決めていて、その時間で本を読んでいる。読み始めてしまえばこっちのもので、続きが気になるようになる。最後の本を読むコツでないですが、これも参考になれば幸いです。 -
内容の6割は読書史。
全力で働くの辞めてゆるっと半分の力で働こう、そしたら本読めるよってまとめだった。
そら知っとるて!
✏つまり、過去や歴史とはノイズである。文脈や歴史や社会の状況を共有しているという前提が、そもそも貧困に「今」苦しんでいる人にとっては重い。
✏「情報」と「読書」の最も大きな差異は、前章で指摘したような、知識のノイズ性である。
つまり読書して得る知識にはノイズ――偶然性が含まれる。教養と呼ばれる古典的な知識や、小説のようなフィクションには、読者が予想していなかった展開や知識が登場する。文脈や説明のなかで、読者が予期しなかった偶然出会う情報を、私たちは知識と呼ぶ。
✏知は常に未知であり、私たちは「何を知りたいのか」を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。 だからこそ本を読むと、他者の文脈に触れることができる。 自分から遠く離れた文脈に触れること――それが読書なのである。 -
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
自分も働き始めてからずっと、書店に寄っては本を買うものの積読が増えて行くだけなのを悩んでいたので、タイトルで共感しかなかった。著者が提案されている半身社会についても同意。結論、本が読めるようになるには、私たちが働き方を変えていく以外に方法は無い。もっとゆるく、短く、全身ではなく半身で働ける社会になることを、切に願う。 -
『花束みたいな恋をした』から自己啓発本を読んでいる描写だったり、読書をできそうな時間にパズドラをやっている描写に着目したりで話が進んでいくところがまず興味深かった。書籍タイトルの考察を早速するのかと思ったら、明治時代以降の「労働と読書」を体系的に見ていく流れなのも面白い。『西国立志編』『痴人の愛』『坂の上の雲』『電車男』『推し、燃ゆ』など、各時代でたくさん読まれてきた本とその背景にある社会を関連させながら現代に至り、なぜ本が読めなくなるのかという話に展開が進む。
読めなくなっている背景として、最近の長時間労働のせいなのもあるのだろうが、昔から長時間労働の体質は変わっていないことを指摘していて、では現在の労働は何が違うのかとなった時に、支配の構造の違いに注目している。20世紀までは、「企業や政府といった組織から押しつけられた規律や命令によって、人々が支配されてしまうこと」が特に問題視されていた一方で、現代の問題は、新自由主義社会の能力主義が植えつけた、「もっとできるという名の、自己に内面化した肯定によって、人々が疲労してしまうこと」(p.245)であるとする。会社に強制されなくても、個人が長時間労働を望んでしまう社会構造があるとし、その結果として本を読む気力もなくなっているという。
個人が長時間労働を望んでしまう文脈の中で「自己啓発」の話が出てくる。これは、「ノイズを除去する姿勢」として本書では位置づけられている。「読書」と「情報」という点を踏まえたときに、前者が「ノイズ込みの知を得る」ことに対し、後者は「ノイズ抜きの知を得る」ことに重きが置かれている。
(※ノイズ=歴史や他作品の文脈・想定していない展開)(p.223)
『推し、燃ゆ』で自分の人生の文脈以外も本当は必要であると悟ることが表現されている箇所があるとする指摘も興味深く、他者の文脈をシャットアウトせずに仕事のノイズになるような知識を受け入れる帰結に繋げる。
そうした文脈の受け入れと合わせて、「半身社会」に進むべきと提言がある。著者も書いているように実現ビジョンはまだないので、結論の唐突感は無きにしも非ずだったが、問題提起としてここまで整理して考える素地になっている点はすごいと思えた。自己成長のために労働を内面化するという話は、自分自身にも心当たりもあり、意識しないうちにノイズをシャットアウトしかけることもあったかもしれない。時々そうなっていないかを確認し直して、自分自身の疲労と正しく向きあわないといけないなと思えた。
(以下補足)
※随所で引用されているが、近年刊行されている新書『ファスト教養』『映画を早送りで観る人たち』の文脈を踏まえて考えてみるとまた理解が深まる気になった。そのように参考文献が充実している点もよかった。
※村上春樹のエルサレム賞スピーチが2009年であることにまず驚いたが、壁と卵の話について、「壁=長時間労働を強いる会社」「卵=生活を大切にしようとする個人」に当てはめることができるかもとしている中で、この当てはめ自体も変化しているのではないかとする指摘も面白い。卵=個人の中で、自ら、壁=社会の競争意識の扇動、を内面化しているということで、卵の内側に壁を抱えている状況であるとして自分自身を搾取しているよう。
※働きながら本を読むコツは実施しているものもあるが、参考にしていきたい。
➀自分と趣味の合う読書アカウントをSNSでフォローする(「次に読みたい本」が流れてくる環境をつくる)
➁iPadを買う(ただしSNSアプリは絶対に入れない)
➂帰宅途中のカフェ読書を習慣にする(癒される趣味の時間、と区切る)
➃書店へ行く(行くだけで気分があがる)
➄今まで読まなかったジャンルに手を出す(社会人になってビジネス書が面白く読めるようになったなど)
⑥無理をしない(読みたくなったら、読めばいい -
Amazonの紹介より
【人類の永遠の悩みに挑む!】
「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」……そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。
「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。
そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?
すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。
【目次】
まえがき 本が読めなかったから、会社をやめました
序章 労働と読書は両立しない?
第一章 労働を煽る自己啓発書の誕生―明治時代
第二章 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級―大正時代
第三章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?―昭和戦前・戦中
第四章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー―1950~60年代
第五章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン―1970年代
第六章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー―1980年代
第七章 行動と経済の時代への転換点―1990年代
第八章 仕事がアイデンティティになる社会―2000年代
第九章 読書は人生の「ノイズ」なのか?―2010年代
最終章 「全身全霊」をやめませんか
あとがき 働きながら本を読むコツをお伝えします。
題名にひかれて、読んでみました。
単純に「時間がないから」とか「文字を読むのが苦手」、「ゲームの方が楽しいから」といった理由だけでなく、その辺りを深掘りしていくことで、その理由が明らかになっていくといった内容になっています。
まさか、働き方の歴史や本に対する考え方を歴史を通じて語るとは驚きでした。
ただ、そこまで深掘りしなくてもよいのではとツッコみをしたくなりました。
なぜ労働と読書は両立しないのか?それを象徴させる映画があるということで、それが「花束みたいな恋をした」という作品。個人的に映画を見たことがないのですが、そこには2人のそれぞれの考えが表現されています。それが労働です。
本好き2人だったけれども、忙しいのを皮切りに、それぞれが変化していきます。本が読めない一方で、ゲームだったら出来るといった話が登場するのですが、そこから労働の歴史を紐解いていきます。
「本」としての目的や立ち位置が、今と昔と異なっていて、色んな事実を知るたびに、「へぇー」と思ってしまいました。
作者の着眼点が面白く、時代時代における本との出会いが魅力的でした。どのようにして、その本を購入するようになったのか?
人生のバイブルや自己啓発やちょっとした非現実を楽しむためなど用途は様々。
この本を読んで、色んな知識を得るというわけではありませんが、こういった考え方もあるんだなといった情報を得ることで、考え方に広がりが見えるのかなと思いました。
ただし、作者の考え方に賛同ができるかは人それぞれです。個人的には、ちょっと違うかなと思う部分もありました。
本好きであるが故、本ありきで作者は考えを披露していますが、理想的な労働をしたとしても、なかなか全員が空いた時間を読書に費やすとは限りません。
私の周りには、本が好きな方はあまりいません。
というのも、なぜ本を読まないか?と質問すると、だいたいは「途中で飽きる」や「文字を読むと眠たくなる」、「そもそも本が苦手」といった方が多数です。
やはり皆さん、ゲームや映画、ギャンブルといった娯楽になってしまいます。どうしても文字だけで追っていくと、頭の中で一度絵や景色みたいものに変換して、想像します。ゲームや映画は、それをダイレクトに頭の中に入るので、変換といったストレスを抱えず、何も考えなくても楽しむことができます。
本の世界でも、ベストセラーや何万部達成といったものは見ますが、果たして最後まで本を読んだ方は何割ぐらいいるのか気になるところです。
また、音声版といった耳で楽しむコンテンツや電子書籍もあるので、忙しくても触れる機会はあるかと思います。また、ビジネスにおいて、参考文献として、使用するとき、それが「読書」として解釈するのか?
あるいは本の中の一部分だけでも読みたいという方もいるので、「本が読めない」の定義がどの辺りを指すのかはわかりませんが、なかなかそこは難しいところかなと思いました。
速読といった方法もあるのですが、それも「読んだ」ことになるのか?人それぞれの解釈があるかなと思いました。
まぁとにかく、「読書ができない」の背景に労働史といった着眼点は面白く、また本に対する人それぞれの考え方も紹介していて、楽しめました。
ちなみに最後の「あとがき」にある「働きながら本を読むコツ」が紹介されているのですが、私はすべて当てはまっていたので、驚きでした。一部目的が異なっていたものの、ほぼ実行されていたので、そこだけでも皆さんの読書ライフに当てはまっているのか?答え合わせしてみても良いかなと思いました。
著者プロフィール
三宅香帆の作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :