推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない―自分の言葉でつくるオタク文章術
- ディスカヴァー・トゥエンティワン (2023年6月23日発売)
 本棚登録 : 538人
本棚登録 : 538人
 感想 : 51件
感想 : 51件
- Amazon.co.jp ・本 (250ページ)
- / ISBN・EAN: 9784799329504
感想・レビュー・書評
-
「伝えたいこと」がある人は絶対読むべし!
っていうか普段からレビューを書いてるブクロガーは一読の価値ありです
最近そこかしこで目にする新進気鋭の書評家三宅香帆さんの文章術の解説本です
すでに10冊くらい本も書いていらっしゃるんで新進でもないか
この本を図書館で借りてきて直ぐに、三宅香帆さんがネットで芦原妃名子さんの事件に関する「想い」を表明している記事を読みまして、「なるほど」と思うところがたくさんあったのでこの本も楽しみに読み始めました
推しの素晴らしさを伝えたい!って思っている人に対して、文章化する必要性や、心構え、技術などの情報が分かりやすく書かれているんだけど、自分ではそこまでしないかな
だってめんどくさいし…w -
「書評家の三宅香帆さんって誰だ?」から関心を持ち、読んでみました。
「若いのに、たくさん読書をして、どんな事を語るのだろう」最初はこんな感じ、、
読み進めると、自分も同じ「本好き」として三宅さんが発信する言葉が自分に新しい刺激を与えてくれます。
(読んでてワクワク楽しい!)
言語化や、思考の整理方法を論ずる内容で他にも多くありますが、切り口がとにかく面白い。
「推し」をテーマにしているため、細々とした箇所が「一般論的」ではなく三宅さん自身の経験からくる「具体的」な話しであり、より読者に「伝わる内容」だと思いました。
何かを発信したいとき、人と話すとき、言葉の選び方、これを知っている人と知らない人では見えない大きな差がありそうです。
自分も若い後輩に同じような思考や言語化の本を勧めたことがありますが、いまいちピンときていない様子。
(勧め方が下手なのかな、、? と悩むこと数十回、、)
でも、本書の三宅さんの言葉(表現)なら誰にでも伝わりそうな予感がします。
人に勧めるだけでなく、自分自身も「これから自分のブログどうしよっか?」と過去を見直し、今後において修正することを楽しむきっかけを貰った気がします。
これからは三宅香帆さんが自分の「推し」になること間違いなし!
自分にとって今後注目の人物となりました。 -
自分には『推し』というほど好きなものが無いなと悲しくなることがあった。だけどこの本を読んで自分は好きなことを言語化してこなかったので、推していることに気付けなかっただけなんだと感じた。
『自分の言葉で、自分の好きなものを語ることで自分が自分に対して信頼できる「好き」をつくれる』というのを筆者は感動を言語化する理由としている。好きと感じるほどのものだからこそ、自分にとって何かしらの大きな影響を与えている。それを言語化することで自己自覚的になれる。
自分の好きだなと思えるものを細かく言語化していくと自分の好きなジャンルの輪郭が少しずつはっきりとしてきた。面白いことに昔好きだったものとかもこのジャンルに属するという発見があった。そこで自分は長年このジャンルを推していたのかと感じ、それまで不鮮明だった自分を少しずつ理解できるようになった。
好きなものを言語化することで自分がどういうものかを見つけられる楽しみと、それを相手に伝えるテクニックがいろいろと載っていてとても良かったです。 -
ひとつひとつの感情を細分化して自分の言葉に向き合うというのはなるほどと思った。
自分は推しがたくさんあるので、公開するにせよしないにせよ、とりあえずいろいろな気持ちを書き綴ってみたくなった。
自分の感情と言葉を大切にすることを意識できるように取り組んでみる。 -
●なぜ気になったか
「やばい!」ばかりの世の中でほんとイヤになることがあるが、その便利さはわからなくもない。自分の言葉で表現する方法を学びたい
●読了感想
そっか、利便性に逃げるのがやっぱりいけないんだ。感想をもう一段細分化し、それを言葉にすることが表現力を広げる、という意識を忘れないようにしよう
#推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない
#三宅香帆
23/6/23出版
#読書好きな人と繋がりたい
#読書
#本好き
https://amzn.to/45PDu28 -
本や映画の感想を書いても「やばい」しか出てこない。まさにタイトル通りの悩みを抱えてたので購入。読了後にさっそく本書の内容を実践したら、驚くほどスラスラ書けるようになっててビックリ!特に良かったポイントは3つ。
1つめは【ありきたりな言葉を使わない】
「泣ける」「やばい」「すごい」「考えさせられた」これらのように一言で感情を片付けられるような言葉は使ってはならない。
う~ん、自分の文章を思い返してみると多用しちゃってるなぁ。試しに上記の言葉を使わずに書いてみようとすると、他に言い換える言葉が見つからず苦戦。今までどれだけ一言で片づけてきたか痛感した。もっと語彙力をつけなければ。
2つめは【書く前に他人の感想を見ない】
自分の感想を書く前に他人の感想を見ると、その言葉に影響されて本来自分の書きたかったことが書けなくなる。
これもめっちゃやってるなー。映画や本を観る前に評価が気になって必ずレビュー見ちゃう。これからは評価を気にせず自分が観たいものを見て、見る前は他人の感想は見ないことにする。
3つめは【良かった箇所と悪かった箇所を具体的に挙げる】
このテクニックは難しいけど一番効果があった。好きなところや嫌いなところに対して、「何で?」「どこが?」「どうして?」と自分に質問しながら考えていくと書きたいことがどんどん見つかってくる。まだ考えてから浮かんでくるまで時間がかかるので簡単ではない。この辺は何回もやって慣れていきたい。
具体的な箇所が見つかってしまえばこっちのもの。むしろ書きたいことがありすぎて長文になってしまう。どこを残してどこを削るか、最終的には自分の本当に好きで書きたい部分を残すことになる。取捨選択の能力も身につくのでありがたい。 -
まさに推しの素晴らしさを語りたいのに語彙力が少ないと悩んでいたところだったのでとても勉強になりました。
気持ちを細分化するということ心がけてみようと思います。 -
推しと呼べるほどのものはないと自覚してるけど、ここに書かれてたことには納得。
面白さとは共感と驚きの2種類である。
他人の意見を見る前に自分の意見を発すること。
言いたいことをひとつ決めること。
どういうところ、どういうシーンが好きなのか、自身のエピソードを描写すれば唯一の語りになる。
改めて先日読んだ三浦しをんの「好きになってしまいました」の秀逸さを理解。
あったあった、コンサートのファンの子の話、逆にキラキラしてると感じたのが蘇ってきた。
232冊目読了。
-
推しについて語るためのメソッドが散りばめられている。私にはここまでの熱量で語る推し対象はないが、文章を書く上で使えるコツというか心構えを学べた。常々、アウトプットが苦手で、ブクログに投稿する感想もありきたりな言葉しか出てこないと考えていたので、非常に勉強になった。
言語化=細分化
ありきたりな言葉を使わない訓練をする
自分のオリジナルな感情を大切にして言葉にして残しておく習慣をつける
-
「推し」に関する本が増えてきた昨今、またこの手の本かあ…と敬遠していたのですが、おすすめされて読みました。めっちゃ良かったです(禁句)前半は推しや好きという感情を分析していて、中盤はそれを相手にどう伝えるか、後半は文章技術という構成。特に前半は好きを大切にしようと決めた24年の最初に読んで正解でした。中盤もコミュニケーション全般に言える大切なことだと思ったしとても勉強になる1冊でした。文章も軽くてとっつきやすいのでぜひ若い子にも読んでほしい。
著者プロフィール
三宅香帆の作品





















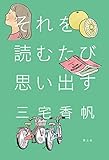










今回はご期待に添えず申し訳ありません
また機会にご利用お待ちしております
今回はご期待に添えず申し訳ありません
また機会にご利用お待ちしております