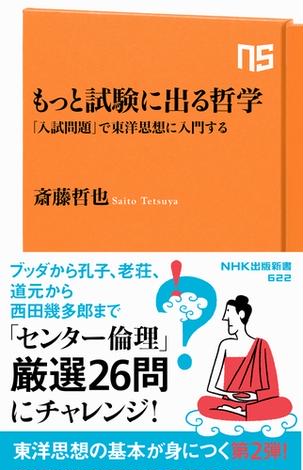●位置: 491
プラトンのいうイデアは、単なる形のことではありません。プラトンの対話篇で登場するイデアとは、「永遠不変の本質」 のことなのです
●位置: 547
このイデア論がなぜ「哲人政治」へとつながっていくのでしょうか。プラトンは、『国家』のなかで、魂のあるべき姿を国家のあるべき姿にあてはめて 理想国家 というものを構想しています。プラトンによれば、人間の魂はイデアを知る「理性」、物事を決断する「意志」、感情に関わる「欲望」 の三つからなります。これを「魂の三分説」といいます。そして、これら三つが正しく働くと、それぞれ知恵・勇気・節制という徳になり、この三つの徳が調和すると正義の徳が生まれると考えました
●位置: 608
アリストテレスは、事物の本質的な特徴がイデア界にあるとは考えませんでした。アリストテレスに言わせれば、椅子の本質的な特徴(座れるような形) は、現実の椅子に内在しています。そして事物に内在している本質的な特徴を、アリストテレスは「形相(エイドス)」 と呼びます。英語でいえば、form ですね。とはいえ、事物は形相だけからできあがっているわけではありません。どんなモノも、それを構成する素材や材料が必要です。椅子や机なら木材、コップならばガラスですね。この材料や素材のことを「質料(ヒューレー)」 といいます。英語でいえば、material です。このように、現実の椅子は、 形相と質料が合わさってできている というのがアリストテレスの考えでした
●位置: 619
自然哲学者たちの議論を思い出してください。万物の根源を水や空気、アトムと考えた彼らの議論は、いわば 形相を抜きにした質料だけに着目する議論 でした(ちなみにアリストテレス自身は、質料は、火・水・空気・土という四元素の組み合わせからできていると考えました)。一方、(ピタゴラス学派から影響を受けた) プラトンのように、永遠的で変化しないイデアは、アリストテレスの形相にあたります。小阪修平さんの卓抜した言い方を用いれば、「アリストテレスはプラトンのイデアから形相の概念を、イオニア自然学から質料の概念を継承し、この二つのアルケーの組み合せで、世界を考えた」(同前) わけです
●位置: 626
アリストテレスは、形相と質料という概念を用いて、事物の運動や変化を説明しています。たとえば、椅子について考えてみましょう。まず、椅子の質料が木材であることはわかりますね。でも、木材そのままでは椅子になりません。そこに形相(形や機能) が加わってはじめて、椅子になるわけです。公式的に書けば、「木材(質料) +椅子の形相→現実の椅子(質料+形相)」 となります。このとき「木材→椅子」という変化を、アリストテレスは、「可能態→現実態」 という概念でも説明しています。どういうことかというと、アリストテレスは、 木材という質料のなかには、家や椅子になる可能性が潜在的に含まれている と考える。そして、椅子の可能態(可能的な状態) である木材に形相が与えられることで、木材は、椅子という現実態(現実の状態) に変化するのです
●位置: 642
でも、なぜ椅子があるのかという問いに対して、私たちの常識的な感覚では、「そりゃ、誰かが座るために、職人さんが木材を使って実際に椅子をつくったからでしょう」と答えたくなるのではないでしょうか。アリストテレスも、こうした要因を忘れてはいません。彼は、物事には、形相因、質料因に加えて、作用因、目的因という 四つの原因 があると説明します。 作用因 とは、物事に作用を及ぼす原因であり、職人さんが木材を使って椅子をつくることにあたります。そして 目的因 は、椅子の目的であり、誰かがそこに座って快適に過ごすためということです
●位置: 649
ただし、形相因と目的因、作用因はまったく別個というわけではなく、重なり合う関係にあるとアリストテレスはいいます。というのは、人工物も含めた あらゆる事物はすべて形相の実現という目的に向かって生成変化していくから です。これを別の言い方でいえば、あらゆる事物は、高次の目的によって、動かされている(変化させられている) ことになります。では、この目的の最高位には何があるでしょうか。最高位の目的は、それ以上の目的はありませんから、何かに動かされることはありません。アリストテレスは、この最高位の目的となる存在を「不動の動者」と呼びました。すなわち神のことです。不動の動者である神は、自らは動かずに、宇宙のさまざまなものを動かす。たとえば、天界を動かすのは神です。神は、それ以上の何かに変化する必要はありませんから、質料をもちません。ですから、神は「純粋形相」 でもあります。このように、宇宙や自然を手段‐目的の連鎖として捉える見方を「目的論的自然観」 といいます。そしてこの目的論的自然観は、アリストテレス以後、近代的な機械論的自然観が登場するまで、ヨーロッパの思考の基本的な枠組みとなっていくのです
●位置: 678
では、理想的なポリスの政治体制とはどのようなものか。アリストテレスは、政治に関わる人間が、一人か、少数か、多数かによって、政治体制を、 王制・貴族制・共和制 の三つに分類します。そして、これらがそれぞれ堕落すると、 僭主 制・寡頭制・民主(衆愚) 制 になるといいます。プラトンの場合、理想の政治体制は、哲学者による独裁的な哲人政治でしたが、アリストテレスは、上記のなかで 共和制こそもっとも安定的な政治形態 だと考えました。そこそこの教養と財産をもった市民が政治に参加し、それぞれ理性を働かせて公共的な問題について判断する。これも中庸を重視したアリストテレスらしい考え方です。 「そこそこの教養と財産」をもつことで、人々は理性的に政治判断を下せるというアリストテレスの共和主義観は、機能不全がいちじるしい現代の民主主義にとって、無視できない示唆を含んでいるのではない
●位置: 714
ヘレニズム期の思想とはどのようなものだったのでしょうか。その特徴は、個人の内面的な幸福を追求した点にあります。ソクラテス、プラトン、アリストテレスにとって、善く生きることは、ポリスという共同体の正義や秩序を考えることと不可分でした。つまり、 倫理と政治は一体だった のです。しかしヘレニズム期は、グローバル化した世界帝国の時代です。そこでは現代と同じように、個人主義が進行したため、哲学・思想ももっぱら 個人の内面的な幸福のあり方を考察すること に力点が置かれるようになりました
●位置: 750
ストア派にとって、幸福とは「自然に従って生きる」 ことです。では、自然に従うとはどういうことでしょうか。ストア派では、宇宙には ロゴス(理性) が貫かれていると考えます。したがって宇宙の一部である人間は、ロゴスに従って生きることがそのまま自然に従って生きることになるわけです。そしてロゴスに従った生き方とは、欲望や快楽など、心をかき乱すような外部のノイズに情念(パトス) が動かされることなく、心の平安を求めることをいいます。ストア派は、このような心が平安にある状態を「アパティア」 と呼びました。これは「パトスがないこと」を意味します。さらに、万物に等しくロゴスが宿っているのですから、あらゆる人間にもロゴスが行きわたっているはずです。ここから、人類は等しく平等であるという「世界市民主義」(コスモポリタニズム) の思想をもつに至りました。ここにも、キュニコス派の影響が強く感じられます
●位置: 782
エピクロス派の求めた、身体に苦痛がなく、魂に動揺がないような平静の境地を「アタラクシア」 といいます。アタラクシアを得るためには、利害損得や野心がうずまく政治や公共的なつきあいは避けなければなりません。そのことを示すのが、エピクロス派のモットー「隠れて生きよ」です
●位置: 791
ヘレニズム期には、 ピュロン(前三六〇頃~前二七〇頃) の唱えた 懐疑主義 も人気を博しました。懐疑主義は、あらゆる物事や感覚を疑います。いくら理性を用いるといっても、理性も習慣に縛られているから、人間は、事物のありのままの姿を認識することはできない。本来は、物事の本質などわからないのに、それをわかると考えるから、心の平静(アタラクシア) が乱されるとピュロンは考えるのです。したがって、心の平静を得るためには、一切の先入観をもたないようにひたすら懐疑することが重要だといいます。つまり、あらゆる物事に対して判断は控える。これを「エポケー(判断中止)」 といいます
●位置: 836
アウレリウス・アウグスティヌス(三五四~四三〇) が生きた四世紀後半から五世紀前半は、古代ローマ帝国末期にあたります。ゲルマン民族が大規模に移動し、帝国の秩序が崩壊していく時代でした。キリスト教の歴史としては、彼が生まれる約四〇年前の三一三年に、キリスト教は公認宗教となり、三〇代のときに帝国の国教となります。キリスト教の普及とともに、何をキリスト教の正統的な教義と認めるかという神学上の論争も勃発し、さまざまな宗派が対立・抗争を繰り広げることになりました。そのなかで、キリスト教の正統的な教義の確立に努めた古代キリスト教の指導者や著作者たちを「教父」 といいます
●位置: 849
アウグスティヌスが大きな関心を寄せたのは、「悪」と「自由意志」についての問題 でした。人間の世界には、さまざまな悪がはびこっています。だとすれば、神は悪も創造したのではないか。このような問いに対して、アウグスティヌスは、神が善なる存在である以上、悪を生み出すはずはないと答えます。では、なぜ泥棒のような悪いおこないが存在するのでしょうか。アウグスティヌスは悪の原因を人間の自由意志に求めます。神は人間に自由意志を与えましたが、人類の祖先であるアダムは、神の命令に 背き、禁断の木の実を食べてしまったため、その子孫である人間は生まれつき悪を犯しやすい傾向をもつと、アウグスティヌスはいいます。つまり、人間は自由意志をもっているものの、放っておけば、罪を犯してしまう性向をおびているというわけです。したがってアウグスティヌスは、自助努力で自分を救済できるという考えを認めません。それは、人間の弱さを直視しない 傲慢 にほかならないからです。アウグスティヌスによれば、原罪を背負い、悪を犯しやすい人間の意志が善へと向かうためには、「神の恩寵」(神からの無償の愛) による以外の道はありません。だからといって、神の恩寵をあてにして神を信じるような信仰は、真の信仰とはいえません。善に向かうために人間にできるのは、 無条件に神を愛することだけなのです
●位置: 913
アウグスティヌスであれば、人間の自由意志とはしょせん不完全な意志であり、生まれつき悪を犯しやすい傾向にあるというでしょう。人間が善に向かうには、神の恩寵による以外、方法はないわけです。それに対してトマスは、 神の恩寵と自由意志は、対立ではなく協働の関係にある ことを示します。神の恩寵によって、人間は自由意志から善をなすことができるというのです。この恩寵と自由意志との協働的な関係は、信仰と理性の関係にもそのままあてはまります。トマスにあっては、信仰と理性は対立するものではありません。たしかに、世界永遠説のように、理性では論証できないこともあります。しかし、神の啓示や神秘が示されることで、新たな問いに向けて理性の可能性が 拓かれる。トマスはこうした信仰と自然の関係を、「恩寵は自然を完成させる」 といいました
●位置: 930
このように見ると、アウグスティヌスとトマス・アクィナスの関係は、プラトンとアリストテレスの関係と類比的です。プラトン‐アウグスティヌスという系譜は、二世界論にもとづいて、彼岸と此岸の間に大きな切断を設けます。地上の世界(此岸) は仮りそめの世界であり、天上や神の国こそが真なる世界です。それに対して、アリストテレスの目的論的自然観は、この世界のあらゆる事物に存在する目的があることを示すものでした。そしてアリストテレスを学んだトマスにとって、神の創造した地上の秩序を探求することは、神の神秘に 与ることでもあった。したがって、此岸と彼岸は断絶したものではなく、どちらも神の創造した目的論的な秩序のなかに位置づけられるのです
●位置: 976
「啓蒙の世紀」と呼ばれるこの時代に、哲学でも神は後景に 退いていきます。神よりも経験に知識の基盤を求めていく。しかし、経験だけで確実な知識を基礎づけることができるだろうか。このような疑問を抱いたのがカントでした。そこでカントは、理性や知性の働きをあらためてゼロから吟味します。カントの代名詞ともいえる『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』という三批判書は、それぞれ「私は何を知りうるか」「私は何をなすべきか」「私は何を望んでよいか」という問いに対応しています。いわば、 神ぬきの理性や知性の働きと限界 を見極めようとしたのがカントの哲学でした
●位置: 1,039
新しい学問はどうあるべきか。ベーコンは、学問の真の目標とは、人間の生活を豊かにすることだと主張します。生活を豊かにするためには、自然の法則に精通し、自然を支配する力を獲得しなくてはなりません。そうしたベーコンの立場を表すのが「知は力なり」という言葉です。
●位置: 1,047
ここからわかるように、ベーコンは、自然法則を把握することを「自然に服従する」 と表現しています。では、いかにして自然の法則を知ることができるのか。その方法論として示されるのが、ベーコンの代名詞となっている「帰納法」です
●位置: 1,068
一つ目の「種族のイドラ」 とは、人類という種族が共通にもつもので、視覚や聴覚といった感覚をそのまま信じ込んでしまうことをいいます。たとえば、星が小さく見えるから、星の大きさも見たままのサイズだろうと判断してしまうのは、見たものはそのまま真実であるという「種族のイドラ」が入り込んでいるからです。二つ目の「洞窟のイドラ」 は、個人の性格や経験、育った環境、受けた教育などによって、狭い見方に陥ってしまうことをいいます。洞窟のように狭く閉じた集団の価値観を絶対視してしまうことも、洞窟のイドラにあたります。三つ目の「市場のイドラ」 は、コミュニケーションのなかで生じる言葉の誤用や不適切な使用がもたらす先入観です。流言やデマを信じたり、抽象的な概念をもてあそんだりする際に、市場のイドラは生じます。四つ目の「劇場のイドラ」 は、芝居や演劇を真実だと思い込むように、伝統や権威、誤った学説や理論を無批判に受け入れてしまうことで起こる先入観です。偉い学者が言っているからきっと本当だろうと、自分で情報を吟味せずに鵜呑みにしてしまう人は、劇場のイドラに囚われていることになります
●位置: 1,119
真理を探究する学問の方法をつくりあげるために、デカルトはまず、 四つの思考の規則 を宣言します。①明証的に真であると認めたもの以外、決して受け入れないこと(明証の規則)②難しい問題はできるだけ小さい部分に分けること(分析の規則)③もっとも単純なものから始めて複雑なものに達すること(総合の規則)④見落としがないように、一つひとつ数えあげること(枚挙のの規則)
●位置: 1,124
このルールにもとづけば、最初にやらねばならないことは「明証の規則」に従うこと、つまり誰にとっても確実な真理を見つけることです。デカルトが真理を導く手順は、「我思う、ゆえに我あり」という確実な真理を最初に置いて、そこから他の真理を導くというものです。このように、確実な原理から出発して、推論を展開する方法を 演繹法 といいます。
●位置: 1,184
省察』では、神の存在証明ののち、物体について論じています。ここでも神の誠実から、物体の存在が確かめられる。つまり、私たちがもつ物体の観念は、客観的に実在するということです。でも物体は「私が感覚で把握するとおりのものとして存在するのではないであろう」(『省察』井上庄七・森啓訳、『省察 情念論』中公クラシックス、一一九頁) とデカルトはいいます。感覚による把握は不明瞭だからです。では、 物体の観念から感覚的な観念を引き算すると何が残るでしょうか。それは数学的に把握される観念であり、つまりは空間的な広がりのことです。この空間的な広がりをデカルトは「延長」 と呼びました
●位置: 1,193
デカルトの哲学では、世界は「精神(心)」と「物体」という二つの実体(他の影響を受けず、それ自体として不変のもの) からできあがっています。これが「物心二元論」 と呼ばれるものです。そして、精神の本質(属性) は 思惟(考えること) であり、物体の本質(属性) は延長(空間的な広がり) であるとデカルトは考えました。このとき身体は、心ではないので物体の側に割り振られます。デカルトにとって、身体は物体にすぎないのです
●位置: 1,199
デカルトの物体観にもとづけば、自然の事物は数学的に把握できる物体にすぎません。このように、身体も含めた自然の事物を、数学的に把握できる機械の部品のように捉える見方のことを「機械論的自然観」 といいます。これは、中世まで支配的だったアリストテレスの目的論的自然観とはまったく異なるものです。アリストテレスの自然観では、自然現象は一定の目的をめざして起きる。たとえば目的論的自然観では、石ころは、下方に落ちる本性があるから、下に向かって落下するのだと考えます。つまり、下に落ちるという目的のために落ちるわけです。一方、機械論的自然観では、ありとあらゆる物体は、引力を原因として同じ法則にもとづいて落下するのであって、自然の事物に目的はありません。こうした機械論的自然観を基礎として、自然現象を操作の対象とする近代科学が発展していくことになります
●位置: 1,246
前節で取りあげたルネ・デカルト、そしてバルフ・デ・スピノザ(一六三二~七七) とゴットフリート・ライプニッツ(一六四六~一七一六) は、みな一七世紀の哲学者です。教科書的には、この三人は「大陸合理論」 という名前で 括られ、次節で見るイギリス経験論と対置されます
●位置: 1,267
スピノザの定義する神とは 世界そのもの です。スピノザによれば、人間の精神や身体、動物、植物、石ころはすべて神のあらわれにほかならない。このことをスピノザは「 神 即 自然」 と表現しました。このように、世界のあらゆる事物に神が行きわたっているという考え方を「 汎神論」 といいます。漢字の「汎」は、物事がすみずみまで行きわたっているという意味。神と世界は同一である、つまりデカルトの二元論に対して、スピノザは「すべては一つの神」という一元論を唱えたのです
●位置: 1,282
神はあらゆる事物の原因ですから、神自身は他の何かに動かされることはありません。したがって神こそが完全に自由な存在です。他方で、人間は神の一部ですから、人間自身に自由意志はありません。「今日はハンバーガーを食べよう」と思って、ハンバーガーを食べる。これは自由意志の働きのように見えますが、スピノザに言わせれば、実際には、神が行きわたった自然のなかでさまざまな外部の原因が働いた結果、ハンバーガーを食べているにすぎません。ですから、 自由意志は思い込み ということになります
●位置: 1,290
では、人間に自由は存在しないのでしょうか。そんなことはありません。『エチカ』の第五部のテーマは「知性の能力あるいは人間の自由について」です。スピノザにとって、人間の自由とは、ハンバーガーを選ぶような自由意志のことではありません。端的にいえば、それは 理性に従って生きること です。神=自然は、さながら幾何学のように、必然の法則に従ってさまざまな事物や運動に変じていきます。人間もまた、その神=自然の秩序に従わなければなりません。しかし、その法則を知らずに生きてしまうと、人は自分の境遇を不満に思ったり、物事がうまくいかないことを他人のせいにして憎んだりします。逆に、理性に従い、自分が神=自然の法則とともにあることを知っている人間は、うまくいかなかった原因や、自分のなすべきこと、自分が本当に望んでいることを知ることができる。?み砕いていえば、 神=自然の法則に無自覚に生きるのではなく、理性に導かれて法則の内にあることを知って生きる。 そこにスピノザは、人間の自由を見るのです
●位置: 1,311
この二人に対して、ライプニッツの立場は 多元論 です。すなわち 世界は無数の実体からなっている と考えたのです。ライプニッツは、この無数の実体を「モナド」 と呼びます。モナドという言葉は、ギリシャ語で「一つのもの」を表すモナスに由来し、日本語では「単子」と訳されます。このように書くと、モナドとは、原子のようなものに思われますが、ライプニッツによれば、モナドとは、単一な実体なので「ひろがりも、形もあるはずがない」。ひろがりや形があれば、分割ができてしまい、単一とはいえないからです。したがって、モナドは物質ではありません(物質であれば、ひろがりや形はあります)。見ることも触ることもできないし、イメージすることすら難しい。そういう意味でモナドは、経験を超えた形而上学的な実体であり、私たちに理解しやすい言葉でいえば、精神的な実体ということになるでしょう。彼のモナド論は、『モナドロジー』という著作で読むことができます。ライプニッツによれば、無数のモナドは相互に独立していて、「何かが出入りできるような窓はない」。だから、モナドは相互に関係をもつことはありません。しかし関係はなくとも、個々のモナドは、無数の表象をもつとライプニッツはいいます。表象とは、何かを映し出すことです。モナドが映し出すのは森羅万象です。といっても、外のモナドを映すのではありません。神が無数のモナドを創造し、個々のモナドは、神によって世界に関するあらゆる事柄がプログラミングされている。個々のモナドは自分の内にあるそのプログラムを表象していくことになります
●位置: 1,340
このように、どんな出来事にも十分な理由がなければならないという原理を「 充足理由律」 といいます。世界が充足理由律に従っていることは、無数のモナドが予定調和的に統一されていることにほかなりません。私たちには理不尽に思えることも、神からすれば十分な理由がある。ライプニッツのモナドは、世界をつねに最善に保ち続ける実体なのです
●位置: 1,376
前節までに述べた「原理」重視の大陸合理論に対して「待った」をかけたのが、ベーコンを源流とし、知識の基盤を経験に置く イギリス経験論 でした。経験論では、 演繹ではなく帰納的な論証を重視 します。合理論の範が数学だとすれば、経験論の範は 観察・実験です
●位置: 1,379
ジョン・ロック(一六三二~一七〇四) の哲学から見ていきましょう。ロックが『人間知性論』のなかでめざしたのは、人間の知性の能力を吟味して、知性は何をどの程度まで認識することができるのかを明らかにすることでした。哲学では、人間の認識能力を考察する議論を「認識論」 といいます。その意味でロックの哲学は、近代認識論の本格的な開幕を宣言するものだといっていいでしょう。 人間の心は「タブラ・ラサ」である人間はどのように知識を獲得するのか。その考察の皮切りとして、ロックは大陸合理論の特徴である「生得説」を批判しました
●位置: 1,390
かわってロックが知識の基盤とするのが経験です。 どこから心は理知的推理と知識のすべての材料をわがものにするか。これに対して、私は一語で 経験 からと答える。この経験に私たちのいっさいの知識は根底を持ち、この経験からいっさいの知識は究極的に由来する。(同前、八一頁)ロックによれば、人間の心は「タブラ・ラサ」 のようなものです。タブラ・ラサとは、ラテン語で「何も書かれていない書板」という意味です。つまり人間は、白紙に文字を書き込むように、経験を通じて、さまざまな事物の観念を手に入れる。そして無数の単純な観念を組み合わせて、より複雑な観念の知識も獲得するというわけです
●位置: 1,405
このように、数学で処理できるような性質を、物体そのものに内属させることで、ロックは客観的な知識が成立する道筋を確保しようとしたわけです。 知覚されなければ事物は存在しない!?この区分に異を唱えたのが、ロックよりも半世紀ほど後に生まれた、ジョージ・バークリー(一六八五~一七五三) でした。バークリーはアイルランド出身の聖職者で、アイルランド国教会の主教を務めています。バークリーは、一次性質と二次性質という区分を否定します。彼によれば、視覚であれ触覚であれ、経験は人によって違う以上、形や大きさ、量といった数学的性質は物体にも客観的に備わっているというロックの考え方は誤っている、というのです。ここでバークリーは「存在するとは知覚されることである」 という驚くべきテーゼを提出します。真っ暗闇では、人間には何も見えません。たとえ、何メートルか離れて机があったとしても、人間がそれを知覚しなければ、机は存在しない。すなわち、知覚から離れて事物は存在しないのだ、とバークリーはいうわけです
●位置: 1,415
誰も知覚しない木は、観念にならないので、存在しないことになってしまいます。彼はこの難局をどう切り抜けたのか。切り札は、神でした。たとえ誰も見ていない木でも、神の心にはあらゆる観念が宿っている。つまり神はつねにその木を見ているので、人が見ていない木でも、 神の観念としては 存在するというのです
●位置: 1,433
物体があるかどうかと問うのは 悪手 であり、何が人間に物体の存在を 信じさせている のか、と問わなくてはならない。ヒュームはこのように問いを転換するのです。では、この問いにヒュームはどう答えたか。ヒュームの鍵概念は「習慣」 です。たとえば、いま見えているコップは、一秒後に消えたりはしない。五秒後も一〇秒後も、ずっと見えている。「ずっと見えている」ことが原因となって、人はコップの存在を信じる、というのがヒュームの考え方です。この議論はバークリーの弱点をうまくかわしています。バークリーの説明では、神をもち出さないかぎり、誰も見ていない机やコップは存在しないことになってしまう。ヒュームであれば、人間は、習慣的にコップの存在を信じるようになるので、知覚されないからといってコップの存在が疑われることにはなりませn
●位置: 1,442
習慣によって知識の形成を説明するヒューム哲学の真骨頂は、「原因と結果の結びつき」(因果論) を論じるところによくあらわれています。たとえば、皿を床に落として割れてしまった場合、人間は「皿を落とした」ことが原因となって、「皿が割れた」という結果を引き起こした、と理解します。ここに原因と結果の関係があることは明らかです。しかしヒュームによれば、その因果関係は明らかでありません。経験しているのは、「皿を落とした」「皿が割れた」という二つの出来事だけです。 その間にある「原因と結果の結びつき」じたいは、経験していないのだから、因果関係が明らかだとはいえない。
●位置: 1,452
ではなぜ、人間は原因と結果という関係で、物事を理解するのでしょうか。これもヒュームによれば、習慣に帰着します。皿を落として割った経験が何度か重なると、「皿を落としたから割れた」というふうに、原因と結果で理解するようになるというのです
●位置: 1,455
したがって、あらゆる因果関係も、真理とはいえず、「確からしさ」だけがある ということになります。ヒュームにあっては、人間の精神でさえ、 蓋然的な存在にすぎません。「人間とは、思いもつかぬ速さでつぎつぎと継起し、たえず変化し、動き続けるさまざまな知覚の束あるいは集合にほかならぬ」(同前、四七一頁) という言葉が示すように、ヒュームにとっては、精神すらも実体ではなく、知覚という経験の集合にすぎないのです。このようにヒュームは、 経験論を徹底的に推し進め、精神、物体、因果の実在を否定しました。 ただし、だからといってヒュームは自然科学の営みを無益と考えたわけではありません。逆にヒュームの意図は、経験的な知識への信頼を示すことにありました。絶対的な真理はない以上、人間が扱えるのは経験的な知識だけです。ならば観察や実験を通じて得られる蓋然的な理論や知識を信頼するほかありません
●位置: 1,513
カントは、 これらのデータは、人間が先天的(ア・プリオリ) に備えている認識の枠組みを通じて処理される と考えました。この認識の枠組みには、「感性の形式」 と「 悟性 のカテゴリー」 という二種類があります。 「感性の形式」とは、物事を時間と空間という形式で捉える枠組みのことです。カントのいう感性とは、視覚や聴覚のような五感のことだとお考えください。 人間はまず、外界の 生 のデータを、感性を通じて、時間と空間という枠組み(形式) で処理 します。しかし、時間と空間の枠組みで整序するだけでは、データを理解することはできません。たとえばリンゴを時間と空間で捉えても、そのリンゴが皿とは切り離された「一つ」のリンゴであることまでは、理解できないということです。そこで、悟性の出番です。悟性とは、 事物を概念的に理解する能力 のことをいいます。五感を通じて時間と空間によって秩序づけられた素材データは、続けて、 悟性が備えているさまざまな概念のカテゴリー(量や質、原因と結果の関係) に従って整理されていく ことになるのです。カントはこのような認識の仕組みを「認識が対象に従うのではなく、対象が認識に従う」 と表現するとともに、この発見を、天動説から地動説へと理論を転換させたコペルニクスにちなんで、自らコペルニクス的転回と評しました。人間の認識は、自然のさまざまな事物の姿を受動的に取り込むのではなく、逆に、人間の認識の枠組みが、自然の事物を秩序だてて理解しているということ
●位置: 1,533
しかし、私たちの認識の枠組みを通じて現れているリンゴは、リンゴそのものではない。カントは、認識の枠組みを通じて把握されたリンゴを「現象」 といい、リンゴそのものを「物自体」 と呼びます。現象の世界では、人間の客観的な知識は成立します。でも人間は、リンゴそのものという物自体(真実の世界) を認識することはできない。このようにしてカントは、認識の条件を明らかにすることで、認識能力の限界を画定したのです。と同時に、カントは理性の能力にもブレーキをかけました。ここでいう理性とは、神の存在や宇宙の始まり、人間の自由など、経験を超えるような真理を論理的に求めようとする能力のことです。結論だけをいえば、カントは、神が存在するかどうかといった形而上学的な問題に、理性は答えを出せないと考えました
●位置: 1,546
定言命法の反対語は仮言命法です。 仮言命法 とは、「~ならば、~せよ」という条件つきの命令のこと。たとえば、「お小遣いが欲しいならば、勉強せよ」というのは仮言命法です。それに対して定言命法は、 無条件に「~せよ」と命令すること を指します。カントによれば、道徳的に善い行為とは、次のような定言命法に従うこと。定言命法にはいくつかバージョンがあるのですが、二つのバージョンを紹介しましょう。①汝の意志の 格率 が、常に同時に普遍的な法則として妥当しうるように行為せよ。(『実践理性批判』)②汝の人格および他のあらゆる人の人格のうちにある人間性を、いつも同時に目的として扱い、決して単に手段としてのみ扱わないように行為せよ。(『道徳形而上学原論』)
●位置: 1,557
たとえば、友人に勉強を教える場合を考えてみましょう。このとき、自分の頭のよさを示すためだけに勉強を教えるとすれば、それは友人を手段としてのみ扱っていることになる。そうではなく、友人の「理解したい」という気持ちに敬意を示し、二人がともに善く生きるために勉強を教えなくてはいけない、とカントはいうのです
●位置: 1,561
これらの定言命法からわかるように、カントは、いくら外見上は道徳的な行為に見えても、そこに善をなそうという意志が伴わなければ、道徳的な行為とは見なせない、と考えます。ここには、カントの自由観がよく表れています。カントにとって、人間の自由とは、好き勝手なことをすることではありません。欲望に従って快楽を求めるような生き方は、自然の生理に支配されているという意味で、自由とはいえないからです。では、カントの考える自由とはどのようなものでしょうか。それは、 自然の生理に服することなく、自ら決めたことをなすことができる自由 です。したがって、カントにとっては意志というものが非常に重要な意味を持ちます。先の定言命法も、無条件に義務に従おうとするからこそ自由なのです。たとえば、自分も親切にされたいから友だちにも親切にするのは、カントにとっては道徳的ではありません。特定の条件や目的のためにおこなう行動は、自由な行為とはいえないからです。定言命法とは、実践理性(なすべきことを判断する理性) の命令です。したがって、友だちが自分に親切にしようがしまいが、無条件に友だちに親切にすることが、カントのいう善意志をともなった道徳的行為なのです
●位置: 1,608
デカルトやロックが切り拓いた近代哲学では「人間の知性はどこまで対象を認識するのか」という認識論が、議論の主戦場となりました。そして、前節で取りあげたカントの哲学は、人間の知性が明らかにできるのは経験的な世界(現象界) までであり、神の存在や宇宙の有限性、魂の不滅など、経験を超えた「物自体」の世界を、人間は論理的に解き明かすことはできないことを論証しました。しかしドイツ観念論の哲学者たちによって、「現象界」と「物自体」という区分に疑問が投げかけられ、両者の線引きを打ち消そうとする哲学 が次々と現れました。その完成形と位置づけられるのがヘーゲルの哲学なのです
●位置: 1,648
ヘーゲルの弁証法は、一般的には「正‐反‐合」 と説明されます。ある主張(正) に対して、それに反する主張(反) が対置され、その両者を高い次元で統合する(合) ことが弁証法です。そして、この「合」の部分(矛盾を統合すること) を「アウフヘーベン( 止揚)」 と呼びます
●位置: 1,667
ヘーゲルは『法の哲学』のなかで、「法の体系は、実現された自由の王国であり、精神自身から生み出された、第二の自然としての、精神の世界である」(『法の哲学Ⅰ』藤野渉・赤沢正敏訳、中公クラシックス、六五頁) と述べています。つまり、 ヘーゲルにとっての法とは、自由を求める人間の精神が生み出した制度にほかなりません。 そして『法の哲学』では、法もまた弁証法的に展開していきます。法はまず、外面的な法という形式で現れます。客観的な法は、人間の自由な行動を保障しますが、法があるからといって、人間の自由が社会的な善と結びつくわけではありません。そこで、精神は外面的な法を否定して、内面的な道徳律に目を向けます。その典型は、前節で解説したカントの定言命法です。わかりやすくいえば、社会的な問題は視野の外におき、もっぱら自分が道徳的に生きればよい、と考えるわけです
●位置: 1,675
客観的な法と、それを否定する主観的な道徳──。この両者が弁証法的に統合されたあり方を、ヘーゲルは「人倫」と呼びました。人倫とは、個人の内面である道徳と、社会全体の秩序をつくる法が矛盾なく共存する共同体であり、いわば、さまざまな人間が相互に自由を承認し合うような場のことです
●位置: 1,788
マルクスは、世界が弁証法的に発展していくことには同意するものの、歴史の主役を精神だとは考えなかった。マルクスにとっての歴史の主役は、 物質的生活 です。人類誕生以来、人間は宗教や思想、芸術など、精神的な営みを連綿と続けてきました。では、そういった精神的な活動を可能にしているものは何か。マルクスによれば、それは物質的な条件です。つまりマルクスは、精神が成長するから物質的に豊かになるのではなく、 物質的な生活や条件の変化が、精神的な営みの変化も生み出す と考えたのです。このことをマルクスは「人間の意識が人間の存在を規定するのではない。逆に人間の社会的存在が人間の意識を規定する」(「経済学批判「}序言」}」木前利秋訳、『マルクス・コレクションⅢ』筑摩書房、二五八頁) と表現しています。マルクスは、物質的、経済的、社会的な状況を「下部構造」 や「土台」 と呼び、政治、法律、宗教、道徳、芸術、哲学、科学といった精神的な営みを「上部構造」 と呼んでいます。つまり、「下部構造は上部構造を規定する」 とマルクスは考えるわけです
●位置: 1,833
マルクスの「疎外された労働」には複数の意味が含まれます。チェーン・レストランの例でいえば、そこで使う料理道具やつくった料理も、結局は資本家が購入した生産手段や商品でしかないので、親しみを感じることができない。現代の非正規労働者にしばしば見られるように、 人間的なつながりからも疎外される ことがあります。ここで重要なことは、「疎外された労働」というマルクスの洞察には、 私的所有に対する批判 が込められていることです。労働がさまざまな局面で疎外される根本的な原因は、生産手段や生産物が資本家の所有物になっているからでしょう。こうした問題意識をさらに発展させて、資本主義社会のメカニズムを徹底的に分析した著作が『資本論』なのです
●位置: 1,908
ではなぜ、私たちは神や真理を殺してしまったのでしょうか。その答えは、真理の探求じたいに含まれています。カントは、真理の世界である「物自体」を人間が認識できないことを明らかにしました。観察や実験に重きを置く実証科学に神の出番はありません。つまり、 真理を探求してきた西洋的な思考は、神や真理の存在そのものを懐疑するところまで行き着いてしまった わけです
●位置: 1,916
したがって「神の死」とは、 真理の虚妄性がいよいよ明らかになってきた事態 を意味しています。その後にやってくるのが「ニヒリズム」 です。ニヒリズムとは、生きることの価値や意味を喪失してしまうことです。何のために生きるのかわからない。生きる目標が見つからない。どうせこの世界に確かな価値などないんだ。神の死や真理の死は、必然的にこうしたニヒリズムをもたらすとニーチェはいいます
●位置: 1,960
たとえば、永遠回帰しない世界を考えてみましょう。キリスト教では、世界の終わりには最後の審判がくだり、そこで救われる者と救われない者が選別される。ヘーゲルは、自由の拡大として世界史を捉えました。どちらも世界はやがて真理を現すことを前提としている点で共通しています。このことからわかるように、永遠回帰のない世界は、真理という考え方を呼び込みやすいのです。ニーチェが断固として否定したかったのは、 現実から逃避して、「いま・ここ」とは違うどこかに生きる意味や目標を見いだす態度 でした
●位置: 1,973
超人とは、この地上の意味のことだ。君たちの意志は、つぎのように言うべきだ。超人よ、この地上であれ、と!(『ツァラトゥストラ(上)』丘沢静也訳、光文社古典新訳文庫、二〇頁)わかりやすくいえば、何かのために生きるのではなく、 生きることそれじたい(=地上) から充足を得よ、 ということです。超人を高すぎる理想と思うかもしれません。でも、ルサンチマンやニヒリズムに囚われたままでは、前に踏み出すことはできないこともまた確かです
●位置: 2,015
パースがいっているのは、 知識(概念) の内実は、その知識がもたらす効果や結果と切り離すことができない、 ということです。パースはこのことを「硬い」「重い」という概念を例に説明しています。あるモノが「硬い」とは「別のモノで引っかいても傷がつかない」という意味であり、このことは実際にやってみなければわからない。同じように、「重い」という概念が「上に引きあげる力がないと下に落ちる」ということも、私たちの行動とともに理解されていくのだとパースはいいます。知識がもたらす効果や結果は、行為や行動がともなわないと知ることはできません。ギリシャ語では行為や行動を「プラグマ」といいます。そこからパースは自らの思想を「プラグマティズム」と名づけたわけです。知識と経験とが強く結びついている点で、パースのプラグマティズムが経験論を引き継いでいることはたしかです。しかし同じく経験を重視する実証主義と異なるのは、パースの場合、「神」や「祈り」のような概念も、その効果を知ることで説明できると考えることです(実証主義では、経験的に神の存在を確かめることができない以上、神を説明することは不可能だと考えます
●位置: 2,037
ジェイムズにとっての真理とは有用性と同義です。パースのように、客観性に近づくことは必ずしも必要ではありません。したがって、たとえ他の人にとっては誤っている信念でも、それが個人にとって有用であれば、その信念は真理と見なしていいことになるわけです
●位置: 2,064
知識や概念を道具とみなす点ではジェイムズと共通していますが、デューイの場合、その道具としての役割は、 社会を改良すること に重心が置かれます。したがって、個人に有用性があることよりも、社会が直面する問題の解決に資する道具かどうかが重視される。このように 知識の公共的な側面 に目を向けている点では、ジェイムズよりもパースのプラグマティズムを受け継いでいるといえるでしょう
●位置: 2,136
ハイデガーの「世界内存在」は、 世界のなかで他者や事物と関係し合っている存在者 として人間を捉えます。ですから、コップや椅子のような事物も、単なる認識の対象ではありません。そこで、人間は、他者や事物とどのような関係を結んでいるのか、という問題が重要になってきます
●位置: 2,140
ハイデガーは、現存在が他者や事物と関わるあり方を「 気遣い」 と呼んでいます。気遣いといっても、おもてなしのようなことではなく、 関心を向けること だとお考えください。ハイデガーは「道具」を例に、モノに対する気遣いについて説明しています。たとえば、箸やスプーンは食べるための道具であり、ノートは何かを書くための道具です。さらに、会議の内容をノートにメモするのは、その後の仕事に役立てるためですから、私たちのモノとの関わりは、一つのモノとの関係だけで完結しているわけではありません。いわば私たちは、「~のために~を使う」という目的と手段のネットワークのなかで、モノと関係しているわけです。 このように、現存在とモノが織りなす目的と手段のネットワークのことをハイデガーは「道具連関」といいます。現存在は、 モノを認識するよりも先に、道具連関のなかでモノと出会う のです。ハイデガーによれば、こうした目的と手段のネットワークにおいて、現存在こそが究極の目的であるといいます。たとえば、フライパンは料理をするための道具であり、料理は現存在である私が食事をするための行為です。つまり、AはBのため、BはCのため……とたどっていくと、最終的な目的は現存在=人間に行き着く。したがって現存在は、道具が織りなす「~のため」というネットワークのなかで、その都度その都度、自分に役立つようにモノに対して関心を向けながら、 自分自身の存在にも気遣いを差し向けている ことになります
●位置: 2,162
ハイデガーにとって、本来的なあり方とは、与えられた可能性のなかから自分自身の生き方を選び取り、自らの存在をその都度 ? みしめるような状態をいいます。それに対して、日常生活に埋没して、周囲に流されるような状態に陥ることをハイデガーは「 頽落」 と呼び、誰であってもいいような非本来的なあり方を「ダス・マン」 と名づけました。「ダス・マン」は「ひと」「 世人」「誰でもない人」などと訳されます。ハイデガーは「ダス・マン」のあり方として、くだらないおしゃべりや、物珍しいものに飛びつくだけの野次馬的な好奇心などを挙げています。このダス・マンというあり方は、「時間」の捉え方とも深く関わっています。過去を引き受けたうえで、将来の自分の可能性を選び取っていく本来的な時間性に対して、ダス・マンは、のっぺりとした単調な時間性のなかに安住してしまっているのです
●位置: 2,177
現存在である人間が、ダス・マンの状態から脱するためには、自分の死を見据えることが必要だとハイデガーはいいます。すなわち、死を自覚することで、人間は「自分はこのように生きなければならない」という良心の声に気づくのだ、と。このように、 死の逃れがたさを直視し、死の自覚を介して、本来的な自己(実存) に立ち戻ろうとするあり方 を、ハイデガーは「先駆的決意」 と名づけました
●位置: 2,188
一九三〇年代後半以降、ハイデガーは、さまざまな著作で近代技術批判を展開していきました。ハイデガーの近代技術批判を表す言葉として「ゲシュテル」 というものがあります。「徴用性」「総駆り立て体制」などと訳され、技術が人間や自然を生産に駆り立てていくシステムのことを意味します。 人間も自然も、すべてが生産に役立つように組み込まれる。 技術が地球全体を支配する時代において、人々は自分の 拠り所となる場所、存在を実感できる場所を喪失してしまった(「故郷喪失」) とハイデガーはいいました
●位置: 2,241
キルケゴールが求めたのは、西洋哲学が探求してきた「客観的真理」ではなく、「私にとって真理であるような真理」すなわち「主体的真理」 でした。キルケゴールからすれば、どれだけ客観的な知識をもったところで、それが自分の人生に深い意味をもたなければガラクタ同然なのです。 実存の三段階キルケゴールは、『哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき』という著作のなかで、実存のあり方を「美的実存」「倫理的実存」「宗教的実存」という三つの段階に分けて説明します。これを「実存の三段階」 といいます
●位置: 2,266
即自存在 とは、反省的な意識をもたない存在者のことです。簡単にいえば、人間以外の動物、植物、人工物はすべて即自存在です。動物は、一日の自分の行動を振り返ったりはしませんし、その意味では、物心つく前の赤ん坊も即自存在でしょう。他方、 対自存在 とは、反省的に考えることのできる存在、つまり人間のことです。「いまの話し方はまずかったな」とか「なんだか緊張してきた」とか、人間は自分自身を反省的に考えることができます。対自存在である人間について、サルトルは「それが あるところのもの ではなく、 あらぬところのもの である」と説明します。「あるところのもの」とは現在であり、「あらぬところのもの」とは未来のことです。人間は、現在の自分を反省的に考えることができる。ですから、現在に埋没するのではなく、 つねに現在の自分を否定して、未来に向かって新しい自分をつくりあげていくことができる のが人間だということ
●位置: 2,277
本質と実存という対概念については、すでに説明しました。ハサミであれば、「切ることができる」ことがハサミの本質で、現実に目の前にあるハサミがハサミの実存(現実存在) です。ハサミのようなモノは、人間がつくり出すものです。人間は、無意味にモノをつくるのではなく、何かを切るための道具としてハサミをつくります。つまり、本質にもとづいて現実のハサミがつくられるわけですから、「本質→実存」 という順番になります。それに対して、人間はモノのように、あらかじめ本質が決められて生まれるわけではありません。何ものでもない状態から、自分の力によって、自分の本質(自分が何ものであるか) をつくりあげていくのです。たとえば、小説家は生まれつき小説家だったわけではなく、自分で努力をして小説家になるのだし、野球選手もユーチューバーも会社員も同様です。このように、人間の本質はあらかじめ決まっているものではなく、具体的な生き方が自分の本質をつくりあげていくことを、サルトルは「実存は本質に先立つ」 と表現しました
●位置: 2,296
自分で選んだ生き方には、自分で責任をもたねばならない。だからこそ、自由には「これを選んで大丈夫だろうか?」という不安がつねにつきまといます。しかも、自由にともなう不安は生きているかぎりずっと続く。その意味で、サルトルがいうように「人間は自由の刑に処されている」 のです。さらにサルトルは、個人が何かを選択したことの責任は、人類に対する責任でもあるといいます。たとえばサルトルによると、誰かと結婚をすることは、人類に対して「一夫一妻制」という制度の支持を表明することになるのです。したがって、個人が自由のもとで何かを選択することは、何らかの社会や組織、制度にコミットすることでもある。このことをサルトルは「アンガージュマン」 という概念で説明しました。英語でいう「コミットメント」です。アンガージュマンは、自己拘束や社会参加などの意をもちます。すなわち、自分をある社会状況に投げ込んで自らを拘束すると同時に、 自分の自由な行為によってその社会を新たにつくりかえていかねばならない、ということ
●位置: 2,359
ウィトゲンシュタインにいわせると、「イデアは存在する」とか「人はよく生きるべきだ」といった真偽を確かめられない思考は、どれだけ議論を尽くしたところで結論の出ない無意味な営みだということになります
●位置: 2,361
そこでウィトゲンシュタインが提出するのは、「写像理論」 と呼ばれる考え方です。写像理論とは、文(命題) を、世界を構成している事実の像として捉えることをいいます。ここで重要なことは、事実と、その像である文(命題) とは、どちらも同じ論理(思考) を共有しているということです。いわば論理(思考) を媒介にして、事実は文(命題) として模写される。たとえばウィトゲンシュタインは、楽譜と音楽を、「像の関係」の例として挙げています。音楽はある規則にもとづいて楽譜として模写されるのですから、楽譜と音楽は、同じ論理を共有していることになります。そして先の引用にあるように、「世界は事実の総体」ですから、論理的には、世界は、事実を正しく写した文(命題) の総体として捉えることができるのです。とすると、文(命題) を正しく分析することが、世界のありようを理解することになります
●位置: 2,375
ここで述べられているように、ウィトゲンシュタインは、真偽を確かめられないような問題については「沈黙せねばならない」のであり、哲学的考察の対象に入れるべきではない、と考えた。それが「思考に対して限界を引く」 ということです。ただしこのことは、ウィトゲンシュタインが倫理のような言語的に考察できない問題を軽視したということではありません。彼は「世界の意義は世界の外になければならない」(同前、一四四頁) といいます。事実からできあがっている世界のなかでは、価値や倫理などの「意義」を語ることはできない。しかし、これらは世界の外にあって、世界を条件づけている。いかに生き、いかに死ぬかということは、沈黙のなかに示されるほかに方法はないのです
●位置: 2,400
このようにウィトゲンシュタインは、言語活動を、特定のルールにもとづいて営まれる「言語ゲーム」として捉えました。私たちは さまざまな言語ゲームに参加することを通じて、言葉の意味に習熟していく のです
●位置: 2,413
ウィトゲンシュタインは、家族写真に見られるような、 ゆるやかな類似性のまとまり を「家族的類似性」 と呼んでいます。言語ゲームや家族的類似性という考え方は、本質主義的な考え方の否定を示唆するものでもあります。本質主義では、あらゆる物事に共通してあてはまる性質があると考えます。プラトンのイデアはその典型でしょう。 「神とは何か」「善とは何か」「自由とは何か」「知識とは何か」と、西洋哲学の問いの多くは、本質主義的な解答を求めるものでした。しかし言語がゲームであり、ゲームは家族的類似性によるゆるやかなまとまりでしかない以上、上記の概念に一義的な定義を与えることはできません。その意味で、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」もまた、前期の写像理論と同様、過去の哲学的思考に引導を渡すねらいがあったと見ていいでしょう
●位置: 2,437
西洋政治思想史講義──精神史的考察』(小野紀明、岩波書店) は読みだしたら止まらないほど知的刺激にあふれています
●位置: 2,465
ベーコンに始まるイギリス経験論については『英米哲学史講義』(一ノ瀬正樹、ちくま学芸文庫) がダントツのおすすめ。
 本棚登録 : 75人
本棚登録 : 75人
 感想 : 10件
感想 : 10件