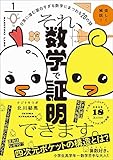-
中学受験 やってはいけない塾選び
- 杉浦由美子
- 青春出版社 / 2022年10月21日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
中学受験の塾選びにおいて、"自分たちにとっての「正解」を考えないことが「やってはいけないこと」ではないか"。
これが本書の軸である。
つまり、塾選びにおいても、我が家における優先順位(通いやすさ?面倒見?難関校に特化したカリキュラム?手厚いフォロー?・・・等)をしっかり整理したうえで、各塾の特性をよく見極め、塾選びをすることがミスマッチを未然に防ぐことが後悔の少ない塾選びの方法であるという方向である。
著者はノンフィクションライター。
本書の情報は、公開情報と、多くの保護者からのインタビューから得た内容に基づいている。
インタビューから得た「失敗談」をもとに、塾選びの際に考慮すべき要素や見落としがちな点を確認し、読者に「我が家の優先順位」を考えさせたうえで、数多くの塾の特徴を紹介していく流れになっている。
多くの読者は、数多くの塾の特徴が列挙されている3章以降が気になるかもしれない。
でも、恐らく本書で一番大事なのは2章で、何はともあれ我が家の軸を定めるための参考情報を提供してくれるのが本書の最大の効用だろう。
あと、もう一つは9章。
転塾についての助言がまとまっているのも貴重かもしれない。
特に、思わず今通っている塾と似たようなスタイルの塾を選びがちだが、それだと失敗を再生産する可能性が高い、というのは有用な指摘だ。
さらっと読めて、ためになる一冊だと思う。
2024年3月1日
-
小学生30億件の学習データからわかった 算数日本一のこども30人を生み出した究極の勉強法
- 今木智隆
- 文響社 / 2023年7月6日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
RISU算数というタブレット算数教材を提供している会社の創業者が、RISU算数にて収集した30億件のデータ(どういう数え方だ?)をベースに解析した、算数が得意になる子の学習法がまとめられている。
本書が参考になるかどうかは、読者が元々どのような常識を持っていたか、に左右される気がする。
例えば、「宿題は無意味だから、負担になってるなら親が代わりにやってしまえばいい」「習い事は極力減らせ」「夜遅くまで勉強させるのはご法度。寝るべし」「女子は算数が苦手、は迷信」「検算の習慣こそ最も大事」「つまづいた単元は完璧に理解するまで徹底的にやり、先に進むな」「ご褒美はあげてもいいが効果は無い」・・・等が、人によっては意外!と思うような主張だろうか。
これらをRISU履修者のデータを解析することによって導き出しており、その説得力はなかなかのものだが、個人的にはどれも「そりゃそうだよなあ」と思うようなことだった。というのも、恐らく多くの塾講師らが出版してきた書籍に似たような主張を散見してきたからだと思う。
第3章の優秀児に共通する親子の勉強への取り組み方についてはよくまとまっていて参考になるとは思う。
2024年4月13日
-
中学受験で大好きな学校に入ろう (ちくま新書 1764)
- 井上修
- 筑摩書房 / 2023年12月7日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
中学受験雑誌『進学レーダー』編集長(兼 日能研勤務)の著者による、私立中選びのための情報書。
内容は主に、中学受験のトレンド、私立中のトレンド、タイプ別に分類した私立中の紹介の三本柱である。
長年中学受験業界に身を置いてきた著者らしく、かつて親世代が受験をした頃と、現在との比較、教育トレンドの変遷について紙幅が割かれている。
進学実績至上主義が後退し、私立中が強化してきたのはキャリアガイダンス機能や持続型学力の涵養。
その実践のためのアクティブラーニングや高大連携への取り組み等の紹介。
そのほか、共学・別学のトレンドや、国際系を標榜する改革を経た学校等の解説等、本書を読めば近年私立中が取り組んできている教育方針のトレンドが一通り把握できる情報量だ。
後半のタイプ別私学紹介は、結構欲張って多くの学校に触れてはいるものの、紙幅の関係上どうしても簡単な案内にならざるを得ない。
最終章の志望校の選び方や塾選びの仕方は取ってつけたような内容で、何だかバランスを欠く。
とは言え、個人的には前半部分の情報だけでも十分一読の価値はあると思うし、志望校選びにおいては、何よりも「校風」を最重要視すべしという著者の見解には共感した。
2024年4月1日
-
中学受験 子どもの人生を本気で考えた受験校選び戦略
- じゅそうけん
- KADOKAWA / 2024年3月4日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
全国の中高大の偏差値が頭に入っている(?)、"受験・学歴オタク"のじゅそうけん氏の処女作。
内容は意外にもクセがなく話題選びもオーソドックス。
「学校は偏差値だけで選ぶものではなく、個性を把握したうえで、子どもや家庭の教育観とのマッチングを考えるべき」と指南する。
そのうえで、「別学or共学」「進学校or附属校」「管理型or自主性尊重型」それぞれの特徴、長所短所、合う人合わない人を述べ、いくつか代表的な学校を短文で紹介する。
中学受験における学校選びの軸としては一般的だし、学校紹介で書いてある内容も割と容易にアクセスできる内容が多く、全体的に中学受験について情報収集を始めたばかりの人向けの一冊と思われる。
少しいじわるな見方をすると、実際に学校を訪れて事細かに取材してきてはいないのではないかと思わせる書きっぷりが目立つ。(「~~な印象だ」「~~のようです」「~~だと思います」)
あくまで外部から収集できる情報(と少数の卒業生等の口コミ)を元に、「恐らくこれは流石に外していないだろう」と判断できるような無難な話題や評価をチョイスしているように見受けられる。
もしかしたらネットで熱心に情報収取すればたどり着けるくらいの情報深度ではあるが、それが一冊にまとまっているから、普段SNSや受験情報サイトを眺める習慣がない人が手に取る一冊としては悪くないのかもしれない。
あ、ただ、第6章の「発達障害の子の受験校選び」は、今の時代に求められていながらも、類書であまりみない切り口で、これはニーズのある情報だなと感心しました。
2024年3月21日
-
中学受験をして本当によかったのか?~10年後に後悔しない親の心得
- 小山美香
- 実務教育出版 / 2024年2月27日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
中学受験のメリットを説いた発信ばかりが注目を浴び、その危険性については話題にならず、過熱する一方の中学受験。
あえて「挫折」を味わった中学受験組の子たちへの取材を通して、幸せな中学受験とは何かを考える一冊。
構成が興味深い。
タイトル通り、中学受験をしてから10年後を迎えた22歳前後の子たちへの取材を中心としている点、志望校不合格や進学後の不登校といった「挫折」を経験した子たちを取材対象としている点だ。
世の中受本の多くは、塾講師等の受験業界の人がものしており、彼らは数千人もの受験生と接してきた長年の経験をもとに「一般論」を説いている。
それに対し本書は、十数人の個別具体な事例から、中学受験とは何かを照射する。
(中学受験経験者のうち大きな挫折を経験した人間は少数派なのだから、本書の執筆動機を考えれば当然そういう構成になるとも言える。)
章立ても良い。
ギリギリ合格の功罪、受験過熱地域の功罪、親の声掛けの功罪、狭まった視野で中学受験を強制することの功罪・・・といった挫折経験から見る受験や志望校選びのヒントから始まり、
数々の挫折を抑止するためのヒント(睡眠の重要性や塾や志望校の選び方)と続き、
最後は、挫折を経験したにも関わらず、取材した子たちみんなが中学受験を良い経験だったと振り返るのはなぜか・・・。そこに焦点をあて、中学受験の本当の目的を見つめ直す。
これ、とっても面白いのは、冒頭で述べた「受験業界の人が書いた一般論」と本書との間で、殆どの観点において結論が同じなのである。
多くの受験成功者を含む一般論から見ても、受験を経て挫折を味わった人たちから見た個別論から見ても、
「幸せな中学受験」を送るためのヒントは、共通している。
そのことが、本書を読んで、自分の中学受験に臨むスタンスをまた一つ強固にしてくれたように思う。
読んでよかった。
2024年3月18日
Youtubeを中心に中学受験の情報発信をしているにしむら先生による、中学受験検討初期の保護者向け書籍。
内容としては、Youtube動画の中から検討初期者向けのものを選び、内容を再構成したもの。
ならば動画でいいじゃん・・・・とはならないで、手元でいつでもさっと参照できるので思わず買ってしまった。
あと動画は見ない配偶者に読んでもらうのも狙いの一つ。
さて、本書で取り扱っているテーマは、
・中学受験を考えたら知っておきたいこと(≒心構え)
・中学受験をするなら保護者が準備しておきたいこと(≒情報収集)
・塾に入る前に知っておきたいこと
・大手塾徹底比較
・入塾したら知っておきたいこと
・わが子の成績を上げるために知っておきたいこと
・わが子をサポートするなら知っておきたいこと
の7つの章立てとなっている。
更に、その中の各論も全て、ポイントを3~10個程度の箇条書き形式で列挙していくスタイル。
一気に読み続けているとポイントが多すぎてめまいがしてくるが(笑)、必要な時に必要な個所を開けば、いま自分が考えていること、取っている行動についての簡易なチェックリストになって使い勝手が良い。
中学受験検討初期に一読し、子どものフェーズ(低学年時、塾選びのタイミング、通い始めのタイミング・・・)に合わせて、一つのガイドラインとして機能する便利な一冊。
2024年3月11日
-
ぼくのかんがえた「さいきょう」の中学受験 (祥伝社新書 693)
- 矢野耕平
- 祥伝社 / 2024年2月1日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
過去に中学受験について多数の発信を行ってきた著者が考える「さいきょう」の中学受験とは・・・。
「さいきょう」の言葉には「最強」と「最凶」の二つがかけられている。
親の価値観や選択次第で中学受験は良いものにも悪いものにもなり得るという意味である。
中学受験ブームの過熱に伴い、主にインターネット上で中学受験について様々な言説が飛び交い、良くも悪くも「一家言」もった親が散見される・・・。
本書は、そのような現状を受けて、よく論点になる点について、時に流布している風説に反論しながら、著者なりの考えを述べていく。
上記のような背景から執筆されているため、全体の印象はやや散漫・・・・というか詰込み感がある。それだけ世間で言われていることに対し言いたい事が多いのだとは思うが次々にテーマをピックアップし、次へ次へと話を進めていくので、あまり体系立っていない印象だ。
せっかくタイトルをこのように定めたのだから、本書の全テーマにおいて「最強」ルートと「最凶」ルートを対比させるような構成にしても面白く、読みやすかったのではないだろうか。
個人的には、中学受験に対する概論としては、著者の『令和の中学受験』を推したい。
勿論、本書には多岐にわたる話題が詰め込まれているので、裏を返せばお得感はあるかもしれない。かねてより著者の考え方はバランスが良いと思っているため、有益な情報はたくさん見つけられる。
なお、本書の章構成は下記の通り。
序章:中学受験の「理想」を掲げよう
一章:中学受験を始める上で考えること
二章:わが子の世界を広げる受験勉強
三章:塾が成績を上げられない理由
四章:氾濫する受験情報
五章:中高一貫校の特徴とその魅力
六章:中学受験での親子の関わり
七章:中学受験のお悩みQ&A
終章:ぼくのかんがえた「最強」の中学受験
2024年3月1日
-
2万人の受験生親子を合格に導いたプロ講師の 後悔しない中学受験100 親が知っておきたいこと、できること
- 渋田隆之
- かんき出版 / 2023年9月22日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
中学受験塾の講師を20年以上続ける著者が、中学受験を志す保護者に伝えたい項目を多面にわたり100項目にも分けて列記した一冊。
テーマは多岐にわたるが大きく10章。
・中学受験をはじめる前に考えておきたいこと
・令和の中学受験常識
・合格する親子の習慣
・人間関係のコツ
・家庭学習の工夫
・保護者の心構え
・志望校との向き合い方
・学力を伸ばすためにできること
・本番までの半年間をどう過ごすか
・中学受験のお悩み相談
1テーマ当たり1~3ページ以内でポンポンと話が進んでいくし、上述した章立てを見て分かる通り、読者の置かれた立場(時期)によってはまだ関心が至らない話題もあって、ともすれば目が滑って行きがちだが、読めば読むほど、真っ当ながら本当に大事なことをピンポイントに語っていることが分かる。
折に触れて見返すと思わぬ救いの言葉が見つかるかもしれない良さがある。
反面、テーマが多岐にわたるため、悩んでいる項目こそ、もっと掘り下げてほしいという部分もあるが、著者のスタンスとしては、個別具体の助言は信頼している塾の講師や家庭教師等、普段の様子を見ているプロがすべきと思っているのかと思われる。
中学受験を志す親が、書棚に一冊控えさせておきたい救いの一冊かもしれない。
2024年3月1日
-
中学受験の失敗学 (光文社新書 379)
- 瀬川松子
- 光文社 / 2008年11月14日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
-
宇宙になぜ、生命があるのか 宇宙論で読み解く「生命」の起源と存在 (ブルーバックス)
- 戸谷友則
- 講談社 / 2023年7月20日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
タイトルの通り、たまらんくらい興味深いテーマで、全般的には知的好奇心を刺激してとても面白い。
でも結論については、大変壮大で、大変肩透かし。
「何も分からない」と言っているに等しいので・・・。
いや、分からないものは分からないからしょうがないんだけど。笑
まず本書の特長は、生命の起源に迫る以上、天文学、物理学が専門の著者が、専門外の生命系化学に足を踏み入れたがゆえに、著者自身も初学者として学び・習得した生命科学系の基礎を、一般の読者同様(知的レベルは遥かに高いが)初学者の立場から平易に解説することに努めている部分である。
著者と共に生命科学の基礎を習得したうえで、著者の専門たる天文学の観点から、宇宙に生命が存在するのは何故か、そして地球外生命体は存在しうるのかという謎に迫っていく。
その本書の構成自体はとても意欲的だし、壮大な範囲の必要知識を、完全に門外漢の私にも分かりやすく説いている部分も素晴らしいと思う。
ただ、そういった周到な前提知識の整理をもとに行った「生命はどうやって誕生したか」という核心部分については、理屈のうえではこうだが厳密には結局どう発生したかよく分からん。という結論。
生命誕生は、地球だけに起きた奇跡的な現象だったのか、割と普遍的な現象だったのか(≒宇宙に他にも生命体が存在するか)という問いに対しては、あり得ないくらい低確率の話だが宇宙はあり得ないくらいデカいので確率論的にはどこかで起こってると言えなくはないよね。という結論。
煮え切らねえ~~~~。
まあ、繰り返しになるけど、分からないものは分からないんだからしょうがないんだけど。。。。
未知の世界を切り拓いていこうとする、研究者の情熱みたいなものは節々に感じられるため、知的エンタメとしては大変面白かった。
2024年2月15日
-
中学受験は算数で受かる
- 州崎真弘
- すばる舎 / 2022年10月24日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
中学受験の立ち位置を決めるにあたり、最も大きなウェイトを占めるのが算数と言われている。
関西は浜学園と馬渕で経験を積んだ算数講師の著者による、中学受験算数の取り組み方を説いた一冊。
ありがちな失敗勉強パターンをまず例示し、そこから効率的な方法の大枠を示す。
更に踏み込んで、日々のルーティンの回し方から、文章題の整理の仕方、塾や模試の活用法、過去問の使い倒し方まで幅広く解説される。
特に、塾との付き合い方(予習の仕方、復習、宿題の仕方)はとても実践的でこれから参考にしたい。
基本的には根性論を排し、効果的で効率的な勉強方法を提唱しているのが好印象なのと、
過去問は10年分を10周しろ、という過去問活用法は目から鱗。
本書の効用を実感できるのは塾に通い始めてからなのと、本の構成が若干分かりづらいので★4とするが、小4以降もお世話になる一冊な気がしている。
2024年2月8日
-
中学受験 金子式「声かけ」メソッド最速の国語読解力
- 金子香代子
- 大和書房 / 2019年8月24日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
中学受験において国語の読解力を磨くための原理原則を説明し、それを身につけさせるために親ができる「声掛け」を紹介した一冊。
何と言っても、具体的かつ豊富な声掛けの例示が特徴的。
著者自身が大手塾で務めていた際に、最下位クラスを担当していた経験が非常にいきており、国語に悩める子供たちのありとあらゆる躓きに寄り添えるのではないかという程の手厚さだ。
子どもが国語ができない原因の第一に「そもそも読んでない」点を挙げるのは最下位クラスの指導経験がなければ出来ないだろうし、そういうところこそ知りたかったという親も多いのでは。
また、読解力を身につけるために必要な力に対する見解の根幹は、ふくしま式(福嶋隆史氏)の系譜に位置づけられ、シンプルかつ汎用的な読解の「型」の習得を理想とする。
その中身も、論理的な繋がりを見出すこと、具体例(対比、理由、言いかえ、たとえ)に着目すること等、ふくしま式や出口式と共通点が多い。
本書では更に、説明文だけでなく物語文についても読解の「型」を示している点(その原則もシンプル。また声掛け例も当然例示)や、
子どものお悩み別攻略法&声掛け法がケース別に解説されていたり、記述力向上の方法、読むスピード向上の方法まで触れられており、正直、分量の割に驚くほど至れり尽くせりの一冊だと思う。
これだけで受験国語を乗り切られるとまでは思わないが、子どもの国語強化に悩む親は活用できるヒントが多く見つけられる一冊だと思う。
2024年1月26日
-
「本当の国語力」が驚くほど伸びる本: 偏差値20アップは当たり前!
- 福嶋隆史
- 大和出版 / 2009年7月18日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
長年、国語単科塾を主催している著者が説く、国語力を高める方法を説いた書。
本書の主張は極めて明快。国語力を高めるには一定の「型」があるという。すなわち
”国語力とは、論理的思考力である。
論理的思考力とは、3つの力である。
3つの力とは、「言いかえる力」「くらべる力」「たどる力」である"
そしてその3つの力がなぜ文章を正しく理解し、科目としての国語の問に正しく答える礎になるのかという原理を説明したうえで、それらの力を高めるための具体的なステップが提示される。
理論的かつ実践的な一冊である。
本書を読むと、著者の著した問題集がなぜあのような構成になっているのかよく理解できる。子どもに問題集を与える前にまず本書を一読したほうが良いであろう。
というのも、著者のもう一つの主張が、教育の要諦は、まず「与え」、次に「待て」というもの。
親や指導者がまず「型」を教え、そのうえで子どもに実践させ、少しずつ手をはなしていくことで、子どもが自らの力を伸ばしてゆくのが理想とする。
本書を読み、親が理解したうえで、問題集を子どもと一緒に紐解き、そして自走させるのが理想的なのだろうと理解した。
さて、余談になるが、本書を読んでもう一つ面白かった点。
それは、同じく受験国語(現代文)の著名講師である出口汪氏が、福嶋氏と同じく、国語力とは論理力であると唱えているばかりか、出口氏の言う国語力=「3つの論理」が福嶋氏の言う「3つの力」と完全に一致していることである。
長年、国語の指導に当たってきた二人が、国語力の核心として同じ要素にたどり着いたという事実が、著者らの主張を信じるにあたり、非常に頼もしいものと思えた。
2024年1月24日
-
予約殺到の東大卒スーパー家庭教師が教える 中学受験自走モードにするために親ができること
- 長谷川智也
- 講談社 / 2021年10月14日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
単発のコンサル等を中心に20年来家庭教師を務めている著者が説く、中学受験を成功させるためのちょっとした秘訣。
それが「自走モード」。
著者の見解では、中学受験で成功する子とそうでない子の差は、本人がほんの少し「主体的になれたかどうか」だけ。
中学受験を戦うのは言うまでもなく子供本人、親は軍師として導き、塾や家庭教師は助っ人コーチくらいの感覚。
最後は戦う本人が主体的にならないと、様々なインプットも成果が十分に上がらないのは確かに当たり前と言えば当たり前。
さて、ではその自走モードに突入するにはどうすれば・・・というと、掲げられている条件は意外とシンプル。
言われてみればそりゃそうだ。親に言われてあれもこれも低年齢の時から詰め込まれた子には自主性なんて育たないもの。
しかし、それらはあくまで自走するための必要条件ではあっても、十分条件ではない。いつ自走に至るかは当然子によるし、親のかかわり方にもよってくる。
そういう意味では、本書には何か万能の処方箋が秘められているわけではない(そんなもの、この世のどこにもあるはずはないけど)
それ以外にも、中学受験のメリット、中学受験のFAQ、志望校の選び方についても述べられている。
個人的には著者の考え方は割とフィットするので、youtube等もその後積極的に見ている。
2024年1月15日
-
未来につなぐ中学受験
- 黒田耕平
- クロスメディア・パブリッシング(インプレス) / 2020年1月20日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
関西のエリート中学受験塾である希学園の学園長による、中学受験を通じて体得してほしい、本当の意義を語った書。
いわゆる中学受験のノウハウ本とはちょっと違う。
いかに偏差値を上げるかといったことより少しスケールが大きい、「中学受験という経験を、子どもが将来大きく羽ばたいていく土台を作る良い経験とするためにはどう考えれば良いか」という観点で、親子に意識してもらいたいことを書き連ねている。
「一生懸命やることの大切さ」「努力・責任・忍耐力」「自分を客観視する力」「ポジティブに振り返る力」「適切な目標設定」「自己管理力」「仲間を尊重する意識」「聴く力」「好奇心」・・・・
気になった項目だけでも、これだけの力を中学受験では要求されるし、身につけることができるという。
しかしそれは、誰でも塾に放り込めば身につくという類のものではなく、まだ幼い子供を、親が上記の力が身につくよう意識しながらうまくサポートしていくことが肝要であるという立場で、多くの助言が書かれている。
本書は、我が子が親に依存していた時期から、少しずつ手を放していく時期に親が意識したい事、とも一般化できるような内容で、中学受験するしないに関わらず示唆に富んだ一冊だと思う。
2024年1月11日
-
中学受験で成功する子が 10歳までに身につけていること
- 村上綾一
- KADOKAWA / 2016年2月10日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
算数に特に特化して高い合格実績を挙げている中学受験塾エルカミノの代表による、中受を目指す家庭の低学年での学びについてTIPs集的に書かれた一冊。
初版が2016年。以降、中受ブームが過熱し、多くの書籍が刊行されてきた故、いま本書を読んでも全く新しい発見は少ないかもしれない。
でも逆に言えば、2016年時点で、今主流となっているような"低学年の過ごし方"をほぼ網羅的に抑えていたことは感嘆に値する。
我が家においても既に実践済みのものも多かったが、そういった項目については日々の取り組みに自信を持てるきっかけになるし、さすがに76項目も書いてあると「あ!これは取り入れてみよう」と思えるような習慣もいくつも見つかる。
ネット上で低学年時に何をすべきか、という情報を収集していると、中にはある意味"過激"なまでの取り組みを推奨している例も散見され、親は情報に振り回されがち。
こういった、落ち着いた、ベーシックな内容の著書はとても重要で、中受を意識し始めた低学年親なら、一度手に取って損はない一冊かなと思う。
2023年11月7日
-
僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない この世で一番おもしろい宇宙入門
- ジョージ・チャム
- ダイヤモンド社 / 2018年11月8日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
宇宙に関する調査研究の最前線を、分かりやすくかみ砕いた語り口調で平易に読むことのできる一般書。
サブタイトルにある「この世で一番おもしろい宇宙入門」というのがこの本の読者層を一番親切に伝えているが、メインタイトルもよく本書の内容を伝えている。
つまり、いま現在の科学で、宇宙について「わかっていないこと」を語ることで、必然的に「ここまでは分かっている」という研究の最前線(限界)の案内になっている。
宇宙は何で出来ているの?
から始まり、物質とは?空間とは?時間とは?次元とは?光より速く動けるのか・・・?等など
物理学と量子力学と一般相対性理論とが、この宇宙について説明できている限界範囲を、楽しく軽妙に読めてしまうかなりの力作。
勿論、読みやすさを重視して、科学的に厳密に正確な説明がなされているかと言ったら、結構端折っているのだとは思うのだが、一般読者層に
「宇宙についての科学って、何だか面白いね!」
と思わせることには成功していると思う。
ただ、全く何の予備知識もなしに読みだしたら、それでもちょっとヘビィかもしれない。
最近、子供用に買った『宇宙』の図鑑を延々読み聞かせをしていたので、ちょっと前提知識があったから、ド文系の私でもすんなり読めた部分はあると思う。
2023年8月30日
-
それ、数学で証明できます。: 日常に潜む面白すぎる数学にまつわる20の謎
- 北川郁馬
- ワニブックス / 2023年3月10日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
タイトルに"証明"とあるが、そんな大それた内容ではなく"日常に潜む数学トリビア"くらいの感じの一冊。
「直角はなぜ90°なのか」と言った簡単な話から、
平均、確率、無限、ゼロ・・・と言ったテーマを中心に20テーマを掲載。
本当にフェアなコイントスの仕方や、無限やゼロにまつわる思考実験は、へえ、そうだったんだ。言われてみればそうだなとちょっと感心できる、いつか誰かに喋りたくなるようなトリビアだった。
暇つぶし本。
2023年7月23日
-
世界でいちばん素敵な地球の教室 (世界でいちばん素敵な教室)
- 三才ブックス
- 三才ブックス / 2017年11月24日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
地球に関する35のテーマを、平易に解説する一般書。
質問のテーマは素朴で基本的なもの。解説も深入りしすぎず、トリビアレベルの簡単な解説にとどめる。
それよりも本書の魅力は、各ページに配された美麗で壮大な世界各地の絶景の写真であろう。
この写真をフックに、そして各テーマのトリビア的な知識を二段目のフックに、少しでも多くの人の興味を喚起したいというのが本書の狙いであろうか。
分かりやすさと情報量を兼ねそろえている本、といえば図鑑にはかなわないものの、
本書の各シリーズ、その写真の美しさで本棚に並べておきたいと思わせるし、どこからでもパっと読める気軽さもあり大変気に入った。
まんまと罠にはまって買い揃えてしまいそうである。
2023年7月1日
-
やりすぎ教育: 商品化する子どもたち (ポプラ新書 た 10-1)
- 武田信子
- ポプラ社 / 2021年5月14日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
言うまでもなく、現代の教育は過熱している(傾向にある)。
親は、子の幸せを願えばこそ、幼少期から習い事をさせ、学歴を身につけさせ、そして立派な社会人として世に旅立たせることを願う。
そうまるで、優れた商品を世の中に「出荷」するかのごとく・・・。
競争社会のシステムが子育てについて親に与えるプレッシャーの大きさ、生まれた時から否応なく競争原理に身を置かれる子供達、それに応えるべく同じくプレッシャーを受ける教育現場・・・。
本書は、親や教員個人を糾弾するものではなく、現代社会の価値観そのものが生み出す「不適切な教育」についての問題提起の書である。
著者は、この現代の不適切な教育の在り方に「エデュケーショナル・マルトリートメント」という術語を与える。
エデュケーショナル・マルトリートメントは、「大人が子供を育てるために役立つ行為だと信じているか、一時的にやむを得ないことだと考えているか、そうする以外に方法を知らない、あるいはないと思い込んでいる(不適切な)行為」とのことであり、公教育の場でも家庭教育の場でも起こり得るものである。
そしてマルトリートメントの中でも、親が子の受忍限度を超えて教育を強制する場合を「教育虐待」と呼ぶ。
つまり、マルトリートメントとは、その行為の範囲も、発生する場所も、いずれも教育虐待より広義であり、社会的な現象をさす言葉である。
必然的に、解決に向けた提言は、家庭だけではなく社会全体での取り組みになっていくため、本書を読んで我が子の教育にすぐ何か処方箋が得られるものではない。
それでも、現今の教育熱心な親の一定数は、子の教育に日々関心を寄せながらもいまの世の中おかしいんじゃないか?子供の時からこんなにやるか?と心のどこかで思っているのではないだろうか。
そう思っていても、あるいは思っていなくても、教育熱心を自負する親は、一度自分の価値観を相対化する意味で、本書を読んでみる価値はあると思う。
2023年6月30日
-
中学受験をしようかなと思ったら読むマンガ 新装版 (日経DUALの本)
- 日経DUAL
- 日経BP / 2019年2月7日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
内容と対象読者はもうタイトルの通り、中学受験をしようかなと思った親である。
漫画という手に取りやすい形式ながら侮ることなかれ、なかなかに良い本だった。
構成としてはタイプの異なる4つの家族の受験体験記が描かれており、受験によってあり得る様々なシナリオが体験でき、受験に対するイメージが膨らむ。理想論ばかりにも偏らず、悪しきイメージにも偏らず。
また、基本的には子の受験を支える親目線の展開で、仕事との両立や塾弁当の用意等、意外と見落としがちな"受験生の親"生活をリアリティをもって予習できる。
我が家では父親である私が中学受験に関心を持っていて、妻は「まあ、あなたが言うなら」という感じ。
本書を読んでおいてもらって「え!こんなに大変なの?!」という予習をしておいてもらったほうが、後々困らない(受験するにせよしないにせよ)と思うので、次はどのように手に取ってもらうかを画策している。笑
2023年6月27日
-
私学の校舎散歩 (進学レーダーブックス)
- 片塩広子
- みくに出版 / 2023年3月15日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
『中学受験 進学レーダー』で連載している学校訪問記の単行本化。
イラストレーターであり子の中学受験を経験した母でもある著者が、実際に訪れその目で見、その肌で感じた私学の姿を手書きのイラストと文章で紹介している。
可愛らしくも、驚くほどの描き込み量に圧倒されること間違いなしの一冊。
あくまで校舎の紹介と、著者が見た生徒や教師の活動紹介なので、志望校選びの参考にできるという程のものではないが、でも私立中が気になっている人からすれば思いきり堪能できる趣味本であることは疑いない。
何せ、親の立場としてはこれだけの数の学校に見学に行くことは不可能だし、そういう意味では貴重。
取材先がどうしても有名進学校に偏りがちなのが玉に瑕(みんな興味あるのはそこだもんね)。
ものすごくニッチでマニアックな本だとは思うけど、良い本ですよ。
2023年4月22日
-
親も子も幸せになれる はじめての中学受験
- 小川大介
- CCCメディアハウス / 2019年12月21日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
中学受験界隈では著名な発信者の一人、小川大介氏。
氏の中学受験に対する向き合い方が最も体系的・直接的に書かれた一冊なのではないかと思う。
個人的に感じた本書の特長は、以下2点にあると思う。
「塾との付き合い方・塾通いの子の勉強の進め方」
「無理なくストレスなく効果的に子供に勉強を促す、親のかかわり方」
上記2点に関する記述が手厚く、我が家は通塾前ながら、塾通いの生活や塾の活用方法などが具体的にイメージ出来て良かった。
また、育児アドバイザーとしての発信も多い著者らしく、随所にちりばめられた親の子に対するかかわり方・声掛け方法は具体的で参考になる。
本書に記載のあった「子どもに勉強することは当たり前のことと思わせる」と「朝ごはんミーティング+予定確認」の二つはそれぞれ実践し、いずれも本当に効果があった。
(なお、前者の手法は、本書ではなく著者の別の本で見て、小学校入学直後から実践。後者は、本書を読んだ後小1終わりの春休みで実践したところ、子自ら計画を立てる学習習慣がついた。)
既に元が取れるくらい活躍してくれた本書ではあるが、著者の思想的にちょっと中学受験を肯定的に捉えすぎていてバランスには欠くと思われる記載が目に付く点、また子供が通塾してからも本書が役に立つかどうかを確認してから再評価したく、暫定的に☆4とする。
2023年3月1日
-
頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある
- 小川大介
- すばる舎 / 2016年3月23日発売
- Amazon.co.jp / 本
- 購入する
もうタイトル通りの本である。
我が子の知的好奇心を育むためには、リビングに「辞書」「地図(地球儀)」「図鑑」を置けという主張である。
これら3つが子供の好奇心を刺激するのに良さそうというのは、誰でもなんとな~くそんな気はする。
では、なぜリビングに置くのか。
それは子供の興味や疑問というのは30秒もすればすぐに移っていくからである。子供が「なんで?」を発したときにぱっと手に取って調べる。この機動力が大事なのである。
それを繰り返していくことで、段々と子どもが、辞書地図図鑑を自発的に手に取るようになっていき、関心領域を広げていくようになるのである。
親とのコミュニケーションの取れる心理的安全性のある環境でのこういった活動が、子供にとっては好ましい記憶として刻まれていくという側面もある。
(確かに、私は子供の頃、自分の部屋に図鑑がずらりと揃っていたが手に取った記憶はない一方、リビングに置いてあった辞書はやたらめくっていた。)
本書は、これらの"三種の神器"を、我が子の関心の発達具合に応じて、どのように少しずつ生活に潜り込ませていくか、どう活用していくかを具体的に指南しており、非常に有益。
おススメの書籍やアイテムも計117点紹介されており、必ずしもこれらを買わないにしても、選書のポイントが分かるようになっている。
きわめて具体的で実践的な内容。
即効性のある教育方法ではないが、種まきは早いほうがいい。
いつかの後伸びに期待して、あとは私自身が調べ物を楽しめそうなので、ぜひリビングに取り込んでいきたいところ。
2023年3月9日