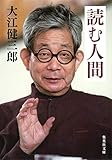ブクログ談話室
言語の面白さを教えてくれるような本を教えてください
欧州語が男性名詞/女性名詞を持つ文化的背景とか
日本語が動詞を最後に持ってくる背景とか、
そういう「言語と歴史背景」みたいなのをテーマや副テーマに
書いてる本ってありますかね。雑学系でも、物語系でも。
単純に興味に過ぎないんですが
言語自体が思考・思想に与えた影響や文化形成
ってあるだろうな、って思うんですが
どうも自分だけで考えてても消化しきれなくて・・・
例えば、宮城谷昌光さんが漢字を甲骨文字の観点から
論理的に組み立てて説明する手法なんかは好きでした。
そういう本筋とは違うけどちらっと出てくる
みたいのでもいいです。
(舟を編む、はちょっと違った・・・)
分かりにくい説明ですみません・・・
---------------------------------------------------------
<追記です>
自分が生まれる前から言語は存在してて、
自分の意思・思考をまずは母語というツールで表現して生きて、
自分が死んだ後も次の生命体がまた同じ言語というツールを使うって、なんというか素晴らしいですね。
皆様にご紹介頂いた中で自分の興味というか疑問点が
フォーカスされてきた気がします。
例えば日本語でいうと、方言であっても変化のない発音てありますよね。
・「この列車は、名古屋と京都に止まります」
・「こん列車さ、名古屋と京都ば止まるでよ」
ってどちらも日本語ですけど、「と」は使い方も発音も一緒ですが
「に」と「ば」は使い方は一緒ですけど発音が違いますよね。
文章(というか口語?)的には「に」でも「ば」でもOKですよね。
でも「と」が、例えば「ゆ」とか「ろ」とか、なんでもいいんですけど
「と」以外の発音だったら意味わかんないですよね?
並列助詞の「と」が全国共通で「と」でなければならなかった理由って何なんだろうとか。
さらに、
英語だったら「and」で、発音的に「d」を略しても2音要しますけど
日本語だと「と」は1音ですよね。
英語の台詞やスピーチを聞いてても、andって結構明確に言ってる気がするんですが、
日本語で普段喋ってて「と」を意識したことあんまり無いんですが、
そうすると英語圏の生活において、
「並列を表す発音」を明確に伝えないと、
なんか、例えば死ぬとか、切迫した事情があったんだろうか、とか。
そういう、それぞれの言語に発音・文法において、
それに至った理由って何なんだろう、
そしてそのルールで続けなければならなくなった生き方って
言語によって違うのかな、というような疑問ですかね。
皆様の教えてくださった本に、それぞれ書いてありそうで、
本当にここで質問してよかったです。
さっそく今週末にでも図書館で集めてきます。
ご紹介くださった皆様、ありがとうございました。
(ちょっとづつ調べていこうと思うので、まだまだご紹介いただけるとありがたいです・・・)
日本語が動詞を最後に持ってくる背景とか、
そういう「言語と歴史背景」みたいなのをテーマや副テーマに
書いてる本ってありますかね。雑学系でも、物語系でも。
単純に興味に過ぎないんですが
言語自体が思考・思想に与えた影響や文化形成
ってあるだろうな、って思うんですが
どうも自分だけで考えてても消化しきれなくて・・・
例えば、宮城谷昌光さんが漢字を甲骨文字の観点から
論理的に組み立てて説明する手法なんかは好きでした。
そういう本筋とは違うけどちらっと出てくる
みたいのでもいいです。
(舟を編む、はちょっと違った・・・)
分かりにくい説明ですみません・・・
---------------------------------------------------------
<追記です>
自分が生まれる前から言語は存在してて、
自分の意思・思考をまずは母語というツールで表現して生きて、
自分が死んだ後も次の生命体がまた同じ言語というツールを使うって、なんというか素晴らしいですね。
皆様にご紹介頂いた中で自分の興味というか疑問点が
フォーカスされてきた気がします。
例えば日本語でいうと、方言であっても変化のない発音てありますよね。
・「この列車は、名古屋と京都に止まります」
・「こん列車さ、名古屋と京都ば止まるでよ」
ってどちらも日本語ですけど、「と」は使い方も発音も一緒ですが
「に」と「ば」は使い方は一緒ですけど発音が違いますよね。
文章(というか口語?)的には「に」でも「ば」でもOKですよね。
でも「と」が、例えば「ゆ」とか「ろ」とか、なんでもいいんですけど
「と」以外の発音だったら意味わかんないですよね?
並列助詞の「と」が全国共通で「と」でなければならなかった理由って何なんだろうとか。
さらに、
英語だったら「and」で、発音的に「d」を略しても2音要しますけど
日本語だと「と」は1音ですよね。
英語の台詞やスピーチを聞いてても、andって結構明確に言ってる気がするんですが、
日本語で普段喋ってて「と」を意識したことあんまり無いんですが、
そうすると英語圏の生活において、
「並列を表す発音」を明確に伝えないと、
なんか、例えば死ぬとか、切迫した事情があったんだろうか、とか。
そういう、それぞれの言語に発音・文法において、
それに至った理由って何なんだろう、
そしてそのルールで続けなければならなくなった生き方って
言語によって違うのかな、というような疑問ですかね。
皆様の教えてくださった本に、それぞれ書いてありそうで、
本当にここで質問してよかったです。
さっそく今週末にでも図書館で集めてきます。
ご紹介くださった皆様、ありがとうございました。
(ちょっとづつ調べていこうと思うので、まだまだご紹介いただけるとありがたいです・・・)
質問No.5630
みんなの回答・返信
-
 名無しさんの回答
2014年01月09日
名無しさんの回答
2014年01月09日
昔テレビで、わずか2~3人の絶滅危機部族と、それに伴い亡びゆく言語について研究する学者を追ったドキュメントを観ました。記録も残されていない言語が消えるという事象に不思議な感覚に陥りました。
回答No.5630-064884
-
 深川夏眠さんの回答
2013年11月19日
深川夏眠さんの回答
2013年11月19日
鈴木孝夫先生の本は他の方が既に紹介していらっしゃいますが、こちらもついでに。
ジャンルで言うと言語社会学。
雑誌連載を再構成した本で、日本語独特のややこしさや、
欧米の言語との様々な違いについて、わかりやすく書かれています。
ギリシア語で「蛾」と「鯨」を表す語が同じなのは何故か、等々、
興味深い話題が登場します。
ジャンルで言うと言語社会学。
雑誌連載を再構成した本で、日本語独特のややこしさや、
欧米の言語との様々な違いについて、わかりやすく書かれています。
ギリシア語で「蛾」と「鯨」を表す語が同じなのは何故か、等々、
興味深い話題が登場します。
回答No.5630-063530
-
 jyakomouseさんの回答
2013年11月18日
jyakomouseさんの回答
2013年11月18日
人工言語をテーマにしたSF小説で、サイバーパンクでスパイもの。古い作品で新刊入手は無理かと思いますが、言語が思考に与える影響を扱った作品の代表作だと思います。
同じく言語テーマの『星の、バベル』は南太平洋の架空の小国を舞台にしてますが、これも入手困難。
同じく言語テーマの『星の、バベル』は南太平洋の架空の小国を舞台にしてますが、これも入手困難。
回答No.5630-063511
-
 土壷波丸さんの回答
2013年11月10日
土壷波丸さんの回答
2013年11月10日
もう一つ、こちらは言葉がもたらしてくれるものについて、非常に緻密な感覚で書かれた一冊。前提にあるのは、言葉を正確にとらえる、ということです。ご質問をふまえますと、こちらも興味深いのではないでしょうか?
回答No.5630-063292
-
 土壷波丸さんの回答
2013年11月10日
土壷波丸さんの回答
2013年11月10日
ご質問の文にありますような、厳密な言葉の定義あるいはニュアンスの違いを生み出すものの背景にある人間の感覚について、興味深い内容のある一冊です。とてもわかりやすい文章です。
回答No.5630-063291
-
 yamaitsuさんの回答
2013年11月08日
yamaitsuさんの回答
2013年11月08日
私も今読んでいる途中なので、お探しのテーマに合っているかどうかわかりませんが・・・
対談形式なので、内容はわかりやすく、とっつきやすいです。
回答No.5630-063240
-
 くまさんの回答
2013年11月05日
くまさんの回答
2013年11月05日
私も興味のある分野で、紹介されている本を読んでみようと思いました。
追記を拝見すると、あまり一致しない内容ですが、言葉の面白さ、難しさがわかる本です。
(既読かもしれませんが…)
追記を拝見すると、あまり一致しない内容ですが、言葉の面白さ、難しさがわかる本です。
(既読かもしれませんが…)
回答No.5630-063167
-
 名無しさんの回答
2013年11月04日
名無しさんの回答
2013年11月04日
ご質問内容とちょっと違うかと思われますが、真っ先に思い出したのが・・・
古い子供向けの本ですが、日本語の言葉遊びやリズムを楽しめる本です。
今で言う、NHK教育の「にほんごであそぼ」みたいな本ですね。
こういう本から質問者様のように日本語に興味を持ちますよね。
古い子供向けの本ですが、日本語の言葉遊びやリズムを楽しめる本です。
今で言う、NHK教育の「にほんごであそぼ」みたいな本ですね。
こういう本から質問者様のように日本語に興味を持ちますよね。
回答No.5630-063143