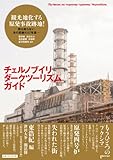- Amazon.co.jp ・本 (192ページ)
- / ISBN・EAN: 9784907188023
作品紹介・あらすじ
Amazon総合ランキングベスト10入り、紀伊國屋書店、青山ブックセンターなど主要書店の人文書ランキングで1位を獲得した、『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』の続編がついに登場!
2013年、現在の福島はどうなっているのか。(第1部「制度をつくる」)
2020年、東京は福島のためになにをすべきか。(第2部「導線をつくる」)
2036年、福島は世界にどのように開かれているべきか。(第3部「欲望をつくる」)
さらに補遺として、『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』の追加取材報告や、官民の福島の復興計画案を網羅した資料集を掲載。
前巻をはるかに上回る192ページフルカラーで、写真・図版を多数収録。テレビ・新聞で話題沸騰の「福島第一原発観光地化計画」の実態がついに明らかに!!!
感想・レビュー・書評
-
はっきり言おう。これは福島を自らの「思想」のもとに従属させる、極めて醜悪な計画だ。もう少し突き詰めて言うと、これは福島を永久に「原発事故」という枠に押しとどめる行為でしかない。
そもそも計画者らは「風化させないことが大事」と言うが、なぜ「風化してはいけないのか」を本書から考えると、そもそも「原発」という象徴に(昔も今も未来も)縛り付けるための方便にしか見えない。そしてその視線が向いているのは、被災地の現実ではなく彼らが打って出たい「東京」「世界」だ。同書には(申し訳程度に藤田浩志の寄稿があるものの)地元経済に対する視線が観光ガイドの育成以外にない。
さらに、同書では導線が世界-東京-福島と設定されているが、震災という視点から考えれば岩手などを経由する必要があろう(世界-東京-八戸-久慈-釜石-大船渡-気仙沼-石巻-仙台-福島第一原発など)。同書にとって福島は「象徴の中心」でしかない。また同書の中には「ツナミの塔」という作品案があるが、津波瓦礫を使った芸術品と称されているにも関わらずなぜか原発事故関連の作品ということになっているのがそれを象徴しているだろう。
もう一度言うが、これは福島をある種の差別構造に従属させるものでしかなく、こういった「思想」の押しつけにどのような効果があるのか、極めて大きな疑問を持たざるを得ない。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
現在すでに始まっている原発周辺のガイドの紹介に始まり、2020年の復興博の提案、2032年の一大施設ふくしまゲートヴィレッジ構想へと続いていく。思ってたよりずっと具体的なプランが描かれていて、読んでてワクワクする。
現在のガイドや未来のプランの中に、原発の問題を風化しない、福島だけの問題にしない、といった重要なメッセージが見えてくる。今、福島でも日本全体でも放射能や原発の問題をなかったことにするような感じになってることを考えると、これはとても大切なことだ。
福島内外の様々な人が出てきてバラエティに富んだ内容になっていて、どこから読んでも面白い。豊富な写真も嬉しい。
読みながら、福島の10年、20年先のビジョンが前向きに語られることが今まであっただろうかと考えてしまった。だからこの本を読んで、涙が出るほど嬉しかった。
あとがきまで読んで思った。福島第一原発観光地化計画は具体的に練られた夢なんだと。今、日本は一つの夢の終わりを迎えていると思う。そこに必要なのは新しい夢なのではないか。その一つの形がこの福島第一原発観光地化計画なんだと思う。
今こそ福島の未来を語りたい。本当に多くの人に読んでもらいたい一冊。 -
お疲れさまでした!
個人的に、結論の出ていること、ではあるので、「ああ、ここまでくるのにこんなに時間が経ったのか。あれから2年半、あれもこれも読んできたけど、そんなにかかったのか…」という感慨の方が大きい一冊となりました。考えを形にする、ということ、人に分かるようにする、ということ、それを広める、ということがいかに大変なことかを、改めて感じました。本当にお疲れさまでした。
とにかく分かりやすく、イメージの膨らむ形での紙面構成。こんなこと考えたこともない、3.11をどのようにとらえたら良いのかまだわからずにいる、という向きには是非。一読に値すると思います。
距離もあり、なかなか直接的に何が出来るということではないけれども、自分の立ち位置で同じように未来を描く力について考えたい、実行していきたい、という意味で、とてもエネルギーを頂きました。あとはこれがどのように世界に染み渡っていくのか、を見つめ続けたいし一緒に考え行動していきたいです。
私的には、巻末の東氏が、今後のテーマを「超越について」とされていたのが一番の見所でした。そこかなやっぱそこかな! -
思ったより真面目な本だった。空想ではなく、実現可能なことが前提なようだ。違和感があるとすると、震災や原発事故をビジネスのチャンスと捉えてしまうことか。本人たちはビジネス最優先とは決して言わないだろうが。
-
やはり見に行くべきだ
-
東日本大震災
-
考え方としては同意したいところではあるが、ざんねんながら実現はかぎりなく難しいだろう。実施主体が東電なのか県なのか国なのか。ね、無理でしょ。むしろデンツーとかウンタラ堂がやるのがいちばん近いのかもしれない。南三陸町の防災庁舎が31年まで保存されるが、これも県のリーダーシップ次第。
-
ダークツーリズムについて具体的に説明した本である。東北は大震災であるが、沖縄、広島、長崎は戦争のダークツーリズムで考えるとほとんどがそうである。会津若松では明治維新のダークツーリズムであるし、韓国、中国、サイパンやパラオやベトナム、マレーシア、フィリピンは日本の戦争のダークツーリズム、アウシュビッツやアムステルダムのアンネの家はナチスのダークツーリズムである。
-
これ、まじめに取り組んだほうが良いのでは?
ダークツーリズムという観点もともかく、日本の原子力技術の集積地としてこのエリアを活用することに、大きな意義があるのでは?と思います。
実際、行ってみたいですしね。 -
タイトルに違和感を持つ人が多いことは、ひとまず横に置く。
日本の代表的なダークツーリズムといえば広島だが、広島は元から中国地方の中心地で産業があった場所。本の中でも指摘しているが、修学旅行などの旅行以外に、出張のついで、なども多いと思う。(実際、自分もそうである。)Fukushimaを観光地化するといっても、本の中の言葉で云えば「動員」力が弱いところを、ショッピングセンターや大型施設でカバーするだけでは難しいのではないか。
とはいえ、福島第一原発の「人災の記憶」を風化させてはならない、そのためには今からプランを立てて実行していくべきだという主張には納得できる。
東日本大震災という「天災の記憶」は、当事者にとって忘れたい/忘れてはならない、の葛藤があるが、福島第一原発は「人災」として記録=アーカイブしなければならない。
著者プロフィール
東浩紀の作品











 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :