- Amazon.co.jp ・本 (412ページ)
- / ISBN・EAN: 9784101253312
作品紹介・あらすじ
昔、英国人一家の別荘だった、今では荒れ放題の洋館。高い塀で囲まれた洋館の庭は、近所の子供たちにとって絶好の遊び場だ。その庭に、苦すぎる想い出があり、塀の穴をくぐらなくなって久しい少女、照美は、ある出来事がきっかけとなって、洋館の秘密の「裏庭」へと入りこみ、声を聞いた-教えよう、君に、と。少女の孤独な魂は、こうして冒険の旅に出た。少女自身に出会う旅に。
感想・レビュー・書評
-
梨木香歩さん。
けっこう打率の高い作家さんです。
「家守奇譚」☆5
「冬虫夏草」☆4
「西の魔女が死んだ」☆3
「村田エフェンディ滞土録」☆4
安定の4打数4安打。内1ホームラン。
これはもうまちがいありません。鉄板でしょう♪
タイトルだけ見てブックオフで購入しました。
しばらく寝かせておいた1冊です。
アカーン_| ̄|○ダメヤコレ
児童文学ファンタジーでした。
合わない。
合わないという言葉は便利なもので、本当はクソだなとか、クズだなとか、ハナクソだなとか、思っていても、でもあれだよなー、きっと好きな人もいるんだろうからいくら個人の感想つってもそんなに正直に辛辣には書けないよなぁ、なんてときに非常に便利な言葉で、今までけっこう多用してきたんですが、今回は本当の意味で合わない。
右打席立つつもりが間違って左打席に立ったみたいな。
主人公は13歳の少女。
きっと現役の少女とか、昔少女だったとか、昔々少女だったとか、昔々のその昔に少女だった片鱗がかすかに残っている気がするとか、そういう方々には刺さる何かがあると思う。
しかし当方、残念ながら身の内のどこをどう探しても13歳の少女は出てこなかった。
読んでる間、これはアレだなと思った。
ちょい和風な「不思議の国のアリス」に「オズの魔法使い」を混ぜ合わせて、「思い出のマーニー」(ジブリ版)をソースにして上からかけたような。
そんな読後感。
一九九五年第一回児童文学ファンタジー大賞受賞作だそうです。
合わないってだけで特に文句はないんですが、あえていうなら、「意外と登場人物多くね? 相関図も欲しくね? なのに人物紹介みたいなのまったくなーい」ってことくらいですかね。
あ、あとね。
少女の頃の魂をどっかに保持したままで、人生をまっとうに頑張って生きてきたおばあちゃんたちは格好良いですな。
これからは本を買うときはあらすじくらい見てから買うことにしようかな。うん。 -
率直に感動した。大作だった。
己の傷と対峙することのどれほど険しく難しいことか。傷との融合の話でもあったのかと思う。印象に残る文が多くて、それぞれの箇所について感想を言い合いたくなる。
日本の家庭って、家に庭って書くんだね。その庭をどう手入れし育み作り上げていくかは庭師次第なのだと。
エピローグ後の展開も気になるけど、それはそれぞれ私たちの中でまた育てていくものなんだろう。
最後に河合隼雄氏の解説があるのもよき。 -
かつて英国人一家の別荘だった洋館。近所の子どもたちは塀の穴をくぐり、洋館の庭で遊んでいた。照美もその一人だったが、面倒を見ていた軽い知恵遅れで双子の弟、純が庭の池に落ち、肺炎で亡くなってからは、庭を避けるようになっていた。
純が亡くなり、家族の中で自分の居場所がなくなったと感じた照美は、友達のおじいちゃんの話を聞くことが唯一の楽しみとなっていた。
おじいちゃんはかつて洋館に住んでいた英国人一家のこと、また洋館の「裏庭」での不思議な出来事について話してくれた。「裏庭」とは、死の世界にとても近い場所で、洋館の玄関つきあたりにある大鏡から入っていけるという。
ある時おじいちゃんが倒れた、と聞いた照美は、いてもたってもいられず、洋館の大鏡の前に立つ。すると、どこからともなく声が聞こえ、照美は導かれるように裏庭に足を踏み入れるのだった。
本書は照美と照美の母であるさっちゃんの視点から描いた現実の世界と、照美が裏庭の世界に入り、冒険を繰り広げる異世界の二つのパートに分かれる。
現実の世界では、登場人物の誰もが心の中に喪失を抱えている。純の面倒見役だった照美は純を失った今、自分を家族の中で不必要な人間だと感じている。さっちゃんは純を失った悲しみから立ち直れず、照美に向き合うことができない。また、彼女は自分の母に愛された記憶がないことに苦しんでいる。照美の父は純を失った悲しみを表すことができずに照美やさっちゃんに無関心な対応を取ってしまう。
洋館に住んでいたレイチェルは、裏庭を自由に行き来できる妹のレベッカに対して疎外感を感じ、レベッカの婚約者マーチンは若くして病気で亡くなったレベッカを忘れられない。
皆が傷を守るために心の内を鎧で固めてしまっている。そんな中、照美が裏庭という異世界を旅し、現実の世界へ戻ってくることで、皆が少しずつ心の鎧を脱いでいくのである。
物語はイギリスの児童文学の世界を模したような設定だが、大きく違うのが、本書では子どもの照美だけでなく、母親のさっちゃんの心の内も描き出していることだ。つまりこの物語は、子どもの成長物語というだけではなく、大人が過去の傷を乗り越えるための物語でもある。
裏庭で繰り広げられる冒険ファンタジーは、やや抽象的な寓話を読んでいるようで、どういう意味を持つのかわかりかねるところもあったが、すべての登場人物がつながり、それぞれに再生の兆しが見えるラストは胸を打たれる。
心の中に喪失を抱える人たちに少しだけ癒しを与えてくれる物語。 -
梨木さんのからくりからくさ、りかさん、家守奇譚などが大好きで手にした作品。
個人的に西洋風ファンタジー(竜や妖精が出る系統)が苦手で世界観に没入出来なかったので評価が低くなってしまったが、そうでない方にとったら良い作品だと思う。
-
一日中のんびりと本を読みました。梨木香歩「裏庭」です。児童文学ファンタジー賞を受賞した作品です。大作という感じで読み込むのにかなり力が必要でした。ファンタジーの部分が多く、この前に読んだ「西の魔女が死んだ」の方がシンプル(一つ一つの心情などはすごく深いですが)で素直に心の中に入ってきました。
-
梨木さんの本はこれで三冊目。
まるで壮大なアニメを観るような感覚で読み終えました。
作品の肩書きは「1995年第一回児童文学ファンタジー大賞受賞作」。
主人公は思春期の少女、照美。
タイトルの「裏庭」とは、照美の家の近所にある、かつて英国人一家の別荘だった洋館の遊び場のこと。
同時に彼女自身の内面をあらわします。
双子の弟「純」を亡くしてから、両親との間の溝を乗り越えられない照美。
友人の祖父から聞いた近所の屋敷の「裏庭」にある日入り込み、不思議な鏡の声を聞いて「裏庭」への長い旅に。
それは照美自身の内面への旅でもあると読者も知らされていくのです。
まるでRPGのような照美の冒険と、「裏庭」に関わる現実の人々との話は並行して進んでいきます。途中に織り込まれる幾多のメッセージが照美を目覚めさせ、読み手の心も大きく揺さぶられます。
一貫して流れるのは「家族の再生」というテーマ。
悲しみにはきちんと向き合って泣かなければならない、大切な家族には「あなたが大切だ」と態度でしめさなければいけない、そんな当たり前の事を知るための、照美の旅の辛さには思わずエールを送りたくなってきます。
家族に対して感じている遠慮や諦め、何となく埋まらない溝。
それらをうやむやにせず言葉で表現する本作品は、特に若い方にお薦め。
当たり前な家族のあり方が出来なくなっている大人にもお薦め。
導入部でワクワクさせ、途中では心のストライクゾーンに何度もヒットを打ち込まれ、最後まで読むと暖かい気持ちになる、さすが梨木さん。
展開のドラマティックさと、色彩感の豊かさとは、アニメ化しても良さそうな気がしますが、読まれた方はどう思われますか?
今日は体調がすぐれなくて寝ていたのですが、そのおかげで本作品を読み終えました。風邪に感謝。 -
中学時代に梨木さんの「西の魔女が死んだ」を読んで、他の作品も興味を持ち購入。
家族旅行の際にこの本を持っていき、夜ホテルで読み始めると、先が気になって、ページを捲る手が止まらなくなり、ほぼ徹夜をして読んでしまったことは今でも覚えています。
学生時代の私に良い読書体験をもたらしてくれた、かけがえのない作品です。近々、再読したいです。 -
穏やかそうな装画から受ける印象に反して、とても壮大なファンタジーだった。
家族との関係性が希薄で孤独を感じている小学生の照美が、打ち捨てられた洋館の裏庭に迷い込んで、冒険しながら自分自身や様々なつながりを取り戻す話。
図書館ではティーンズ文庫のコーナーにあったけど、大人でも結構難し目の話で、読みながら現実と対比させて考えることが沢山あった。
著者プロフィール
梨木香歩の作品






この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。











 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 : 
















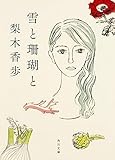


































どっちが先がいいのかな?読み方指南みたいな感じっぽい...
どっちが先がいいのかな?読み方指南みたいな感じっぽいから『ノート』が先かな?
猫が言うのもアレですが、『秘密の花園』はキイワード一杯の話ですから、見方の例は後にされた方が。。。
猫が言うのもアレですが、『秘密の花園』はキイワード一杯の話ですから、見方の例は後にされた方が。。。
ブックレットの方も近隣図書館にあったので近々借りてきて読んでみますねん
ブックレットの方も近隣図書館にあったので近々借りてきて読んでみますねん